【論考】1950年代東京の「連れ込み旅館」について ―「城南の箱根」ってどこ?― [論文・講演アーカイブ]
2020年4月8日(水)
この論考は、明治大学文学部の平山満紀教授が主催する「セクシュアリティ研究会」(第2回:2018年08月11日)で発表したものである。
(さらに、その原形は、2011年10月29日の井上章一先生主催の「性欲研究会」で報告)
私の「連れ込み旅館」研究のベースになる報告だが、1年半が経っても、活字にしてくれる所はなさそうなので、原稿化して、このアーカイブに載せておく。
引用される際には、著者名と、この記事のURLを注記していただきたい。
【目次】
はじめに ―思い出―
1 「連れ込み旅館」とはなにか
2 「東京『連れ込み旅館』広告データベース(1953~1957年)」を作る
3 その分布
4 分布から見えるもの ―西の「連れ込み旅館」、東の「赤線」―
5 その設備
(1)建築様式 (2)基本設備 (3)鏡 (4)テレビ (5)暖房 (6)冷房 (7)風呂
6 その立地
(1)森 (2)水辺・川 (3)水辺・池 (4)水辺?・水族館 (5)高台 (6)山・山荘
7 そのイメージ
(1)温泉偽装・温泉詐称・有名温泉への仮託 (2)温泉マークの使用 (3)なぜか南国
8 「連れ込み旅館」の機能 ―むすびに代えて―
----------------------------------------------------------------
1950年代東京の「連れ込み旅館」について
―「城南の箱根」ってどこ?―
三橋順子(性社会文化史研究者)
はじめに ―思い出―
「今日はちょっと面白いところに連れてってあげるよ」
運転席の彼が言う。
新宿で待ち合わせて、いつもはユーミン(荒井由実=松任谷由実)の「中央フリーウェイ」の歌詞そのままに、右手に競馬場(府中の東京競馬場)、左手にビール工場(サントリー 武蔵野ビール工場)を見ながら中央自動車道を飛ばし、八王子インターチェンジで降りて手ごろなラブホテルに入るのだが、今日は山手通りを南下する。五反田を通ったのはわかったが、その後、どこを走っているのかわからなくなった。
車が着いたのは大きな日本旅館風の建物の前だった。母屋に行って彼が声をかけると、凛とした感じの着物姿の老女が出てきた。「大浴場はもう沸かしてなくて、離れのお風呂だけなのですが、よろしいですか?」「ええ、けっこうです」というやり取りが聞こえる。
鍵をもらった彼について木戸をくぐる。すでに暗くなっていたが、そこが広い庭になっていることがわかった。緩い石段を上りながら、「順子は、こういう昔ながらの『連れ込み旅館』って来たことないだろう。しかも、ここは部屋が離れなんだよ」と彼が説明してくれる。
そして、することをした翌朝、身支度を整えて「離れ」から外に出て、思わず「わーっ」と声を出してしまった。思っていたよりずっと大きな庭だった。緑の木々に囲まれ、そこここに躑躅(つつじ)が植えられ赤や白の花をつけている。その間に黒っぽい岩塊があちこちに置かれている。それが溶岩であることは、地学少年だった私にはわかる。
彼は「朝、出るとき、鍵を返してね」と言って深夜に帰っていった。まあ、いつものことだ。母屋に行って「おはようございます。鍵を返しに来ました」と声をかけると、まだ9時前なのにあの老女がきちんと着物を着て出てきた。
「お支払いは済んでおります」
「あの~ぉ、ちょっとお尋ねしますが、ここはどこなんでしょうか? 最寄りの電車の駅はどちらでしょうか?」
「ここは大田区の石川町という所です。門を出て左に行ってすぐの道を下って行けば東急池上線の石川台の駅に出ます」
「あっ、なるほど、ありがとうございます」
お礼を行って出ようとしたら、
「ちょっと、お嬢さん」
と呼び止められた。
「余計なお世話かもしれませんが、あなた、こういう遊びをしているのなら、自分がどこにいるかくらい、わかっていないといけませんよ」
「まことにごもっともです」なのだが、思いがけずいきなりのお説教に、私は口ごもる。
私の戸惑いを察知したのか、老女の顔が少し和らぎ、口調がやさしくなった。
「ここ、もうずいぶん古いのですけど、あと半年ほどで閉めるんですよ」
「閉めちゃうんですか、すてきなお庭なのに」
「手入れがたいへんでね。昔はお風呂も売りものだったのですけど、ボイラーが壊れてしまって」
「残念ですね」
「あと半年の内に、機会があったら、またおいでください」
「はい」
それは1994年4月の終わり頃のことだったと思う。それから6年ほど経って、私は国会図書館の新聞閲覧室で『日本観光新聞』のマイクロフィルムを閲覧していた。
「性転換の社会史」という論文の執筆のために1950年代の「性転換」の記事を探していたのだが、たまたま紙面の下の方にある広告が目に止まった。

「城南の箱根 思い出の緑風園 池上線石川台下車三分」
「あっ、あそこだ!」
小声だけども、思わず叫んでしまった。
そう気づくと、「緑風園」と同類の「連れ込み旅館」の広告がたくさん載っている。「これは面白い材料(資料)になる」、私は直感した。

1963年頃の「緑風荘」。左側に主屋、中間に広い庭、右寄りに離れが点在する。

跡地には巨大なマンション「プレステート石川台」(7階建、102戸、1996年3月)が建った。
1 「連れ込み旅館」とはなにか
「連れ込み宿(旅館)」とはなんだろう? それには「連れ込み」という言葉から考えないといけない。まず、1つ目の意味として、街娼(ストリート・ガール)およびそれに類する女性が売春行為をするために男性を誘い導いて「連れ込む」宿のこと。2つ目として、カップルの男性が性行為のために相手の女性を「連れ込む」宿のこと。前者が玄人(くろうと)の女性が男性を「連れ込む」、後者は男性が素人(しろうと)の女性を「連れ込む」意味で、歴史的には前者から後者へと意味(ニュアンス)が転換していく(井上章一『愛の空間』第4章「円宿時代」)。
「連れ込む」主体に違いはあるが、どちらにしても、性行為を前提に「連れ込む」宿である。したがって、一般の旅館のように宿泊を必ずしも前提とせず、一時的な滞在(「ご休憩」「ご休息」)のための部屋利用が想定され、料金が設定されている点に特徴がある。
歴史的に見れば、江戸時代の茶屋で休憩室の奥に布団が敷かれている「出会い茶屋」(上野池之端に多かった)、明治以降、芸者遊びの場であり、お忍びの男女の待ち合わせにも利用された「待合」と呼ばれる施設、さらに昭和戦前期(1930年代)になると「待合」よりずっと気軽に安価に(1人1円)利用できるは「円宿」(えんじゅく)が都市部に出現する。また戦後の混乱期、「パンパン」と呼ばれた街娼が多かった時代には、彼女たちが進駐軍(主に米軍)兵士を連れ込む「パンパン宿」が盛り場の周辺にたくさんあった。「連れ込み旅館」はこうした系譜に連なるもので、戦後の社会的混乱が一段落した1950年代中頃に急増する。
2 「東京『連れ込み旅館』広告データベース(1953~1957年)」を作る
さて、『日本観光新聞』の調査で「連れ込み旅館」の広告の存在に気づいた私は、その後、『内外タイムス』の調査で、さらに大量の「連れ込み宿」広告に出会うことになる。そして、本筋の調査の傍ら、「連れ込み旅館」広告が載っている頁もコピーしていった。
ちなみに『日本観光新聞』も『内外タイムス』も、政治、経済、芸能、スポーツ、そして性風俗を網羅した軟らか系の新聞で、イメージとしては現代の『夕刊フジ』や『日刊ゲンダイ』に近い。
そんな経緯で収集し始めた「連れ込み旅館」広告だが、性風俗関係の頁に広告を出していること、料金設定が「お二人様(御同伴)」で「休憩(休息)」であることの2点を条件に『内外タイムス』と『日本観光新聞』から抽出したところ、1953~57年(昭和28~32)の5年間で690点の広告が集まった。それを整理して「東京『連れ込み旅館』広告データベース(1953~1957年)」を作成した
旅館の軒数にすると385軒。場所が異なる「別館」は1軒にカウントしてある。
完璧とは言わないが、かなりの程度、網羅していると思う。これだけの材料があれば、当時の東京の「連れ込み旅館」の様相は十分にうかがえるだろう。
3 その分布
まず、「連れ込み旅館」の分布から見てみよう。
【エリア別集計】
都心エリア( 85軒)
城西エリア(125軒)
城南エリア(106軒)
城北エリア( 60軒)
城東エリア( 9軒)
【集中地域(5軒以上)】
千駄ヶ谷(39軒)
渋谷(32軒)
新宿(31軒)
池袋(21軒)
大塚(12軒)
代々木(11軒)
新橋・芝田村町(11軒)
長原・洗足池・石川台(10軒)
高田馬場(8軒)
銀座(7軒)
原宿(7軒)
五反田(7軒)
大井町(7軒)
大森・大森海岸(7軒)蒲田(7軒)
新大久保・大久保(6軒)
飯田橋・神楽坂(5軒)
浅草(5軒)
赤坂見附・山王下(5軒)
エリア別の割合は、城西エリア32%、城南エリア28%、城北エリア16%、都心エリア22
%、城東エリア2%で、東京区部の西と南、つまり(拡大)山の手地区に多く、東の下町地区は極端に少なくなっている。
城西エリア(125)では千駄ヶ谷(39)が都内最大の集中地域で、新宿(31)、代々木(11)がそれに次ぐ。代々木は新宿と千駄ヶ谷の間で両者をつなぎ、巨大な「連れ込み旅館」ベルトを形成している。
城南エリア(106)は渋谷(32)に顕著に集中し、離れて長原・洗足池・石川台(10)が次ぐ。
都心エリア(85)は新橋・芝田村町(11)が多いが、他は分散的である。後にラブホテルの集中地域になる湯島は坂上に2軒、天神下に2軒でまだ集中傾向はない。現在、東京最大のラブホテル密集地域の鶯谷は2軒だけで目立っていない
城北エリア(60)は池袋(21)とその東の大塚(12)に集まっている。大塚は「花街」(三業地)からの転身である。
ほとんど広告がない城東地区(9)は、やはり後にラブホテルが集中する錦糸町もまだ2軒だけだ。
さらに細かく、鉄道沿線別に見てみる(都心は区別)。
都心エリア(85軒)
【千代田区】(9)
神田(鍛冶町)(1)秋葉原(1)御茶ノ水(3)神田小川町(2)神田神保町(1)九段下(1)
【中央区】(15)
銀座(7)築地(1)日本橋(1)人形町・浜町(4)東京駅八重洲(2)
【港区】(25)
新橋(6)芝田村町(5)虎の門(1)神谷町(1)浜松町(1)田町(2)芝公園(1)坂見附(2)赤坂山王下(3)麻布霞町(1)麻布竜土町(1)青山一丁目(1)
【台東区】(20)
御徒町(3)上野池ノ端(3)根津八重垣町(1)上野桜木町(1)鶯谷(2)下谷坂本町二丁目(3)蔵前(1)浅草(5)浅草橋場(1)
【文京区】(8)
湯島天神下(2)湯島(2)本郷真砂町(1)小石川柳町(1)白山(本郷肴町)(1)小日向(石切橋)(1)
【新宿区】(8)
飯田橋・神楽坂(5)市ヶ谷新見附(1)牛込矢来町(1)四谷荒木町(1)
城西エリア(125軒)
【国電山手線】
高田馬場(8)新大久保・大久保(6)新宿(31)原宿(7)
【国電中央線】
千駄ヶ谷(39)東中野(1)中野(1)高円寺(1)阿佐ヶ谷(2)吉祥寺(2)
【小田急線】9
参宮橋(3)代々木八幡(1)代々木上原(1)下北沢(1)登戸(2)向ヶ丘遊園前(1)
【京王本線】
幡ヶ谷(1)明大前(2)高井戸(2)調布(1)
【京王井の頭線】
浜田山(1)
城南エリア(106軒)
【国電山手線】
渋谷(32)恵比寿(1)目黒(4)五反田(7)
【東急東横線】(16)
代官山(1)中目黒(1)都立大学(1)自由が丘(3)多摩川園(1)新丸子(4)武蔵小杉(2)元住吉(2)大倉山(2)
【東急大井町線】
二子玉川(1)二子新地(1)高津(1)
【東急目蒲線】
目黒不動前(1)鵜の木(1)
【東急池上線】
長原・洗足池・石川台(10)雪ヶ谷大塚(1)千鳥町(2)久ヶ原(1)池上(1)
【国電京浜東北線】
品川(3)大井町(7)大森(5)蒲田(7)川崎(1)鶴見(1)
【京浜急行】
大森海岸(2)
城北エリア(60軒)
【国電山手線】
目白(2)池袋(21)大塚(13)巣鴨(4)駒込(2)田端(1)日暮里(3)
【国電京浜東北線】
王子(1)東十条(1)赤羽(1)川口(1)北浦和(1)大宮(3)
【国電赤羽線】
板橋(1)
【国鉄常磐線】
三河島(1)北千住(1)
【東武東上線】
大山(1)常盤台(1)
【西武池袋線】
桜台(1)
城東エリア(9軒)
【国電総武線】
錦糸町(2)亀戸(1)平井(2)新小岩(1)小岩(1)船橋(1)
【東武鉄道】
玉ノ井(1)
鉄道沿線で見ると、都心から西に延びる幹線である中央線沿線は、御茶ノ水、飯田橋・神楽坂に始まり、最大の集中地区である千駄ヶ谷、代々木、新宿、大久保、東中野、中野、高円寺、阿佐ヶ谷とほぼ連続的に立地し、この沿線の需要が高かったことがうかがえる。
山手環状線の駅もほぼまんべんなく立地し、確認できないのは有楽町駅と大崎駅だけである(西日暮里駅はまだない)。大崎は工場地帯や電車区があり駅周辺の開発が遅れていたので仕方がないだろう。
城西、城南エリアはかなり郊外まで分布が伸びている。東急目蒲線の鵜の木、東急東横線の新丸子、武蔵小杉、東急大井町線の二子多摩川、二子新地、小田急線の登戸など、多摩川の河川交通と陸上の街道との結節点に発達した花街に立地しているのは興味深い。
また、地区別の上位が国電山手線・中央線沿線で占められている中で、唯一の私鉄である東急池上線沿線の長原・洗足池・石川台(10)が目立つ。私が泊まった石川台の「緑風園」もこの地区に含まれる。
4 分布から見えるもの ―西の「連れ込み旅館」、東の「赤線」―
1953~1957年の東京の「連れ込み旅館」の分布で、最も注目すべきは、城東エリアの極端な少なさだろう。
全体のわずか3%、区部で広告が確認できるのは、江東区2軒(錦糸町)、墨田区1軒(向島)、葛飾区1軒(新小岩)、江戸川区2軒(平井、小岩)、足立区1軒(北千住)の7軒に過ぎない。
広告が確認できないからまったく「連れ込み旅館」がなかったとは言えないが、少なくとも広告を出すほど経営意欲がある「連れ込み旅館」はきわめて少なかった。
その理由を推測すれば、単純に需要が少なかったから、と思われる。
性行為の場として、「連れ込み旅館」を考えた場合、その需要、利用形態は次のように推定される。
① 街娼(一部の芸妓や女給を含む)など「売春」を業とする女性が客の男性を「連れ込む」。
② 男性が、芸妓、女給さらには、素人など「売春」を業としない女性を口説いて「連れ込む」。
③ 住宅事情など、自宅でSexする環境に恵まれていない夫婦や恋人同士が利用する。
この内、①は、街娼からすると「連れ込み宿」の料金が高すぎ、経営者側からすると売春行為を禁止した「東京都売春取締条例」(1949年5月31日制定)の「場所提供」に違反することから、主流ではなかったと思われる。
つまり、「連れ込み宿」の需要は②③、さらに言えば②が中心だった。

千駄ヶ谷駅ホームのアベック(『週刊東京』1956年5月12日号)

千駄ヶ谷駅前の立て看板(『週刊東京』1956年5月12日号)

千駄ヶ谷・羽衣苑に入る男女(『週刊サンケイ』1957年3月10日号)
梶山季之『朝は死んでいた』(1960年『週刊文春』に連載)で殺人犯に仕立てられる主人公のように、都心の会社に通うサラリーマンで、銀座、次いで新宿の盛り場で飲んで、女性(女給やBG)を口説いて、千駄ヶ谷あたりの旅館に連れ込んでSexする男たちだ。
彼らのようなサラリーマンの自宅は、都心から西の新宿や、南の渋谷から、さらに西に延びる私鉄沿線に多く、東側には少なかった。千駄ヶ谷、新宿、渋谷が「連れ込み旅館」の密集地であり、そこを起点とする私鉄沿線に連続的に分布するのは、彼らの需要があったからだ。東京の「連れ込み旅館」の分布がサラリーマンの自宅の立地と性行動のパターンと深く関係していることは間違いないと思う。
では、「連れ込み旅館」が少ない東京の東側の男たちはどうしていたのだろうか?
この時期は「赤線」があった時代だ、「赤線」とは1946年12月~1958年3月末に存在した黙認買売春地帯である。警察が地域を限って「特殊飲食店」の営業を許可し、そこで働く女給が客と自由恋愛の末に性行為をし、プレゼントとしてお金をもらうという建前を警察が黙認することで成り立っていた。
東京区部には13カ所の「赤線」が存在していたが、その分布は、「連れ込み旅館」とはまったく逆で、城西、城南エリアに少なく、城東エリアに圧倒的に多かった。
都心エリア なし
城西エリア 1カ所(新宿区:新宿二丁目)
74軒 従業婦477人(1952年末)
城南エリア 2カ所(品川区:北品川、大田区:武蔵新田)
45軒 従業婦185人
城北エリア 1カ所(台東区:新吉原)※
313軒 従業婦1485人
城東エリア 9カ所(墨田区:玉の井・鳩の街、江東区:洲崎・亀戸、葛飾区:新小岩・亀有・立石、江戸川区:東京パレス、足立区:千住柳町)
710軒 従業婦2307人
(※)新吉原は行政区分は台東区なので、この報告では都心エリアに分類されるが、かつて「北里(ほくり)」と通称されたように、江戸・東京の地理感覚では城北エリアとした方が実態的だと思う。
こうした分布から、東京の東側の男たちの性行為の場は圧倒的に「赤線」で、「連れ込み旅館」の需要は少なかったと推測される。下町の伝統的な花街、たとえば深川(門前仲町)などには芸妓と客の性行為の場としての「待合」のような施設があったが、それは「連れ込み旅館」の広告には現れていない。
つまり、性行為の場として、「赤線」と「連れ込み旅館」は対置関係にあった。実際、新吉原、洲崎、玉の井、鳩の街、そして新宿二丁目など規模の大きな「赤線」の周囲には「連れ込み旅館」はほとんど立地しない。需要がないからだ。
「赤線」と「連れ込み旅館」が対置関係にあったということは、裏を返せば、両者は補完関係にあったということだ。
極言すれば、東京には「赤線」に行って女給(実態は娼婦)を買ってSexする男(商店主・職人・工員など)と、BGやクラブの女給(後のホステス)を口説いて「連れ込み旅館」に連れ込んでSexする男(会社員が中心)の2タイプがいた。前者のタイプは東京の東半分に多く、後者のタイプは西半分に多く住んでいたと思われる。
東京においては、少なくとも1950年代までは、性行為の文化が地域によってかなり異なっていたことが浮かび上がってきた。「赤線」と「連れ込み旅館」の補完関係は1958年3月の「赤線」廃止(「売春防止法」の完全施行)によって崩壊する。その後、こうした性行為の地域性がどう変化していったのか? 今後の課題としたい。
5 その設備
次に、広告にあらわれた「連れ込み旅館」の設備について見てみよう。
(1)建築様式
「数寄屋造り、離れ家式」(おほた:千駄ヶ谷)
「古代桂を偲ばせる 城北に誇る新日本風数寄屋造りの静かな旅荘」(浮月:池袋)
「全荘離家式、数寄屋造り」(三越:千駄ヶ谷)
「全室離式 那知廊下伝」(川梅:蒲田)←「那知(智)廊下」って何?
「純洋室高級ベッド完備」「別館数寄屋造り」
(大久保ホテル:新大久保・大久保)
「歌舞伎調スタイル」(音羽:蒲田)
「各室歌舞伎調好み」(龍美:目黒) ←「歌舞伎調」とは具体的に?
「歌舞伎」(原宿)という旅館もある
建築様式は、圧倒的に数寄屋造り・離れ家式が好まれている。洋室主体のホテルも、数寄屋造りの別館を増築する。コンセプトは高級&和風である。


若水(池袋:19571206) 夕月荘(大塚:19540305k)


紅屋(池袋:19540319k) 可悦(高田馬場:19571229)
(2)基本設備
「和洋各室、離式・風呂・トイレ・電話付」(深草:千駄ヶ谷)
「トイレ 風呂 ラジオ 電話付」(夕月荘:大塚)
「新装開店 各室共外線直通電話 ラジオ設備」(成光館:飯田橋:1955年6月)
基本設備は、各室に風呂、トイレ、そして電話である。それにラジオが加わる。
(3)鏡
「鏡風呂」「鏡の間」(利女八:阿佐ヶ谷)
「鏡風呂(四面鏡)」(川梅:蒲田)
「鏡天上」(ほていや:高田馬場) →「天上」は「天井」の誤り
「鏡風呂・鏡部屋」(天竜:大井町)
井上章一『愛の空間』(角川選書、1999年)が、ラブホテルのインテリアの特徴としている「鏡」だが、広告にはあまり現れない。「鏡部屋」「鏡天井」「鏡風呂」が存在したのは確実だが、普及度はまだ今一つだったと思われる。

川梅(鎌田:19530107)
(4)テレビ
「テレビ各室」(みやこホテル:参宮橋:1956年3月)
「各室テレビ・バス・トイレ・電話付」(京や:代々木:1956年12月)
テレビは、1956年3月の参宮橋「みやこホテル」の広告が最初。1956年は、まだNHK総合+民放2社の時代で、世の中は「街頭テレビ」の時代。「各室テレビ」はとても贅沢で画期的だと思う。

みやこホテル(参宮橋:19560304)
(5)暖房
(こたつ)
「温かなコタツを用意して」(紫雲荘:五反田:1953年9月)
「全室おこたの用意が出来ました」(夕月荘:大塚:1953年9月)


夕月荘(大塚:19540305k) ホテルしぐれ荘(大森・19550213)
(スチーム暖房)
「スチーム暖房完備」(ホテル・スワニー:高田馬場:1953年3月)
「冬知らぬ スチーム暖房」(みやこホテル:参宮橋:1954年11月)
「初夏の宿 スチーム暖房」(山のホテル:渋谷:1954年12月)
「各部屋スチーム暖房」(かすみ荘:千駄ヶ谷:1955年2月)
「全館スチーム暖房 お部屋は小春の暖かさ」(白樺荘本館:千駄ヶ谷:1956年1月)

山のホテル(渋谷:19541207)
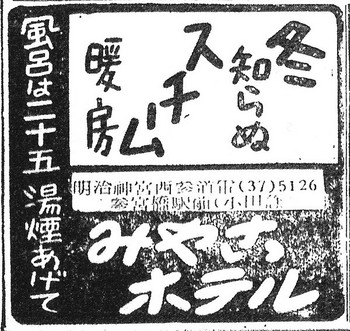
みやこホテル(参宮橋:19550213)
暖房は、炬燵からスチーム暖房へという流れ。スチーム暖房の初見は1953年春で、1955~56年の冬にはかなり普及した様子がうかがえる。
(6)冷房
(扇風機)
「各室、離家式 電話、扇風機付」(御苑荘:千駄ヶ谷:1953年9月)
「各室バス付 扇風機」(山のホテル:渋谷:1954年8月)

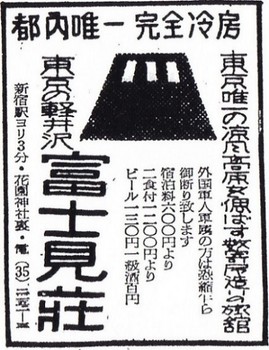
紅屋(池袋:19540813k) 富士見荘(新宿区役所通り:19550819k)
(クーラー)
「涼味みなぎる 完全冷房店」(富士見荘:新宿区役所通り:1955年7月)
「完全冷房」(玉荘:千駄ヶ谷:1956年7月)
冷房は、扇風機からクーラーへという流れだが、暖房に比べると転換は遅い。「冷房」の広告上の初見は、1955年夏の新宿「富士見荘」。他にも千駄ヶ谷の高級旅荘「玉荘」のみ。普及は1960年代になってからと思われる。
(7)風呂
(形状)
「岩風呂」(福住:鶯谷)(やまと:桐ケ谷)(可悦:高田馬場)(大洋:渋谷)(天竜:大井町)(高津ホテル:高津)(ホテル赤坂:赤坂)(葵:大塚)(寿美吉:大塚)(緑風園:池上石川台)(福田屋:登戸)(トキワホテル:日暮里)(みやこ:目白)
「岩戸風呂」(東洋荘:渋谷)(のぼりと館:向ケ丘遊園前)
「穴風呂」(緑風園:池上石川台)
「滝風呂」(すずきや:代々木)(大洋:渋谷)(白梅:船橋)(洗足池旅館:池上洗足)
「寝風呂」(藤よし:駒込)
「寝台風呂」(筑波旅館:恵比寿)
「舟風呂」(東洋荘:渋谷)
「水族館付き舟風呂」(黒岩荘:渋谷)
「屋形風呂」(川梅:蒲田)
「数寄屋風呂」(鶴栄:大塚)
「数寄屋造りのロマンス風呂」(城北閣:池袋)
「瓢箪風呂」(二幸:渋谷)
「扇風呂」(東芳閣:池袋)
「末広風呂」(香川:大塚)
「ダルマ風呂」(夕月荘:大塚)
「鏡風呂」(川梅:蒲田)(利女八:阿佐ヶ谷)(天竜:大井町)
「大理石風呂」(菊富士松韻亭:原宿)
「大理石のパール風呂」(藤よし:駒込)
「風趣あふれる京の竈風呂」(御苑荘:千駄ヶ谷)
「むし風呂」(ピースホテル:大塚)
「スポンジ風呂」(ほていや:高田馬場)(のぼりと館:向ケ丘遊園前)
(立地)
「露天岩風呂」(深山荘:千駄ヶ谷)
「露天大岩風呂」(照の家:池上長原)
「若返り温泉 二階風呂」(加島屋旅館:川崎)
「階上ロマンス風呂」(旭:巣鴨)
「せせらぎの音にゆあみする優雅な川辺風呂」(大都:大井町)
(香り)
「レモン風呂」(白樺荘別館:千駄ヶ谷)(湯島荘:湯島)
「香水風呂」(高田旅館:渋谷)(飛龍閣:渋谷)(蓬莱:上野桜木町)(目白山手ホテル:目白)
「香気漂う丁子風呂」(あおば荘:白山)
「松葉風呂」(松実園:千駄ヶ谷)
(添加)
「牛乳風呂」(みやこ:新宿)(小梅荘:五反田)
「薬湯」(高津ホテル:高津)
「ホルモン風呂」(しぐれ荘:大森)
「ホルモン入葉緑素風呂」(ふじた:鵜の木)
「珪藻土入りのお風呂」(いずみ:池袋)
(数)
「二十五の湯殿」→「三十の湯殿」→「三十五の湯殿」(みやこホテル:参宮橋)
「八つの御風呂」(みすず:渋谷)
「七ツのお湯が溢れている」(山王温泉ホテル:大森)
(実態不明)
「ヨーマ風呂」(川梅:蒲田)
「金魚風呂」(きりしま:代々木)
「孔雀風呂」(永好:渋谷)
「虹風呂」(はなぶさ新館:原宿)
「ローマ風呂」(東芳閣:池袋)
「豪華なフランス風呂」(鶴栄:大塚)
「情緒あふれる浅妻風呂」(音羽:蒲田)
「ロマンス風呂」(菊半旅館:渋谷神泉)(美鈴:巣鴨)(緑風園:池上石川台)
『愛の空間』が注目しているように、風呂は、旅館にとって誘客の「目玉」であり、風呂がない家庭が多い時代の利用者にとって大きな魅力だった。広告文には実に多彩な「風呂」が現れる。岩風呂、滝風呂、鏡風呂、蒸し風呂、舟風呂、寝風呂などの形状、香水風呂、丁子風呂、レモン風呂など香り付けをしたと思われるもの、牛乳風呂、ホルモン風呂、葉緑素風呂、珪藻土風呂などなにかを添加して美容効果をねらったもの、やたらと数を増やした挙句、火事を出したホテル。一方、ロマンス風呂、虹風呂、金魚風呂、孔雀風呂など実態がよくわからないものもある。


岩風呂:やまと 滝風呂:洗足池旅館
(桐ケ谷:19540306) (池上洗足池:19531020)


滝風呂:よしみ 露天大岩風呂:照の家
(蒲田:19540813k) (池上長原:19540730k)


大岩風呂:登戸館 特に特徴のないタイル風呂:桂
(向ケ丘遊園前:19570505) (大塚:19540319k)

謎の「ヨーマ風呂」:川梅
(蒲田:19560621)
6 その立地
水辺や高台など地理的な特長、森、川、池、山などの自然のイメージを強調する広告も多い。
(1)森
「御苑の森かげに七彩の湯湧き出づる」(南風荘:千駄ヶ谷)
「鬱蒼と茂った千駄ヶ谷の森に囲まれた閑静な憩の宿」(松実苑:千駄ヶ谷)
「外苑の森に囲れた静かな皆様のお宿」(かなりや:代々木)
「緑の森 静かなお部屋」(まつかさ:千駄ヶ谷)
「目黒の森に囲まれた静かな皆様のお宿」(菊富士ホテル:目黒)
「新宿の自然境」(とみ田:新宿駅南口)
「森」は、新宿御苑や神宮外苑に隣接する千駄ヶ谷、代々木エリアの旅館に多くみられ、静寂・閑静がイメージ化される。さらに都会の俗塵を離れた自然も・・・。


まつかさ(千駄ヶ谷:19541023k) とみ田(新宿駅南口:19530731)
(2)水辺・川
「浜町河岸」(矢の倉ホテル:日本橋浜町)←隅田川
「江戸情緒豊かな隅田河畔で!」(龍村:浅草)←隅田川
「静かな川辺の宿」(杵屋:錦糸町)←堅川
「TOKYOのセーヌのほとり」(東京スターホテル:銀座)←築地川
「情緒豊かな神田川畔のお宿」(白:秋葉原)←神田川
「せせらぎの音にゆあみする優雅な川辺風呂」(大都:大井町)←立会川
「多摩川畔の静かな別荘」←多摩川(高津ホテル:高津)←多摩川
「多摩川の四季に眺める二子橋玉川堤」(幸林:二子新地)←多摩川
「多摩川の涼風が誘う」(新雪:登戸)←多摩川
「水辺・川」は、隅田川と多摩川が中心。神田川、築地川はともかく、堅川や立会川になると「川」の風情を感じるのは難しいのではないか。立会川の「せせらぎの音」はいかにも誇大広告。東京の川辺が「風流」なイメージを保てた最後の時代か。1960年代に高度経済成長期になると、川の汚濁と悪臭がひどくなり、川の埋め立て(築地川)や暗渠化(立会川)が進行する。
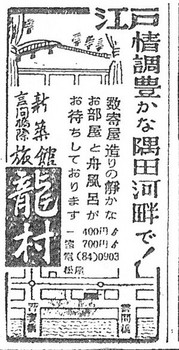

龍村 大都
(浅草:19570713) (大井町:19550410)

新雪(登戸:19570823)
(3)水辺・池
「新宿十二社池ノ上」(浮世荘:新宿十二社)
「涼風をさそう池畔の荘」(ホテル・スワニー:高田馬場)
↑ どこの池? 調べたが近隣に池はない。もしかして庭の池?
「上野不忍池畔」(かりがね荘:上野)
「静かな洗足池畔」(翠明館:池上洗足池)
「思い出の洗足池 静かな池畔の宿」(やくも:池上洗足池)
「池畔の幽緑境」(洗足ふじや:池上北千束)
「水辺・池」は、洗足池(大田区)、不忍池(台東区)、十二社弁天池(新宿区、1968年埋め立て、消滅)など。高田馬場の池は不明。とくに現在は住宅地に囲まれている洗足池が郊外の行楽地として機能していたことが興味深い。

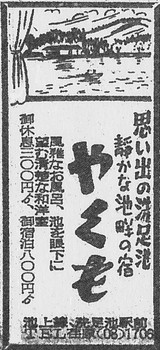
かりがね荘(上野:19561201) やくも(池上洗足池:19521007)

翠明館(池上洗足池:19530204)
(4)水辺?・水族館
「自慢の新しい水族館付き(黒岩荘:渋谷)」
なぜ「水族館」が・・・、正直言ってよくわからない。
(5)高台
「新宿歌舞伎町高台」(小町園:新宿歌舞伎町)
「高台の静けさ」(東京ホテル:新宿区役所通り)
「見晴らしのよい高台」(大洋:渋谷)
「渋谷の高台」(高田旅館:渋谷)
「高台閑静 眺望渋谷随一!」(平安楼:渋谷)
「断崖上の三層楼」(三平:渋谷)
「大塚駅北口高台」「眺望絶佳」(式部荘:大塚)
「国電田端駅高台」(清風荘:田端)
「国電日暮里駅高台西口」(喜久屋:日暮里)
「高台」の立地を強調する広告も多い。特に渋谷は道玄坂や桜丘町のように坂上、高台に「連れ込み旅館」が多く立地する。また大塚・田端・日暮里は台地と低地を分ける崖線の上に立地するものが多い。いずれも、閑静さ、眺望の良さを特長にしている。高台の立地は、次の時代の「ラブホテル」の集中域、新宿歌舞伎町二丁目、渋谷円山町、湯島などに引き継がれる。

夕月荘(大塚:19541023k)
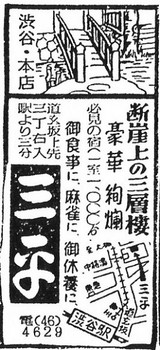

三平(渋谷:19571004) 式部荘(大塚:19560607))
(6)山・山荘
「山の中から水の音 滝の音 渓渡るせせらぎ すずしさよ」
(みやこホテル:参宮橋)
「軽井沢の元祖」「東京にある軽井沢」(旅館富士見荘:新宿区役所通り)
「静かな山荘の離れ」(ホテル ニューフジ:渋谷)
「丘の離れ、都会の山荘」(山のホテル:渋谷)
「都心の山荘」(平安楼:渋谷)
「趣味の山荘」(強羅ホテル:五反田)
「広大な芝生に立つ山荘風のホテル」(若宮荘ホテル:神楽坂)
「ロマンな憩いの山荘」(ホテル赤坂:赤坂見附)
「城南の箱根 山林峡谷 2千坪に点在する離れ家」(緑風園:池上石川台)
「東京の箱根 もずの声 ここは都のなかか 山の里」(緑風園:池上石川台)
山の手エリアには「山・山荘」のイメージを強調する広告が多い。中には軽井沢(長野県)や箱根(神奈川県)などの高級別荘・山荘とイメージを重ねているものもある。
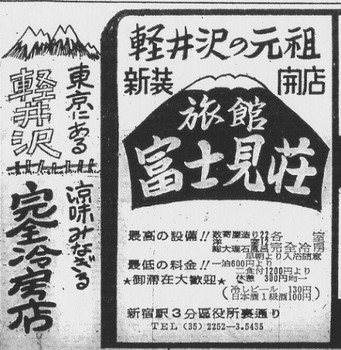
「東京にある軽井沢」富士見荘(新宿区役所通り:19550721)

山荘のイメージ「ホテル ニューフジ」(渋谷:19540508)


山のホテル(渋谷:19550702) 緑風園(池上石川台:19570130)
7 そのイメージ
「連れ込み旅館」の広告は、集客のために様々イメージを作り出している。それは,良く言えば豊かなイメージの喚起であるが、悪く言えばイメージの捏造であり、現代の感覚(法規)からしたら、誇大広告の批判を免れない。
(1)温泉偽装・温泉詐称・有名温泉への仮託
「東京唯一の天然温泉」(山水荘:亀戸) ← 「亀戸温泉」は実在
↓ 以下はずべて偽装・詐称
「温泉ホテル」(ホテル自由ヶ丘:自由ヶ丘)
「山王温泉ホテル」「温泉情緒」(山王温泉ホテル:大森)
「地下温泉」(二幸:渋谷)
「渋谷にも温泉出現」(菊半旅館:渋谷神泉)
「都心の温泉郷」(あぽろ旅館:九段下)
「銀座温泉 憩いの出湯」(せきれい荘:銀座)
「不忍温泉」(かりがね荘:上野)
「鶯谷温泉」(福住・鶯谷)
「巣鴨温泉」(三晴:巣鴨)
「東郷台温泉」(はなぶさ新館:原宿)
「温泉気分」「湯湧き出ずる」などのように文章の雰囲気で温泉イメージを喚起する広告は多い。さらに「銀座温泉」「鶯谷温泉」「(上野)不忍温泉」「巣鴨温泉」「(大森)山王温泉」「(原宿)東郷台温泉」など、明らかな温泉を詐称する旅館もある。
当時の法律(1948年7月10日制定の「温泉法」)では、温泉は源泉温度25度以上で有効な成分をもつもの、とされており、東京区部にはそれに適合する温泉はなかった。ただし、城南地区(港区、大田区、品川区、世田谷区など)には「黒湯」と呼ばれる25度以下だが有効成分を含む「鉱泉」が分布する。


山水荘 山王温泉ホテル
(亀戸:19530204)(大森:196560222)


あぽろ旅館 せきれい荘
(九段下:19541219)(銀座:19550702)
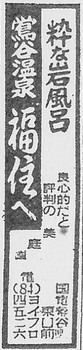
福住
(鶯谷:19560107)
(有名温泉地への仮託)
「都内で湯河原の気分を!」(芳川:市ヶ谷新見附)
「熱海」(熱海:池上洗足池)
「京浜の熱海」(東横ホテル:武蔵小杉)
「京浜の箱根」(菊家ホテル:武蔵小杉)
「東京の箱根」(富士屋ホテル:代々木)
「郊外の箱根」(錦:高井戸)
「城北の箱根」(荒川荘:三河島)
「城南の箱根」「東京の箱根」(緑風園:池上石川台)
「箱根気分を上原で」(鶴家:代々木上原)
「新箱根」(新箱根:板橋)←方向が違う!
「タッタ30分で箱根の気分」(いずみ荘:大宮)←方向が違う!
「強羅ホテル」(強羅ホテル:五反田)
「渋谷の衣川(鬼怒川)」(黒岩荘:渋谷)
「城北の水上」(目白文化ホテル:目白)
「九州の地 別府温泉を偲ばせる」(別府:代々木)
「東京の谷間 幽境霧島を偲ぶ閑静さ」(きりしま:代々木)
温泉偽装・詐称との関連で、「城南の箱根」「京浜の熱海」のように、箱根(神奈川県)、熱海(静岡県)、湯河原(神奈川県)、水上(群馬県)、鬼怒川(栃木県)、別府(大分県)、霧島(鹿児島県)などの有名温泉地とイメージを重ねる広告が見られる。
とくに箱根温泉は人気で、城北(三河島)、城南(石川台)などあちこちに「箱根」があった。中には板橋のように明らかに方向が違うものも。東急東横線の武蔵小杉などは「京浜の熱海」と「京浜の箱根」と「いったいどっちなんだ?」と言いたくなる。さらに、有名温泉地をそのまま旅館の名にしたものもあり、五反田には「強羅温泉」が、洗足池には「熱海」が、代々木には「別府」「きりしま」があった。


荒川荘 緑風園
(三河島:19541113)(池上石川台:19521007)


東横ホテル 菊家ホテル
(武蔵小杉:19561205)(武蔵小杉:19540302)


黒岩荘 別府
(渋谷:19570204) (代々木:19550109)

ホテルきりしま
(代々木:19570130)
(2)温泉マークの使用
典型的な温泉マーク


熱海(池上洗足池:19530403k) 多ま木(新宿:19530918k)
デザイン化された温泉マーク

大久保ホテル(新大久保・大久保:19550115)

ホテル明光(品川:19530925k)
広告文での温泉マークの使用は、1953年が多く、1954年半ばまででほぼ納まる(例外は1955年3月の「川梅」)。1955年4月以降の使用例は見られない。当時、温泉マークの乱用が問題視されており、1954年半ば頃に、なんらかの規制(自粛)が行われた可能性が高い。
(3)なぜか南国(椰子の木、ラクダ)
なぜか、南の国のイメージを絵にしている広告が2つある。モチーフはいずれもラクダと椰子の木。
「南風荘」は、その名称からだろう。「エデン」の園は、アルメニア付近にあてるのが通説で、エジプトではないと思う。


南風荘(千駄ヶ谷:19530731) エデンホテル(目白:19531016k)
(4)文化人・インテリ・旧華族
「文化人好みの画廊スタイル」(強羅ホテル:五反田)
「モダンクラッシックの文化人スタイル」(ホテル山王:渋谷)
「インテリ層の憩の宿」(ホテルおしどり:大森)
「旧徳大寺公邸です」(光雲閣:代官山)
「文化人」「インテリ」を強調した広告が散見され、ターゲットにした顧客層がうかがえる。
『愛の空間』には、戦後の社会変動や財産税などで手放された「没落階級の屋敷を再利用したものが多かったらしい」と記されているが、広告から確認できるのは、渋谷区代官山の徳大寺公爵邸を転用した「光雲閣」のみ(現在も同地に「光雲閣ビル」がある)。


強羅ホテル ホテル山王ホテル
(五反田:19560730) (渋谷:19540728)

おしどり(大森:19560607)

光雲閣(代官山:19540428)
8 「連れ込み旅館」の機能 ―むすびに代えて―
「連れ込み旅館」は、その立地や設備からして、庶民(と言っても、貧困層ではなく中間層)にとって、日常を離れた特別な場だった。
その背景には、戦後の混乱期から抜け出し、飢える心配こそなくなったものの、狭い家に住み、ほとんどの家にテレビや冷暖房(クーラー、スチーム)はなく、多くの家に風呂や電話がない住環境がベースにある。
つまり、「連れ込み旅館」は、日常の延長上のワンランク、ツーランク上の住環境を一時であっても手に入れ、Sexを楽しむ場所だった。
ここで重要なのは、日常の延長上であることだ。「数寄屋造り」にしろ「離れ家」にしろ、「連れ込み旅館」はあくまでも和風の贅沢環境であり、豪華なベッドがあるような洋風の住環境ではなかった。おそらく、当時の日本人カップルは、まだベッドでは落ち着いてSexができなかったのではないだろうか。
「連れ込み旅館」の(1室2人)休憩400~500円、泊り800~1000円という料金は、約15倍すると現代の貨幣価値に近づく。つまり、休憩6000~7500円、泊り12000~15000円ということになり、けっして安くはない。それだけの価値があったということだ。
あるいは、箱根や熱海の温泉に2人で旅行したくても、金銭的・状況的に難しいカップルにとって、疑似的であっても「連れ込み旅館」で温泉気分を楽しみことは、十分にお金を払う価値があることだったと思う。
ところが、1960年代後半、日本社会が高度経済成長期に入り、住環境の改善が進み、また生活の洋風化が進むと、「連れ込み旅館」を支えていた背景が変化してくる。
中間層の多くの家にお風呂が備えられ、電話やテレビが設置され、裕福な家には床の間・床柱のある数寄屋造り風の和室が設けられ、そこが夫婦の寝室になる。
そうなると、和風の特別な環境(Sexの場)である「連れ込み旅館」の意味が薄らいでいく。そして、次の時代(1970年代)のカップルが求めるのは、洋風な特別な環境(Sexの場)になる。
「連れ込み旅館」から「ラブホテル」への「進化」はそうして進行していった。
【備考】
広告図版の8桁の数字は、掲載年月日を示す。
末尾にkがついているのは『日本観光新聞』、他はすべて『内外タイムス』。
【文献】
梶山季之『朝は死んでいた』(文藝春秋、1962年)←小説
佐野 洋『密会の宿』
(アサヒ芸能出版、1964年、 『講談倶楽部』連載は1962年、後に徳間文庫、1983年)←小説
保田一章『ラブホテル学入門』(晩聲社、ヤゲンブラ選書、1983年)
花田一彦『ラブホテル文化誌』(現代書館、1996年)
井上章一『愛の空間』(角川選書、1999年)
鈴木由加里『ラブホテルの力 ―現代日本のセクシュアリティ―』(廣済堂ライブラリー、2002年)
金 益見『ラブホテル進化論』(文春新書、2008年)
金 益見『性愛空間の文化史』(ミネルヴァ書房、2012年)
【追記】
2020年5月5日 「データベース」の改訂に伴い、データを修正。
この論考は、明治大学文学部の平山満紀教授が主催する「セクシュアリティ研究会」(第2回:2018年08月11日)で発表したものである。
(さらに、その原形は、2011年10月29日の井上章一先生主催の「性欲研究会」で報告)
私の「連れ込み旅館」研究のベースになる報告だが、1年半が経っても、活字にしてくれる所はなさそうなので、原稿化して、このアーカイブに載せておく。
引用される際には、著者名と、この記事のURLを注記していただきたい。
【目次】
はじめに ―思い出―
1 「連れ込み旅館」とはなにか
2 「東京『連れ込み旅館』広告データベース(1953~1957年)」を作る
3 その分布
4 分布から見えるもの ―西の「連れ込み旅館」、東の「赤線」―
5 その設備
(1)建築様式 (2)基本設備 (3)鏡 (4)テレビ (5)暖房 (6)冷房 (7)風呂
6 その立地
(1)森 (2)水辺・川 (3)水辺・池 (4)水辺?・水族館 (5)高台 (6)山・山荘
7 そのイメージ
(1)温泉偽装・温泉詐称・有名温泉への仮託 (2)温泉マークの使用 (3)なぜか南国
8 「連れ込み旅館」の機能 ―むすびに代えて―
----------------------------------------------------------------
1950年代東京の「連れ込み旅館」について
―「城南の箱根」ってどこ?―
三橋順子(性社会文化史研究者)
はじめに ―思い出―
「今日はちょっと面白いところに連れてってあげるよ」
運転席の彼が言う。
新宿で待ち合わせて、いつもはユーミン(荒井由実=松任谷由実)の「中央フリーウェイ」の歌詞そのままに、右手に競馬場(府中の東京競馬場)、左手にビール工場(サントリー 武蔵野ビール工場)を見ながら中央自動車道を飛ばし、八王子インターチェンジで降りて手ごろなラブホテルに入るのだが、今日は山手通りを南下する。五反田を通ったのはわかったが、その後、どこを走っているのかわからなくなった。
車が着いたのは大きな日本旅館風の建物の前だった。母屋に行って彼が声をかけると、凛とした感じの着物姿の老女が出てきた。「大浴場はもう沸かしてなくて、離れのお風呂だけなのですが、よろしいですか?」「ええ、けっこうです」というやり取りが聞こえる。
鍵をもらった彼について木戸をくぐる。すでに暗くなっていたが、そこが広い庭になっていることがわかった。緩い石段を上りながら、「順子は、こういう昔ながらの『連れ込み旅館』って来たことないだろう。しかも、ここは部屋が離れなんだよ」と彼が説明してくれる。
そして、することをした翌朝、身支度を整えて「離れ」から外に出て、思わず「わーっ」と声を出してしまった。思っていたよりずっと大きな庭だった。緑の木々に囲まれ、そこここに躑躅(つつじ)が植えられ赤や白の花をつけている。その間に黒っぽい岩塊があちこちに置かれている。それが溶岩であることは、地学少年だった私にはわかる。
彼は「朝、出るとき、鍵を返してね」と言って深夜に帰っていった。まあ、いつものことだ。母屋に行って「おはようございます。鍵を返しに来ました」と声をかけると、まだ9時前なのにあの老女がきちんと着物を着て出てきた。
「お支払いは済んでおります」
「あの~ぉ、ちょっとお尋ねしますが、ここはどこなんでしょうか? 最寄りの電車の駅はどちらでしょうか?」
「ここは大田区の石川町という所です。門を出て左に行ってすぐの道を下って行けば東急池上線の石川台の駅に出ます」
「あっ、なるほど、ありがとうございます」
お礼を行って出ようとしたら、
「ちょっと、お嬢さん」
と呼び止められた。
「余計なお世話かもしれませんが、あなた、こういう遊びをしているのなら、自分がどこにいるかくらい、わかっていないといけませんよ」
「まことにごもっともです」なのだが、思いがけずいきなりのお説教に、私は口ごもる。
私の戸惑いを察知したのか、老女の顔が少し和らぎ、口調がやさしくなった。
「ここ、もうずいぶん古いのですけど、あと半年ほどで閉めるんですよ」
「閉めちゃうんですか、すてきなお庭なのに」
「手入れがたいへんでね。昔はお風呂も売りものだったのですけど、ボイラーが壊れてしまって」
「残念ですね」
「あと半年の内に、機会があったら、またおいでください」
「はい」
それは1994年4月の終わり頃のことだったと思う。それから6年ほど経って、私は国会図書館の新聞閲覧室で『日本観光新聞』のマイクロフィルムを閲覧していた。
「性転換の社会史」という論文の執筆のために1950年代の「性転換」の記事を探していたのだが、たまたま紙面の下の方にある広告が目に止まった。

「城南の箱根 思い出の緑風園 池上線石川台下車三分」
「あっ、あそこだ!」
小声だけども、思わず叫んでしまった。
そう気づくと、「緑風園」と同類の「連れ込み旅館」の広告がたくさん載っている。「これは面白い材料(資料)になる」、私は直感した。

1963年頃の「緑風荘」。左側に主屋、中間に広い庭、右寄りに離れが点在する。

跡地には巨大なマンション「プレステート石川台」(7階建、102戸、1996年3月)が建った。
1 「連れ込み旅館」とはなにか
「連れ込み宿(旅館)」とはなんだろう? それには「連れ込み」という言葉から考えないといけない。まず、1つ目の意味として、街娼(ストリート・ガール)およびそれに類する女性が売春行為をするために男性を誘い導いて「連れ込む」宿のこと。2つ目として、カップルの男性が性行為のために相手の女性を「連れ込む」宿のこと。前者が玄人(くろうと)の女性が男性を「連れ込む」、後者は男性が素人(しろうと)の女性を「連れ込む」意味で、歴史的には前者から後者へと意味(ニュアンス)が転換していく(井上章一『愛の空間』第4章「円宿時代」)。
「連れ込む」主体に違いはあるが、どちらにしても、性行為を前提に「連れ込む」宿である。したがって、一般の旅館のように宿泊を必ずしも前提とせず、一時的な滞在(「ご休憩」「ご休息」)のための部屋利用が想定され、料金が設定されている点に特徴がある。
歴史的に見れば、江戸時代の茶屋で休憩室の奥に布団が敷かれている「出会い茶屋」(上野池之端に多かった)、明治以降、芸者遊びの場であり、お忍びの男女の待ち合わせにも利用された「待合」と呼ばれる施設、さらに昭和戦前期(1930年代)になると「待合」よりずっと気軽に安価に(1人1円)利用できるは「円宿」(えんじゅく)が都市部に出現する。また戦後の混乱期、「パンパン」と呼ばれた街娼が多かった時代には、彼女たちが進駐軍(主に米軍)兵士を連れ込む「パンパン宿」が盛り場の周辺にたくさんあった。「連れ込み旅館」はこうした系譜に連なるもので、戦後の社会的混乱が一段落した1950年代中頃に急増する。
2 「東京『連れ込み旅館』広告データベース(1953~1957年)」を作る
さて、『日本観光新聞』の調査で「連れ込み旅館」の広告の存在に気づいた私は、その後、『内外タイムス』の調査で、さらに大量の「連れ込み宿」広告に出会うことになる。そして、本筋の調査の傍ら、「連れ込み旅館」広告が載っている頁もコピーしていった。
ちなみに『日本観光新聞』も『内外タイムス』も、政治、経済、芸能、スポーツ、そして性風俗を網羅した軟らか系の新聞で、イメージとしては現代の『夕刊フジ』や『日刊ゲンダイ』に近い。
そんな経緯で収集し始めた「連れ込み旅館」広告だが、性風俗関係の頁に広告を出していること、料金設定が「お二人様(御同伴)」で「休憩(休息)」であることの2点を条件に『内外タイムス』と『日本観光新聞』から抽出したところ、1953~57年(昭和28~32)の5年間で690点の広告が集まった。それを整理して「東京『連れ込み旅館』広告データベース(1953~1957年)」を作成した
旅館の軒数にすると385軒。場所が異なる「別館」は1軒にカウントしてある。
完璧とは言わないが、かなりの程度、網羅していると思う。これだけの材料があれば、当時の東京の「連れ込み旅館」の様相は十分にうかがえるだろう。
3 その分布
まず、「連れ込み旅館」の分布から見てみよう。
【エリア別集計】
都心エリア( 85軒)
城西エリア(125軒)
城南エリア(106軒)
城北エリア( 60軒)
城東エリア( 9軒)
【集中地域(5軒以上)】
千駄ヶ谷(39軒)
渋谷(32軒)
新宿(31軒)
池袋(21軒)
大塚(12軒)
代々木(11軒)
新橋・芝田村町(11軒)
長原・洗足池・石川台(10軒)
高田馬場(8軒)
銀座(7軒)
原宿(7軒)
五反田(7軒)
大井町(7軒)
大森・大森海岸(7軒)蒲田(7軒)
新大久保・大久保(6軒)
飯田橋・神楽坂(5軒)
浅草(5軒)
赤坂見附・山王下(5軒)
エリア別の割合は、城西エリア32%、城南エリア28%、城北エリア16%、都心エリア22
%、城東エリア2%で、東京区部の西と南、つまり(拡大)山の手地区に多く、東の下町地区は極端に少なくなっている。
城西エリア(125)では千駄ヶ谷(39)が都内最大の集中地域で、新宿(31)、代々木(11)がそれに次ぐ。代々木は新宿と千駄ヶ谷の間で両者をつなぎ、巨大な「連れ込み旅館」ベルトを形成している。
城南エリア(106)は渋谷(32)に顕著に集中し、離れて長原・洗足池・石川台(10)が次ぐ。
都心エリア(85)は新橋・芝田村町(11)が多いが、他は分散的である。後にラブホテルの集中地域になる湯島は坂上に2軒、天神下に2軒でまだ集中傾向はない。現在、東京最大のラブホテル密集地域の鶯谷は2軒だけで目立っていない
城北エリア(60)は池袋(21)とその東の大塚(12)に集まっている。大塚は「花街」(三業地)からの転身である。
ほとんど広告がない城東地区(9)は、やはり後にラブホテルが集中する錦糸町もまだ2軒だけだ。
さらに細かく、鉄道沿線別に見てみる(都心は区別)。
都心エリア(85軒)
【千代田区】(9)
神田(鍛冶町)(1)秋葉原(1)御茶ノ水(3)神田小川町(2)神田神保町(1)九段下(1)
【中央区】(15)
銀座(7)築地(1)日本橋(1)人形町・浜町(4)東京駅八重洲(2)
【港区】(25)
新橋(6)芝田村町(5)虎の門(1)神谷町(1)浜松町(1)田町(2)芝公園(1)坂見附(2)赤坂山王下(3)麻布霞町(1)麻布竜土町(1)青山一丁目(1)
【台東区】(20)
御徒町(3)上野池ノ端(3)根津八重垣町(1)上野桜木町(1)鶯谷(2)下谷坂本町二丁目(3)蔵前(1)浅草(5)浅草橋場(1)
【文京区】(8)
湯島天神下(2)湯島(2)本郷真砂町(1)小石川柳町(1)白山(本郷肴町)(1)小日向(石切橋)(1)
【新宿区】(8)
飯田橋・神楽坂(5)市ヶ谷新見附(1)牛込矢来町(1)四谷荒木町(1)
城西エリア(125軒)
【国電山手線】
高田馬場(8)新大久保・大久保(6)新宿(31)原宿(7)
【国電中央線】
千駄ヶ谷(39)東中野(1)中野(1)高円寺(1)阿佐ヶ谷(2)吉祥寺(2)
【小田急線】9
参宮橋(3)代々木八幡(1)代々木上原(1)下北沢(1)登戸(2)向ヶ丘遊園前(1)
【京王本線】
幡ヶ谷(1)明大前(2)高井戸(2)調布(1)
【京王井の頭線】
浜田山(1)
城南エリア(106軒)
【国電山手線】
渋谷(32)恵比寿(1)目黒(4)五反田(7)
【東急東横線】(16)
代官山(1)中目黒(1)都立大学(1)自由が丘(3)多摩川園(1)新丸子(4)武蔵小杉(2)元住吉(2)大倉山(2)
【東急大井町線】
二子玉川(1)二子新地(1)高津(1)
【東急目蒲線】
目黒不動前(1)鵜の木(1)
【東急池上線】
長原・洗足池・石川台(10)雪ヶ谷大塚(1)千鳥町(2)久ヶ原(1)池上(1)
【国電京浜東北線】
品川(3)大井町(7)大森(5)蒲田(7)川崎(1)鶴見(1)
【京浜急行】
大森海岸(2)
城北エリア(60軒)
【国電山手線】
目白(2)池袋(21)大塚(13)巣鴨(4)駒込(2)田端(1)日暮里(3)
【国電京浜東北線】
王子(1)東十条(1)赤羽(1)川口(1)北浦和(1)大宮(3)
【国電赤羽線】
板橋(1)
【国鉄常磐線】
三河島(1)北千住(1)
【東武東上線】
大山(1)常盤台(1)
【西武池袋線】
桜台(1)
城東エリア(9軒)
【国電総武線】
錦糸町(2)亀戸(1)平井(2)新小岩(1)小岩(1)船橋(1)
【東武鉄道】
玉ノ井(1)
鉄道沿線で見ると、都心から西に延びる幹線である中央線沿線は、御茶ノ水、飯田橋・神楽坂に始まり、最大の集中地区である千駄ヶ谷、代々木、新宿、大久保、東中野、中野、高円寺、阿佐ヶ谷とほぼ連続的に立地し、この沿線の需要が高かったことがうかがえる。
山手環状線の駅もほぼまんべんなく立地し、確認できないのは有楽町駅と大崎駅だけである(西日暮里駅はまだない)。大崎は工場地帯や電車区があり駅周辺の開発が遅れていたので仕方がないだろう。
城西、城南エリアはかなり郊外まで分布が伸びている。東急目蒲線の鵜の木、東急東横線の新丸子、武蔵小杉、東急大井町線の二子多摩川、二子新地、小田急線の登戸など、多摩川の河川交通と陸上の街道との結節点に発達した花街に立地しているのは興味深い。
また、地区別の上位が国電山手線・中央線沿線で占められている中で、唯一の私鉄である東急池上線沿線の長原・洗足池・石川台(10)が目立つ。私が泊まった石川台の「緑風園」もこの地区に含まれる。
4 分布から見えるもの ―西の「連れ込み旅館」、東の「赤線」―
1953~1957年の東京の「連れ込み旅館」の分布で、最も注目すべきは、城東エリアの極端な少なさだろう。
全体のわずか3%、区部で広告が確認できるのは、江東区2軒(錦糸町)、墨田区1軒(向島)、葛飾区1軒(新小岩)、江戸川区2軒(平井、小岩)、足立区1軒(北千住)の7軒に過ぎない。
広告が確認できないからまったく「連れ込み旅館」がなかったとは言えないが、少なくとも広告を出すほど経営意欲がある「連れ込み旅館」はきわめて少なかった。
その理由を推測すれば、単純に需要が少なかったから、と思われる。
性行為の場として、「連れ込み旅館」を考えた場合、その需要、利用形態は次のように推定される。
① 街娼(一部の芸妓や女給を含む)など「売春」を業とする女性が客の男性を「連れ込む」。
② 男性が、芸妓、女給さらには、素人など「売春」を業としない女性を口説いて「連れ込む」。
③ 住宅事情など、自宅でSexする環境に恵まれていない夫婦や恋人同士が利用する。
この内、①は、街娼からすると「連れ込み宿」の料金が高すぎ、経営者側からすると売春行為を禁止した「東京都売春取締条例」(1949年5月31日制定)の「場所提供」に違反することから、主流ではなかったと思われる。
つまり、「連れ込み宿」の需要は②③、さらに言えば②が中心だった。

千駄ヶ谷駅ホームのアベック(『週刊東京』1956年5月12日号)

千駄ヶ谷駅前の立て看板(『週刊東京』1956年5月12日号)

千駄ヶ谷・羽衣苑に入る男女(『週刊サンケイ』1957年3月10日号)
梶山季之『朝は死んでいた』(1960年『週刊文春』に連載)で殺人犯に仕立てられる主人公のように、都心の会社に通うサラリーマンで、銀座、次いで新宿の盛り場で飲んで、女性(女給やBG)を口説いて、千駄ヶ谷あたりの旅館に連れ込んでSexする男たちだ。
彼らのようなサラリーマンの自宅は、都心から西の新宿や、南の渋谷から、さらに西に延びる私鉄沿線に多く、東側には少なかった。千駄ヶ谷、新宿、渋谷が「連れ込み旅館」の密集地であり、そこを起点とする私鉄沿線に連続的に分布するのは、彼らの需要があったからだ。東京の「連れ込み旅館」の分布がサラリーマンの自宅の立地と性行動のパターンと深く関係していることは間違いないと思う。
では、「連れ込み旅館」が少ない東京の東側の男たちはどうしていたのだろうか?
この時期は「赤線」があった時代だ、「赤線」とは1946年12月~1958年3月末に存在した黙認買売春地帯である。警察が地域を限って「特殊飲食店」の営業を許可し、そこで働く女給が客と自由恋愛の末に性行為をし、プレゼントとしてお金をもらうという建前を警察が黙認することで成り立っていた。
東京区部には13カ所の「赤線」が存在していたが、その分布は、「連れ込み旅館」とはまったく逆で、城西、城南エリアに少なく、城東エリアに圧倒的に多かった。
都心エリア なし
城西エリア 1カ所(新宿区:新宿二丁目)
74軒 従業婦477人(1952年末)
城南エリア 2カ所(品川区:北品川、大田区:武蔵新田)
45軒 従業婦185人
城北エリア 1カ所(台東区:新吉原)※
313軒 従業婦1485人
城東エリア 9カ所(墨田区:玉の井・鳩の街、江東区:洲崎・亀戸、葛飾区:新小岩・亀有・立石、江戸川区:東京パレス、足立区:千住柳町)
710軒 従業婦2307人
(※)新吉原は行政区分は台東区なので、この報告では都心エリアに分類されるが、かつて「北里(ほくり)」と通称されたように、江戸・東京の地理感覚では城北エリアとした方が実態的だと思う。
こうした分布から、東京の東側の男たちの性行為の場は圧倒的に「赤線」で、「連れ込み旅館」の需要は少なかったと推測される。下町の伝統的な花街、たとえば深川(門前仲町)などには芸妓と客の性行為の場としての「待合」のような施設があったが、それは「連れ込み旅館」の広告には現れていない。
つまり、性行為の場として、「赤線」と「連れ込み旅館」は対置関係にあった。実際、新吉原、洲崎、玉の井、鳩の街、そして新宿二丁目など規模の大きな「赤線」の周囲には「連れ込み旅館」はほとんど立地しない。需要がないからだ。
「赤線」と「連れ込み旅館」が対置関係にあったということは、裏を返せば、両者は補完関係にあったということだ。
極言すれば、東京には「赤線」に行って女給(実態は娼婦)を買ってSexする男(商店主・職人・工員など)と、BGやクラブの女給(後のホステス)を口説いて「連れ込み旅館」に連れ込んでSexする男(会社員が中心)の2タイプがいた。前者のタイプは東京の東半分に多く、後者のタイプは西半分に多く住んでいたと思われる。
東京においては、少なくとも1950年代までは、性行為の文化が地域によってかなり異なっていたことが浮かび上がってきた。「赤線」と「連れ込み旅館」の補完関係は1958年3月の「赤線」廃止(「売春防止法」の完全施行)によって崩壊する。その後、こうした性行為の地域性がどう変化していったのか? 今後の課題としたい。
5 その設備
次に、広告にあらわれた「連れ込み旅館」の設備について見てみよう。
(1)建築様式
「数寄屋造り、離れ家式」(おほた:千駄ヶ谷)
「古代桂を偲ばせる 城北に誇る新日本風数寄屋造りの静かな旅荘」(浮月:池袋)
「全荘離家式、数寄屋造り」(三越:千駄ヶ谷)
「全室離式 那知廊下伝」(川梅:蒲田)←「那知(智)廊下」って何?
「純洋室高級ベッド完備」「別館数寄屋造り」
(大久保ホテル:新大久保・大久保)
「歌舞伎調スタイル」(音羽:蒲田)
「各室歌舞伎調好み」(龍美:目黒) ←「歌舞伎調」とは具体的に?
「歌舞伎」(原宿)という旅館もある
建築様式は、圧倒的に数寄屋造り・離れ家式が好まれている。洋室主体のホテルも、数寄屋造りの別館を増築する。コンセプトは高級&和風である。


若水(池袋:19571206) 夕月荘(大塚:19540305k)


紅屋(池袋:19540319k) 可悦(高田馬場:19571229)
(2)基本設備
「和洋各室、離式・風呂・トイレ・電話付」(深草:千駄ヶ谷)
「トイレ 風呂 ラジオ 電話付」(夕月荘:大塚)
「新装開店 各室共外線直通電話 ラジオ設備」(成光館:飯田橋:1955年6月)
基本設備は、各室に風呂、トイレ、そして電話である。それにラジオが加わる。
(3)鏡
「鏡風呂」「鏡の間」(利女八:阿佐ヶ谷)
「鏡風呂(四面鏡)」(川梅:蒲田)
「鏡天上」(ほていや:高田馬場) →「天上」は「天井」の誤り
「鏡風呂・鏡部屋」(天竜:大井町)
井上章一『愛の空間』(角川選書、1999年)が、ラブホテルのインテリアの特徴としている「鏡」だが、広告にはあまり現れない。「鏡部屋」「鏡天井」「鏡風呂」が存在したのは確実だが、普及度はまだ今一つだったと思われる。

川梅(鎌田:19530107)
(4)テレビ
「テレビ各室」(みやこホテル:参宮橋:1956年3月)
「各室テレビ・バス・トイレ・電話付」(京や:代々木:1956年12月)
テレビは、1956年3月の参宮橋「みやこホテル」の広告が最初。1956年は、まだNHK総合+民放2社の時代で、世の中は「街頭テレビ」の時代。「各室テレビ」はとても贅沢で画期的だと思う。

みやこホテル(参宮橋:19560304)
(5)暖房
(こたつ)
「温かなコタツを用意して」(紫雲荘:五反田:1953年9月)
「全室おこたの用意が出来ました」(夕月荘:大塚:1953年9月)


夕月荘(大塚:19540305k) ホテルしぐれ荘(大森・19550213)
(スチーム暖房)
「スチーム暖房完備」(ホテル・スワニー:高田馬場:1953年3月)
「冬知らぬ スチーム暖房」(みやこホテル:参宮橋:1954年11月)
「初夏の宿 スチーム暖房」(山のホテル:渋谷:1954年12月)
「各部屋スチーム暖房」(かすみ荘:千駄ヶ谷:1955年2月)
「全館スチーム暖房 お部屋は小春の暖かさ」(白樺荘本館:千駄ヶ谷:1956年1月)

山のホテル(渋谷:19541207)
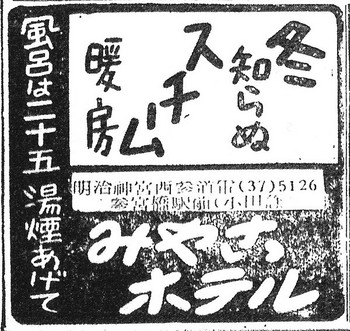
みやこホテル(参宮橋:19550213)
暖房は、炬燵からスチーム暖房へという流れ。スチーム暖房の初見は1953年春で、1955~56年の冬にはかなり普及した様子がうかがえる。
(6)冷房
(扇風機)
「各室、離家式 電話、扇風機付」(御苑荘:千駄ヶ谷:1953年9月)
「各室バス付 扇風機」(山のホテル:渋谷:1954年8月)

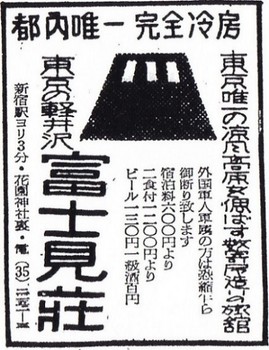
紅屋(池袋:19540813k) 富士見荘(新宿区役所通り:19550819k)
(クーラー)
「涼味みなぎる 完全冷房店」(富士見荘:新宿区役所通り:1955年7月)
「完全冷房」(玉荘:千駄ヶ谷:1956年7月)
冷房は、扇風機からクーラーへという流れだが、暖房に比べると転換は遅い。「冷房」の広告上の初見は、1955年夏の新宿「富士見荘」。他にも千駄ヶ谷の高級旅荘「玉荘」のみ。普及は1960年代になってからと思われる。
(7)風呂
(形状)
「岩風呂」(福住:鶯谷)(やまと:桐ケ谷)(可悦:高田馬場)(大洋:渋谷)(天竜:大井町)(高津ホテル:高津)(ホテル赤坂:赤坂)(葵:大塚)(寿美吉:大塚)(緑風園:池上石川台)(福田屋:登戸)(トキワホテル:日暮里)(みやこ:目白)
「岩戸風呂」(東洋荘:渋谷)(のぼりと館:向ケ丘遊園前)
「穴風呂」(緑風園:池上石川台)
「滝風呂」(すずきや:代々木)(大洋:渋谷)(白梅:船橋)(洗足池旅館:池上洗足)
「寝風呂」(藤よし:駒込)
「寝台風呂」(筑波旅館:恵比寿)
「舟風呂」(東洋荘:渋谷)
「水族館付き舟風呂」(黒岩荘:渋谷)
「屋形風呂」(川梅:蒲田)
「数寄屋風呂」(鶴栄:大塚)
「数寄屋造りのロマンス風呂」(城北閣:池袋)
「瓢箪風呂」(二幸:渋谷)
「扇風呂」(東芳閣:池袋)
「末広風呂」(香川:大塚)
「ダルマ風呂」(夕月荘:大塚)
「鏡風呂」(川梅:蒲田)(利女八:阿佐ヶ谷)(天竜:大井町)
「大理石風呂」(菊富士松韻亭:原宿)
「大理石のパール風呂」(藤よし:駒込)
「風趣あふれる京の竈風呂」(御苑荘:千駄ヶ谷)
「むし風呂」(ピースホテル:大塚)
「スポンジ風呂」(ほていや:高田馬場)(のぼりと館:向ケ丘遊園前)
(立地)
「露天岩風呂」(深山荘:千駄ヶ谷)
「露天大岩風呂」(照の家:池上長原)
「若返り温泉 二階風呂」(加島屋旅館:川崎)
「階上ロマンス風呂」(旭:巣鴨)
「せせらぎの音にゆあみする優雅な川辺風呂」(大都:大井町)
(香り)
「レモン風呂」(白樺荘別館:千駄ヶ谷)(湯島荘:湯島)
「香水風呂」(高田旅館:渋谷)(飛龍閣:渋谷)(蓬莱:上野桜木町)(目白山手ホテル:目白)
「香気漂う丁子風呂」(あおば荘:白山)
「松葉風呂」(松実園:千駄ヶ谷)
(添加)
「牛乳風呂」(みやこ:新宿)(小梅荘:五反田)
「薬湯」(高津ホテル:高津)
「ホルモン風呂」(しぐれ荘:大森)
「ホルモン入葉緑素風呂」(ふじた:鵜の木)
「珪藻土入りのお風呂」(いずみ:池袋)
(数)
「二十五の湯殿」→「三十の湯殿」→「三十五の湯殿」(みやこホテル:参宮橋)
「八つの御風呂」(みすず:渋谷)
「七ツのお湯が溢れている」(山王温泉ホテル:大森)
(実態不明)
「ヨーマ風呂」(川梅:蒲田)
「金魚風呂」(きりしま:代々木)
「孔雀風呂」(永好:渋谷)
「虹風呂」(はなぶさ新館:原宿)
「ローマ風呂」(東芳閣:池袋)
「豪華なフランス風呂」(鶴栄:大塚)
「情緒あふれる浅妻風呂」(音羽:蒲田)
「ロマンス風呂」(菊半旅館:渋谷神泉)(美鈴:巣鴨)(緑風園:池上石川台)
『愛の空間』が注目しているように、風呂は、旅館にとって誘客の「目玉」であり、風呂がない家庭が多い時代の利用者にとって大きな魅力だった。広告文には実に多彩な「風呂」が現れる。岩風呂、滝風呂、鏡風呂、蒸し風呂、舟風呂、寝風呂などの形状、香水風呂、丁子風呂、レモン風呂など香り付けをしたと思われるもの、牛乳風呂、ホルモン風呂、葉緑素風呂、珪藻土風呂などなにかを添加して美容効果をねらったもの、やたらと数を増やした挙句、火事を出したホテル。一方、ロマンス風呂、虹風呂、金魚風呂、孔雀風呂など実態がよくわからないものもある。


岩風呂:やまと 滝風呂:洗足池旅館
(桐ケ谷:19540306) (池上洗足池:19531020)


滝風呂:よしみ 露天大岩風呂:照の家
(蒲田:19540813k) (池上長原:19540730k)


大岩風呂:登戸館 特に特徴のないタイル風呂:桂
(向ケ丘遊園前:19570505) (大塚:19540319k)

謎の「ヨーマ風呂」:川梅
(蒲田:19560621)
6 その立地
水辺や高台など地理的な特長、森、川、池、山などの自然のイメージを強調する広告も多い。
(1)森
「御苑の森かげに七彩の湯湧き出づる」(南風荘:千駄ヶ谷)
「鬱蒼と茂った千駄ヶ谷の森に囲まれた閑静な憩の宿」(松実苑:千駄ヶ谷)
「外苑の森に囲れた静かな皆様のお宿」(かなりや:代々木)
「緑の森 静かなお部屋」(まつかさ:千駄ヶ谷)
「目黒の森に囲まれた静かな皆様のお宿」(菊富士ホテル:目黒)
「新宿の自然境」(とみ田:新宿駅南口)
「森」は、新宿御苑や神宮外苑に隣接する千駄ヶ谷、代々木エリアの旅館に多くみられ、静寂・閑静がイメージ化される。さらに都会の俗塵を離れた自然も・・・。


まつかさ(千駄ヶ谷:19541023k) とみ田(新宿駅南口:19530731)
(2)水辺・川
「浜町河岸」(矢の倉ホテル:日本橋浜町)←隅田川
「江戸情緒豊かな隅田河畔で!」(龍村:浅草)←隅田川
「静かな川辺の宿」(杵屋:錦糸町)←堅川
「TOKYOのセーヌのほとり」(東京スターホテル:銀座)←築地川
「情緒豊かな神田川畔のお宿」(白:秋葉原)←神田川
「せせらぎの音にゆあみする優雅な川辺風呂」(大都:大井町)←立会川
「多摩川畔の静かな別荘」←多摩川(高津ホテル:高津)←多摩川
「多摩川の四季に眺める二子橋玉川堤」(幸林:二子新地)←多摩川
「多摩川の涼風が誘う」(新雪:登戸)←多摩川
「水辺・川」は、隅田川と多摩川が中心。神田川、築地川はともかく、堅川や立会川になると「川」の風情を感じるのは難しいのではないか。立会川の「せせらぎの音」はいかにも誇大広告。東京の川辺が「風流」なイメージを保てた最後の時代か。1960年代に高度経済成長期になると、川の汚濁と悪臭がひどくなり、川の埋め立て(築地川)や暗渠化(立会川)が進行する。
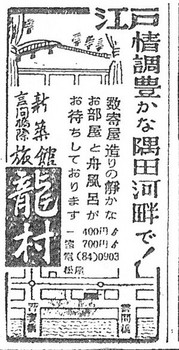

龍村 大都
(浅草:19570713) (大井町:19550410)

新雪(登戸:19570823)
(3)水辺・池
「新宿十二社池ノ上」(浮世荘:新宿十二社)
「涼風をさそう池畔の荘」(ホテル・スワニー:高田馬場)
↑ どこの池? 調べたが近隣に池はない。もしかして庭の池?
「上野不忍池畔」(かりがね荘:上野)
「静かな洗足池畔」(翠明館:池上洗足池)
「思い出の洗足池 静かな池畔の宿」(やくも:池上洗足池)
「池畔の幽緑境」(洗足ふじや:池上北千束)
「水辺・池」は、洗足池(大田区)、不忍池(台東区)、十二社弁天池(新宿区、1968年埋め立て、消滅)など。高田馬場の池は不明。とくに現在は住宅地に囲まれている洗足池が郊外の行楽地として機能していたことが興味深い。

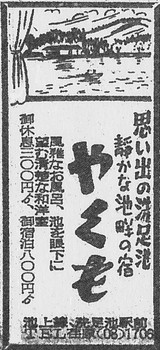
かりがね荘(上野:19561201) やくも(池上洗足池:19521007)

翠明館(池上洗足池:19530204)
(4)水辺?・水族館
「自慢の新しい水族館付き(黒岩荘:渋谷)」
なぜ「水族館」が・・・、正直言ってよくわからない。
(5)高台
「新宿歌舞伎町高台」(小町園:新宿歌舞伎町)
「高台の静けさ」(東京ホテル:新宿区役所通り)
「見晴らしのよい高台」(大洋:渋谷)
「渋谷の高台」(高田旅館:渋谷)
「高台閑静 眺望渋谷随一!」(平安楼:渋谷)
「断崖上の三層楼」(三平:渋谷)
「大塚駅北口高台」「眺望絶佳」(式部荘:大塚)
「国電田端駅高台」(清風荘:田端)
「国電日暮里駅高台西口」(喜久屋:日暮里)
「高台」の立地を強調する広告も多い。特に渋谷は道玄坂や桜丘町のように坂上、高台に「連れ込み旅館」が多く立地する。また大塚・田端・日暮里は台地と低地を分ける崖線の上に立地するものが多い。いずれも、閑静さ、眺望の良さを特長にしている。高台の立地は、次の時代の「ラブホテル」の集中域、新宿歌舞伎町二丁目、渋谷円山町、湯島などに引き継がれる。

夕月荘(大塚:19541023k)
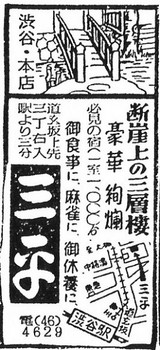

三平(渋谷:19571004) 式部荘(大塚:19560607))
(6)山・山荘
「山の中から水の音 滝の音 渓渡るせせらぎ すずしさよ」
(みやこホテル:参宮橋)
「軽井沢の元祖」「東京にある軽井沢」(旅館富士見荘:新宿区役所通り)
「静かな山荘の離れ」(ホテル ニューフジ:渋谷)
「丘の離れ、都会の山荘」(山のホテル:渋谷)
「都心の山荘」(平安楼:渋谷)
「趣味の山荘」(強羅ホテル:五反田)
「広大な芝生に立つ山荘風のホテル」(若宮荘ホテル:神楽坂)
「ロマンな憩いの山荘」(ホテル赤坂:赤坂見附)
「城南の箱根 山林峡谷 2千坪に点在する離れ家」(緑風園:池上石川台)
「東京の箱根 もずの声 ここは都のなかか 山の里」(緑風園:池上石川台)
山の手エリアには「山・山荘」のイメージを強調する広告が多い。中には軽井沢(長野県)や箱根(神奈川県)などの高級別荘・山荘とイメージを重ねているものもある。
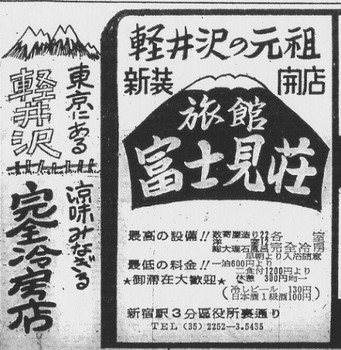
「東京にある軽井沢」富士見荘(新宿区役所通り:19550721)

山荘のイメージ「ホテル ニューフジ」(渋谷:19540508)


山のホテル(渋谷:19550702) 緑風園(池上石川台:19570130)
7 そのイメージ
「連れ込み旅館」の広告は、集客のために様々イメージを作り出している。それは,良く言えば豊かなイメージの喚起であるが、悪く言えばイメージの捏造であり、現代の感覚(法規)からしたら、誇大広告の批判を免れない。
(1)温泉偽装・温泉詐称・有名温泉への仮託
「東京唯一の天然温泉」(山水荘:亀戸) ← 「亀戸温泉」は実在
↓ 以下はずべて偽装・詐称
「温泉ホテル」(ホテル自由ヶ丘:自由ヶ丘)
「山王温泉ホテル」「温泉情緒」(山王温泉ホテル:大森)
「地下温泉」(二幸:渋谷)
「渋谷にも温泉出現」(菊半旅館:渋谷神泉)
「都心の温泉郷」(あぽろ旅館:九段下)
「銀座温泉 憩いの出湯」(せきれい荘:銀座)
「不忍温泉」(かりがね荘:上野)
「鶯谷温泉」(福住・鶯谷)
「巣鴨温泉」(三晴:巣鴨)
「東郷台温泉」(はなぶさ新館:原宿)
「温泉気分」「湯湧き出ずる」などのように文章の雰囲気で温泉イメージを喚起する広告は多い。さらに「銀座温泉」「鶯谷温泉」「(上野)不忍温泉」「巣鴨温泉」「(大森)山王温泉」「(原宿)東郷台温泉」など、明らかな温泉を詐称する旅館もある。
当時の法律(1948年7月10日制定の「温泉法」)では、温泉は源泉温度25度以上で有効な成分をもつもの、とされており、東京区部にはそれに適合する温泉はなかった。ただし、城南地区(港区、大田区、品川区、世田谷区など)には「黒湯」と呼ばれる25度以下だが有効成分を含む「鉱泉」が分布する。


山水荘 山王温泉ホテル
(亀戸:19530204)(大森:196560222)


あぽろ旅館 せきれい荘
(九段下:19541219)(銀座:19550702)
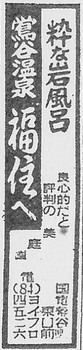
福住
(鶯谷:19560107)
(有名温泉地への仮託)
「都内で湯河原の気分を!」(芳川:市ヶ谷新見附)
「熱海」(熱海:池上洗足池)
「京浜の熱海」(東横ホテル:武蔵小杉)
「京浜の箱根」(菊家ホテル:武蔵小杉)
「東京の箱根」(富士屋ホテル:代々木)
「郊外の箱根」(錦:高井戸)
「城北の箱根」(荒川荘:三河島)
「城南の箱根」「東京の箱根」(緑風園:池上石川台)
「箱根気分を上原で」(鶴家:代々木上原)
「新箱根」(新箱根:板橋)←方向が違う!
「タッタ30分で箱根の気分」(いずみ荘:大宮)←方向が違う!
「強羅ホテル」(強羅ホテル:五反田)
「渋谷の衣川(鬼怒川)」(黒岩荘:渋谷)
「城北の水上」(目白文化ホテル:目白)
「九州の地 別府温泉を偲ばせる」(別府:代々木)
「東京の谷間 幽境霧島を偲ぶ閑静さ」(きりしま:代々木)
温泉偽装・詐称との関連で、「城南の箱根」「京浜の熱海」のように、箱根(神奈川県)、熱海(静岡県)、湯河原(神奈川県)、水上(群馬県)、鬼怒川(栃木県)、別府(大分県)、霧島(鹿児島県)などの有名温泉地とイメージを重ねる広告が見られる。
とくに箱根温泉は人気で、城北(三河島)、城南(石川台)などあちこちに「箱根」があった。中には板橋のように明らかに方向が違うものも。東急東横線の武蔵小杉などは「京浜の熱海」と「京浜の箱根」と「いったいどっちなんだ?」と言いたくなる。さらに、有名温泉地をそのまま旅館の名にしたものもあり、五反田には「強羅温泉」が、洗足池には「熱海」が、代々木には「別府」「きりしま」があった。


荒川荘 緑風園
(三河島:19541113)(池上石川台:19521007)


東横ホテル 菊家ホテル
(武蔵小杉:19561205)(武蔵小杉:19540302)


黒岩荘 別府
(渋谷:19570204) (代々木:19550109)

ホテルきりしま
(代々木:19570130)
(2)温泉マークの使用
典型的な温泉マーク


熱海(池上洗足池:19530403k) 多ま木(新宿:19530918k)
デザイン化された温泉マーク

大久保ホテル(新大久保・大久保:19550115)

ホテル明光(品川:19530925k)
広告文での温泉マークの使用は、1953年が多く、1954年半ばまででほぼ納まる(例外は1955年3月の「川梅」)。1955年4月以降の使用例は見られない。当時、温泉マークの乱用が問題視されており、1954年半ば頃に、なんらかの規制(自粛)が行われた可能性が高い。
(3)なぜか南国(椰子の木、ラクダ)
なぜか、南の国のイメージを絵にしている広告が2つある。モチーフはいずれもラクダと椰子の木。
「南風荘」は、その名称からだろう。「エデン」の園は、アルメニア付近にあてるのが通説で、エジプトではないと思う。


南風荘(千駄ヶ谷:19530731) エデンホテル(目白:19531016k)
(4)文化人・インテリ・旧華族
「文化人好みの画廊スタイル」(強羅ホテル:五反田)
「モダンクラッシックの文化人スタイル」(ホテル山王:渋谷)
「インテリ層の憩の宿」(ホテルおしどり:大森)
「旧徳大寺公邸です」(光雲閣:代官山)
「文化人」「インテリ」を強調した広告が散見され、ターゲットにした顧客層がうかがえる。
『愛の空間』には、戦後の社会変動や財産税などで手放された「没落階級の屋敷を再利用したものが多かったらしい」と記されているが、広告から確認できるのは、渋谷区代官山の徳大寺公爵邸を転用した「光雲閣」のみ(現在も同地に「光雲閣ビル」がある)。


強羅ホテル ホテル山王ホテル
(五反田:19560730) (渋谷:19540728)

おしどり(大森:19560607)

光雲閣(代官山:19540428)
8 「連れ込み旅館」の機能 ―むすびに代えて―
「連れ込み旅館」は、その立地や設備からして、庶民(と言っても、貧困層ではなく中間層)にとって、日常を離れた特別な場だった。
その背景には、戦後の混乱期から抜け出し、飢える心配こそなくなったものの、狭い家に住み、ほとんどの家にテレビや冷暖房(クーラー、スチーム)はなく、多くの家に風呂や電話がない住環境がベースにある。
つまり、「連れ込み旅館」は、日常の延長上のワンランク、ツーランク上の住環境を一時であっても手に入れ、Sexを楽しむ場所だった。
ここで重要なのは、日常の延長上であることだ。「数寄屋造り」にしろ「離れ家」にしろ、「連れ込み旅館」はあくまでも和風の贅沢環境であり、豪華なベッドがあるような洋風の住環境ではなかった。おそらく、当時の日本人カップルは、まだベッドでは落ち着いてSexができなかったのではないだろうか。
「連れ込み旅館」の(1室2人)休憩400~500円、泊り800~1000円という料金は、約15倍すると現代の貨幣価値に近づく。つまり、休憩6000~7500円、泊り12000~15000円ということになり、けっして安くはない。それだけの価値があったということだ。
あるいは、箱根や熱海の温泉に2人で旅行したくても、金銭的・状況的に難しいカップルにとって、疑似的であっても「連れ込み旅館」で温泉気分を楽しみことは、十分にお金を払う価値があることだったと思う。
ところが、1960年代後半、日本社会が高度経済成長期に入り、住環境の改善が進み、また生活の洋風化が進むと、「連れ込み旅館」を支えていた背景が変化してくる。
中間層の多くの家にお風呂が備えられ、電話やテレビが設置され、裕福な家には床の間・床柱のある数寄屋造り風の和室が設けられ、そこが夫婦の寝室になる。
そうなると、和風の特別な環境(Sexの場)である「連れ込み旅館」の意味が薄らいでいく。そして、次の時代(1970年代)のカップルが求めるのは、洋風な特別な環境(Sexの場)になる。
「連れ込み旅館」から「ラブホテル」への「進化」はそうして進行していった。
【備考】
広告図版の8桁の数字は、掲載年月日を示す。
末尾にkがついているのは『日本観光新聞』、他はすべて『内外タイムス』。
【文献】
梶山季之『朝は死んでいた』(文藝春秋、1962年)←小説
佐野 洋『密会の宿』
(アサヒ芸能出版、1964年、 『講談倶楽部』連載は1962年、後に徳間文庫、1983年)←小説
保田一章『ラブホテル学入門』(晩聲社、ヤゲンブラ選書、1983年)
花田一彦『ラブホテル文化誌』(現代書館、1996年)
井上章一『愛の空間』(角川選書、1999年)
鈴木由加里『ラブホテルの力 ―現代日本のセクシュアリティ―』(廣済堂ライブラリー、2002年)
金 益見『ラブホテル進化論』(文春新書、2008年)
金 益見『性愛空間の文化史』(ミネルヴァ書房、2012年)
【追記】
2020年5月5日 「データベース」の改訂に伴い、データを修正。
【ブックレビュー】「LGBTをめぐる出版状況」(『ジェンダー研究21』第7号) [論文・講演アーカイブ]
2018年3月13日(火)
早稲田大学ジェンダー研究所の紀要『ジェンダー研究21』第7号(2018年1月)に寄稿したLGBTについての定期刊行物と学術書のレビューです。

日本でLGBTムーブメントが起こった2012年以降、2017年秋までを範囲として、できるだけ網羅的に記述したつもりです。
LGBTについて学ぼうとする方のご参考になれば幸いです。
----------------------------------------------
LGBTをめぐる出版状況
三橋 順子
はじめにーLGBTとはー
LGBTとは性的に非典型な主な4つのカテゴリーの英語の頭文字を合成したものである。Lはレズビアン(Lesbian:女性同性愛者)、Gはゲイ(Gay:男性同性愛者)、Bはバイセクシュアル(Bisexual:両性愛者)、Tはトランスジェンダー(Transgender:性別越境者)を表す。
本来、性的に非典型な人々が共通の政治・社会的課題に立ち向かう際の連帯を示す概念で、最初からLGBTというカテゴリーやコミュニティがあるわけではない。ところが、この言葉が日本に輸入されたときに、意味が微妙にずれてしまい、LGBTという人がいるかのような使い方がされるようになってしまった。たとえば、マスメディアに見られる「LGBT男性」「LGBT女性」という用法はあきらかに誤りだ。また「LGBT活動家」というのも首を傾げる。なぜなら1人の人間がL・G・Bを兼ねることは不可能だからだ(L・G・BとTは兼ねられる)。
それはともかく、近年、日本社会でLGBTへの注目が急速に高まっていることは間違いない。それにともなってLGBTに関連する出版が急増している。本稿は、そうした状況を概観することで、LGBTをめぐる諸問題に関心をもつ人たちへのささやかな案内になればと思う。
最初に定期刊行物の「LGBT特集」の状況について分析し、次にLGBT関連の学術系書籍を紹介する。
1 定期刊行物の「LGBT特集」
近年の定期刊行物の「LGBT特集」を、国立国会図書館の検索機能(NDL-OPAC)で拾い出して、分野別に分類して時系列的に並べてみた。もちろん、拾い漏れはあると思うし、特集になっていない重要な論考もあると思うが、一応の傾向は見えてくると思う。
2012年(2)経済2
2013年(0)
2014年(2)人権1 報道1
2015年(10)労働3 経済2 人権2 労務管理1 教育1 思想1
2016年(16)法律・司法5 経営3 医療・心理3 金融2 労働1 教育1 文芸1
2017年(11)労働2 法律・司法2 総合2 労務管理1 教育1 生活1 女性運動1 社会問題1
まず、指摘しておかなければならないのは、2012年夏に今回の「LGBTブーム」に火を着けたのが『週刊ダイヤモンド』(「国内市場5.7兆円 『LGBT市場』を攻略せよ!」)と『東洋経済』(「知られざる巨大市場 日本のLGBT」)の2つの経済誌だったということだ。つまり、今回の「LGBTブーム」は人権意識(社会的平等)に根差して始まったものではなく、経済的需要・思惑が先行して始まったということである。ライバル関係にある二大経済誌がまったく同時に特集を組んだのは偶然とは思えない。背後に何か大きな意図があった(誰かが仕掛けている)ことを思わせる。
しかし、経済誌が着火したものの、すぐには燃え上がらず、2013年は特集を組んだ定期刊行物は皆無、2014年も報道系、人権系各1誌だけで、火は燻(くすぶ)った状態だった。
それが、2015年夏から一気に燃え上がり、10誌が特集を組む。これは明らかに同年6月にアメリカ連邦最高裁が同性婚を認めないのは違法という決定を下したことがきっかけになっている。注目すべきは、2015年に特集を組んだのは、労働、労務管理関係の定期刊行物が多かったことだ(計4誌)。たとえば労務行政研究所の『労政時報』3892号(「新たな人事課題として認識され始める LGBT」)や労働開発研究会の『季刊労働法』251号(「LGBTと労働法」)などが出た。
これは、経済誌の『日経ビジネス』が「究極のダイバーシティー:LGBTあなたの会社も無視できない」という特集を組んだことでわかるように、これまで長い間、LGBTの存在を無視してきた日本企業が、LGBTの顕在化に「危機感」を抱き始めた結果だと思う。2000年代初頭の「性同一性障害ブーム」の時に、労務管理系の刊行物の動きが意外に早かったことを思い出す。
学術的には、『現代思想』(青土社)10月号が「LGBT―日本と世界のリアル」という特集を組み、L・G・B・T全分野にわたって、ほとんどが当事者性をもつ執筆者による24本の論考が並ぶさまはまさに壮観だった。『現代思想』がこの分野の特集を組むのは、1997年5月臨時増刊号(レズビアン/ゲイ・スタディーズ)以来18年ぶりのことだった。その18年の空白は1990年代の「クィア・ムーブメント」が頓挫して以降、日本の性的マイノリティの運動の長い停滞を表していると思う。
-21026.jpg)
2016年になると、火はますます盛大に燃え盛り、なんと16誌が特集を組む。まず、春から夏にかけて経営誌・金融誌の特集が続く(計5誌)。たとえば、経営倫理実践研究センターの『経営倫理』82号(「LGBTと経営倫理」)や金融財政事情研究会の『ファイナンシャル・プラン』7月号(「知らないではすまされない LGBTの話」)などがある。正直言って、LGBTと金融がどう関わるのか、よくわからない。Tには優秀なトレーダーが何人かいるのは知っているが、金融トレードの場では別にLBGTだからといって特別扱いされるわけはないだろう。
夏になると法律・司法系誌の特集が連続する(計5誌)。日本司法書士会連合会の『月報司法書士』7月号(「セクシュアル・マイノリティ~その先の多様化社会を見つめて~」)、『法律のひろば』(ぎょうせい)7月号(「セクシュアル・マイノリティへの現状と課題解決に向けて」)、日本司法書士会連合会の『月報司法書士』7月号(「セクシュアル・マイノリティ : その先の多様化社会を見つめて」)、日本弁護士連合会の『自由と正義』8月号(「LGBTと弁護士業務」)などが出て、先行していた経済的視点にようやく人権的な視点が追いついてきた。
さらに注目すべきは、これまでなかった医療・心理系誌の特集が現われることだ(計3誌)。まず『精神療法』(金剛出版)2月号(「セクシュアル・マイノリティ(LGBT)への理解と支援」)、続いて『精神科治療学』(星和出版)8月号(「LGBTを正しく理解し、適切に対応するために」)、そして『こころの科学』(日本評論社)9月号(「LGBTと性別違和」)が出た。
とくに精神医学の専門誌がLGBTを特集することには、かつて同性愛が精神病として抑圧され、そこからの脱却(脱病理化)に長く苦しい闘いを強いられたこと、性別の移行を望む人たちは今なお精神疾患の軛(くびき)のもとにあることなどを考えるといささか危惧もあった。しかし、結果的には、それらの経緯を踏まえた有益な論考が多かった。
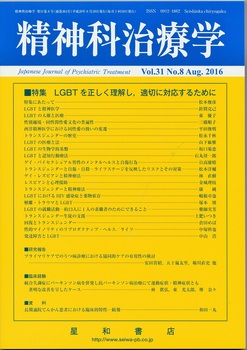
2017年は11誌で、10月までの途中集計ではあるが、2016年に比べてやや勢いが落ちたように見える。また、特集の内容にはかなり変化が見られる。それは、これまで注目されていなかったLGBTブームの「影」の部分への着目だ。まず、そのものズバリの『世界』(岩波書店)5月号(「〈LGBT〉ブームの光と影」が出て、アジア女性資料センターの『女たちの21世紀』90号(「LGBT主流化の影で」)、『AERA』2017年6月12日号(「LGBTブームという幻想:虹のふもとにある現実」)と続いた。さらに青少年問題研究会の『青少年問題』668号(「LGBTとは」)が社会問題の視点で特集を組んだ。華やかなブームの「影」で、LGBTをとりまく厳しい現実への注目は、LGBTの問題の本質が経済需要ではなく人権・社会問題であることを改めて確認する意味で重要だと思う。
法律・司法系誌は前年に引き続き活発で、『刑事弁護』(現代人文社)89号(「セクシュアルマイノリティの刑事弁護」)、『法学セミナー』(日本評論社)10月号(「LGBTと法」)が出た。とりわけ後者は14本の論考が並ぶ重厚な特集になっている。
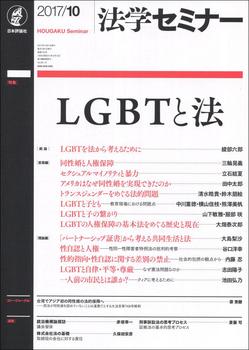
このほか、印刷媒体でないインターネット・マガジンにもLGBT関係の記事が増えている。とりわけ「BuzzFeed Japan」「ハフィントンポスト(日本版)」「ニューズウィーク(日本版)」など外資系にその傾向が顕著だ(と言うか、本体ではそれが当然)。
通時的に見ると、中には内容が伴わないブーム便乗の特集もあるように思うが、これだけ多くの定期刊行物がLGBTを特集した意味は大きい。一過性のブームではなく、日本社会にLGBT問題への関心をしっかり根付かせることができるかどうか、今がまさに正念場だと思う。
2 LGBT関連の学術系書籍
LGBTブームが起こった2012年頃以降、数多くのLGBT関連の書籍が出版されている。ここでは学術系の書籍を中心に概観してみたい。
(1)L(レズビアン)
明治から昭和戦前期の女性間性愛の歴史をまとめた赤枝香奈子の大著『近代日本における女同士の親密な関係』(角川学芸出版、2011年)以来、社会史研究にはあまり目立った進展がない。当事者性に乏しい私が「日本におけるレズビアンの隠蔽とその影響」(小林富久子ほか編『ジェンダー研究/教育の深化のためにー早稲田からの発信』彩流社、2016年)を書いたのも、そうした研究状況が背景にある。
「日本におけるレズビアン・ミニコミ誌の言説分析 ―1970年代から1980年代前半まで」(『和光大学現代人間学部紀要』10号、2017年)など昭和戦後期以降のレズビアン・コミュニティの形成過程の分析を積み重ねている杉浦郁子の研究が一書にまとまるのが待たれる。
堀江有里『レズビアン・アイデンティティーズ』(洛北出版、2015年)レズビアンであることをベースに思索を深める。とりわけ「『反婚』思想/実践の可能性」は、「家族」制の拡大が新たな排除につながらないか、単純な同性婚推進論に疑問を提起する。
パリで国際同性婚をした牧村朝子の『百合のリアル』 (星海社新書 2013年) はレズビアンの現実を語る。
また、レズビアン活動家たちのトークを収録した『日本Lばなしー日本のレズビアンの過去・現在・未来をつなぐ』(パフスクール、2017年)は私家版ながら資料として貴重だ。
(2)G(ゲイ)
2000年代に入って、風間孝・河口和也『同性愛と異性愛』(岩波新書、2010年)がある程度で長らく停滞が続いていたが、近年、一気に活況を呈してきた。とりわけゲイ・コミュニティの本格的な分析がようやく現れたことは、うれしい。
森山至貴『「ゲイコミュニティ」の社会学』(勁草書房、2012年)は、ゲイ・コミュニティにおける「つながり」に着目し、「ついていけなさ」=「つながりの困難」を社会学的に分析する。かなり難解だが、一般的にはコミュニティを形成する力であるはずの「つながり」を、逆機能的にとらえた点で画期的。
新ケ江章友『日本の『ゲイ』とエイズーコミュニティ・国家・アイデンティティ』は、1980年代以降、ゲイ世界の深刻な課題であったHIV感染/エイズ問題研究の到達点を示す。
砂川秀樹『新宿二丁目の文化人類学 ―ゲイ・コミュニティから都市をまなざす』(太郎次郎社エディタ、2015年)は、文化人類学の手法で新宿二丁目のゲイ・コミュニティを分析していて都市論に結び付けた点も興味深い。ただ、2008年提出の博士論文ほぼそのままで、その後の研究の進展が参照されていないのが惜しまれる。
三成美保編著『同性愛をめぐる歴史と法 ―尊厳としてのセクシュアリティ』 (明石書店、2015年)は、性的指向の自由は人間の尊厳にかかわる人権という観点に立った多角的な8本の論考からなる論集。
フレデリック・マルテル『現地レポート 世界LGBT事情 ―変わりつつある人権と文化の地政学』(岩波書店、2016年)は、フランスのジャーナリストによる2013年に刊行された大著『Global Gay』の全訳で、約8年にわたって世界52カ国を取材したリアリティと情報量は圧倒的。日本版では2016年前半までを視野に入れた増補がなされていて、世界各地の「ゲイ革命」の現状を知ることができる。と同時に日本のゲイ運動が世界の潮流から取り残されている状況もわかる。
前川直哉『〈男性同性愛者〉の社会史―アイデンティティの受容/クローゼットへの解放』(作品社、2017年)は、昭和期、とりわけ戦後の同性愛者の歩みを収資料に基づいて丁寧にたどった力作。資料として収集したいわゆる「変態雑誌」、「男性同性愛同人誌」の書誌研究としても有益。前著『男の絆―明治の学生からボーイズ・ラブまでー』 (筑摩書房、2011年)と合わせて、男性同性愛者の社会史研究を大きく進展させた。
-7f528.JPG)
このほか、クレア・マリィ『「おネエことば」論』(青土社、2013年)は、男性同性愛者に特徴的な「おネエことば」のジェンダー言語学的な分析だが、対象がテレビ・メディアを中心としており、ゲイ・コミュニティにおける一次的な使用例の分析に乏しいのが残念だが、ゲイ・コミュニティの深部に入れない女性研究者にそれを望むのは酷か。牧村朝子『同性愛は「病気」なの? 僕たちを振り分けた世界の「同性愛診断法」クロニクル』 (星海社新書、2016年) は同性愛の病理化の歴史をわかりやすくたどる。
また「いわゆる淫乱旅館について」(井上章一・三橋順子編著『性欲の研究・東京のエロ地理編』平凡社、2015年)、「戦後釜ヶ崎の周縁的セクシュアリティ」(『薔薇窗』26号、2015年、鹿野由行との共著)など、男性同性愛者の性愛の場である「ハッテン場」の歴史研究を精力的に進めている石田仁の研究が早く一書にまとまることを期待している。
(3)B(バイセクシュアル)
LGBTブームであるにもかかわらずバイセクシュアルの研究書は刊行されず、研究の真空地帯になっている。針間克己・平田俊明編著『セクシュアル・マイノリティへの心理的支援 ―同性愛、性同一性障害を理解する』(岩崎学術出版社 2014年)が言及している程度。
そんな状況の中で、青山薫「「『バイセクシュアル』である」と、いうこと」再考―「バイセクシュアル・アイデンティティ」の不可能性と可能性」(『現代思想』2015年10月号)は当事者性のある著者による貴重な成果。
バイセクシュアル研究の不振は世界的な傾向のようだが、日本においてはさらにその傾向が著しい。
(4)T(トランスジェンダー)
異性装の文化論は、三橋順子『女装と日本人』(講談社現代新書、2008年)、佐伯順子『「女装と男装」の文化史』(講談社新書メチエ、2009年)以降、停滞気味だったが、総合芸術誌の『ユリイカ』(青土社)2015年9月号が「男の娘ー”かわいい”ボクたちの現在」を特集した。さまざまな分野から数多くの論考が集まり、女装文化が現代日本にもしっかり受け継がれていることが確認できた。
.jpg)
服藤早苗・新實五穂『(アジア遊学)歴史のなかの異性装』 (勉誠出版、2017年)は、古今東西の異性装についての論考18本を収録し、トランスジェンダー文化の普遍性と多様性を知る上で有益。
長島淳子『江戸の異性装者(クロスドレッサー)たち―セクシュアルマイノリティの理解のために―』(勉誠出版、2017年)は近世史家による本格的な江戸時代の異性装研究。従来、日本の歴史学界はセクシュアル・マイノリティ的な存在に目を向けてこなかった傾向があるだけに画期的な著作。今後、さらなる異性装についての史料発掘が期待される。
佐々木掌子『トランスジェンダーの心理学―多様な性同一性の発達メカニズムと形成』(晃洋書房、2017年)は、臨床心理学の立場から性別移行とジェンダー・アイデンティティ(性同一性)の関係を、独自のスケールを用いて分析する。私のように数字に弱い者には歯ごたえがある内容だが、世界的な研究動向もしっかり把握していて得るものは大きい。また、これまで「性同一性障害」を論文名にすることが多かった著者が、書名を「トランスジェンダー」としたことも注目。「性同一性障害」に限定せずより広い範囲(たとえば「Xジェンダー」など)を包摂する概念として「トランスジェンダー」を選んだとのことだが、やはり時代の流れ(世界の潮流)を感じる。内分泌系の医学専門雑誌『ホルモンと臨床』(医学の世界社)が2017年秋に「内分泌科医が理解すべきトランスジェンダー」という特集を組んだのも、そうした流れだ。

その「性同一性障害」だが、2018年のWHO(世界保健機関)の疾患リストの改訂(ICD-11の施行)により、病名(疾患名)として完全に消えることがほぼ確定的となっている。同時に今まで性別の移行を望むことは精神疾患とされてきたが、その軛がようやく外れることになりそうだ(性別移行の脱精神疾患化)。
子どもの「性同一性障害」の第一人者である康純『性別に違和感がある子どもたちートランスジェンダー・SOGI・性の多様性』(合同出版、2017年)も、すでに「性同一性障害」を使っていない。「性同一性障害」を書名に掲げた学術書としては、エスノメソドロジーの手法で分析した鶴田幸恵『性同一性障害のエスノグラフィ―性現象の社会学』 (ハーベスト社 2009年)が最後になるかもしれない。
(5)その他
近年、「Xジェンダー」という言葉をしばしば聞くようになった。一見、英語のように思えるが、外国では通用しない和製英語で、gender queerに近い概念と言われていた。
LABELX編著『Xジェンダーって何? ―日本における多様な性のあり方』(緑風出版 2016年)は、初めてのXジェンダーの専論書。読んでみると、gender queerだけでなく、海外で言うgender-neutral(中性)、bi-gender(両性) A-gender(無性)、gender-fluid(不定性)、 Questioning(未確定)などを含み、内実はきわめて多様でとらえどころがない。
とらえどころがないのが「Xジェンダー」の特質という説もあるが、私は「こうあらねばならない」という規範性が強い「性同一性障害」概念から自分は外れていると感じている人たちが作りだした居場所だと考えている。世界でも稀なほど「性同一性障害」概念が広くかつ強く流布した日本で「Xジェンダー」概念が生まれた理由もそれで説明できる。
(6)LGBT
最後に、LGBT全体について。原ミナ汰・土肥いつき編著『にじ色の本棚 ―LGBTブックガイド』(三一書房、2016年)は、本稿では触れられなかった「古典」を数多く紹介している。ただ、紹介のレベルにばらつきがあるのが惜しまれる。
森山至貴『LGBTを読みとくークィア・スタディーズ入門』(ちくま新書 2017年3月)は、クィア・スタディーズの入門書。基礎的な理論から最近のLGBTの状況まで幅広く、そしてバランス良く論じていて、LGBTを学ぶのに最適・最新の書籍だと思う。ただ、Tの分野についてはやや感覚が古い気がする。日本のLGBTをめぐる状況の変化は早い。それを反映しながら改訂・増補をしていってほしい。
おわりに
1990年代の「クィア・スタディーズ」が挫折した後、2000年代の原野に1人立っているような寂々寥々たる状況を知る者にとっては、この数年のLGBT関連書籍の活況はまさに隔世の感がある。それでも、レズビアンやバイセクシュアルの研究は明らかに不足している。さらにはL・G・B・T以外のセクシュアリティ、たとえばAセクシュアル(無性愛)やパンセクシュアル(汎性愛)などはほとんど未開拓に近い。
私は非才に加えて研究者としてのスタートが遅く、日本におけるトランスジェンダー・スタディーズの細い道筋を切り拓くのが精一杯だった。今後、より才能に富んだ後進たちが豊かな学術研究の花を咲かせてくれることを心から期待している。
早稲田大学ジェンダー研究所の紀要『ジェンダー研究21』第7号(2018年1月)に寄稿したLGBTについての定期刊行物と学術書のレビューです。

日本でLGBTムーブメントが起こった2012年以降、2017年秋までを範囲として、できるだけ網羅的に記述したつもりです。
LGBTについて学ぼうとする方のご参考になれば幸いです。
----------------------------------------------
LGBTをめぐる出版状況
三橋 順子
はじめにーLGBTとはー
LGBTとは性的に非典型な主な4つのカテゴリーの英語の頭文字を合成したものである。Lはレズビアン(Lesbian:女性同性愛者)、Gはゲイ(Gay:男性同性愛者)、Bはバイセクシュアル(Bisexual:両性愛者)、Tはトランスジェンダー(Transgender:性別越境者)を表す。
本来、性的に非典型な人々が共通の政治・社会的課題に立ち向かう際の連帯を示す概念で、最初からLGBTというカテゴリーやコミュニティがあるわけではない。ところが、この言葉が日本に輸入されたときに、意味が微妙にずれてしまい、LGBTという人がいるかのような使い方がされるようになってしまった。たとえば、マスメディアに見られる「LGBT男性」「LGBT女性」という用法はあきらかに誤りだ。また「LGBT活動家」というのも首を傾げる。なぜなら1人の人間がL・G・Bを兼ねることは不可能だからだ(L・G・BとTは兼ねられる)。
それはともかく、近年、日本社会でLGBTへの注目が急速に高まっていることは間違いない。それにともなってLGBTに関連する出版が急増している。本稿は、そうした状況を概観することで、LGBTをめぐる諸問題に関心をもつ人たちへのささやかな案内になればと思う。
最初に定期刊行物の「LGBT特集」の状況について分析し、次にLGBT関連の学術系書籍を紹介する。
1 定期刊行物の「LGBT特集」
近年の定期刊行物の「LGBT特集」を、国立国会図書館の検索機能(NDL-OPAC)で拾い出して、分野別に分類して時系列的に並べてみた。もちろん、拾い漏れはあると思うし、特集になっていない重要な論考もあると思うが、一応の傾向は見えてくると思う。
2012年(2)経済2
2013年(0)
2014年(2)人権1 報道1
2015年(10)労働3 経済2 人権2 労務管理1 教育1 思想1
2016年(16)法律・司法5 経営3 医療・心理3 金融2 労働1 教育1 文芸1
2017年(11)労働2 法律・司法2 総合2 労務管理1 教育1 生活1 女性運動1 社会問題1
まず、指摘しておかなければならないのは、2012年夏に今回の「LGBTブーム」に火を着けたのが『週刊ダイヤモンド』(「国内市場5.7兆円 『LGBT市場』を攻略せよ!」)と『東洋経済』(「知られざる巨大市場 日本のLGBT」)の2つの経済誌だったということだ。つまり、今回の「LGBTブーム」は人権意識(社会的平等)に根差して始まったものではなく、経済的需要・思惑が先行して始まったということである。ライバル関係にある二大経済誌がまったく同時に特集を組んだのは偶然とは思えない。背後に何か大きな意図があった(誰かが仕掛けている)ことを思わせる。
しかし、経済誌が着火したものの、すぐには燃え上がらず、2013年は特集を組んだ定期刊行物は皆無、2014年も報道系、人権系各1誌だけで、火は燻(くすぶ)った状態だった。
それが、2015年夏から一気に燃え上がり、10誌が特集を組む。これは明らかに同年6月にアメリカ連邦最高裁が同性婚を認めないのは違法という決定を下したことがきっかけになっている。注目すべきは、2015年に特集を組んだのは、労働、労務管理関係の定期刊行物が多かったことだ(計4誌)。たとえば労務行政研究所の『労政時報』3892号(「新たな人事課題として認識され始める LGBT」)や労働開発研究会の『季刊労働法』251号(「LGBTと労働法」)などが出た。
これは、経済誌の『日経ビジネス』が「究極のダイバーシティー:LGBTあなたの会社も無視できない」という特集を組んだことでわかるように、これまで長い間、LGBTの存在を無視してきた日本企業が、LGBTの顕在化に「危機感」を抱き始めた結果だと思う。2000年代初頭の「性同一性障害ブーム」の時に、労務管理系の刊行物の動きが意外に早かったことを思い出す。
学術的には、『現代思想』(青土社)10月号が「LGBT―日本と世界のリアル」という特集を組み、L・G・B・T全分野にわたって、ほとんどが当事者性をもつ執筆者による24本の論考が並ぶさまはまさに壮観だった。『現代思想』がこの分野の特集を組むのは、1997年5月臨時増刊号(レズビアン/ゲイ・スタディーズ)以来18年ぶりのことだった。その18年の空白は1990年代の「クィア・ムーブメント」が頓挫して以降、日本の性的マイノリティの運動の長い停滞を表していると思う。
-21026.jpg)
2016年になると、火はますます盛大に燃え盛り、なんと16誌が特集を組む。まず、春から夏にかけて経営誌・金融誌の特集が続く(計5誌)。たとえば、経営倫理実践研究センターの『経営倫理』82号(「LGBTと経営倫理」)や金融財政事情研究会の『ファイナンシャル・プラン』7月号(「知らないではすまされない LGBTの話」)などがある。正直言って、LGBTと金融がどう関わるのか、よくわからない。Tには優秀なトレーダーが何人かいるのは知っているが、金融トレードの場では別にLBGTだからといって特別扱いされるわけはないだろう。
夏になると法律・司法系誌の特集が連続する(計5誌)。日本司法書士会連合会の『月報司法書士』7月号(「セクシュアル・マイノリティ~その先の多様化社会を見つめて~」)、『法律のひろば』(ぎょうせい)7月号(「セクシュアル・マイノリティへの現状と課題解決に向けて」)、日本司法書士会連合会の『月報司法書士』7月号(「セクシュアル・マイノリティ : その先の多様化社会を見つめて」)、日本弁護士連合会の『自由と正義』8月号(「LGBTと弁護士業務」)などが出て、先行していた経済的視点にようやく人権的な視点が追いついてきた。
さらに注目すべきは、これまでなかった医療・心理系誌の特集が現われることだ(計3誌)。まず『精神療法』(金剛出版)2月号(「セクシュアル・マイノリティ(LGBT)への理解と支援」)、続いて『精神科治療学』(星和出版)8月号(「LGBTを正しく理解し、適切に対応するために」)、そして『こころの科学』(日本評論社)9月号(「LGBTと性別違和」)が出た。
とくに精神医学の専門誌がLGBTを特集することには、かつて同性愛が精神病として抑圧され、そこからの脱却(脱病理化)に長く苦しい闘いを強いられたこと、性別の移行を望む人たちは今なお精神疾患の軛(くびき)のもとにあることなどを考えるといささか危惧もあった。しかし、結果的には、それらの経緯を踏まえた有益な論考が多かった。
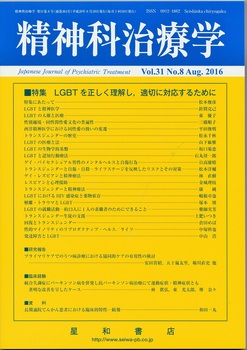
2017年は11誌で、10月までの途中集計ではあるが、2016年に比べてやや勢いが落ちたように見える。また、特集の内容にはかなり変化が見られる。それは、これまで注目されていなかったLGBTブームの「影」の部分への着目だ。まず、そのものズバリの『世界』(岩波書店)5月号(「〈LGBT〉ブームの光と影」が出て、アジア女性資料センターの『女たちの21世紀』90号(「LGBT主流化の影で」)、『AERA』2017年6月12日号(「LGBTブームという幻想:虹のふもとにある現実」)と続いた。さらに青少年問題研究会の『青少年問題』668号(「LGBTとは」)が社会問題の視点で特集を組んだ。華やかなブームの「影」で、LGBTをとりまく厳しい現実への注目は、LGBTの問題の本質が経済需要ではなく人権・社会問題であることを改めて確認する意味で重要だと思う。
法律・司法系誌は前年に引き続き活発で、『刑事弁護』(現代人文社)89号(「セクシュアルマイノリティの刑事弁護」)、『法学セミナー』(日本評論社)10月号(「LGBTと法」)が出た。とりわけ後者は14本の論考が並ぶ重厚な特集になっている。
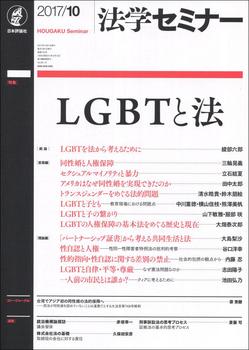
このほか、印刷媒体でないインターネット・マガジンにもLGBT関係の記事が増えている。とりわけ「BuzzFeed Japan」「ハフィントンポスト(日本版)」「ニューズウィーク(日本版)」など外資系にその傾向が顕著だ(と言うか、本体ではそれが当然)。
通時的に見ると、中には内容が伴わないブーム便乗の特集もあるように思うが、これだけ多くの定期刊行物がLGBTを特集した意味は大きい。一過性のブームではなく、日本社会にLGBT問題への関心をしっかり根付かせることができるかどうか、今がまさに正念場だと思う。
2 LGBT関連の学術系書籍
LGBTブームが起こった2012年頃以降、数多くのLGBT関連の書籍が出版されている。ここでは学術系の書籍を中心に概観してみたい。
(1)L(レズビアン)
明治から昭和戦前期の女性間性愛の歴史をまとめた赤枝香奈子の大著『近代日本における女同士の親密な関係』(角川学芸出版、2011年)以来、社会史研究にはあまり目立った進展がない。当事者性に乏しい私が「日本におけるレズビアンの隠蔽とその影響」(小林富久子ほか編『ジェンダー研究/教育の深化のためにー早稲田からの発信』彩流社、2016年)を書いたのも、そうした研究状況が背景にある。
「日本におけるレズビアン・ミニコミ誌の言説分析 ―1970年代から1980年代前半まで」(『和光大学現代人間学部紀要』10号、2017年)など昭和戦後期以降のレズビアン・コミュニティの形成過程の分析を積み重ねている杉浦郁子の研究が一書にまとまるのが待たれる。
堀江有里『レズビアン・アイデンティティーズ』(洛北出版、2015年)レズビアンであることをベースに思索を深める。とりわけ「『反婚』思想/実践の可能性」は、「家族」制の拡大が新たな排除につながらないか、単純な同性婚推進論に疑問を提起する。
パリで国際同性婚をした牧村朝子の『百合のリアル』 (星海社新書 2013年) はレズビアンの現実を語る。
また、レズビアン活動家たちのトークを収録した『日本Lばなしー日本のレズビアンの過去・現在・未来をつなぐ』(パフスクール、2017年)は私家版ながら資料として貴重だ。
(2)G(ゲイ)
2000年代に入って、風間孝・河口和也『同性愛と異性愛』(岩波新書、2010年)がある程度で長らく停滞が続いていたが、近年、一気に活況を呈してきた。とりわけゲイ・コミュニティの本格的な分析がようやく現れたことは、うれしい。
森山至貴『「ゲイコミュニティ」の社会学』(勁草書房、2012年)は、ゲイ・コミュニティにおける「つながり」に着目し、「ついていけなさ」=「つながりの困難」を社会学的に分析する。かなり難解だが、一般的にはコミュニティを形成する力であるはずの「つながり」を、逆機能的にとらえた点で画期的。
新ケ江章友『日本の『ゲイ』とエイズーコミュニティ・国家・アイデンティティ』は、1980年代以降、ゲイ世界の深刻な課題であったHIV感染/エイズ問題研究の到達点を示す。
砂川秀樹『新宿二丁目の文化人類学 ―ゲイ・コミュニティから都市をまなざす』(太郎次郎社エディタ、2015年)は、文化人類学の手法で新宿二丁目のゲイ・コミュニティを分析していて都市論に結び付けた点も興味深い。ただ、2008年提出の博士論文ほぼそのままで、その後の研究の進展が参照されていないのが惜しまれる。
三成美保編著『同性愛をめぐる歴史と法 ―尊厳としてのセクシュアリティ』 (明石書店、2015年)は、性的指向の自由は人間の尊厳にかかわる人権という観点に立った多角的な8本の論考からなる論集。
フレデリック・マルテル『現地レポート 世界LGBT事情 ―変わりつつある人権と文化の地政学』(岩波書店、2016年)は、フランスのジャーナリストによる2013年に刊行された大著『Global Gay』の全訳で、約8年にわたって世界52カ国を取材したリアリティと情報量は圧倒的。日本版では2016年前半までを視野に入れた増補がなされていて、世界各地の「ゲイ革命」の現状を知ることができる。と同時に日本のゲイ運動が世界の潮流から取り残されている状況もわかる。
前川直哉『〈男性同性愛者〉の社会史―アイデンティティの受容/クローゼットへの解放』(作品社、2017年)は、昭和期、とりわけ戦後の同性愛者の歩みを収資料に基づいて丁寧にたどった力作。資料として収集したいわゆる「変態雑誌」、「男性同性愛同人誌」の書誌研究としても有益。前著『男の絆―明治の学生からボーイズ・ラブまでー』 (筑摩書房、2011年)と合わせて、男性同性愛者の社会史研究を大きく進展させた。
このほか、クレア・マリィ『「おネエことば」論』(青土社、2013年)は、男性同性愛者に特徴的な「おネエことば」のジェンダー言語学的な分析だが、対象がテレビ・メディアを中心としており、ゲイ・コミュニティにおける一次的な使用例の分析に乏しいのが残念だが、ゲイ・コミュニティの深部に入れない女性研究者にそれを望むのは酷か。牧村朝子『同性愛は「病気」なの? 僕たちを振り分けた世界の「同性愛診断法」クロニクル』 (星海社新書、2016年) は同性愛の病理化の歴史をわかりやすくたどる。
また「いわゆる淫乱旅館について」(井上章一・三橋順子編著『性欲の研究・東京のエロ地理編』平凡社、2015年)、「戦後釜ヶ崎の周縁的セクシュアリティ」(『薔薇窗』26号、2015年、鹿野由行との共著)など、男性同性愛者の性愛の場である「ハッテン場」の歴史研究を精力的に進めている石田仁の研究が早く一書にまとまることを期待している。
(3)B(バイセクシュアル)
LGBTブームであるにもかかわらずバイセクシュアルの研究書は刊行されず、研究の真空地帯になっている。針間克己・平田俊明編著『セクシュアル・マイノリティへの心理的支援 ―同性愛、性同一性障害を理解する』(岩崎学術出版社 2014年)が言及している程度。
そんな状況の中で、青山薫「「『バイセクシュアル』である」と、いうこと」再考―「バイセクシュアル・アイデンティティ」の不可能性と可能性」(『現代思想』2015年10月号)は当事者性のある著者による貴重な成果。
バイセクシュアル研究の不振は世界的な傾向のようだが、日本においてはさらにその傾向が著しい。
(4)T(トランスジェンダー)
異性装の文化論は、三橋順子『女装と日本人』(講談社現代新書、2008年)、佐伯順子『「女装と男装」の文化史』(講談社新書メチエ、2009年)以降、停滞気味だったが、総合芸術誌の『ユリイカ』(青土社)2015年9月号が「男の娘ー”かわいい”ボクたちの現在」を特集した。さまざまな分野から数多くの論考が集まり、女装文化が現代日本にもしっかり受け継がれていることが確認できた。
.jpg)
服藤早苗・新實五穂『(アジア遊学)歴史のなかの異性装』 (勉誠出版、2017年)は、古今東西の異性装についての論考18本を収録し、トランスジェンダー文化の普遍性と多様性を知る上で有益。
長島淳子『江戸の異性装者(クロスドレッサー)たち―セクシュアルマイノリティの理解のために―』(勉誠出版、2017年)は近世史家による本格的な江戸時代の異性装研究。従来、日本の歴史学界はセクシュアル・マイノリティ的な存在に目を向けてこなかった傾向があるだけに画期的な著作。今後、さらなる異性装についての史料発掘が期待される。
佐々木掌子『トランスジェンダーの心理学―多様な性同一性の発達メカニズムと形成』(晃洋書房、2017年)は、臨床心理学の立場から性別移行とジェンダー・アイデンティティ(性同一性)の関係を、独自のスケールを用いて分析する。私のように数字に弱い者には歯ごたえがある内容だが、世界的な研究動向もしっかり把握していて得るものは大きい。また、これまで「性同一性障害」を論文名にすることが多かった著者が、書名を「トランスジェンダー」としたことも注目。「性同一性障害」に限定せずより広い範囲(たとえば「Xジェンダー」など)を包摂する概念として「トランスジェンダー」を選んだとのことだが、やはり時代の流れ(世界の潮流)を感じる。内分泌系の医学専門雑誌『ホルモンと臨床』(医学の世界社)が2017年秋に「内分泌科医が理解すべきトランスジェンダー」という特集を組んだのも、そうした流れだ。

その「性同一性障害」だが、2018年のWHO(世界保健機関)の疾患リストの改訂(ICD-11の施行)により、病名(疾患名)として完全に消えることがほぼ確定的となっている。同時に今まで性別の移行を望むことは精神疾患とされてきたが、その軛がようやく外れることになりそうだ(性別移行の脱精神疾患化)。
子どもの「性同一性障害」の第一人者である康純『性別に違和感がある子どもたちートランスジェンダー・SOGI・性の多様性』(合同出版、2017年)も、すでに「性同一性障害」を使っていない。「性同一性障害」を書名に掲げた学術書としては、エスノメソドロジーの手法で分析した鶴田幸恵『性同一性障害のエスノグラフィ―性現象の社会学』 (ハーベスト社 2009年)が最後になるかもしれない。
(5)その他
近年、「Xジェンダー」という言葉をしばしば聞くようになった。一見、英語のように思えるが、外国では通用しない和製英語で、gender queerに近い概念と言われていた。
LABELX編著『Xジェンダーって何? ―日本における多様な性のあり方』(緑風出版 2016年)は、初めてのXジェンダーの専論書。読んでみると、gender queerだけでなく、海外で言うgender-neutral(中性)、bi-gender(両性) A-gender(無性)、gender-fluid(不定性)、 Questioning(未確定)などを含み、内実はきわめて多様でとらえどころがない。
とらえどころがないのが「Xジェンダー」の特質という説もあるが、私は「こうあらねばならない」という規範性が強い「性同一性障害」概念から自分は外れていると感じている人たちが作りだした居場所だと考えている。世界でも稀なほど「性同一性障害」概念が広くかつ強く流布した日本で「Xジェンダー」概念が生まれた理由もそれで説明できる。
(6)LGBT
最後に、LGBT全体について。原ミナ汰・土肥いつき編著『にじ色の本棚 ―LGBTブックガイド』(三一書房、2016年)は、本稿では触れられなかった「古典」を数多く紹介している。ただ、紹介のレベルにばらつきがあるのが惜しまれる。
森山至貴『LGBTを読みとくークィア・スタディーズ入門』(ちくま新書 2017年3月)は、クィア・スタディーズの入門書。基礎的な理論から最近のLGBTの状況まで幅広く、そしてバランス良く論じていて、LGBTを学ぶのに最適・最新の書籍だと思う。ただ、Tの分野についてはやや感覚が古い気がする。日本のLGBTをめぐる状況の変化は早い。それを反映しながら改訂・増補をしていってほしい。
おわりに
1990年代の「クィア・スタディーズ」が挫折した後、2000年代の原野に1人立っているような寂々寥々たる状況を知る者にとっては、この数年のLGBT関連書籍の活況はまさに隔世の感がある。それでも、レズビアンやバイセクシュアルの研究は明らかに不足している。さらにはL・G・B・T以外のセクシュアリティ、たとえばAセクシュアル(無性愛)やパンセクシュアル(汎性愛)などはほとんど未開拓に近い。
私は非才に加えて研究者としてのスタートが遅く、日本におけるトランスジェンダー・スタディーズの細い道筋を切り拓くのが精一杯だった。今後、より才能に富んだ後進たちが豊かな学術研究の花を咲かせてくれることを心から期待している。
【対談】「変わるものと、かわらないもの。女装文化への語らい。」 [論文・講演アーカイブ]
8月11日(金・祝)
『女装と思想』第6号(テクノコスプレ研究会、2015年12月31日刊行)に「巻頭特別対談」として掲載されたロングインタビュー「変わるものと、かわらないもの。女装文化への語らい。」。
聞き手は、あしやまひろこさん。
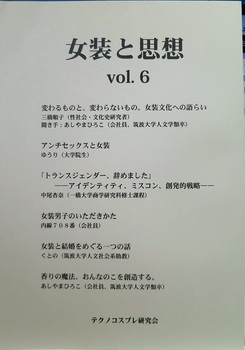

【目次】
1.女装者と男。女装者と女。
2.女装世界の変遷と媒体。ネット以前の出会い。
3.性同一性障害と女装世界
4.男の存在しない女装世界の登場
5.口コミと草の根の時代への回想
6.女装と容姿
7.「場」の変化。変わらぬ根底。
8.女装とテクノロジー、発達障害
9.女装の力。変化と連続の文化。
----------------------------
対談「変わるものと、かわらないもの。女装文化への語らい。」
20-20E382B3E38394E383BC-c3a3b.jpg)
↑ 「ネオンが似合う女」になれた頃(1997年4月)。
『週刊Spa!』に掲載された写真。
聞き手:あしやまひろこ
語り手:三橋順子

↑ 対談時(2015年10月17日:下北沢)
1.女装者と男。女装者と女。
あしやま 女装者は男性が好きって誤解されがちなのですが、私もですが、三橋先生も女性がお好きでしたよね。
三橋 かなりの女好きです(断言)。ただね、90年代の六本木や新宿歌舞伎町を女装で歩いていると、男性が寄ってくるんですよ。最初は誘われても断っていたのですが、だんだん面倒になってくるし、自分がヘテロセクシュアル(異性愛)の男性に、女として見られ、誘われ、扱われることで、承認欲求が満たされるということがあって、そのうち場合によってはOKするようになりました。
私は性行為的には男性もOKで、男性とのプレイには性的な快感は十分にありました。請われるままにセックスフレンドとして長く関係をもった人もいましたが、心理的に惚れたことはありません。相手の男性も色恋を求めないさばけた人が多かったので、うまくいってたように思います。
あしやま 僕も共感します。相手ではなく、相手と接触している自分自身を見ているという。自分自身が女としての立場であるために、相手としての男を利用している。
三橋 自分を女にしてくれる道具のように男性を思っていましたね。私を女として扱い、女として気持良くしてくれる男が望ましい。それで、ホテルの部屋に大きな鏡があればなおいい。女として扱われる自分を鏡に映して自分で見たい、そういう欲望は強くありました。そこに相手の男が映る必要はないのです。そこらへん、ゲイの人たちとは感覚がかなり違うと思います。
あしやま その感覚はヘテロセクシャルな女装者にもかなりあると思います。男性相手にそういう感情を抱かなくとも、女として扱われたいと。
三橋 性的な関係が長く続いた相手が何人もいたのは、早い話、相手も気持ち良かったのだと思うのですね。
『性的なことば』(講談社現代新書)に書きましたが、ある経験豊富な男性に「あんたみたいな尻を、金の茶釜というんや。覚えとき」って教えられたことがありました。「金の茶釜」とは、おしりの名器のことです、女性の名器と同じで、相手にしか分からない、自分ではわからないのですけど、「フィット感が抜群だ」とよく言われました。
あしやま そのような体を作るための訓練は必要ではなかったのですか。
三橋 訓練はほとんどしてないです。かなり先天的なものだと思います。筋肉の質というか伸縮性がすごくあって、かつ丈夫。今にしてみると、ある種の才能なのだろうと思いますが、当時は、それほど自覚はなかったです。
で、繰り返しになりますが、本質的には男好きじゃないんですね。女装していても、寄ってくる女性もいます。しかも、けっこう「いい女」が。でも、相手の女性は私に男を求めてくるわけではないし、私も男性として接する気はない。レズビアン・ファンタジーなんですね。
何度もデートした女性とは、お互い好意を抱いていたわけですが、行為にうつれない。互いの手と手をずっと握りあっているだけ。後になって「どうしてあの時、押し倒してくれなかったの?」と言われましたが、それは、私も同じ気持ちで(笑)。レズビアン・ラブの経験がないから、お互いどういう手順を踏んだらいいのか分からなかったのです。
あしやま 女性として振舞っているわけですから、どう振る舞うかは難しいですよね。でも、三橋先生はすごいなとも思うところで、僕がそのようなシチュエーションにあったら男性として振る舞うだろうなと思います。
三橋 そう簡単には切り替われないし、そこで男になっちゃうのはなんか違うと思うのですよ。
歌舞伎町の「ジュネ」というお店でお手伝いホステスしていた頃、まだ「キャバクラ」なんていう言葉ができる前の話です。女性が接客する飲み屋は深夜営業できないわけですが、女装者が接客するお店は、法的には男性なので風営法の適用外で深夜営業ができるんです。
だから、六本木のクラブ・ホステスさんが、自分の店が終わった後に、タクシーに乗って飲みに来てくれます。でも、自分の店や、アフター(閉店後のお客さんとの付き合い)で飲んでるから、かなり酔っぱらっていて、会うなりいきなり「順子さ~ん」と抱きついてくる。危ないからしっかり抱き止めるわけですが、なにしろ六本木の高級クラブのナンバーワンクラスですから、胸も大きいし、腰のクビレもしっかりあって、すごい身体してるわけです。
そんな女性に密着されても、私は勃たない。もったいないなという気持ちと、自分が女というロール(役割)をちゃんとやっているんだという自己満足の両方がありました。
あしやま 自分はそういうシチュエーションはオイシイと思ってしまって。学生時代に他大学を交えた懇親コンパみたいなところで、女の子が可愛いでね、なんて言いながらハグをしてきたりしたときは嬉しかったりして。まあ、途中でそいつは男だからって止めが入るんですけれど。
三橋 女性が女装者を女性として認識しているから距離が近くなるんです。逆に女装者と男性とは対人距離が遠くなる。一般的に、男同士の距離は遠いですが、女性同士の距離は近いですね。
あしやま 女装しているとその基準になりますね。自分の女装を男性は遠巻きに見るんですが、女性はグイグイ寄ってきて。見た目は大きい感じがします。
三橋 女性の身体距離がすごく近いです。心理的には女同士という感覚であっても、もし体が反応してしまうと相手を裏切ることになる。女として近づいておきながら、男を出すというのは、とてもフェアーじゃない気がする。そういう可能性がある自分が嫌というか、恐怖感を抱いていましたね。
あしやま 僕は女性と女装者を描いた、例えば糸杉柾宏さんの作品を読むと、時には「生えている」女の子を求めている場合もあったりしないかなと思うこともあれば、男と前置きはしますが女装で仲良くなって男として……というのも良いのではないかという感覚もあって。好きな漫画に『ゆびさきミルクティー』というものがあるのですが、主人公は女装をしているけれども、色々と女性関係もあり彼女もいるというか、すごい都合がいい話だなとも思いますが。
三橋 私の世代にも、シメシメと思っていた人もいたかもしれませんけれど、私は嫌でした。だから、とても素敵な女性と共寝して、上半身はしっかり抱き合っていても、下半身は離すようにしていました。男相手の時は徹底的に女を演じ、女相手の時は男を出さないというのが、私の原則。
私が妻と良好な関係なのは、相手があまり私に男を求めてきていないからということがあるのかもしれません。女性との関係は精神的には深いわけですが、肉体的なものはほとんどなく、男性との関係は、その逆で、肉体的には深かったけど、精神的にはまったく浅いという感じでした。
あしやま トラニーチェイサーのような、女装が好きな人というのは何を求めてきていたのでしょうかね。
三橋 私は、ホステス倫理としてお店のお客さんとは寝ない主義だったので、一度もしたことはありません。お付き合いした男性は、全部、店の外の人です。だから、トラニーチェイサー的な人との付き合いは多くなくて、中には女装者が好きな男性もいましたが、長くお付き合いした方はそうではなかったですね。
声を掛けてくる男性には、自分が女装者であることを告げるわけですが、「自分はあなたみたいな女装の人は初めてだけど、それでもいいから付き合ってくれ」と言われたときは、うれしかったです。その男性、材木商の若旦那とはいちばん長く続きました。松本侑子さんの小説「女装夢変化」(『性遍歴』収録)のモデルになった出会いです。
あしやま 歌舞伎町は男性向けのキャバクラのようなイメージがありますが、当時は違うものもあったのでしょうか。
三橋 私が、男遊びが面白くてしかたがなかった時期は、九四年から九七年くらいですが、声を掛けられるのは、新宿では歌舞伎町エリアより、新宿駅周辺が多かったです。二丁目はゲイの世界ですから近づきません。六本木は、路上でも、ゲームセンターでも、酒場でもどこでもナンパされるという感じ。不思議なのは渋谷で、声を掛けられたことがほとんどなく、やっぱり性的な雰囲気が薄いのだと思います。
性的快楽に積極的な、濃い人が多かったから、その4年間で色々なことをやり尽くした感じがあって、その後は性的なものに執着しなくなりました。
あしやま 濃い人といえば、両性的なな……「生えてる」女の子こそ最高という人もいますよね。
三橋 『女装と日本人』にも書きましたが、乳房もペニスもどちらもある「娘」が大好き、ペニスのついた女の子を射精させるのが最高という男性もがいますよね。女装者は変態なって言われるけど、そっちの方がよっぽど変態じゃない、って言いたくなるような男性。
でも、そういう人が女装文化を裏から支えてきた部分があるわけで、江戸時代の陰間茶屋から現代のニューハーフや女装の飲み屋まで、そうした女装者大好きの男性が連綿と続いてきたんじゃないかと思います。性にも歌舞伎の女形にキャーキャー言っている人が途絶えることなく続いている。それが、日本文化の特質のひとつなんだと思います。
あしやま 自分自身は、バイセクシャルやパンセクシャルな女性とお付き合いした経験があって、女性同士だと入れるものもないし、みたいな話をされた事があって。
三橋 一種のレズビアン・ファンタジーを持っている女性はけっこういますよ。『女装と日本人』にも書いた通り、日本人の「曖昧な性」への嗜好は、近代化の中で上部構造は男女二元的に変わっても、ベーシックな部分では変わっていないというのが私の感覚ですね。
20-20E382B3E38394E383BC.jpg)
↑ 六本木で遊び始めた頃(1994年11月)
2.女装世界の変遷と媒体。ネット以前の出会い。
あしやま 自分自身が今こうして女装しているのは、コスプレを含めてインターネットとの関わりが深いのかなと。
三橋 インターネットの登場は、大きな転換点でした。普及は1997~98年ごろに若い男性から始まり、最後に到達したのが中年女性でした。たとえば着物趣味の女性のコミュニティの成立が2001年ごろです。女装世界は、男性の世界なのでインターネットの普及が早く、97年にはもういくつかのサイトが立ち上がっていました。
その前に90年代前半からパソコン通信が広まって、東京中心の「EON」、大阪中心の「スワンの夢」の東西二大ネットが成立していました。パソコン通信からインターネットへの転換がだいたい98年くらいです。
これは偶然なのですが、性同一性障害の概念が流布しはじめたのもその時期でした。そして、00年代になると、直接的な対人コミュニティで成立していた新宿の女装世界が衰えていき、『くいーん』『ひまわり』『ニューハーフ倶楽部』といった雑誌媒体も次々に廃刊になりました。雑誌媒体の衰退理由は、端的に言えば、インターネット上で無修正のシーメールポルノが簡単に見られるようになったからですね。
『くいーん』は「女装交際誌」を名乗っていたように雑誌が仲介する「文通」がメインだったわけですが、90年代半ばに、パソコン通信や、ポケベル、PHSが普及していくと、時代遅れになって衰退していきました。
私が遊んでいたのは、ちょうどポケベルからPHSの時代で、NTTの伝言ダイヤルの全盛期でした。伝言ダイヤルには「02134649(オニイサンヨロシク)」という女装系のボードがあって、パスワードは「1919(イクイク)」でした(笑)。どこに書いてあるわけでなく、コミュニティ内の口コミで広がっていましたね。
伝言ダイヤルですから、声を録音するわけですが、私は声が絶対の強みだったので、週末にセクシーボイスで伝言を入れておくと、一時間に五~六本というペースで掛かってきます。それを聞いてPHSや公衆電話からかけ直して、この人は大丈夫そうだなと判断すると、待ち合わせ場所と時間を決めて、実際に会うわけです。
あしやま 相手は女装者の場合もあったのですか。
三橋 女装者はほとんどありません。もっぱら相手は男性でした。ゲイ系の人は感性が合わないので避けて、女装者好きで、私を女性として見立ててくれる人とだけ会いました。いきなりホテルへということもありましたけど、いっしょに食事をして軽く飲んで、それから・・・という普通のデートが多かったです。
バブルの余韻が残っていた時代ですから、たとえばサラ金業界の幹部とのデートは、必ず「かに道楽」。すごい量の蟹を食べさせてもらってからラブホテルに行くのですが、セックスの方はからきし弱い方で、こんなに奢ってもらっているのに申し訳ないなぁ、という感じでした。
逆に、東京出張の度に赤坂や西新宿の高級ホテルに呼んでくれる関西の社長さんは、セックスがとても強い人で、まず大東京の夜景眺めながら窓辺で立ちバックで一回、ベッドでもう一回、一眠りして朝日の中でもう一回。相手は「じゃあ、またな」って感じで、そのまま仕事へ。
私が化粧を直して、キーを返しにフロントに行くと、フロントマンから「ご伝言です」と封筒を渡されて、中には1万円札3枚のお小遣いと朝食券なんてこともありました。3000円の朝食って、後にも先にも、その時だけです。まあ、良い時代って言えば、そうでしたね。
3.性同一性障害と女装世界
あしやま 九〇年代末の変化は媒体以外にもありましたか。
三橋 「性同一性障害」(GID)の概念の普及が大きかったですね。それまでは、女になりたいと思う人は、まずは女装やニューハーフの世界に足を踏み入れていたわけです。店が入口だったのです。ところが、メディアがGIDをしきりに報道するようになると、性別に違和感を持っている人は、病院を入口にしてしまうわけですね。そうなると、お店に新人が来なくなってしまう。
00年代前半のGID概念の広がりは、人材を奪われるという意味で女装業界にとって大打撃でした。それと、ほぼ同時にインターネットが普及するわけですが、今にして思うと「ジュネ」をはじめとして新宿のお店はネット対応が遅れていましたね。
あしやま 口コミで構築されていたコミュニティを敢えてネットに出すというのも違うということでしょうか。
三橋 そうですね。「ジュネ」のママは株取引をネットでやっていましたから、ネットができないわけではなかったけど、お店の宣伝をネットでやろうという発想はまったくなかったです。「女装なんて、わざわざ宣伝して広めるもんじゃない」という考え方でした。そんなこともあって、女装系のお店の最大の危機は00年代でした。
ですから06年から07年にかけて『女装と日本人』を書いた頃の私には、女装の世界がもう無くなってしまうという危機感が強くありました。ともかくこの世界のことを書き残しておこうという、ある種の遺言のようなつもりで、かなりの悲壮感をもって執筆しました。
ところが、原稿を出版社に入れた08年頃に、何か様子がおかしいと気づきはじめました。街頭で、見た目は女性同士だけど、片方は女装者らしいカップルを立て続けに目撃したことがきっかけでした。九七年に私が女性と同伴出勤したら、「女装者なのに、女性とデートするなんて変態!」だって言われましたから、10年の間になにかが大きく変わりつつあることに気づいたのです。
あしやま オネエ系タレントがメディアに登場することも増えましたし関係性が変わったのでしょうか。女装者はただの変態ではないという認識が広まったのでしょうか。
三橋 日本テレビの「おネエ★MANS!」は06年秋からです。関係性が変わってきた理由について思うのは、97年ごろに「性同一性障害」の概念が登場してから10年の間に、性別越境の病理化がどんどん浸透していき、病気としての性別移行という形態に、息苦しさを感じるようになった人が増えてきたのだと思います。
4.男の存在しない女装世界の登場
三橋 『女装と日本人』執筆以降の変化についてまとめた「変容する女装文化」という論文を2009年に『『コスプレする社会 -サブカルチャーの身体文化-』(せりか書房)という論集に発表しました。
そこでのポイントは関係性の変化です。それまで、女装することと男性と性的関係をもつことは表裏一体でした。私は男から店で声を掛けられても断る第一世代だったので、ずいぶんで「生意気だ」と言われましたけれど、そうした男性との関係性から女性との関係性に移行してきたことに注目したわけです。
あしやま 男と寝ることと表裏一体であった女装文化が、ここ最近変化してきたということですよね。
三橋 昔(90年代半ば頃)の女装者は男性からの誘いはまず拒否しなかったです。どれだけたくさんの男と寝たかが女装者の勲章という雰囲気がありましたからね。
あしやま 当時も居たと思うのですが、男と関係を持ちたくないという女装者はどのようにしていたのでしょうか。
三橋 そうした人たちが、最初に集団を成したのが「エリザベス会館」です。「エリザベス」ができたのが78年ですが、かなり初期の段階(1980年代初頭)で男性とのセクシャリティを切りました。
60~70年代が全盛だった女装秘密結社「富貴クラブ」では、男性が圧倒的な力を持っていたのとは対照的ですね、新宿で男を相手にしてきた女装者の中には、年をとってモテなくなって、「エリザベス」に「隠居」する人もいました。
若いころモテた中高年女装者には二パターンがあり、モテなくなった段階でいっさい男性との性的関係を断ち切って、例えば「エリザベス」へ隠居しちゃうようなプライドの高い人。もう一方は60、70歳になっても、なんとか男を捕まえようとあがく人。どちらも大先輩で、その姿を間近でみていました。
後者の方は、着物女装なんですけど、店に来る若い男性客の隣に座ると、男の手をとって(女性着物の脇の下に開いている)身八つ口に引き込んで、乳房に触らせるんです。でも、若い男性にしてみたら、老女のおっぱいなんて触りたくないわけで、トイレに行くふりをして、チーママや私のところに「席、変えてくれ」って苦情を言ってくる。業が深いというか、もう完全に悪あがきですよ。いろいろお世話になった先輩ですけど、正直「自分は、絶対にああはなりたくない」と思いましたね。
加齢は、女装者だれでも避けられないことですから、やはり歳をとったときの身の処し方は、店に迷惑をかけないように、ちゃんと考えるべきです。
あしやま 今の女装者は、必ずしも男性との関係性を前提としていなかったり、異性愛者も多いように感じますから、この場の文化は今にも影響を与えているようにも思います。
三橋 「プロパガンダ」は、もっと男性中心なのかなと思いながら行ったら、おじさんたちは隅で小さくなっていて全然勢いがない。元気よく女装者に声を掛けているのは女の子ばかりで、つくづく時代も変わったんだなと思いました。
あしやま 女の子も女装者に近づきたい欲が開放されたんでしょうかね。
5.口コミと草の根の時代への回想
あしやま 八〇年代ごろからそのように文化にも幅が出てきたわけですね。しかし、今の若い女装者はエリザベスに行くわけでもないですし、先ほどのお話にあったように媒体の変遷もありました。今は、よりポップな、もっとファッション感覚の女装が生まれたのかなと思うところがありまして。
三橋 おそらく同人誌の活動やコスプレ文化が影響して、新しい女装文化が誕生したのだと思います。「性同一性障害」的なものに嫌気のさした若い世代と、コスプレ系の感覚がマッチしたのではないでしょうか。
90年代にも、コスプレ系の女装者も居なくはなかったのすよ。コスプレ系女装は、新宿でも「エリザベス」でもなく、やはりキャンディ・ミルキィさん(現在キャンディ・H・ミルキィと改名)の雑誌『ひまわり』に集まっていましたね。キャンディさん自身がああだから、コスプレ系女装の人にとっては、とても居心地の良い場所だったと思います。
あしやま 僕よりも一世代上のコスプレ女装関係の人は、みなさん必ずキャンディさんのお名前を出されますよね。
三橋 「向日葵学園女子高等学校」という誌上企画があって、制服女装も『ひまわり』が中心でした。
『ひまわり』の創刊は87年で最初はキャンディさんの個人誌です。キャンディさんがメディアに登場して有名になるにつれて徐々に雑誌としての体裁が整って、93年に季刊になり、98年には隔月になり…。90年代半ばが、一番活気があったと思います。
ただし、当時もコスプレ女装に一定の需要はあったと思いますが、コミケも大規模でなく、そこで『ひまわり』を頒布ということもなかったわけで、キャンディさん自身があの格好でバイクで配達していたわけで、最後まで個人発行の同人誌という色彩が濃厚でした。
そういう意味では、現代のコスプレ女装に通じる淵源ではあると思いますが、やはり、相当の世代差があると思います。文化的に論じる場合、現代のコスプレ女装の隆盛とは、ある程度、切り分けた方がいいかもしれません。
現代のコスプレ女装には、いろいろな系統があると思います。コスプレから入る人、性同一性障害的なところから入ってくる人。そして、女装ができる場が昔よりずっと多様になっている。それは、とても良いことだと思います。
話がずれましたが、女装するという行為が男性との関係性から抜け出して、むしろ女性との関係性の比重が増していく、その転換の意味はすごく大きいと思います。
あしやま それが00年代の転換というわけですね。
三橋 女装者好きの女性は、いつ、どこから出現してきたのか、いわゆる腐女子的な世界からなのか、それとも違うのか、まだリサーチしていないのでわかりませんが、もともとそうした嗜好をもった女性は一定数いて、それが表に出やすくなったのだと思います。
やはり「場」の問題で、「プロパガンダ」みたいにそこに行けば女装者に会えるという場所があること、その情報に容易にアクセスできるようになったことが、何より大きいと思います。私たちの時代にはそれがまったくと言っていいほどなかった。稀にお店にくる女性は水商売や風俗産業の方がほとんどでした。
「場」の設定、そこへのアクセスという点で、90年代と00年代とでは根本的に違っていると思うのです。
あしやま 古代から日本人の中にあった根源的欲求のようなものが、アクセスできる手段と場所が設定されたことで、表出したという。
三橋 そうですね。『女装と日本人』に書いたように、日本人は男女を問わず、基本的に女装者が好きなのですよ。ただ、現実にはそこになかなかたどり着けなかった。新宿のゴールデン街に女装の店があるという話が、週刊誌やスポーツ新聞の隅っこに小さく載っている。情報っていってもその程度なんですね。
私の友人は、そういう記事を見て、ポケットに札束を入れて、ゴールデン街の店を一軒一軒、片端から飲み歩いて、10万円くらい飲んだところで、やっと店主から「ジュネ」の場所を教えてもらい、「ジュネ」にたどり着きました。おそらく他の店でも知っていたのでしょうが、教えてくれなかったのでしょうね。執念に加えて偶然、それに相当な根性とお金がないと、たどり着けない世界だったのです、女装の世界は。
6.女装と容姿
三橋 そうやって、やっと新宿女装世界にたどり着いても、ママから「あなたは(女装に)向いていないから止めなさい」なんて言われることもあります。傍から見ていてもむごい話だと思いますが、きれいになる素質に恵まれていない人が女装しても、辛いだけの世界なんですよね。
「エリザベス会館」は純粋アマチュアの世界なので、どんな容姿レベルでも「来るな」とは言いません。だから、10年通って、たくさんのお金を使っても、毎年開催される女装コンテストで、一度もノミネートされない人もいるわけです。逆に、入ってきてすぐに新人賞、翌年には準グランプリを獲って、店の「看板娘」に駆け上がっていく人もいます。私ですが(笑)。残酷と言えば残酷な世界なのですけど、それでも自分が我慢しさえすれば、そこにいられるわけです。
新宿の女装世界は酒場を拠点にした客商売ですからもっと露骨で、スタッフならお客が呼べる容姿かどうかがシビアに問われます。スタッフでない女装会員でも、とりあえずソファーに座って「枯れ木も山の賑わい」になるレベルならOKだけど、シビアな男性客に「お前、もっとどうにかしたらどうだ」なんて言われたら、ほんとうにどうしようもなくなってしまうわけですね。つまり、容姿的な適性で淘汰が起きるわけです。
一方、「性同一性障害」の場合は、お医者さんは「あなたはきれいにならないから、女になるのは止めなさい」とは絶対に言わない、言えないですから、診察・治療段階では容姿適性による淘汰は起きません。
あしやま コスプレの世界でも同じで、男女問わず見た目で判断されますよね。そして悪あがきではないのですが、パソコン上で写真を補正してなんとか、という人も多いわけです。実際会うと、誰?となる人も多くて。
三橋 コスプレ趣味であっても、美形とそうでない人とでは、周りに集まるカメラの数は明らかに違うでしょうし、更にいろいろ言われるわけでしょう。いくら写真で補正していても、いざ実際に会うと「写真とぜんぜん違う」という問題も出てきてしまうわけですよね。
あしやま 似合うかの問題はどうしようもなくて……。
三橋 「そんな醜い女装者は見たくない、勘弁してくれ」と思う権利も一般人にはあるわけです。そして、中にはそれを口に出しちゃう人もいる。少なくともなんでもアリかといえばそうではなく、容姿が問われてしまうわけです。
けれども、「性同一性障害」というレッテルを貼ると、医療福祉の問題になりますから、容姿をあれこれ言うことはできなくなる。「病気じゃあ、仕方がないだろう」ということです。そういう意味で「性同一性障害」という概念は「救い」であったわけです。
でも、そういう「性同一性障害」というレッテルを貼った「かわいそうな病気の人たち」が10年近くメディアに出ていたところに、病気ではないカワイイ女装者が「男の娘」というレッテルで出てくれば、メディアも一般の人の視線も一斉にそちらに行ってしまうのは仕方がないと思います。
「医療福祉」より「カワイイ」が受けるのが現実です。それを容姿主義、ルッキズム(lookism)だとの批判する人もいますけど、人間社会はおそらく有史以来ずっとルッキズムなんですね。良い悪いはともかく、現実にルッキズムがなくなるとは近未来的には思えません。
女装の世界は昔から完全にルッキズムで、ブサイクが生意気なこと言うと内容にかかわらずボコボコに批判される。美人は生意気を言っても許される。酷い世界と言えば酷い世界です。
「エリザベス会館」も新宿の女装世界も、見た目、容姿によって扱いが全然違うんですね。「人権」とか「平等」とかいう話とはまったく別の価値基準です。でもそういう「場」しかなかったんです。
そういう世界に身を置いて認められる、そしてその世界でのし上がるには、容姿を磨くしかないんです。ですから、女装と「性同一性障害」はまったく別の論理で成り立っているわけで、一緒にするのはもちろん、同列に論じるのも意味がありません。
女装の世界はルッキズムによる実力世界ですから、どれだけの人が淘汰されていったか、それこそ振り返れば死屍累々です。「性同一性障害」は医療福祉の世界ですから、淘汰が機能しちゃあいけないのです。少なくとも建前上は「かわいそうな病気の人たち」は皆、救われなければならない。
でも、この世界の現実は違う。だから「性同一性障害」の人たちもたいへんなのです。
今日は、ある自治体の主催の講座で「服装は自由である」というテーマで講演してきたのですが、それは論理的な話であって、現実は厳しいです。
あしやま 似つかわしいかどうかは大きな問題だと思っていまして、例えば僕が男姿でスカートを履いたら気持ちが悪いと思うんです。それはどうしようもないといいますか。
三橋 「気持ち悪い」と思う人に、「その感情を止めろ」と言うのは難しいし、実際にできませんよね。現実には、こちらが気持ち悪いと思われないようになるしかないのです。
20-20E382B3E38394E383BC-3bb97.jpg)
↑ 新宿歌舞伎町区役所通り「ジュネ」にて(1999年11月)
7.「場」の変化。変わらぬ根底。
三橋 飲み屋を拠点に成り立っている新宿の女装世界は、店自体が女装者と女装者を好む男性(女装者愛好男性)の出会いの場という要素があるわけですが、新宿の店育ちが一番で、次がエリザベス会館、一番下が上野などのハッテン映画館育ちという序列感覚がはっきりありました。
パソコン通信からネット掲示板時代の大スターで、一時期、フェミニズム系の活動の方にも評価されて、しきりに講演活動をされていた宮崎留美子先生という方がいらっしゃいます。ハッテン場育ちでも、上手に愛嬌を振り撒いて新宿で受け入れられる人もいるわけですけど、宮崎先生はそういうタイプじゃなく、弁が立つ分、反発も強かったわけです。
「最近、留美子って生意気な奴がいるようだけど、どこの出なの?」、「どこかのハッテン映画館の出らしいですよ」、「新宿の作法を教えてやるから、夜中の2時に花園神社の裏に呼び出しな」なんて話になったことがありました。留美子先生は終電車で帰るから、そんな時間にはもう新宿にいないのですけどね。
そんなエピソードが語るように新宿の女装世界は、よく言えば体育会系なんです。各店に古手の姐さんがいて、その世界に入るには、ママはもちろん、そうした姐さんたちにも挨拶しないといけない、悪く言えば、任侠世界的なノリがありました。
私は「エリザベス会館」から新宿に流れてきた新参者だったわけですが、新宿女装世界のドン(元締め)だった「ジュネ」の薫ママに仁義を切って、「ジュネ」のナンバーワン(若頭)の麻衣子姐さんと五分の杯を交わした客分ということになると、もう誰も文句を言えないんですね。
逆に留美子先生みたいなフリーの女装者が遊ぶのはけっこう難しい。意地悪そうな姐さんに「あんた、見ない顔ね、どこの娘?」みたいなことを言われて、いじめられかねない。でもそこで、ちゃんと挨拶して「あなた見込みがあるわね」という話になると、「ウチにいらっしゃいよ」ということで、店の支度部屋(着替えや化粧をしたり、仮眠したりする部屋)に所属することになる。そうなると「○○(店名)の〇〇子です」って名乗れて、女装コミュニティの他の店に飲みに行っても「あの子は〇〇の娘だから」ということで、飲み代が千円割引になるわけです。
あしやま お客さんがお店の更衣室で着替えるんですね。
三橋 店の中に更衣室があるところもありましたけど、「ジュネ」は店から十分程のマンションの一室が支度部屋でした。そこで着替える人が圧倒的に多くて、私みたいに家から女装して電車に乗って新宿に来る人は少なかったですね。
「ジュネ」の場合、そこで着替えたら一度は店に顔を出すのがルールで、その後はどこで遊んでも構いません。当時、月会費は1万5000円だったと思います。会員さんは店が忙しい時には接客を手伝ったりもしますが、「ジュネ」で飲んでる限り、いくら飲んでも飲み代はタダでした。フリーの女装者の料金は4000円なので、毎週末、店に来るなら会員になった方が安かったんです。
あしやま そういう世界に一度行ってみたいなと思います。
三橋 もうそういう世界はなくなっちゃったかな。もともと支度部屋は店に付属していたものだったのですが、ある時、大きなロッカールームを構えて、そちらをメインにして固定費を稼ぎ、店は遊び場という業態が現れました。それが「グッピー」&「アクトレス」で、「グッピー」が支度部屋機能、「アクトレス」がスナックでした。90年代末の最盛期には100人くらい会員がいましたね。
「ジュネ」のような、女装者と女装者が好きな男性が酒場で出会って仲良くなるという機能をもつ店は、67年に新宿の「花園五番街」に開店した「ふき」(後に「梢(こずえ)」に改称)が最初でした。「ジュネ」の閉店が03年ですから、一つのシステムが35年間機能したということです。35年続いたら立派なもので、GIDの影響もありましたが、店、さらにシステム自体の寿命もあったと思います。
女装文化のひとつの形態が終わったということですが、その後に残ったのが性別越境を病理化したGIDだけというのは、文化的にあまりにも貧しい。GIDは「医療福祉」であって「文化」じゃないですから。00年代前半には、もう日本の女装文化は終わりかなと思いましたが、00年代後半から新しい形お店が出てきました。
新宿では浜野さつきさんが「花園三番街」で「JAN JUNE」というお店をやっているし、湯島天神下(上野広小路)には井上魅夜さんが「化粧男子」(現在は閉店)を開店したり。魅夜ちゃんの店は、江戸時代に湯島天神界隈に栄えた陰間茶屋へのあこがれが詰まっていますね。
あしやま 井上さんは内心が女性の方を採るって言っていましたね。そういう方が生きられる場所を提供したいって。
三橋 魅夜ちゃんの店の子は、みんなすぐに女になっちゃうから長続きしないらしいです。「プロパガンダ」を始めたモカさんも女になりましたけど、今、30代くらいの人たちが、みなさんそれぞれ違う形でやりたいことをやっていて、それで女装文化がつながっていくと思っています。まったく同じ形態でやっても意味がないわけで、新宿の女装世界のシステムは35年も続いたわけですから、新しい形態にリニューアルしていくのは当然のことですよね。
女装者と女装者が好きな男性が酒場で出会って仲良くなるという、60年代に画期的で90年代まで機能したシステムが、新しい世紀になってその役目を終わったということです。でも、完全になくなったわけではなくて、お酒を飲みながら、女装者と重くない話をしたいみたい人には「JANE JUNE」に行けばいいわけです。
あしやま 今度行ってみたいと思います。
三橋 あなたは男姿で行ってもバレますよ。カウンターに座るなり、ママに「あなた女装するでしょう」って言われますよ。行きにくかったら初めは男姿で行って「今度は女装してきます」って言えば喜ばれます。
あしやま フレンドリーなのですね。より行ってみたい気持ちになりました。
三橋 『ユリイカ』の「男の娘」特集(2015年9月号)に載せた「トランスジェンダー文化の原理 ー双性のシャーマンの末裔たちへー」にも書いたのですが、性別越境への親和性は、ずっと日本人の感性や文化に組み込まれていて不変だろうと思います。ただ、それが表出する形態や商業システムは変わっていく。でも、トランスジェンダー的なものへの親和性という基本は変わらない。
欧米にはトランスジェンダー的なものと相いれない宗教的規範があるけれども、日本にはそうした宗教規範がない。それどころか、むしろ性別越境的存在にある種の神性を見、その魅力を賛美してきた歴史がある。そうした感覚は、現代にも生きています。人々が美輪明宏さんに感じるオーラなどがその典型です。
世代や時代によって形は変わるけれど、根本にある伝統、性別越境の文化への親和性は変わらない。
あしやま 三橋先生の目から見ても、00年代以降の、一見すると新しくみえる女装者たちも、根っこの部分では全く変わらないということですね。
三橋 「女をする」という根っこは同じですよ。社会環境やインターネットの普及のように媒体は大きく変化しているだけで、それはメディア論的に捉えるならば大変化かもしれませんが、文化として捉えるならば本質ではなく手段・手法の問題ですね。
そこらへんのことは「(講演録)『男の娘(おとこのこ)』なるもの―その今と昔・性別認識を考える―」(駒沢女子大学・日本文化研究所『日本文化研究』10号 2013年 http://zoku-tasogare-2.blog.so-net.ne.jp/2015-08-08)で語ってます。
8.女装とテクノロジー、発達障害
あしやま テクノロジーといえば、一つ気になることがありまして。女装者はパソコンもそうですが、電車や機械などが好きな人が多く感じます。
三橋 女装の世界は、パソコン通信でも、インターネットでも、時代時代で最先端のものをすぐに取り込んできました。女装系のパソコン通信は90年に東西ほぼ同時に始まり、95年頃には全盛期を迎えました。隣村であるゲイ世界と比べるとテクノロジーの取り入れが圧倒的に早かったです。
実際、パソコン関連の仕事をしている女装者は多かったです。その理由については、パソコン業界が急速に拡大しソフトウェア需要が一気に高まった勃興期には、技術者が不足したため、容姿に関係なく、能力で採用したからという説があります。それは部分的には正解かもしれません。
でも、どうもそれだけではないような気がします。女装者には、鉄道オタクや軍事(ミリタリ)オタクがけっこう多い。それにバイクオタクも。なぜなのだろうと、ずっと疑問に思っていましたが、最近になって有力な仮説が浮上してきました。それは発達障害との関連。
あしやま あはは(笑)。それは、くとの先生も言っていて。女装者と発達障害は相関しているんじゃないかって。
三橋 オタク世界の住人と発達障害とはけっこう重なるわけですが、それと同じなのではないかということです。根っこに発達障害があって、なにか特定の分野に著しく入れ込む傾向がある。それが、鉄道だったり、ミリタリだったり、バイクだったり、そして女装だったり……。一見、遠いように思えるけど、根っこは同じ。だから、それらがしばしば重なって現れるという仮説です。
実は、性同一性障害と発達障害との関連、性同一性障害の人で性別の移行が難しいケースでは発達障害との重複が疑われるということは、臨床系の精神科医はかなり早い時期から気づいていたようです、ただ、性同一性障害の当事者が嫌がるので、公の場でなかなか言いにくかった。
ところが、2014年6月に横浜で開催された日本精神神経学会シンポジウムで、岡山大学の松本洋輔先生(精神科)が「広汎性発達障害と gender dysphoria の合併をめぐる臨床的問題」という題で発達障害と性別違和が合併した症例を報告しました。おそらく、これが公の場で発達障害と性別違和の重なりを指摘した初めての報告だと思います。私もパネラーとしてその場にいたのですが、堰を切ったように、臨床系の精神科の先生が賛同して、一年も経たずに性同一性障害と発達障害とはかなり重なるという認識が一気に広がりました。
あしやま 女装の世界にもいずれ普及してきそうですね。
三橋 以前、日本近代思想史研究の大家で鉄道趣味の原武史先生が、鉄道趣味はなぜ男性に偏っているのかという問題提起をしていた時に、「先生、実は、鉄道趣味は女装者や性同一性障害の人にも多いんですよ」という話をしました。
原先生、最初は信じてくれなかったのですが、お調べになると『ひまわり』の「向日葵学園女子高等学校」に鉄道サークルがあって、車両や駅で撮った女装写真がたくさん並んでいる。それで、現象としては納得されて、二人で何故なのかを議論したのですけど、当時は納得できる結論に至らなかった。
でも、発達障害と性同一性障害との重複が見えてくると、鉄道趣味と女装もしくは性同一性障害の重なりも単なる趣味の問題、文化的な傾向ではなく、より根源的なもの、つまり共通の根源としての発達障害ということで、解釈ができると思います。私もそうですけど、あしやまさんも鉄道も女装も好きという話で、他人事じゃあないですよね。
あしやま そうですね。僕は生活に支障も無いですし、病気ではないのですが、大学の保健管理センターで受けた正確な心理検査の結果は、分野間での開きが相当ありましたね。
三橋 まあ、私もあしやまさんもその傾向はあると思います。この相関は完全に立証されているわけではないのですが、おそらくそうでしょう。有名な女装者で、とても注意力散漫な方がいたり、ともかく思い当たるところが多いのです。発達障害の傾向がある人が一つの事に集中するという意味では、学者、研究者向きかもしれませんね。
9.女装の力。変化と連続の文化。
三橋 学者といえば、先日のニコニコ学会βでお会いした、くとの先生もお元気そうですし、小林秀章さん(セーラー服おじさん)も国際的に大活躍ですごいですよね。
あしやま セーラー服おじさんのすごいところは、ヨーロッパでもアジアでも通じるところですよね。
三橋 ニコニコ学会βでも語ったことですが、異形のダブル・ジェンダーが最強である、という理論は世界共通なのかなと思います。お人形みたいに綺麗じゃなく、あの風体だからこそ許されているのかなと思いますね。
あしやま 工学で言う不気味の谷のような話で、谷に落ちるまえのピークじゃないかなと思うんですね。
三橋 『女装と日本人』の段階で双性(ダブル・ジェンダー)の人は神に近くなるという「双性原理」の話を書きました。その後、神は本来異形であるという仮説を立てました。日本には異形の神がたくさんいるわけです。それを合わせると、ダブル・ジェンダーでかつ異形の人が、いちばん神性が強いということになります。
今や「セーラー服おじさんに出会ってツーショットを撮ると幸せになれる」という都市伝説が流れているわけで、セーラー服おじさんは「幸せを運ぶ都市神」的存在になっています。「双性&異形=最強」という私の理論は、セーラー服おじさんによって証明されたことになります。
あしやま でも、それは妖怪みたいな女装やコスプレとは違うという。
三橋 妖怪は零落した神なので、最初から零落していては駄目なんですね。セーラー服おじさんには、何だかよく分からないけどパワーがある。あのパワーがセーラー服おじさんを双性&異形の都市神として成立させているわけで、それをもう少し考えてみたいと思ってます。
あしやま パワーといえば、女装一般においても見た目と同じで、それ以上のプラスアルファの価値が必要ではないかというのは、過去の本誌でも度々話題になりました。
三橋 若い女性と同じで、よほど超越した美しさを持っている人以外は、外見だけでは持たない。他の魅力が必要ですね。女装でも、お人形さんみたいな女装ではすぐに飽きられる。当たり前のことですけど、容姿的な美しさに加えてタレント、つまり才能や魅力が必要です。
たとえば、はるな愛さんは、とてもクレバーな頭の回転の早い方で、実業家としても成功されているわけで、そういう人でないと長続きはしないのです。プロはもちろん、アマチュア女装やコスプレイヤーでも同じではないかと思います。
あしやま 川本直は前回の本誌で、一度女装界は落ちるところまで落ちたものもあったから上に伸びるのではなんて仰っていましたが。
三橋 どんな世界にも、上があれば下もある。しょうもない人はたくさんいます。しょうもない、というのは容姿に限らず、人格的なものも含めての話ですが。逆に、綺麗な人は昔からいるわけです。「富貴クラブ」のトップクラスはさすがに綺麗ですよ。ただ、そういうレベルの人は数人しかいない。現代はそのレベルが沢山いるという違いですね。
あしやま タレントの話で言えば、普通の人、のような人は少ないようにも感じます。たまに、女装者は知的水準が高いなんて言う人がいますが、おそらく上澄みしか見ていなくて、平均すると普通になるのではと思います。これも今も昔も何も変わっていないと思います。大きく変わっているところもあるけれど、変わっていないと言えば全く変わっていない。
三橋 時代(世代)とともに変わった部分はあるけど、変わらない部分もある。端的に言えば、どの時代にも女装したい人がいて、そうした女装者を愛でる人がいる。そうした人たちが作ってきた女装文化は、日本においては前近代以来脈々と連なる伝統がある。女装(異性装)への強い親和性が日本文化の伝統の一部になっている。現代のコスプレ要素の強い女装も、そこから外れるものではないと思います。
変わらない部分も大事だし、変わっていく部分も大切。つまりは、松尾芭蕉が言った「不易と流行」だと思うのです。「不易を知らざれば基立ちがたく、流行を知らざれば風新たならず」「その本は一つなり」、つまり、不変の真理を知らなければ基礎が確立せず、変化を知らなければ新たな進展がない。両者の根本は一つである、ということです。
それが、「エリザベス会館」、新宿女装コミュニティ、そしてGIDの三つの世界を渡り歩いて、いろいろ見聞きし、今は若い女装の人たちの活動を観察している私の結論ですね。
あしやま 今の女装の世界は、昔から脈々と続いてきているけれど、多様な文化が花開いていると。今日はとても貴重なお話が聞けました、ありがとうございました。
三橋 こんな老人の昔話みたいなインタビューを載せて、コミケで売るわけでしょう。やっぱり続いているし、変化している。面白いですね。

↑ 対談風景(あしやまさんは風邪を引いていたため「B面」)
2015年10月17日 下北沢にて
『女装と思想』第6号(テクノコスプレ研究会、2015年12月31日刊行)に「巻頭特別対談」として掲載されたロングインタビュー「変わるものと、かわらないもの。女装文化への語らい。」。
聞き手は、あしやまひろこさん。
【目次】
1.女装者と男。女装者と女。
2.女装世界の変遷と媒体。ネット以前の出会い。
3.性同一性障害と女装世界
4.男の存在しない女装世界の登場
5.口コミと草の根の時代への回想
6.女装と容姿
7.「場」の変化。変わらぬ根底。
8.女装とテクノロジー、発達障害
9.女装の力。変化と連続の文化。
----------------------------
対談「変わるものと、かわらないもの。女装文化への語らい。」
20-20E382B3E38394E383BC-c3a3b.jpg)
↑ 「ネオンが似合う女」になれた頃(1997年4月)。
『週刊Spa!』に掲載された写真。
聞き手:あしやまひろこ
語り手:三橋順子
↑ 対談時(2015年10月17日:下北沢)
1.女装者と男。女装者と女。
あしやま 女装者は男性が好きって誤解されがちなのですが、私もですが、三橋先生も女性がお好きでしたよね。
三橋 かなりの女好きです(断言)。ただね、90年代の六本木や新宿歌舞伎町を女装で歩いていると、男性が寄ってくるんですよ。最初は誘われても断っていたのですが、だんだん面倒になってくるし、自分がヘテロセクシュアル(異性愛)の男性に、女として見られ、誘われ、扱われることで、承認欲求が満たされるということがあって、そのうち場合によってはOKするようになりました。
私は性行為的には男性もOKで、男性とのプレイには性的な快感は十分にありました。請われるままにセックスフレンドとして長く関係をもった人もいましたが、心理的に惚れたことはありません。相手の男性も色恋を求めないさばけた人が多かったので、うまくいってたように思います。
あしやま 僕も共感します。相手ではなく、相手と接触している自分自身を見ているという。自分自身が女としての立場であるために、相手としての男を利用している。
三橋 自分を女にしてくれる道具のように男性を思っていましたね。私を女として扱い、女として気持良くしてくれる男が望ましい。それで、ホテルの部屋に大きな鏡があればなおいい。女として扱われる自分を鏡に映して自分で見たい、そういう欲望は強くありました。そこに相手の男が映る必要はないのです。そこらへん、ゲイの人たちとは感覚がかなり違うと思います。
あしやま その感覚はヘテロセクシャルな女装者にもかなりあると思います。男性相手にそういう感情を抱かなくとも、女として扱われたいと。
三橋 性的な関係が長く続いた相手が何人もいたのは、早い話、相手も気持ち良かったのだと思うのですね。
『性的なことば』(講談社現代新書)に書きましたが、ある経験豊富な男性に「あんたみたいな尻を、金の茶釜というんや。覚えとき」って教えられたことがありました。「金の茶釜」とは、おしりの名器のことです、女性の名器と同じで、相手にしか分からない、自分ではわからないのですけど、「フィット感が抜群だ」とよく言われました。
あしやま そのような体を作るための訓練は必要ではなかったのですか。
三橋 訓練はほとんどしてないです。かなり先天的なものだと思います。筋肉の質というか伸縮性がすごくあって、かつ丈夫。今にしてみると、ある種の才能なのだろうと思いますが、当時は、それほど自覚はなかったです。
で、繰り返しになりますが、本質的には男好きじゃないんですね。女装していても、寄ってくる女性もいます。しかも、けっこう「いい女」が。でも、相手の女性は私に男を求めてくるわけではないし、私も男性として接する気はない。レズビアン・ファンタジーなんですね。
何度もデートした女性とは、お互い好意を抱いていたわけですが、行為にうつれない。互いの手と手をずっと握りあっているだけ。後になって「どうしてあの時、押し倒してくれなかったの?」と言われましたが、それは、私も同じ気持ちで(笑)。レズビアン・ラブの経験がないから、お互いどういう手順を踏んだらいいのか分からなかったのです。
あしやま 女性として振舞っているわけですから、どう振る舞うかは難しいですよね。でも、三橋先生はすごいなとも思うところで、僕がそのようなシチュエーションにあったら男性として振る舞うだろうなと思います。
三橋 そう簡単には切り替われないし、そこで男になっちゃうのはなんか違うと思うのですよ。
歌舞伎町の「ジュネ」というお店でお手伝いホステスしていた頃、まだ「キャバクラ」なんていう言葉ができる前の話です。女性が接客する飲み屋は深夜営業できないわけですが、女装者が接客するお店は、法的には男性なので風営法の適用外で深夜営業ができるんです。
だから、六本木のクラブ・ホステスさんが、自分の店が終わった後に、タクシーに乗って飲みに来てくれます。でも、自分の店や、アフター(閉店後のお客さんとの付き合い)で飲んでるから、かなり酔っぱらっていて、会うなりいきなり「順子さ~ん」と抱きついてくる。危ないからしっかり抱き止めるわけですが、なにしろ六本木の高級クラブのナンバーワンクラスですから、胸も大きいし、腰のクビレもしっかりあって、すごい身体してるわけです。
そんな女性に密着されても、私は勃たない。もったいないなという気持ちと、自分が女というロール(役割)をちゃんとやっているんだという自己満足の両方がありました。
あしやま 自分はそういうシチュエーションはオイシイと思ってしまって。学生時代に他大学を交えた懇親コンパみたいなところで、女の子が可愛いでね、なんて言いながらハグをしてきたりしたときは嬉しかったりして。まあ、途中でそいつは男だからって止めが入るんですけれど。
三橋 女性が女装者を女性として認識しているから距離が近くなるんです。逆に女装者と男性とは対人距離が遠くなる。一般的に、男同士の距離は遠いですが、女性同士の距離は近いですね。
あしやま 女装しているとその基準になりますね。自分の女装を男性は遠巻きに見るんですが、女性はグイグイ寄ってきて。見た目は大きい感じがします。
三橋 女性の身体距離がすごく近いです。心理的には女同士という感覚であっても、もし体が反応してしまうと相手を裏切ることになる。女として近づいておきながら、男を出すというのは、とてもフェアーじゃない気がする。そういう可能性がある自分が嫌というか、恐怖感を抱いていましたね。
あしやま 僕は女性と女装者を描いた、例えば糸杉柾宏さんの作品を読むと、時には「生えている」女の子を求めている場合もあったりしないかなと思うこともあれば、男と前置きはしますが女装で仲良くなって男として……というのも良いのではないかという感覚もあって。好きな漫画に『ゆびさきミルクティー』というものがあるのですが、主人公は女装をしているけれども、色々と女性関係もあり彼女もいるというか、すごい都合がいい話だなとも思いますが。
三橋 私の世代にも、シメシメと思っていた人もいたかもしれませんけれど、私は嫌でした。だから、とても素敵な女性と共寝して、上半身はしっかり抱き合っていても、下半身は離すようにしていました。男相手の時は徹底的に女を演じ、女相手の時は男を出さないというのが、私の原則。
私が妻と良好な関係なのは、相手があまり私に男を求めてきていないからということがあるのかもしれません。女性との関係は精神的には深いわけですが、肉体的なものはほとんどなく、男性との関係は、その逆で、肉体的には深かったけど、精神的にはまったく浅いという感じでした。
あしやま トラニーチェイサーのような、女装が好きな人というのは何を求めてきていたのでしょうかね。
三橋 私は、ホステス倫理としてお店のお客さんとは寝ない主義だったので、一度もしたことはありません。お付き合いした男性は、全部、店の外の人です。だから、トラニーチェイサー的な人との付き合いは多くなくて、中には女装者が好きな男性もいましたが、長くお付き合いした方はそうではなかったですね。
声を掛けてくる男性には、自分が女装者であることを告げるわけですが、「自分はあなたみたいな女装の人は初めてだけど、それでもいいから付き合ってくれ」と言われたときは、うれしかったです。その男性、材木商の若旦那とはいちばん長く続きました。松本侑子さんの小説「女装夢変化」(『性遍歴』収録)のモデルになった出会いです。
あしやま 歌舞伎町は男性向けのキャバクラのようなイメージがありますが、当時は違うものもあったのでしょうか。
三橋 私が、男遊びが面白くてしかたがなかった時期は、九四年から九七年くらいですが、声を掛けられるのは、新宿では歌舞伎町エリアより、新宿駅周辺が多かったです。二丁目はゲイの世界ですから近づきません。六本木は、路上でも、ゲームセンターでも、酒場でもどこでもナンパされるという感じ。不思議なのは渋谷で、声を掛けられたことがほとんどなく、やっぱり性的な雰囲気が薄いのだと思います。
性的快楽に積極的な、濃い人が多かったから、その4年間で色々なことをやり尽くした感じがあって、その後は性的なものに執着しなくなりました。
あしやま 濃い人といえば、両性的なな……「生えてる」女の子こそ最高という人もいますよね。
三橋 『女装と日本人』にも書きましたが、乳房もペニスもどちらもある「娘」が大好き、ペニスのついた女の子を射精させるのが最高という男性もがいますよね。女装者は変態なって言われるけど、そっちの方がよっぽど変態じゃない、って言いたくなるような男性。
でも、そういう人が女装文化を裏から支えてきた部分があるわけで、江戸時代の陰間茶屋から現代のニューハーフや女装の飲み屋まで、そうした女装者大好きの男性が連綿と続いてきたんじゃないかと思います。性にも歌舞伎の女形にキャーキャー言っている人が途絶えることなく続いている。それが、日本文化の特質のひとつなんだと思います。
あしやま 自分自身は、バイセクシャルやパンセクシャルな女性とお付き合いした経験があって、女性同士だと入れるものもないし、みたいな話をされた事があって。
三橋 一種のレズビアン・ファンタジーを持っている女性はけっこういますよ。『女装と日本人』にも書いた通り、日本人の「曖昧な性」への嗜好は、近代化の中で上部構造は男女二元的に変わっても、ベーシックな部分では変わっていないというのが私の感覚ですね。
20-20E382B3E38394E383BC.jpg)
↑ 六本木で遊び始めた頃(1994年11月)
2.女装世界の変遷と媒体。ネット以前の出会い。
あしやま 自分自身が今こうして女装しているのは、コスプレを含めてインターネットとの関わりが深いのかなと。
三橋 インターネットの登場は、大きな転換点でした。普及は1997~98年ごろに若い男性から始まり、最後に到達したのが中年女性でした。たとえば着物趣味の女性のコミュニティの成立が2001年ごろです。女装世界は、男性の世界なのでインターネットの普及が早く、97年にはもういくつかのサイトが立ち上がっていました。
その前に90年代前半からパソコン通信が広まって、東京中心の「EON」、大阪中心の「スワンの夢」の東西二大ネットが成立していました。パソコン通信からインターネットへの転換がだいたい98年くらいです。
これは偶然なのですが、性同一性障害の概念が流布しはじめたのもその時期でした。そして、00年代になると、直接的な対人コミュニティで成立していた新宿の女装世界が衰えていき、『くいーん』『ひまわり』『ニューハーフ倶楽部』といった雑誌媒体も次々に廃刊になりました。雑誌媒体の衰退理由は、端的に言えば、インターネット上で無修正のシーメールポルノが簡単に見られるようになったからですね。
『くいーん』は「女装交際誌」を名乗っていたように雑誌が仲介する「文通」がメインだったわけですが、90年代半ばに、パソコン通信や、ポケベル、PHSが普及していくと、時代遅れになって衰退していきました。
私が遊んでいたのは、ちょうどポケベルからPHSの時代で、NTTの伝言ダイヤルの全盛期でした。伝言ダイヤルには「02134649(オニイサンヨロシク)」という女装系のボードがあって、パスワードは「1919(イクイク)」でした(笑)。どこに書いてあるわけでなく、コミュニティ内の口コミで広がっていましたね。
伝言ダイヤルですから、声を録音するわけですが、私は声が絶対の強みだったので、週末にセクシーボイスで伝言を入れておくと、一時間に五~六本というペースで掛かってきます。それを聞いてPHSや公衆電話からかけ直して、この人は大丈夫そうだなと判断すると、待ち合わせ場所と時間を決めて、実際に会うわけです。
あしやま 相手は女装者の場合もあったのですか。
三橋 女装者はほとんどありません。もっぱら相手は男性でした。ゲイ系の人は感性が合わないので避けて、女装者好きで、私を女性として見立ててくれる人とだけ会いました。いきなりホテルへということもありましたけど、いっしょに食事をして軽く飲んで、それから・・・という普通のデートが多かったです。
バブルの余韻が残っていた時代ですから、たとえばサラ金業界の幹部とのデートは、必ず「かに道楽」。すごい量の蟹を食べさせてもらってからラブホテルに行くのですが、セックスの方はからきし弱い方で、こんなに奢ってもらっているのに申し訳ないなぁ、という感じでした。
逆に、東京出張の度に赤坂や西新宿の高級ホテルに呼んでくれる関西の社長さんは、セックスがとても強い人で、まず大東京の夜景眺めながら窓辺で立ちバックで一回、ベッドでもう一回、一眠りして朝日の中でもう一回。相手は「じゃあ、またな」って感じで、そのまま仕事へ。
私が化粧を直して、キーを返しにフロントに行くと、フロントマンから「ご伝言です」と封筒を渡されて、中には1万円札3枚のお小遣いと朝食券なんてこともありました。3000円の朝食って、後にも先にも、その時だけです。まあ、良い時代って言えば、そうでしたね。
3.性同一性障害と女装世界
あしやま 九〇年代末の変化は媒体以外にもありましたか。
三橋 「性同一性障害」(GID)の概念の普及が大きかったですね。それまでは、女になりたいと思う人は、まずは女装やニューハーフの世界に足を踏み入れていたわけです。店が入口だったのです。ところが、メディアがGIDをしきりに報道するようになると、性別に違和感を持っている人は、病院を入口にしてしまうわけですね。そうなると、お店に新人が来なくなってしまう。
00年代前半のGID概念の広がりは、人材を奪われるという意味で女装業界にとって大打撃でした。それと、ほぼ同時にインターネットが普及するわけですが、今にして思うと「ジュネ」をはじめとして新宿のお店はネット対応が遅れていましたね。
あしやま 口コミで構築されていたコミュニティを敢えてネットに出すというのも違うということでしょうか。
三橋 そうですね。「ジュネ」のママは株取引をネットでやっていましたから、ネットができないわけではなかったけど、お店の宣伝をネットでやろうという発想はまったくなかったです。「女装なんて、わざわざ宣伝して広めるもんじゃない」という考え方でした。そんなこともあって、女装系のお店の最大の危機は00年代でした。
ですから06年から07年にかけて『女装と日本人』を書いた頃の私には、女装の世界がもう無くなってしまうという危機感が強くありました。ともかくこの世界のことを書き残しておこうという、ある種の遺言のようなつもりで、かなりの悲壮感をもって執筆しました。
ところが、原稿を出版社に入れた08年頃に、何か様子がおかしいと気づきはじめました。街頭で、見た目は女性同士だけど、片方は女装者らしいカップルを立て続けに目撃したことがきっかけでした。九七年に私が女性と同伴出勤したら、「女装者なのに、女性とデートするなんて変態!」だって言われましたから、10年の間になにかが大きく変わりつつあることに気づいたのです。
あしやま オネエ系タレントがメディアに登場することも増えましたし関係性が変わったのでしょうか。女装者はただの変態ではないという認識が広まったのでしょうか。
三橋 日本テレビの「おネエ★MANS!」は06年秋からです。関係性が変わってきた理由について思うのは、97年ごろに「性同一性障害」の概念が登場してから10年の間に、性別越境の病理化がどんどん浸透していき、病気としての性別移行という形態に、息苦しさを感じるようになった人が増えてきたのだと思います。
4.男の存在しない女装世界の登場
三橋 『女装と日本人』執筆以降の変化についてまとめた「変容する女装文化」という論文を2009年に『『コスプレする社会 -サブカルチャーの身体文化-』(せりか書房)という論集に発表しました。
そこでのポイントは関係性の変化です。それまで、女装することと男性と性的関係をもつことは表裏一体でした。私は男から店で声を掛けられても断る第一世代だったので、ずいぶんで「生意気だ」と言われましたけれど、そうした男性との関係性から女性との関係性に移行してきたことに注目したわけです。
あしやま 男と寝ることと表裏一体であった女装文化が、ここ最近変化してきたということですよね。
三橋 昔(90年代半ば頃)の女装者は男性からの誘いはまず拒否しなかったです。どれだけたくさんの男と寝たかが女装者の勲章という雰囲気がありましたからね。
あしやま 当時も居たと思うのですが、男と関係を持ちたくないという女装者はどのようにしていたのでしょうか。
三橋 そうした人たちが、最初に集団を成したのが「エリザベス会館」です。「エリザベス」ができたのが78年ですが、かなり初期の段階(1980年代初頭)で男性とのセクシャリティを切りました。
60~70年代が全盛だった女装秘密結社「富貴クラブ」では、男性が圧倒的な力を持っていたのとは対照的ですね、新宿で男を相手にしてきた女装者の中には、年をとってモテなくなって、「エリザベス」に「隠居」する人もいました。
若いころモテた中高年女装者には二パターンがあり、モテなくなった段階でいっさい男性との性的関係を断ち切って、例えば「エリザベス」へ隠居しちゃうようなプライドの高い人。もう一方は60、70歳になっても、なんとか男を捕まえようとあがく人。どちらも大先輩で、その姿を間近でみていました。
後者の方は、着物女装なんですけど、店に来る若い男性客の隣に座ると、男の手をとって(女性着物の脇の下に開いている)身八つ口に引き込んで、乳房に触らせるんです。でも、若い男性にしてみたら、老女のおっぱいなんて触りたくないわけで、トイレに行くふりをして、チーママや私のところに「席、変えてくれ」って苦情を言ってくる。業が深いというか、もう完全に悪あがきですよ。いろいろお世話になった先輩ですけど、正直「自分は、絶対にああはなりたくない」と思いましたね。
加齢は、女装者だれでも避けられないことですから、やはり歳をとったときの身の処し方は、店に迷惑をかけないように、ちゃんと考えるべきです。
あしやま 今の女装者は、必ずしも男性との関係性を前提としていなかったり、異性愛者も多いように感じますから、この場の文化は今にも影響を与えているようにも思います。
三橋 「プロパガンダ」は、もっと男性中心なのかなと思いながら行ったら、おじさんたちは隅で小さくなっていて全然勢いがない。元気よく女装者に声を掛けているのは女の子ばかりで、つくづく時代も変わったんだなと思いました。
あしやま 女の子も女装者に近づきたい欲が開放されたんでしょうかね。
5.口コミと草の根の時代への回想
あしやま 八〇年代ごろからそのように文化にも幅が出てきたわけですね。しかし、今の若い女装者はエリザベスに行くわけでもないですし、先ほどのお話にあったように媒体の変遷もありました。今は、よりポップな、もっとファッション感覚の女装が生まれたのかなと思うところがありまして。
三橋 おそらく同人誌の活動やコスプレ文化が影響して、新しい女装文化が誕生したのだと思います。「性同一性障害」的なものに嫌気のさした若い世代と、コスプレ系の感覚がマッチしたのではないでしょうか。
90年代にも、コスプレ系の女装者も居なくはなかったのすよ。コスプレ系女装は、新宿でも「エリザベス」でもなく、やはりキャンディ・ミルキィさん(現在キャンディ・H・ミルキィと改名)の雑誌『ひまわり』に集まっていましたね。キャンディさん自身がああだから、コスプレ系女装の人にとっては、とても居心地の良い場所だったと思います。
あしやま 僕よりも一世代上のコスプレ女装関係の人は、みなさん必ずキャンディさんのお名前を出されますよね。
三橋 「向日葵学園女子高等学校」という誌上企画があって、制服女装も『ひまわり』が中心でした。
『ひまわり』の創刊は87年で最初はキャンディさんの個人誌です。キャンディさんがメディアに登場して有名になるにつれて徐々に雑誌としての体裁が整って、93年に季刊になり、98年には隔月になり…。90年代半ばが、一番活気があったと思います。
ただし、当時もコスプレ女装に一定の需要はあったと思いますが、コミケも大規模でなく、そこで『ひまわり』を頒布ということもなかったわけで、キャンディさん自身があの格好でバイクで配達していたわけで、最後まで個人発行の同人誌という色彩が濃厚でした。
そういう意味では、現代のコスプレ女装に通じる淵源ではあると思いますが、やはり、相当の世代差があると思います。文化的に論じる場合、現代のコスプレ女装の隆盛とは、ある程度、切り分けた方がいいかもしれません。
現代のコスプレ女装には、いろいろな系統があると思います。コスプレから入る人、性同一性障害的なところから入ってくる人。そして、女装ができる場が昔よりずっと多様になっている。それは、とても良いことだと思います。
話がずれましたが、女装するという行為が男性との関係性から抜け出して、むしろ女性との関係性の比重が増していく、その転換の意味はすごく大きいと思います。
あしやま それが00年代の転換というわけですね。
三橋 女装者好きの女性は、いつ、どこから出現してきたのか、いわゆる腐女子的な世界からなのか、それとも違うのか、まだリサーチしていないのでわかりませんが、もともとそうした嗜好をもった女性は一定数いて、それが表に出やすくなったのだと思います。
やはり「場」の問題で、「プロパガンダ」みたいにそこに行けば女装者に会えるという場所があること、その情報に容易にアクセスできるようになったことが、何より大きいと思います。私たちの時代にはそれがまったくと言っていいほどなかった。稀にお店にくる女性は水商売や風俗産業の方がほとんどでした。
「場」の設定、そこへのアクセスという点で、90年代と00年代とでは根本的に違っていると思うのです。
あしやま 古代から日本人の中にあった根源的欲求のようなものが、アクセスできる手段と場所が設定されたことで、表出したという。
三橋 そうですね。『女装と日本人』に書いたように、日本人は男女を問わず、基本的に女装者が好きなのですよ。ただ、現実にはそこになかなかたどり着けなかった。新宿のゴールデン街に女装の店があるという話が、週刊誌やスポーツ新聞の隅っこに小さく載っている。情報っていってもその程度なんですね。
私の友人は、そういう記事を見て、ポケットに札束を入れて、ゴールデン街の店を一軒一軒、片端から飲み歩いて、10万円くらい飲んだところで、やっと店主から「ジュネ」の場所を教えてもらい、「ジュネ」にたどり着きました。おそらく他の店でも知っていたのでしょうが、教えてくれなかったのでしょうね。執念に加えて偶然、それに相当な根性とお金がないと、たどり着けない世界だったのです、女装の世界は。
6.女装と容姿
三橋 そうやって、やっと新宿女装世界にたどり着いても、ママから「あなたは(女装に)向いていないから止めなさい」なんて言われることもあります。傍から見ていてもむごい話だと思いますが、きれいになる素質に恵まれていない人が女装しても、辛いだけの世界なんですよね。
「エリザベス会館」は純粋アマチュアの世界なので、どんな容姿レベルでも「来るな」とは言いません。だから、10年通って、たくさんのお金を使っても、毎年開催される女装コンテストで、一度もノミネートされない人もいるわけです。逆に、入ってきてすぐに新人賞、翌年には準グランプリを獲って、店の「看板娘」に駆け上がっていく人もいます。私ですが(笑)。残酷と言えば残酷な世界なのですけど、それでも自分が我慢しさえすれば、そこにいられるわけです。
新宿の女装世界は酒場を拠点にした客商売ですからもっと露骨で、スタッフならお客が呼べる容姿かどうかがシビアに問われます。スタッフでない女装会員でも、とりあえずソファーに座って「枯れ木も山の賑わい」になるレベルならOKだけど、シビアな男性客に「お前、もっとどうにかしたらどうだ」なんて言われたら、ほんとうにどうしようもなくなってしまうわけですね。つまり、容姿的な適性で淘汰が起きるわけです。
一方、「性同一性障害」の場合は、お医者さんは「あなたはきれいにならないから、女になるのは止めなさい」とは絶対に言わない、言えないですから、診察・治療段階では容姿適性による淘汰は起きません。
あしやま コスプレの世界でも同じで、男女問わず見た目で判断されますよね。そして悪あがきではないのですが、パソコン上で写真を補正してなんとか、という人も多いわけです。実際会うと、誰?となる人も多くて。
三橋 コスプレ趣味であっても、美形とそうでない人とでは、周りに集まるカメラの数は明らかに違うでしょうし、更にいろいろ言われるわけでしょう。いくら写真で補正していても、いざ実際に会うと「写真とぜんぜん違う」という問題も出てきてしまうわけですよね。
あしやま 似合うかの問題はどうしようもなくて……。
三橋 「そんな醜い女装者は見たくない、勘弁してくれ」と思う権利も一般人にはあるわけです。そして、中にはそれを口に出しちゃう人もいる。少なくともなんでもアリかといえばそうではなく、容姿が問われてしまうわけです。
けれども、「性同一性障害」というレッテルを貼ると、医療福祉の問題になりますから、容姿をあれこれ言うことはできなくなる。「病気じゃあ、仕方がないだろう」ということです。そういう意味で「性同一性障害」という概念は「救い」であったわけです。
でも、そういう「性同一性障害」というレッテルを貼った「かわいそうな病気の人たち」が10年近くメディアに出ていたところに、病気ではないカワイイ女装者が「男の娘」というレッテルで出てくれば、メディアも一般の人の視線も一斉にそちらに行ってしまうのは仕方がないと思います。
「医療福祉」より「カワイイ」が受けるのが現実です。それを容姿主義、ルッキズム(lookism)だとの批判する人もいますけど、人間社会はおそらく有史以来ずっとルッキズムなんですね。良い悪いはともかく、現実にルッキズムがなくなるとは近未来的には思えません。
女装の世界は昔から完全にルッキズムで、ブサイクが生意気なこと言うと内容にかかわらずボコボコに批判される。美人は生意気を言っても許される。酷い世界と言えば酷い世界です。
「エリザベス会館」も新宿の女装世界も、見た目、容姿によって扱いが全然違うんですね。「人権」とか「平等」とかいう話とはまったく別の価値基準です。でもそういう「場」しかなかったんです。
そういう世界に身を置いて認められる、そしてその世界でのし上がるには、容姿を磨くしかないんです。ですから、女装と「性同一性障害」はまったく別の論理で成り立っているわけで、一緒にするのはもちろん、同列に論じるのも意味がありません。
女装の世界はルッキズムによる実力世界ですから、どれだけの人が淘汰されていったか、それこそ振り返れば死屍累々です。「性同一性障害」は医療福祉の世界ですから、淘汰が機能しちゃあいけないのです。少なくとも建前上は「かわいそうな病気の人たち」は皆、救われなければならない。
でも、この世界の現実は違う。だから「性同一性障害」の人たちもたいへんなのです。
今日は、ある自治体の主催の講座で「服装は自由である」というテーマで講演してきたのですが、それは論理的な話であって、現実は厳しいです。
あしやま 似つかわしいかどうかは大きな問題だと思っていまして、例えば僕が男姿でスカートを履いたら気持ちが悪いと思うんです。それはどうしようもないといいますか。
三橋 「気持ち悪い」と思う人に、「その感情を止めろ」と言うのは難しいし、実際にできませんよね。現実には、こちらが気持ち悪いと思われないようになるしかないのです。
20-20E382B3E38394E383BC-3bb97.jpg)
↑ 新宿歌舞伎町区役所通り「ジュネ」にて(1999年11月)
7.「場」の変化。変わらぬ根底。
三橋 飲み屋を拠点に成り立っている新宿の女装世界は、店自体が女装者と女装者を好む男性(女装者愛好男性)の出会いの場という要素があるわけですが、新宿の店育ちが一番で、次がエリザベス会館、一番下が上野などのハッテン映画館育ちという序列感覚がはっきりありました。
パソコン通信からネット掲示板時代の大スターで、一時期、フェミニズム系の活動の方にも評価されて、しきりに講演活動をされていた宮崎留美子先生という方がいらっしゃいます。ハッテン場育ちでも、上手に愛嬌を振り撒いて新宿で受け入れられる人もいるわけですけど、宮崎先生はそういうタイプじゃなく、弁が立つ分、反発も強かったわけです。
「最近、留美子って生意気な奴がいるようだけど、どこの出なの?」、「どこかのハッテン映画館の出らしいですよ」、「新宿の作法を教えてやるから、夜中の2時に花園神社の裏に呼び出しな」なんて話になったことがありました。留美子先生は終電車で帰るから、そんな時間にはもう新宿にいないのですけどね。
そんなエピソードが語るように新宿の女装世界は、よく言えば体育会系なんです。各店に古手の姐さんがいて、その世界に入るには、ママはもちろん、そうした姐さんたちにも挨拶しないといけない、悪く言えば、任侠世界的なノリがありました。
私は「エリザベス会館」から新宿に流れてきた新参者だったわけですが、新宿女装世界のドン(元締め)だった「ジュネ」の薫ママに仁義を切って、「ジュネ」のナンバーワン(若頭)の麻衣子姐さんと五分の杯を交わした客分ということになると、もう誰も文句を言えないんですね。
逆に留美子先生みたいなフリーの女装者が遊ぶのはけっこう難しい。意地悪そうな姐さんに「あんた、見ない顔ね、どこの娘?」みたいなことを言われて、いじめられかねない。でもそこで、ちゃんと挨拶して「あなた見込みがあるわね」という話になると、「ウチにいらっしゃいよ」ということで、店の支度部屋(着替えや化粧をしたり、仮眠したりする部屋)に所属することになる。そうなると「○○(店名)の〇〇子です」って名乗れて、女装コミュニティの他の店に飲みに行っても「あの子は〇〇の娘だから」ということで、飲み代が千円割引になるわけです。
あしやま お客さんがお店の更衣室で着替えるんですね。
三橋 店の中に更衣室があるところもありましたけど、「ジュネ」は店から十分程のマンションの一室が支度部屋でした。そこで着替える人が圧倒的に多くて、私みたいに家から女装して電車に乗って新宿に来る人は少なかったですね。
「ジュネ」の場合、そこで着替えたら一度は店に顔を出すのがルールで、その後はどこで遊んでも構いません。当時、月会費は1万5000円だったと思います。会員さんは店が忙しい時には接客を手伝ったりもしますが、「ジュネ」で飲んでる限り、いくら飲んでも飲み代はタダでした。フリーの女装者の料金は4000円なので、毎週末、店に来るなら会員になった方が安かったんです。
あしやま そういう世界に一度行ってみたいなと思います。
三橋 もうそういう世界はなくなっちゃったかな。もともと支度部屋は店に付属していたものだったのですが、ある時、大きなロッカールームを構えて、そちらをメインにして固定費を稼ぎ、店は遊び場という業態が現れました。それが「グッピー」&「アクトレス」で、「グッピー」が支度部屋機能、「アクトレス」がスナックでした。90年代末の最盛期には100人くらい会員がいましたね。
「ジュネ」のような、女装者と女装者が好きな男性が酒場で出会って仲良くなるという機能をもつ店は、67年に新宿の「花園五番街」に開店した「ふき」(後に「梢(こずえ)」に改称)が最初でした。「ジュネ」の閉店が03年ですから、一つのシステムが35年間機能したということです。35年続いたら立派なもので、GIDの影響もありましたが、店、さらにシステム自体の寿命もあったと思います。
女装文化のひとつの形態が終わったということですが、その後に残ったのが性別越境を病理化したGIDだけというのは、文化的にあまりにも貧しい。GIDは「医療福祉」であって「文化」じゃないですから。00年代前半には、もう日本の女装文化は終わりかなと思いましたが、00年代後半から新しい形お店が出てきました。
新宿では浜野さつきさんが「花園三番街」で「JAN JUNE」というお店をやっているし、湯島天神下(上野広小路)には井上魅夜さんが「化粧男子」(現在は閉店)を開店したり。魅夜ちゃんの店は、江戸時代に湯島天神界隈に栄えた陰間茶屋へのあこがれが詰まっていますね。
あしやま 井上さんは内心が女性の方を採るって言っていましたね。そういう方が生きられる場所を提供したいって。
三橋 魅夜ちゃんの店の子は、みんなすぐに女になっちゃうから長続きしないらしいです。「プロパガンダ」を始めたモカさんも女になりましたけど、今、30代くらいの人たちが、みなさんそれぞれ違う形でやりたいことをやっていて、それで女装文化がつながっていくと思っています。まったく同じ形態でやっても意味がないわけで、新宿の女装世界のシステムは35年も続いたわけですから、新しい形態にリニューアルしていくのは当然のことですよね。
女装者と女装者が好きな男性が酒場で出会って仲良くなるという、60年代に画期的で90年代まで機能したシステムが、新しい世紀になってその役目を終わったということです。でも、完全になくなったわけではなくて、お酒を飲みながら、女装者と重くない話をしたいみたい人には「JANE JUNE」に行けばいいわけです。
あしやま 今度行ってみたいと思います。
三橋 あなたは男姿で行ってもバレますよ。カウンターに座るなり、ママに「あなた女装するでしょう」って言われますよ。行きにくかったら初めは男姿で行って「今度は女装してきます」って言えば喜ばれます。
あしやま フレンドリーなのですね。より行ってみたい気持ちになりました。
三橋 『ユリイカ』の「男の娘」特集(2015年9月号)に載せた「トランスジェンダー文化の原理 ー双性のシャーマンの末裔たちへー」にも書いたのですが、性別越境への親和性は、ずっと日本人の感性や文化に組み込まれていて不変だろうと思います。ただ、それが表出する形態や商業システムは変わっていく。でも、トランスジェンダー的なものへの親和性という基本は変わらない。
欧米にはトランスジェンダー的なものと相いれない宗教的規範があるけれども、日本にはそうした宗教規範がない。それどころか、むしろ性別越境的存在にある種の神性を見、その魅力を賛美してきた歴史がある。そうした感覚は、現代にも生きています。人々が美輪明宏さんに感じるオーラなどがその典型です。
世代や時代によって形は変わるけれど、根本にある伝統、性別越境の文化への親和性は変わらない。
あしやま 三橋先生の目から見ても、00年代以降の、一見すると新しくみえる女装者たちも、根っこの部分では全く変わらないということですね。
三橋 「女をする」という根っこは同じですよ。社会環境やインターネットの普及のように媒体は大きく変化しているだけで、それはメディア論的に捉えるならば大変化かもしれませんが、文化として捉えるならば本質ではなく手段・手法の問題ですね。
そこらへんのことは「(講演録)『男の娘(おとこのこ)』なるもの―その今と昔・性別認識を考える―」(駒沢女子大学・日本文化研究所『日本文化研究』10号 2013年 http://zoku-tasogare-2.blog.so-net.ne.jp/2015-08-08)で語ってます。
8.女装とテクノロジー、発達障害
あしやま テクノロジーといえば、一つ気になることがありまして。女装者はパソコンもそうですが、電車や機械などが好きな人が多く感じます。
三橋 女装の世界は、パソコン通信でも、インターネットでも、時代時代で最先端のものをすぐに取り込んできました。女装系のパソコン通信は90年に東西ほぼ同時に始まり、95年頃には全盛期を迎えました。隣村であるゲイ世界と比べるとテクノロジーの取り入れが圧倒的に早かったです。
実際、パソコン関連の仕事をしている女装者は多かったです。その理由については、パソコン業界が急速に拡大しソフトウェア需要が一気に高まった勃興期には、技術者が不足したため、容姿に関係なく、能力で採用したからという説があります。それは部分的には正解かもしれません。
でも、どうもそれだけではないような気がします。女装者には、鉄道オタクや軍事(ミリタリ)オタクがけっこう多い。それにバイクオタクも。なぜなのだろうと、ずっと疑問に思っていましたが、最近になって有力な仮説が浮上してきました。それは発達障害との関連。
あしやま あはは(笑)。それは、くとの先生も言っていて。女装者と発達障害は相関しているんじゃないかって。
三橋 オタク世界の住人と発達障害とはけっこう重なるわけですが、それと同じなのではないかということです。根っこに発達障害があって、なにか特定の分野に著しく入れ込む傾向がある。それが、鉄道だったり、ミリタリだったり、バイクだったり、そして女装だったり……。一見、遠いように思えるけど、根っこは同じ。だから、それらがしばしば重なって現れるという仮説です。
実は、性同一性障害と発達障害との関連、性同一性障害の人で性別の移行が難しいケースでは発達障害との重複が疑われるということは、臨床系の精神科医はかなり早い時期から気づいていたようです、ただ、性同一性障害の当事者が嫌がるので、公の場でなかなか言いにくかった。
ところが、2014年6月に横浜で開催された日本精神神経学会シンポジウムで、岡山大学の松本洋輔先生(精神科)が「広汎性発達障害と gender dysphoria の合併をめぐる臨床的問題」という題で発達障害と性別違和が合併した症例を報告しました。おそらく、これが公の場で発達障害と性別違和の重なりを指摘した初めての報告だと思います。私もパネラーとしてその場にいたのですが、堰を切ったように、臨床系の精神科の先生が賛同して、一年も経たずに性同一性障害と発達障害とはかなり重なるという認識が一気に広がりました。
あしやま 女装の世界にもいずれ普及してきそうですね。
三橋 以前、日本近代思想史研究の大家で鉄道趣味の原武史先生が、鉄道趣味はなぜ男性に偏っているのかという問題提起をしていた時に、「先生、実は、鉄道趣味は女装者や性同一性障害の人にも多いんですよ」という話をしました。
原先生、最初は信じてくれなかったのですが、お調べになると『ひまわり』の「向日葵学園女子高等学校」に鉄道サークルがあって、車両や駅で撮った女装写真がたくさん並んでいる。それで、現象としては納得されて、二人で何故なのかを議論したのですけど、当時は納得できる結論に至らなかった。
でも、発達障害と性同一性障害との重複が見えてくると、鉄道趣味と女装もしくは性同一性障害の重なりも単なる趣味の問題、文化的な傾向ではなく、より根源的なもの、つまり共通の根源としての発達障害ということで、解釈ができると思います。私もそうですけど、あしやまさんも鉄道も女装も好きという話で、他人事じゃあないですよね。
あしやま そうですね。僕は生活に支障も無いですし、病気ではないのですが、大学の保健管理センターで受けた正確な心理検査の結果は、分野間での開きが相当ありましたね。
三橋 まあ、私もあしやまさんもその傾向はあると思います。この相関は完全に立証されているわけではないのですが、おそらくそうでしょう。有名な女装者で、とても注意力散漫な方がいたり、ともかく思い当たるところが多いのです。発達障害の傾向がある人が一つの事に集中するという意味では、学者、研究者向きかもしれませんね。
9.女装の力。変化と連続の文化。
三橋 学者といえば、先日のニコニコ学会βでお会いした、くとの先生もお元気そうですし、小林秀章さん(セーラー服おじさん)も国際的に大活躍ですごいですよね。
あしやま セーラー服おじさんのすごいところは、ヨーロッパでもアジアでも通じるところですよね。
三橋 ニコニコ学会βでも語ったことですが、異形のダブル・ジェンダーが最強である、という理論は世界共通なのかなと思います。お人形みたいに綺麗じゃなく、あの風体だからこそ許されているのかなと思いますね。
あしやま 工学で言う不気味の谷のような話で、谷に落ちるまえのピークじゃないかなと思うんですね。
三橋 『女装と日本人』の段階で双性(ダブル・ジェンダー)の人は神に近くなるという「双性原理」の話を書きました。その後、神は本来異形であるという仮説を立てました。日本には異形の神がたくさんいるわけです。それを合わせると、ダブル・ジェンダーでかつ異形の人が、いちばん神性が強いということになります。
今や「セーラー服おじさんに出会ってツーショットを撮ると幸せになれる」という都市伝説が流れているわけで、セーラー服おじさんは「幸せを運ぶ都市神」的存在になっています。「双性&異形=最強」という私の理論は、セーラー服おじさんによって証明されたことになります。
あしやま でも、それは妖怪みたいな女装やコスプレとは違うという。
三橋 妖怪は零落した神なので、最初から零落していては駄目なんですね。セーラー服おじさんには、何だかよく分からないけどパワーがある。あのパワーがセーラー服おじさんを双性&異形の都市神として成立させているわけで、それをもう少し考えてみたいと思ってます。
あしやま パワーといえば、女装一般においても見た目と同じで、それ以上のプラスアルファの価値が必要ではないかというのは、過去の本誌でも度々話題になりました。
三橋 若い女性と同じで、よほど超越した美しさを持っている人以外は、外見だけでは持たない。他の魅力が必要ですね。女装でも、お人形さんみたいな女装ではすぐに飽きられる。当たり前のことですけど、容姿的な美しさに加えてタレント、つまり才能や魅力が必要です。
たとえば、はるな愛さんは、とてもクレバーな頭の回転の早い方で、実業家としても成功されているわけで、そういう人でないと長続きはしないのです。プロはもちろん、アマチュア女装やコスプレイヤーでも同じではないかと思います。
あしやま 川本直は前回の本誌で、一度女装界は落ちるところまで落ちたものもあったから上に伸びるのではなんて仰っていましたが。
三橋 どんな世界にも、上があれば下もある。しょうもない人はたくさんいます。しょうもない、というのは容姿に限らず、人格的なものも含めての話ですが。逆に、綺麗な人は昔からいるわけです。「富貴クラブ」のトップクラスはさすがに綺麗ですよ。ただ、そういうレベルの人は数人しかいない。現代はそのレベルが沢山いるという違いですね。
あしやま タレントの話で言えば、普通の人、のような人は少ないようにも感じます。たまに、女装者は知的水準が高いなんて言う人がいますが、おそらく上澄みしか見ていなくて、平均すると普通になるのではと思います。これも今も昔も何も変わっていないと思います。大きく変わっているところもあるけれど、変わっていないと言えば全く変わっていない。
三橋 時代(世代)とともに変わった部分はあるけど、変わらない部分もある。端的に言えば、どの時代にも女装したい人がいて、そうした女装者を愛でる人がいる。そうした人たちが作ってきた女装文化は、日本においては前近代以来脈々と連なる伝統がある。女装(異性装)への強い親和性が日本文化の伝統の一部になっている。現代のコスプレ要素の強い女装も、そこから外れるものではないと思います。
変わらない部分も大事だし、変わっていく部分も大切。つまりは、松尾芭蕉が言った「不易と流行」だと思うのです。「不易を知らざれば基立ちがたく、流行を知らざれば風新たならず」「その本は一つなり」、つまり、不変の真理を知らなければ基礎が確立せず、変化を知らなければ新たな進展がない。両者の根本は一つである、ということです。
それが、「エリザベス会館」、新宿女装コミュニティ、そしてGIDの三つの世界を渡り歩いて、いろいろ見聞きし、今は若い女装の人たちの活動を観察している私の結論ですね。
あしやま 今の女装の世界は、昔から脈々と続いてきているけれど、多様な文化が花開いていると。今日はとても貴重なお話が聞けました、ありがとうございました。
三橋 こんな老人の昔話みたいなインタビューを載せて、コミケで売るわけでしょう。やっぱり続いているし、変化している。面白いですね。
↑ 対談風景(あしやまさんは風邪を引いていたため「B面」)
2015年10月17日 下北沢にて
【論文】和装のモダンガールはいなかったのか? ―モダン・ファッションとしての銘仙―/ [論文・講演アーカイブ]
この論考は、2014年7月11日に京都女子大学で開催されたデザイン史学研究会第13回シンポジウ「スーツと着物―日本のモダン・ファッション再考」での研究報告「和装のモダンガールはいなかったのか?―モダン・ファッションとしての銘仙」をもとに論文化し、『デザイン史学』第14号(デザイン史学研究会、2016年7月)に日本文(123~128頁)と英文(151~158頁:Did Modern Girls wear Kimonos? -Meisen Silk as Modern Fashion-)で掲載されたものである。


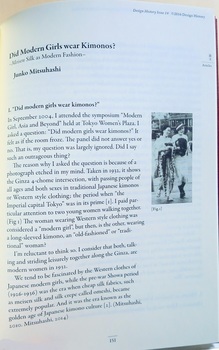
なお、『デザイン史学』第14号では紙幅の関係で図5・6は割愛したが、ここでは成稿時の形に復元した。
【追記】報告レジュメはこちら(↓)。
画像がたくさん入っています。
http://junko-mitsuhashi.blog.so-net.ne.jp/2015-07-12
------------------------------------------------
和装のモダンガールはいなかったのか?
―モダン・ファッションとしての銘仙―
三橋 順子(明治大学非常勤講師:着物文化論・性社会文化史)
1 「和装のモダンガールはいなかったのですか?」
2004年9月、東京「ウィメンズプラザ」で開催された「シンポジウム アジアのモダンガール」に出席した私は「和装のモダンガールはいなかったのですか?」と質問した。その瞬間、会場の温度が3度くらい下がったような気がした。報告者からは「いる」とも「いない」とも返答はなかった。つまり、ほとんど無視されたのである。私は、そんなにとんでもないことを言ってしまったのだろうか?
そんな質問をしたのは、1枚の写真が頭にあったからだ。それは「帝都東京」がもっとも華やいだ時代、昭和7年(1932)、老若男女、和装・洋装の人たちが行き交う東京銀座4丁目交差点を写したものだ(石川光陽1987)。とくに注目したのは、若い女性の二人連れだ(図1)。右側の洋装の女性は「モダンガール」で、左側の振袖姿の女性は「旧弊な」あるいは「伝統的な」女性なのだろうか?
.jpg)
(図1)
私にはそうは思えない。仲良く語らいながら銀座を闊歩する2人は、どちらも昭和7年における近代的(モダン)な女性なのだと思う。
「モダンガール」の洋装に目を奪われがちだが、昭和戦前期(1926~1936)は大衆絹織物(銘仙・お召)の大流行期であり、大衆レベルで見て日本の和装文化の全盛期と言っていい時代だった(三橋2010、同2014)。
考現学の創始者、今和次郎の調査によれば、大正14年(1925)の銀座には、洋装の女性は1%しかいなかった。その後、徐々に増えたかもしれないが、昭和戦前期の女性ファッションは和装が圧倒的に主流である。和装の女性の内訳は、銘仙が50.5%で半数を超え、お召と合わせると先染の織物は62.8%と3分の2に近くなる(今和次郎1925)。
こうした和装の主流を占めた銘仙には、人工染料の強い鮮やかな色味を用いたものがかなりあった。図1の左側の女性の振袖は、地色を部分的に変えながら、大きな「破れ麻の葉」柄を織り出した銘仙のように思われる。現在、残っている類似の品から想像して、濃い地色はおそらく臙脂で、そこに明るい薄鼠色で「破れ麻の葉」を織り出し、薄い地色の部分はその反対の色使いではないかと思う。いずれにしても、強いコントラストの大柄で、伝統的な(明治時代以前の)着物にはあり得ない、大胆でモダンな色使いである。
現代の私たちは、昭和戦前期に対して「モノクロームの昭和」というイメージを持っている。しかし今に残る大柄で色鮮やかな多色使いの銘仙やお召からして、少なくとも、日中戦争が始まる昭和12年(1937)以前の昭和初期については、そのイメージは間違いであり、むしろ「多彩・多色の昭和」とイメージすべきだと思う。
2 「モダン着物」としての銘仙
「多彩・多色の昭和」を演出した銘仙とは、どのような織物だったのだろうか。
銘仙とは、糸の段階で染めた(先染)絹糸を経糸と緯糸の直交組織(平織)で織り上げた絹織物である。養蚕地帯(生糸産地)である北関東の風土から生まれた織物で、もともとは玉繭などから取った節糸を天然染料で染めた堅牢な自家生産品だった。江戸時代には「目千」「太織(ふとり)」などと表記されたが、明治中期になって「銘仙」の字が当てられるようになった。たとえば、「伊勢崎太織」が「伊勢崎銘仙」と改称したのは明治21年(1888)のことだった。
明治末期~大正時代前期(1910年代)に工場生産化され、人工染料で経糸に着色し、絹紡糸を緯糸に使い、力織機で織りあげる技術が完成した。
大正~昭和戦前期に銘仙が大流行するには、いくつかの要素があった。
第一は、人工(化学)染料の導入である。これによって染色効率が飛躍的に向上し、多彩で鮮やかな(強い)色味を染められるようになった。
第二は、動力織機の普及である。従来の手動織機に比べて生産効率は格段に向上し、織物は工場生産による大量生産品となり、コストが大幅に低下し大量流通が可能になった。それにより、それまで経済的に絹織物を着られなかった(木綿を着ていた)階層にも銘仙は普及していった。
第三は、新技術「解し織り(ほぐしおり)」の開発である。「解し織り」とは 経糸をざっくりと仮織りした上で型染め捺染し、織機にかけた後で仮糸を解しながら緯糸を入れて本織をしていく技法である。明治42年(1909)に、群馬県伊勢崎で開発された技術で、たちまち他の生産地(埼玉県秩父、栃木県足利など)に広まった。「解し織り」の導入によって、多彩な色柄を精密かつ効率的に織り出すことが可能になった。
第四は、華麗・斬新な色柄である。伝統的な縞銘仙、絣(かすり)銘仙に加えて「解し織り」による模様銘仙の登場により色柄がきわめて豊富になった。麻の葉、石畳、折鶴、傘などの伝統的な意匠をリニューアルしたものに加えて、アール・ヌーボー、アール・デコなどヨーロッパ美術界の先端的デザインが積極的に導入された(図2,3,4)。主要生産地だった埼玉県秩父では、上野の美術学校(現:東京芸術大学)の卒業生・学生などに基本デザインを依頼していた。そうした最新デザインを直交組織の織物で表現することが職人の腕の見せ所だった。
-6083b.jpg)
(図2)アール・ヌーボー系の銘仙
巨大なチューリップ。黒の地に、白、黄、緑で花を、緑とショッキング・ピンクで葉を織り出す
-a86ee.jpg)
(図3)アール・デコ系の銘仙
黒、白、赤で折れ線模様を織り出す。 薄鼠色に見える部分は、白地に細い黒の格子柄。
-4a52a.jpg)
(図4)伝統的意匠のリニューアル
群青の地に、大きな椿の花を赤で、葉を青緑で織り出す。花や葉の縁には白を入れて雪椿であることを表現している。
第五は、流行の演出である。大正末期~昭和初期の大都市に新たな商業施設としてデパートが出現する。たとえば、東京銀座の松坂屋(1924年)、松屋(1925年)、三越(1930年)、新興の「盛り場」として台頭しつつあった新宿の三越(1929年)、伊勢丹(1933年)などである。そうしたデパートが都市大衆消費文化の目玉商品として注目したのが銘仙であり、産地と提携した展示会などを開催して「流行」を積極的に演出していった。
当時の新聞の婦人欄には、「色は濃めに 柄は横段、格子風 生地も変化ある新物 夏物の流行」(『読売新聞』1928年5月4日朝刊)とか、「この秋・流行の王座を飾るもの 銘仙オンパレード? 模様は平面から立体へ 色は渋好みになりました」(『同』1931年9月16日朝刊)のように、その年の銘仙の流行が報じられている。
第六は、都市中産階層の成長による新たな着用層の増加である。消費活動を活発化していった中産階層の女性たちにとって、銘仙は格好の消費対象だった。たとえば、昭和8年(1933)秩父産の模様銘仙は5円80銭~6円50銭だった。当時の6円は、現代の21000~24000円ほどと思われるので、都市中産階層ならシーズン1着の購入は十分に可能な値段である。
こうした銘仙の大流行を支えた諸要素は、いずれもそれまでの伝統的な着物には見られなかった特質である。銘仙は、形態的にはともかく、デザイン的には明治以前の着物とは明らかに異なる「モダン着物」(化学染料+力織機+新柄+流行演出)だった。旧癖な人たちの目からすれば、「モダン着物」である銘仙は、「最近の若い娘は・・・」と眉をひそめるという点で、洋装とそれほど異なるものではなかったと思う。
そして、生産・流通という視点で重要なことは、銘仙は、日本における最初の工業的デザインによる大量生産品であり、生産地とバイヤーの連携によって流行が演出された大量流通品であるということだ。
つまり、銘仙はプレタポルテ(既製服)的である。その点で、高価な手工業少量生産品でオートクチュール(注文服)的だった明治時代以前の友禅染などの絹の着物と異なり、むしろ現代の大衆的な洋服に近い。また当時の「モダンガール」が着ていた洋服がオートクチュール的であったことを考えれば、プレタポルテ的な銘仙は、ファッションの流れの中で、より先行的・現代的であると言える。
3 日本近代ファッション史における銘仙
昭和戦前期、洋装の「モダンガール」と同じ時代に、銘仙を着た娘たちがいた。彼女たちが着ていた銘仙は、旧来の着物とはデザイン的にも、生産・流通的にも大きく異なる「モダン着物」だった。そして、「モダンガール」よりも銘仙を着た「モダン着物娘」の方が圧倒的に多数だった。「モダン着物(銘仙)」と 「モダン着物娘」の存在を無視して日本近代ファッション史、デザイン史を語るのはまったく実態にそぐわないし、誤りである。
-c98eb.jpg)
(図5) 日本近代ファッション史の単線的なイメージ
従来の日本近代ファッション史は、和装から洋装へという変化を単線的に考え、その接続点に「モダンガール」を位置させることが多い。しかし、そうした単線的な図式(図5)は明らかに誤りだ。
-a9ce5.jpg)
(図6) 日本近代ファッション史の複線的なイメージ
実際には、「モダン着物娘」と「モダンガール」は、昭和戦前期において同時併存していたのであり、この時期には和装、洋装の2つの流れが相互に影響しあっていたと、複線的にイメージすべきなのだ(図6)。
おわりに
銘仙は、日本人女性の日常衣料の洋装化の進展にともない、昭和40年(1965)頃から急速に衰退し、生産がほぼ途絶する。工場生産品だったために伝統工芸として認められることもなく、ファッション史だけでなく、着物の歴史においてさえ、長らく忘れ去られた存在だった。しかし、2000年代に入ってようやくその魅力が再認識され、コレクションの紹介や研究が進みつつある(須坂クラシック美術館1996、三橋2002、別冊太陽2004、日本きもの文化美術館2010)。2015年には東京六本木の「泉屋博古館」で大規模な展覧会が行われた(須坂クラシック美術館2015)。
今後、銘仙を日本近代ファッション史、デザイン史に正しく位置づける研究が望まれる。本稿がその端緒になれば幸いに思う。
【文献】
今和次郎1925「東京銀座街風俗記録」(『婦人公論』1925年7月号)
石川光陽1987『昭和の東京 ―あのころの街と風俗―』朝日新聞社)
須坂クラシック美術館1996『岡信孝コレクション 華やかな美―大正の着物モード―』(須坂クラシック美術館)
三橋順子2002「艶やかなる銘仙」
(『KIMONO道』2号、祥伝社。後に『KIMONO姫』2号、2003年、祥伝社、に拡大再掲)
別冊太陽2004『銘仙 ―大正・昭和のおしゃれ着―』(平凡社)
日本きもの文化美術館2010『ハイカラさんのおしゃれじょうず ―銘仙きもの 多彩な世界―』(日本きもの文化美術館)
三橋順子2010「銘仙とその時代」(『ハイカラさんのおしゃれじょうず ―銘仙きもの 多彩な世界―』日本きもの文化美術館)
三橋順子2014「『着物趣味』の成立」(『現代風俗学研究』15号 現代風俗研究会 東京の会)
須坂クラシック美術館2015『きものモダニズムー須坂クラッシック美術館 銘仙コレクションー』(須坂クラシック美術館)
なお、『デザイン史学』第14号では紙幅の関係で図5・6は割愛したが、ここでは成稿時の形に復元した。
【追記】報告レジュメはこちら(↓)。
画像がたくさん入っています。
http://junko-mitsuhashi.blog.so-net.ne.jp/2015-07-12
------------------------------------------------
和装のモダンガールはいなかったのか?
―モダン・ファッションとしての銘仙―
三橋 順子(明治大学非常勤講師:着物文化論・性社会文化史)
1 「和装のモダンガールはいなかったのですか?」
2004年9月、東京「ウィメンズプラザ」で開催された「シンポジウム アジアのモダンガール」に出席した私は「和装のモダンガールはいなかったのですか?」と質問した。その瞬間、会場の温度が3度くらい下がったような気がした。報告者からは「いる」とも「いない」とも返答はなかった。つまり、ほとんど無視されたのである。私は、そんなにとんでもないことを言ってしまったのだろうか?
そんな質問をしたのは、1枚の写真が頭にあったからだ。それは「帝都東京」がもっとも華やいだ時代、昭和7年(1932)、老若男女、和装・洋装の人たちが行き交う東京銀座4丁目交差点を写したものだ(石川光陽1987)。とくに注目したのは、若い女性の二人連れだ(図1)。右側の洋装の女性は「モダンガール」で、左側の振袖姿の女性は「旧弊な」あるいは「伝統的な」女性なのだろうか?
.jpg)
(図1)
私にはそうは思えない。仲良く語らいながら銀座を闊歩する2人は、どちらも昭和7年における近代的(モダン)な女性なのだと思う。
「モダンガール」の洋装に目を奪われがちだが、昭和戦前期(1926~1936)は大衆絹織物(銘仙・お召)の大流行期であり、大衆レベルで見て日本の和装文化の全盛期と言っていい時代だった(三橋2010、同2014)。
考現学の創始者、今和次郎の調査によれば、大正14年(1925)の銀座には、洋装の女性は1%しかいなかった。その後、徐々に増えたかもしれないが、昭和戦前期の女性ファッションは和装が圧倒的に主流である。和装の女性の内訳は、銘仙が50.5%で半数を超え、お召と合わせると先染の織物は62.8%と3分の2に近くなる(今和次郎1925)。
こうした和装の主流を占めた銘仙には、人工染料の強い鮮やかな色味を用いたものがかなりあった。図1の左側の女性の振袖は、地色を部分的に変えながら、大きな「破れ麻の葉」柄を織り出した銘仙のように思われる。現在、残っている類似の品から想像して、濃い地色はおそらく臙脂で、そこに明るい薄鼠色で「破れ麻の葉」を織り出し、薄い地色の部分はその反対の色使いではないかと思う。いずれにしても、強いコントラストの大柄で、伝統的な(明治時代以前の)着物にはあり得ない、大胆でモダンな色使いである。
現代の私たちは、昭和戦前期に対して「モノクロームの昭和」というイメージを持っている。しかし今に残る大柄で色鮮やかな多色使いの銘仙やお召からして、少なくとも、日中戦争が始まる昭和12年(1937)以前の昭和初期については、そのイメージは間違いであり、むしろ「多彩・多色の昭和」とイメージすべきだと思う。
2 「モダン着物」としての銘仙
「多彩・多色の昭和」を演出した銘仙とは、どのような織物だったのだろうか。
銘仙とは、糸の段階で染めた(先染)絹糸を経糸と緯糸の直交組織(平織)で織り上げた絹織物である。養蚕地帯(生糸産地)である北関東の風土から生まれた織物で、もともとは玉繭などから取った節糸を天然染料で染めた堅牢な自家生産品だった。江戸時代には「目千」「太織(ふとり)」などと表記されたが、明治中期になって「銘仙」の字が当てられるようになった。たとえば、「伊勢崎太織」が「伊勢崎銘仙」と改称したのは明治21年(1888)のことだった。
明治末期~大正時代前期(1910年代)に工場生産化され、人工染料で経糸に着色し、絹紡糸を緯糸に使い、力織機で織りあげる技術が完成した。
大正~昭和戦前期に銘仙が大流行するには、いくつかの要素があった。
第一は、人工(化学)染料の導入である。これによって染色効率が飛躍的に向上し、多彩で鮮やかな(強い)色味を染められるようになった。
第二は、動力織機の普及である。従来の手動織機に比べて生産効率は格段に向上し、織物は工場生産による大量生産品となり、コストが大幅に低下し大量流通が可能になった。それにより、それまで経済的に絹織物を着られなかった(木綿を着ていた)階層にも銘仙は普及していった。
第三は、新技術「解し織り(ほぐしおり)」の開発である。「解し織り」とは 経糸をざっくりと仮織りした上で型染め捺染し、織機にかけた後で仮糸を解しながら緯糸を入れて本織をしていく技法である。明治42年(1909)に、群馬県伊勢崎で開発された技術で、たちまち他の生産地(埼玉県秩父、栃木県足利など)に広まった。「解し織り」の導入によって、多彩な色柄を精密かつ効率的に織り出すことが可能になった。
第四は、華麗・斬新な色柄である。伝統的な縞銘仙、絣(かすり)銘仙に加えて「解し織り」による模様銘仙の登場により色柄がきわめて豊富になった。麻の葉、石畳、折鶴、傘などの伝統的な意匠をリニューアルしたものに加えて、アール・ヌーボー、アール・デコなどヨーロッパ美術界の先端的デザインが積極的に導入された(図2,3,4)。主要生産地だった埼玉県秩父では、上野の美術学校(現:東京芸術大学)の卒業生・学生などに基本デザインを依頼していた。そうした最新デザインを直交組織の織物で表現することが職人の腕の見せ所だった。
-6083b.jpg)
(図2)アール・ヌーボー系の銘仙
巨大なチューリップ。黒の地に、白、黄、緑で花を、緑とショッキング・ピンクで葉を織り出す
-a86ee.jpg)
(図3)アール・デコ系の銘仙
黒、白、赤で折れ線模様を織り出す。 薄鼠色に見える部分は、白地に細い黒の格子柄。
-4a52a.jpg)
(図4)伝統的意匠のリニューアル
群青の地に、大きな椿の花を赤で、葉を青緑で織り出す。花や葉の縁には白を入れて雪椿であることを表現している。
第五は、流行の演出である。大正末期~昭和初期の大都市に新たな商業施設としてデパートが出現する。たとえば、東京銀座の松坂屋(1924年)、松屋(1925年)、三越(1930年)、新興の「盛り場」として台頭しつつあった新宿の三越(1929年)、伊勢丹(1933年)などである。そうしたデパートが都市大衆消費文化の目玉商品として注目したのが銘仙であり、産地と提携した展示会などを開催して「流行」を積極的に演出していった。
当時の新聞の婦人欄には、「色は濃めに 柄は横段、格子風 生地も変化ある新物 夏物の流行」(『読売新聞』1928年5月4日朝刊)とか、「この秋・流行の王座を飾るもの 銘仙オンパレード? 模様は平面から立体へ 色は渋好みになりました」(『同』1931年9月16日朝刊)のように、その年の銘仙の流行が報じられている。
第六は、都市中産階層の成長による新たな着用層の増加である。消費活動を活発化していった中産階層の女性たちにとって、銘仙は格好の消費対象だった。たとえば、昭和8年(1933)秩父産の模様銘仙は5円80銭~6円50銭だった。当時の6円は、現代の21000~24000円ほどと思われるので、都市中産階層ならシーズン1着の購入は十分に可能な値段である。
こうした銘仙の大流行を支えた諸要素は、いずれもそれまでの伝統的な着物には見られなかった特質である。銘仙は、形態的にはともかく、デザイン的には明治以前の着物とは明らかに異なる「モダン着物」(化学染料+力織機+新柄+流行演出)だった。旧癖な人たちの目からすれば、「モダン着物」である銘仙は、「最近の若い娘は・・・」と眉をひそめるという点で、洋装とそれほど異なるものではなかったと思う。
そして、生産・流通という視点で重要なことは、銘仙は、日本における最初の工業的デザインによる大量生産品であり、生産地とバイヤーの連携によって流行が演出された大量流通品であるということだ。
つまり、銘仙はプレタポルテ(既製服)的である。その点で、高価な手工業少量生産品でオートクチュール(注文服)的だった明治時代以前の友禅染などの絹の着物と異なり、むしろ現代の大衆的な洋服に近い。また当時の「モダンガール」が着ていた洋服がオートクチュール的であったことを考えれば、プレタポルテ的な銘仙は、ファッションの流れの中で、より先行的・現代的であると言える。
3 日本近代ファッション史における銘仙
昭和戦前期、洋装の「モダンガール」と同じ時代に、銘仙を着た娘たちがいた。彼女たちが着ていた銘仙は、旧来の着物とはデザイン的にも、生産・流通的にも大きく異なる「モダン着物」だった。そして、「モダンガール」よりも銘仙を着た「モダン着物娘」の方が圧倒的に多数だった。「モダン着物(銘仙)」と 「モダン着物娘」の存在を無視して日本近代ファッション史、デザイン史を語るのはまったく実態にそぐわないし、誤りである。
-c98eb.jpg)
(図5) 日本近代ファッション史の単線的なイメージ
従来の日本近代ファッション史は、和装から洋装へという変化を単線的に考え、その接続点に「モダンガール」を位置させることが多い。しかし、そうした単線的な図式(図5)は明らかに誤りだ。
-a9ce5.jpg)
(図6) 日本近代ファッション史の複線的なイメージ
実際には、「モダン着物娘」と「モダンガール」は、昭和戦前期において同時併存していたのであり、この時期には和装、洋装の2つの流れが相互に影響しあっていたと、複線的にイメージすべきなのだ(図6)。
おわりに
銘仙は、日本人女性の日常衣料の洋装化の進展にともない、昭和40年(1965)頃から急速に衰退し、生産がほぼ途絶する。工場生産品だったために伝統工芸として認められることもなく、ファッション史だけでなく、着物の歴史においてさえ、長らく忘れ去られた存在だった。しかし、2000年代に入ってようやくその魅力が再認識され、コレクションの紹介や研究が進みつつある(須坂クラシック美術館1996、三橋2002、別冊太陽2004、日本きもの文化美術館2010)。2015年には東京六本木の「泉屋博古館」で大規模な展覧会が行われた(須坂クラシック美術館2015)。
今後、銘仙を日本近代ファッション史、デザイン史に正しく位置づける研究が望まれる。本稿がその端緒になれば幸いに思う。
【文献】
今和次郎1925「東京銀座街風俗記録」(『婦人公論』1925年7月号)
石川光陽1987『昭和の東京 ―あのころの街と風俗―』朝日新聞社)
須坂クラシック美術館1996『岡信孝コレクション 華やかな美―大正の着物モード―』(須坂クラシック美術館)
三橋順子2002「艶やかなる銘仙」
(『KIMONO道』2号、祥伝社。後に『KIMONO姫』2号、2003年、祥伝社、に拡大再掲)
別冊太陽2004『銘仙 ―大正・昭和のおしゃれ着―』(平凡社)
日本きもの文化美術館2010『ハイカラさんのおしゃれじょうず ―銘仙きもの 多彩な世界―』(日本きもの文化美術館)
三橋順子2010「銘仙とその時代」(『ハイカラさんのおしゃれじょうず ―銘仙きもの 多彩な世界―』日本きもの文化美術館)
三橋順子2014「『着物趣味』の成立」(『現代風俗学研究』15号 現代風俗研究会 東京の会)
須坂クラシック美術館2015『きものモダニズムー須坂クラッシック美術館 銘仙コレクションー』(須坂クラシック美術館)
【インタビュー】「わたしの光になった表現」(聞き手:外山雄太) [論文・講演アーカイブ]
集英社の文芸誌『すばる』2016年8月号は「特集・LGBT-海の向こうから-」。

虹色の表紙が目印。
インタビュー記事「わたしの光になった表現」(聞き手:外山雄太)は、牧村朝子・杉山文野・中村キヨ・マーガレット・田亀源五郎・橋口亮輔という豪華なメンバーが「人生の大切な局面をともにした三つの作品」を語る。
その他、海外のLGBT関係の評論・エッセイ8本を掲載。
東京の主要書店では、7月6日発売(税込950円)。
インタビューは、5月31日(火)。
明治大学(駿河台)での講義の後、17時少し前、神田神保町三丁目の「集英社」へ。
インタビュアーは外山雄太さん。
昨年3月、『朝日新聞』の原田朱美記者の紹介で知り合った方。
ご縁が形になってうれしい。
最初に撮影。
簡単な撮影かと思ったら、ちゃんとプロのカメラマンが待機していて、まず室内で、さらに、屋外に出て撮影。
着物、着てきてよかった。

↑ 撮影:隼田大輔氏
その後、2時間半ほど、「わたしの光となった表現」というテーマであれこれしゃべる。
まず、1980年代までに青年期を過ごした私の世代は、そもそも世の中に性別越境についての情報が乏しく、それを見つける(実際には、偶然、出会う)ことがたいへんだったことを話す。
「性別違和」という自分の状況を説明する言葉も、「性同一性障害」という概念も日本には入っていなかった。
そんな状況の中で「自分を見つける」導きになった書籍として、
(1)存在への気づき、(2)「成りたい」自己イメージの形成、(3)自己肯定化の理論、という観点で3冊を挙げた。
----------------------------
今回、豪華なメンバーの驥尾に付して出していただいたが、いろいろな意味で、トランスジェンダーとしての私の社会的な役割は終わったのかなと思う、今日この頃。
たくさんの方に「まだまだ」と言っていただけるのは励みにはなるけど、もう表舞台に出るのは心身ともに辛くなってきた。
あと何年生きられるかわからないが、残りの人生は研究生活、とりわけ、自分の著述のまとめに専念しようと思う。
『すばる』は創刊(1970年)から数年間、高校生の頃に購読していた思い出のある雑誌で、そこに出られたのは、そういう意味で良い記念になった。
-----------------------------------------------------
わたしの光となった表現
「あなたはどのような表現に影響を受け、また、支えられてきましたか?」
セクシュアリティー/世代/職業の異なる七名に、
人生の大切な局面をともにした三つの作品との出会いと、
その魅力についてうかがった。
探すものではなく、出会うもの
三橋順子
「二〇〇〇年、初めて大学の教壇に立った最初の講義の日、忘れもしません。週刊誌が三誌も取材に来たんです。日本で最初の、トランスジェンダーの大学教員。いったいそれ何? というまったく興味本位な反応でした」
三橋順子さんは、日本における性別越境、トランスジェンダーの社会・文化史研究家だ。歴史学的な手法で調査対象に取り組み、トランスジェンダーおよびセクシャルマイノリティーの歴史を探求してきた。
「自分が〝ふつう〟の男子と違うかも? と気づいたのは遅かったです。高校生のころ、おぼろげにそうかもしれない……と思ったくらいで、それ以前はとくになにも感じていませんでした。少なくとも、自分としては気づていないことになってました。のちのち専門の精神科医の先生にカウンセリングしてもらうと、どうも〝ふつう〟でない、記憶に蓋をしていたエピソードがたくさん出てきましたが。
自分のなかに別の人格がいて、それが女性だったと気づいたのは二十一歳のころ。性同一性障害とか、性別違和とか、そういう概念がない時代です。すてきな女性に対して、『付き合いたい』よりも、『ああいうふうになりたい』という気持ちを抱きました。
そんな自分が不可解で、図書館で精神分析学の本を読んだけど、答えは見つかりません。二十代後半が、自分がなぜこうなのか、よく分からず、つらかった時期でした。
そんな田舎から東京に出てきた青年が、いちばん最初に共鳴したのが『別冊SMスナイパー』一九八〇年十一月号に掲載されていた館淳一さんの「ナイロンの罠」という小説。一九八三年に単行本が刊行されますが、雑誌掲載時に読んで、これだ……! と思いました。自分の姉と義兄の手によって女性化されていく男子予備校生のお話。 女装の道に引き摺りこまれる美少年に自分を重ねたんですね。この作品は、二十五歳だったわたしのセクシュアル・ファンタジーの形成に多大な影響を与えました。三十数年後、著者の館淳一さんにお会いしたときは、大感激でした。

↑ 館 淳一『ナイロンの罠』(ミリオン出版 1983年)

↑ 初出の『別冊SMスナイパー』1980年11月号。
ほぼ時期を同じくして存在を知ったのが、土田ヒロミ撮影『青い花――東京ドール――』(世文社、一九八一年)でした。これは、一九七〇年代の東京のゲイボーイを主題にした写真集です。ゲイボーイというのは、当時は女装した男性のことを指しました。いまのゲイということばと、、八〇年代までのゲイとでは意味のズレがあるんです。
トランスジェンダー的な人物をテーマに撮影した日本初の写真集の存在は、スポーツ新聞で見て知っていましたが、当時二八〇〇円もする本なんて手が出ませんでした。あるとき、たまたま立ち寄った神保町の古本屋さんでめぐり会ったんです。店の前側には真面目な古本が、奥にSMやポルノ雑誌が置かれているような、お堅い本でエロをカムフラージュした本屋さんでした。そこで、『青い花』をやっと手に入れました。当時は、今のように情報が流通していませんから、こういった本は、探してもなかなか見つかるものではありません。存在が隠されているから探しようがなく、偶然出会うものだったんです。
写真集を見て、それまでぼんやりとしたイメージでしかなかった〝女装〟というものが、明確に可視化されました。「東京のどこかに、こうやって美しく着飾ったゲイボーイがいるんだ!」という強い実感。見えること、視覚的にイメージ化できることはそれだけ重要なんです。被写体になっていた〝お姉さん〟たちは、たぶん、赤坂、六本木あたりでお勤めの方々だったと思います。記載がないから、確かではないけれど。でも、自分と似たような感じの人がこれだけいるということを知って、なりたいわたしのイメージはより強固なものになっていきました」
.jpg)
-a7dc7.jpg)
↑ 土田ヒロミ撮影『青い花ー東京ドールー』(世文社 1981年)
しかし、そんなイメージを頼りに女装をし始めた八〇年代の終わりごろ、また別の問題が浮上したのだという。
「自己イメージは定まってきたけれど、それを言語化することがなかなかできませんでした。そんなときに出会ったのが、渡辺恒夫先生の『脱男性の時代――アンドロジナスを目指す文明学――』(勁草書房、一九八六年)でした。女装、性転換、アンドロジナス(両性具有)の世界を探求した評論集で、 女装者としての私の形成に際して、理論的な面で大きな影響を受けました。
評論として高く評価された『脱男性の時代』以外にも、二冊ほど同じような内容の本を書かれていて、『精神科治療か服装革命か』なんて、いまにも通じる問いを投じられました。〝トランスジェンダー〟というワードを書名にした日本最初の本の著者は、渡辺先生なんです(『トランス・ジェンダーの文化―異世界へ越境する知―』勁草書房、一九八九年)。
でも、その後はトランスジェンダーについては事実上、筆を折っちゃったんです。詳しい事情はよくわかりませんが、「おかしな研究をしている」というような社会的な圧力があったのではないでしょうか。いずれにせよ、日本にトランスジェンダリズムの原点をつくった重要な研究者であることは間違いありません」
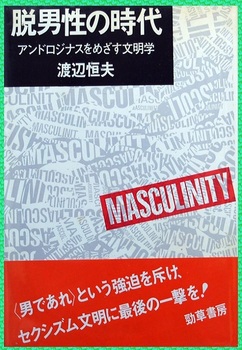
↑ 渡辺恒夫『脱男性の時代ーアンドロジナスを目指す文明学ー』(勁草書房 1986年)
九〇年代に入り、一九七九年創業の女装メイクルーム&サロン「エリザベス会館」に所属、自己流の女装から、本格的な技術を学んで女装をするようになった。のちに新宿歌舞伎町の女装スナック「ジュネ」でホステスとして働きはじめる。現在につながる〝研究〟を本格的に始められたきっかけは、何だったんだろう。
「九六、七年くらいに、〝性同一性障害〟ということばが一気に広まりました。「性同一性障害のあとに、トランスジェンダーということばが入ってきた」と言う人もいるけど、それは事実誤認です。トランスジェンダーが先にあって、その概念こそが性別を越えて生きようというわたしたちの自己肯定の出発点になっていたんです。
〝性同一性障害〟という概念の登場によって、新宿の女装世界はものすごく影響を受けました。分かりやすく言うと、いままでお店のドアを叩いていた女の子になりたい願望を持つ子たちが、みんな病院に行くようになってしまったんです。性別を越えて生きたいと思うのは障害であり、治療すべき病気だという考えが広まるにつれて、ずいぶんお客さんが減りました。
ある常連さんからは、「おまえたちが病気ってことは、俺は病気の人間と、病気をネタに酒を飲んでいるのか? そんなことする俺って人でなしじゃないか」と言われて。「そうじゃないのよ。楽しく飲めばいいじゃない」となだめても、一度落ちた気分は直りません。
そんななか、ママや古いお客さんからお店の昔話を聞くのが好きだったわたしに、先輩ホステスがこんなふうに言いました。
「わたしたちが作ってきた女装世界は、近い将来になくなっちゃうかもしれない。こんな世界があったことを、記録して残すことが、歴史学を勉強した順ちゃんの役目よ」
それ以来、研究者というよりは当事者として、調べて記録しなくてはならないという強い意識を持つようになりました。「ジュネ」という店の歴史、それを中核とした新宿の女装世界の成り立ちを遡って調べていきました。そんな調査をより社会史的な研究にしていこうと思い始めた時期に、中央大学の矢島正見先生(社会学)から声をかけられて、一九九九年に「戦後日本〈トランスジェンダー〉社会史研究会」を立ち上げ、歴史学と社会学の二つの手法で研究をしていくことになりました」
二〇〇〇年代初頭から、「性別を越えて生きることは病ではない」と一貫して性別越境の病理化を批判しつづけ、性同一性障害という病理概念に絡めとられることを拒否してきた三橋さん。ようやく時代の流れが変わりつつあるようだ。
「来年か、再来年かに実施されるWHOの国際疾病分類(ICD)の改訂にともなって、性別越境が精神疾患でなくなる見通しなんです。性同一性障害という病名も国際的には消えることになります。同性愛の脱病理化に遅れること二十七、八年、自分が唱えてきたことが実現することへ期待と喜びはもちろんあります。
「研究ができる女装者がいたんだ!」と驚かれたり、「病気と認められて良かったですね」と善意の人に言われた時代もありました。当時とくらべれば、ずいぶんトランスジェンダーが生きやすい世の中になったと思います。でも、まだまだ調べて記録しなければならないことはたくさんあります」
着物の襟を正しながら、まっすぐ前を見据える三橋さん。
「トランスジェンダー研究をきちんと引き継いでくれるひとが現われるまで、わたしもがんばりますよ」
虹色の表紙が目印。
インタビュー記事「わたしの光になった表現」(聞き手:外山雄太)は、牧村朝子・杉山文野・中村キヨ・マーガレット・田亀源五郎・橋口亮輔という豪華なメンバーが「人生の大切な局面をともにした三つの作品」を語る。
その他、海外のLGBT関係の評論・エッセイ8本を掲載。
東京の主要書店では、7月6日発売(税込950円)。
インタビューは、5月31日(火)。
明治大学(駿河台)での講義の後、17時少し前、神田神保町三丁目の「集英社」へ。
インタビュアーは外山雄太さん。
昨年3月、『朝日新聞』の原田朱美記者の紹介で知り合った方。
ご縁が形になってうれしい。
最初に撮影。
簡単な撮影かと思ったら、ちゃんとプロのカメラマンが待機していて、まず室内で、さらに、屋外に出て撮影。
着物、着てきてよかった。
↑ 撮影:隼田大輔氏
その後、2時間半ほど、「わたしの光となった表現」というテーマであれこれしゃべる。
まず、1980年代までに青年期を過ごした私の世代は、そもそも世の中に性別越境についての情報が乏しく、それを見つける(実際には、偶然、出会う)ことがたいへんだったことを話す。
「性別違和」という自分の状況を説明する言葉も、「性同一性障害」という概念も日本には入っていなかった。
そんな状況の中で「自分を見つける」導きになった書籍として、
(1)存在への気づき、(2)「成りたい」自己イメージの形成、(3)自己肯定化の理論、という観点で3冊を挙げた。
----------------------------
今回、豪華なメンバーの驥尾に付して出していただいたが、いろいろな意味で、トランスジェンダーとしての私の社会的な役割は終わったのかなと思う、今日この頃。
たくさんの方に「まだまだ」と言っていただけるのは励みにはなるけど、もう表舞台に出るのは心身ともに辛くなってきた。
あと何年生きられるかわからないが、残りの人生は研究生活、とりわけ、自分の著述のまとめに専念しようと思う。
『すばる』は創刊(1970年)から数年間、高校生の頃に購読していた思い出のある雑誌で、そこに出られたのは、そういう意味で良い記念になった。
-----------------------------------------------------
わたしの光となった表現
「あなたはどのような表現に影響を受け、また、支えられてきましたか?」
セクシュアリティー/世代/職業の異なる七名に、
人生の大切な局面をともにした三つの作品との出会いと、
その魅力についてうかがった。
探すものではなく、出会うもの
三橋順子
「二〇〇〇年、初めて大学の教壇に立った最初の講義の日、忘れもしません。週刊誌が三誌も取材に来たんです。日本で最初の、トランスジェンダーの大学教員。いったいそれ何? というまったく興味本位な反応でした」
三橋順子さんは、日本における性別越境、トランスジェンダーの社会・文化史研究家だ。歴史学的な手法で調査対象に取り組み、トランスジェンダーおよびセクシャルマイノリティーの歴史を探求してきた。
「自分が〝ふつう〟の男子と違うかも? と気づいたのは遅かったです。高校生のころ、おぼろげにそうかもしれない……と思ったくらいで、それ以前はとくになにも感じていませんでした。少なくとも、自分としては気づていないことになってました。のちのち専門の精神科医の先生にカウンセリングしてもらうと、どうも〝ふつう〟でない、記憶に蓋をしていたエピソードがたくさん出てきましたが。
自分のなかに別の人格がいて、それが女性だったと気づいたのは二十一歳のころ。性同一性障害とか、性別違和とか、そういう概念がない時代です。すてきな女性に対して、『付き合いたい』よりも、『ああいうふうになりたい』という気持ちを抱きました。
そんな自分が不可解で、図書館で精神分析学の本を読んだけど、答えは見つかりません。二十代後半が、自分がなぜこうなのか、よく分からず、つらかった時期でした。
そんな田舎から東京に出てきた青年が、いちばん最初に共鳴したのが『別冊SMスナイパー』一九八〇年十一月号に掲載されていた館淳一さんの「ナイロンの罠」という小説。一九八三年に単行本が刊行されますが、雑誌掲載時に読んで、これだ……! と思いました。自分の姉と義兄の手によって女性化されていく男子予備校生のお話。 女装の道に引き摺りこまれる美少年に自分を重ねたんですね。この作品は、二十五歳だったわたしのセクシュアル・ファンタジーの形成に多大な影響を与えました。三十数年後、著者の館淳一さんにお会いしたときは、大感激でした。

↑ 館 淳一『ナイロンの罠』(ミリオン出版 1983年)

↑ 初出の『別冊SMスナイパー』1980年11月号。
ほぼ時期を同じくして存在を知ったのが、土田ヒロミ撮影『青い花――東京ドール――』(世文社、一九八一年)でした。これは、一九七〇年代の東京のゲイボーイを主題にした写真集です。ゲイボーイというのは、当時は女装した男性のことを指しました。いまのゲイということばと、、八〇年代までのゲイとでは意味のズレがあるんです。
トランスジェンダー的な人物をテーマに撮影した日本初の写真集の存在は、スポーツ新聞で見て知っていましたが、当時二八〇〇円もする本なんて手が出ませんでした。あるとき、たまたま立ち寄った神保町の古本屋さんでめぐり会ったんです。店の前側には真面目な古本が、奥にSMやポルノ雑誌が置かれているような、お堅い本でエロをカムフラージュした本屋さんでした。そこで、『青い花』をやっと手に入れました。当時は、今のように情報が流通していませんから、こういった本は、探してもなかなか見つかるものではありません。存在が隠されているから探しようがなく、偶然出会うものだったんです。
写真集を見て、それまでぼんやりとしたイメージでしかなかった〝女装〟というものが、明確に可視化されました。「東京のどこかに、こうやって美しく着飾ったゲイボーイがいるんだ!」という強い実感。見えること、視覚的にイメージ化できることはそれだけ重要なんです。被写体になっていた〝お姉さん〟たちは、たぶん、赤坂、六本木あたりでお勤めの方々だったと思います。記載がないから、確かではないけれど。でも、自分と似たような感じの人がこれだけいるということを知って、なりたいわたしのイメージはより強固なものになっていきました」
.jpg)
-a7dc7.jpg)
↑ 土田ヒロミ撮影『青い花ー東京ドールー』(世文社 1981年)
しかし、そんなイメージを頼りに女装をし始めた八〇年代の終わりごろ、また別の問題が浮上したのだという。
「自己イメージは定まってきたけれど、それを言語化することがなかなかできませんでした。そんなときに出会ったのが、渡辺恒夫先生の『脱男性の時代――アンドロジナスを目指す文明学――』(勁草書房、一九八六年)でした。女装、性転換、アンドロジナス(両性具有)の世界を探求した評論集で、 女装者としての私の形成に際して、理論的な面で大きな影響を受けました。
評論として高く評価された『脱男性の時代』以外にも、二冊ほど同じような内容の本を書かれていて、『精神科治療か服装革命か』なんて、いまにも通じる問いを投じられました。〝トランスジェンダー〟というワードを書名にした日本最初の本の著者は、渡辺先生なんです(『トランス・ジェンダーの文化―異世界へ越境する知―』勁草書房、一九八九年)。
でも、その後はトランスジェンダーについては事実上、筆を折っちゃったんです。詳しい事情はよくわかりませんが、「おかしな研究をしている」というような社会的な圧力があったのではないでしょうか。いずれにせよ、日本にトランスジェンダリズムの原点をつくった重要な研究者であることは間違いありません」
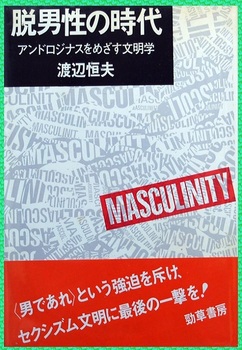
↑ 渡辺恒夫『脱男性の時代ーアンドロジナスを目指す文明学ー』(勁草書房 1986年)
九〇年代に入り、一九七九年創業の女装メイクルーム&サロン「エリザベス会館」に所属、自己流の女装から、本格的な技術を学んで女装をするようになった。のちに新宿歌舞伎町の女装スナック「ジュネ」でホステスとして働きはじめる。現在につながる〝研究〟を本格的に始められたきっかけは、何だったんだろう。
「九六、七年くらいに、〝性同一性障害〟ということばが一気に広まりました。「性同一性障害のあとに、トランスジェンダーということばが入ってきた」と言う人もいるけど、それは事実誤認です。トランスジェンダーが先にあって、その概念こそが性別を越えて生きようというわたしたちの自己肯定の出発点になっていたんです。
〝性同一性障害〟という概念の登場によって、新宿の女装世界はものすごく影響を受けました。分かりやすく言うと、いままでお店のドアを叩いていた女の子になりたい願望を持つ子たちが、みんな病院に行くようになってしまったんです。性別を越えて生きたいと思うのは障害であり、治療すべき病気だという考えが広まるにつれて、ずいぶんお客さんが減りました。
ある常連さんからは、「おまえたちが病気ってことは、俺は病気の人間と、病気をネタに酒を飲んでいるのか? そんなことする俺って人でなしじゃないか」と言われて。「そうじゃないのよ。楽しく飲めばいいじゃない」となだめても、一度落ちた気分は直りません。
そんななか、ママや古いお客さんからお店の昔話を聞くのが好きだったわたしに、先輩ホステスがこんなふうに言いました。
「わたしたちが作ってきた女装世界は、近い将来になくなっちゃうかもしれない。こんな世界があったことを、記録して残すことが、歴史学を勉強した順ちゃんの役目よ」
それ以来、研究者というよりは当事者として、調べて記録しなくてはならないという強い意識を持つようになりました。「ジュネ」という店の歴史、それを中核とした新宿の女装世界の成り立ちを遡って調べていきました。そんな調査をより社会史的な研究にしていこうと思い始めた時期に、中央大学の矢島正見先生(社会学)から声をかけられて、一九九九年に「戦後日本〈トランスジェンダー〉社会史研究会」を立ち上げ、歴史学と社会学の二つの手法で研究をしていくことになりました」
二〇〇〇年代初頭から、「性別を越えて生きることは病ではない」と一貫して性別越境の病理化を批判しつづけ、性同一性障害という病理概念に絡めとられることを拒否してきた三橋さん。ようやく時代の流れが変わりつつあるようだ。
「来年か、再来年かに実施されるWHOの国際疾病分類(ICD)の改訂にともなって、性別越境が精神疾患でなくなる見通しなんです。性同一性障害という病名も国際的には消えることになります。同性愛の脱病理化に遅れること二十七、八年、自分が唱えてきたことが実現することへ期待と喜びはもちろんあります。
「研究ができる女装者がいたんだ!」と驚かれたり、「病気と認められて良かったですね」と善意の人に言われた時代もありました。当時とくらべれば、ずいぶんトランスジェンダーが生きやすい世の中になったと思います。でも、まだまだ調べて記録しなければならないことはたくさんあります」
着物の襟を正しながら、まっすぐ前を見据える三橋さん。
「トランスジェンダー研究をきちんと引き継いでくれるひとが現われるまで、わたしもがんばりますよ」
【論文】「日本におけるレズビアンの隠蔽とその影響」 [論文・講演アーカイブ]
2016年3月末に刊行された「早稲田大学ジェンダー研究所」の創立15周年記念論集
小林 富久子・村田 晶子・弓削 尚子編
『ジェンダー研究/教育の深化のために― 早稲田からの発信』

彩流社、2016年3月、474頁、定価4300円+税
ISBN-13: 978-4779121968
これからの「ジェンダー研究/教育」に向けて、文学、表象・メディア、歴史、法・社会などの専門領域の「ジェンダー研究の展開」と、教育実践をもとにした「ジェンダー教育のあり方」の二本立てで、計24編の論考を収録している。
私は、論文「日本におけるレズビアンの隠蔽とその影響」を執筆。
日本における女性同士の性愛の歴史をトピック的にたどり、その隠蔽の在り様を明らかにした上で、その現代における影響、具体的には「なぜ日本では女性から男性への性別移行者(Female to Male=FtM)が(国際比較で)突出的に多いのか?」を考えてみた。
論集では割愛した、図版を加えた。
-------------------------------------------------------------------------
日本におけるレズビアンの隠蔽とその影響
三橋順子(性社会・文化史研究者)
はじめに
「日本にもレズビアンがいると知って驚きました。テレビなどに出てこないのでいないものだと思っていました」
「今までレズビアンは性同一性障害の一種だと思っていましたが、今日の講義でレズビアンと性同一性障害は違うものだとわかりました」
いずれも、私の「ジェンダー論」の受講生のコメント票の記述である。読んで私は愕然とした。レズビアンへの認識不足は実感していたが、まさかこれほどとは……。しかし、学生の無知と笑って済ますことはできない。前者は教員養成で長い実績がある公立大学、後者は日本有数の私立大学の学生だ。つまり、レズビアンへの同様の認識不足は若者たち、いや世間に広く存在することを示しているからだ。
現代日本におけるレズビアン(Lesbian 女性同性愛)への認識と理解は、トランスジェンダー(Transgender性別越境者)の病理化概念である性同一性障害(Gender Identity Disorder=GID)や、同じ同性愛であるゲイ(Gay 男性同性愛)と比べて格段に低い。
その原因としては、学生が「テレビなどに出てこないので」と言っているように、一般の人が目にするところにレズビアンが存在しない(ように見える)ことが大きい。もちろん、現実には日本社会にはたくさんのレズビアンが生活している。その数は男性同性愛者とそれほど大きくは変わらないだろうし、性同一性障害の人よりずっと(おそらく2桁)多いはずだ。概数的に言えば、100人に2~3人いてもおかしくない。なのに、なぜ、目に見えないのか? それは隠されているからにほかならない。
日本におけるレズビアン差別については、杉浦郁子「レズビアンの欲望/主体/排除を不可視にする社会について―現代日本におけるレズビアン差別の特徴と現状―」(杉浦2010b)という優れた研究がある。男性ホモソーシャル体制を堅持するために、ホモフォビアを伴う異性愛主義を浸透させた、「女同士の絆」が未分化で曖昧なものとして構築されている現代日本社会の中で「男を望まない欲望」「男に望まれたくない欲望」を表出することは困難であり、それがレズビアンの不可視化、差別を招いているという杉浦の社会構造的な分析にほとんど異論はない。
しかし、杉浦はレズビアンが隠蔽されてきた個々の事例についてはあまり触れていない。そこで本稿では、不十分ながらレズビアンが隠蔽されてきた歴史をトピック的にたどり、それが現代日本社会にどんな影響を与えているかを考えてみたい。
1 レズビアンの前史 ―先行概念がない―
実態として、平安時代の後宮、江戸時代の将軍家大奥や大名家の奥向き、遊廓の妓楼など、女性が多く集まり暮らす場で、女性同士の性愛はあったと思われる。しかし、文献的に明確な例としては、『我身にたどる姫君』(鎌倉時代中期、1259~1278年頃)第6巻の主人公「前斎宮」(嵯峨院上皇の娘)が周囲の女性たちと次々に関係をもつ話があるくらいで数少ない。あるいは、江戸時代の性具の中に「互形(たがいがた)」と呼ばれた双頭の張形が残っていること(田中2004)や、同時期の春画の中に僅かながら女性同士の性愛を描いたものがあることなどからうかがえるに過ぎない。
このように女性同士の性愛を示す資料は、男と女の関係はもちろん、男と男(正確には男と若衆)の関係に比べても圧倒的に少ない。そもそも、女性同士の性愛を示す概念、言葉がなかった。「互形」を用いた女性同士の擬似性交を「互先(たがいせん)」と言い(田中2004)、女性同士の性愛を示す「貝合せ」とか「合淫(ともぐい)」という言葉があった(白倉2002)。あるいは、「といちはいち(ト一ハ一?)」という語源不詳(「上」「下」の意か?)の言い方もあった。これらは、いずれも卑語、隠語の類であり、世間に広く通用した言葉ではなかった。
これは江戸時代の「色」の概念が、男性から遊女に向かうものを「女色」、男性から若衆に向かうものを「男色」と言い、「色」の発信は常に男性が主体であるとされていたことによる(三橋2013)。つまり、女性が発信主体となることは想定されていないので、女と女の関係は概念として存在しないのだ。さらに、当時の著述・出版事業が圧倒的に男性支配下にあり、女性が自らの性愛を記録し刊行することが困難な事情もあった。
ところで、同性の間の性愛、あるいは性的指向(sexual orientation)が同性に向いていることを意味するhomosexualityという概念は、明治時代の末、1910年頃にドイツの精神医学者リヒャルト・フォン・クラフト=エビングの学説が日本に輸入され、「同性的情慾」「顚倒的同性間性慾」などの訳語で、精神疾患である「変態性慾」のひとつとして概念化された(古川1994)。日本において最初に「女性間の顚倒性慾」が「発見」されたのもこの時期だった(肥留間2003)。その後、訳語は「同性愛」に定着するが、同性愛という言葉が新聞・雑誌などで使用され、倒錯的な性愛として一般に広く知られるようになるのは、1920年代、大正末期から昭和初期のことである。
同性愛概念が導入される以前(明治時代以前)の日本では、同性愛という概念は存在しない。男性同士の性愛は「男色」として概念化されていたが、それは成人した男性と元服前の少年、あるいは年長の少年と年少の少年との関係に限定されていて、成人男性同士の性愛を含む「男性同性愛」とはかなり異なる(三橋2015a、2015b)。とはいえ、それでも類似の先行概念があるだけ男性同性愛という概念を受容しやすかっただろう。
これに対して、女性同士の性愛は、同性愛概念が導入される以前には概念化されていなかった。つまり、女性同性愛は類似の先行概念がなく、(前近代)「男色」→(近代)「男性同性愛」のような概念の継承、読み替えが成り立たず、大正~昭和初期にいきなり世の中に出てくることになる。
このことが、日本近代における女性同性愛の受容に大きく影響しているように思う。大衆は、よくわからないものには警戒的になる。女性同性愛が男性同性愛よりもさらに社会的に警戒されたのは、基本的には男尊女卑の社会構造が大きいが、先行概念の欠落にも理由があったのではないだろうか。
2 「富美子・エリ子事件」―「同性心中」と女性同性愛の危険視―
日本で女性同性愛が注目されたきっかけは、1911年(明治44)7月に新潟で起こった「令嬢風の二美人」の入水心中事件だった。東京の第二高等女学校(都立竹早高校の前身)の同級生だった二人は在学中から「非常の仲よし」だったが、卒業後は交際を控えるよう父親から注意されたのを悲観しての自殺だった。この事件に注目して日本最初の女性同性愛に関する論文、桑谷定逸「戦慄す可き女性間の顚倒性慾」が書かれる(桑谷1911)。日本における女性同性愛は最初から「戦慄すべき」ものだったのだ。
これ以降、昭和戦前期の新聞で、女性同士の「同性心中」がしばしば新聞報道されるようになり、女性同性愛のイメージを「危険」なものにしていった。「同性心中」なのだから男性同士の心中(自殺)もあるはずだが、実際に報道されたもののほとんどは女性同士の心中だった。また、女性同士の自殺だからといって、その二人が同性愛関係だったとは限らないのだが、イメージとして同性心中と女性同性愛が結び付けられ、ことさらに危険視されたことは間違いない。「同性心中」への注目と問題視は戦後期まで継続し、「危険な女性同性愛」のイメージを再生産していくことになる(小峰・南1985)。
ところで、日本で女学校が開設され、女学生が増えるとともに、女学生同士の親密な関係が社会的に浮上してくる。こうした一種の疑似恋愛関係は「エス」(Sisterの頭文字)と呼ばれ、1920年代には女学校文化として定着するようになった(赤枝2011)。それを危険視する見解がある一方で、親にしてみれば女学生の娘が男性と恋愛関係におちいるより、女学生同士の疑似恋愛に没頭している方が安全であり、「エス」の関係は卒業とともに終え、男性と結婚し良妻賢母になってくれればそれでいいという容認的な考えもあったようだ。
もちろん、親の思惑通りに行かない場合もあり、先の新潟の入水心中事件はその典型である。「エス」と女性同性愛の間に明確な線引きができるわけではないにもかかわらず、女学生同士の親密な関係である「エス」は許容され、女性同性愛は危険視されるというダブルスタンダードが生じていく。
一方、1933年(昭和8)に清朝皇室の粛親王善耆の第十四王女である川島芳子(愛新覺羅顯玗)をモデルにした小説、村松梢風『男装の麗人』が出版されたことをきっかけに「男装の麗人」ブームが起こる。その中心は、川島芳子と松竹歌劇団の男役スター「ターキー」こと水の江瀧子だった。当時の新聞は、川島とターキーの動静をしばしば伝えている。


(左)水の江瀧子(右)川島芳子
そんな時代を背景に、1935年(昭和10)1月末、「富美子・エリ子事件」が起こる。増田富美子は大阪の銀行頭取の令嬢ながら増田夷希(やすまれ)と名乗る「男装の麗人」で当時28歳、その恋人西條エリ子は「松竹少女歌劇」の女役トップスターだった人気映画女優で当時23歳。その二人の「女性同士の愛の逃避行」が新聞で大きく報道された。二人は「愛の逃避行」の末に1月28日夜、東京麹町区平河町の「万平ホテル」に同宿する。その夜、富美子はエリ子への遺書を残して睡眠薬自殺をはかり昏睡状態になってしまう。
.jpg)
↑ 増田夷希(やすまれ)と名乗った増田登美子(『読売新聞』1935年1月30日)
まるで犯罪者のように富美子たちの動向を追跡していた『読売新聞』は「『男装の麗人』富美子さん 萬平ホテルで服毒す 西條エリ子と共に投宿 遂に『死』への逃避行」という大見出しのもとに、男姿の富美子の写真と「本当いへば一緒に死んでほしかった」と記された遺書を掲載するなど、連日のようにセンセーショナルに伝えた。

↑ 『読売新聞』1935年1月29日
結局、富美子は一命をとりとめ、エリ子との関係を解消して大阪に帰り一件落着となった。この事件は「同性心中」としては不完全なものだったが、登場人物が著名人だっただけに大きな評判になり、「危険な女性同性愛」を世間にいっそう印象づける「事件」になってしまった。
「富美子・エリ子事件」が印象付けた女性同性愛の危険性とはなんだろう。それは第一に、本来、男性の性愛の対象になるべき女性が(富美子のように)「男を望まない欲望」「男に望まれたくない欲望」を抱くことで、男性の性愛対象から離脱してしまうことである。第二に「男を望まない欲望」が「女を望む欲望」に転化することで、男性の性愛の対象になるべき女性が(エリ子のように)女性同性愛者に奪われてしまうことである。そして、第三はそれらによって男性を主体として築かれた異性愛秩序が崩されかねない危険性を男性たちが感じるからである。
男性たちの女性同性愛への危険視には、本来自分たちのものであるべき女性が奪われることへの怒りが裏打ちされていると思う。
3 「佐良直美事件」―芸能界におけるレズビアン追放―
敗戦(1945年8月)直後の日本は、旧来の社会体制と倫理観の崩壊で、百花繚乱的に多様なセクシュアリティが展開していく。中でも男性同性愛(ゲイ)の顕在化は目覚しく、1950年代後半にはシスターボーイやゲイバーが話題になり、「第1次ゲイブーム」というべき現象が起こる。しかし、そうした社会状況の中でも、レズビアンの顕在化は進まなかった。
この時期の性風俗雑誌には、レズビアンについての記事が散見されるが、男性の興味本位の視点からのものがほとんどで、当事者性のある「語り」はきわめて少ない。そして、「男を望まない」「男に望まれたくない」はずのレズビアンに対して、男性の性的欲望の視線が向けられるようになる。こうして1950年代から60年代にかけて「危険な女性同性愛」は「ポルノグラフィーとしてのレズビアン」へと変化していく。
なぜ、男性の性的欲望を拒絶しているレズビアンに男性の性的視線が向けられるのだろうか。それはレズビアンが「性的快楽を貪欲に追求する」「性的に奔放な」女性としてイメージされたからである(杉浦2010b)。先に述べたように江戸時代において性的欲望の発信は男性に限定されてきた。近代以降の性慾学でも、性的欲望を抱き、性的快楽を追求する女性は「色情狂」であり、変態性慾のカテゴリーだった。同性愛の女性は、単に性愛対象が同性に向いているだけでなく、性的欲望を発信することにおいても変態とされたのだった。
こうした誤った認識がベースになり、性的に奔放な女性なら、男性の性的欲望にも応じるだろう、「レズビアンなんて俺(のペニス)が直してやる」というようなまったくお門違いの妄想がはびこることになる。そこまで愚かでなくても「レズビアン・ポルノビデオは、女性が2人出てくるので2倍おいしい」と言う男性は数多く実在した。
そうした性的奔放というイメージを付与されたレズビアンをめぐって、芸能界の大スキャンダルが勃発する。1980年(昭和55)5月19日、テレビ朝日のワイドショー番組『アフタヌーンショー』が「キャッシー涙の告白!! 佐良直美との愛の破局」と題して、女性歌手佐良直美と女性タレント、キャッシーのレズビアン関係を暴露した「佐良直美事件」である。
佐良直美は、1967年、デビュー曲「世界は二人のために」が120万枚の大ヒットとなり第9回日本レコード大賞の新人賞を受賞し、NHK紅白歌合戦に初出場を果たし、1969年には「いいじゃないの幸せならば」で第11回日本レコード大賞を受賞した。ショートヘアでスカートよりもパンタロンなどのスラックス姿を好み、若い女性にしては低音のハスキーボイスというマニッシュなイメージで、テレビのホームドラマ「ありがとう」(TBS、1970~74年)に出演するなど、歌手だけでなく女優や司会者など多方面で活躍する、押しも押されもせぬ一流歌手で、事件当時35歳だった。
それに対して、キャッシーは大阪弁でまくしたてるハーフのタレントとして注目され、テレビドラマにチョイ役で出演していた。佐良より6歳年下で事件当時は29歳だった。
佐良は、1972年、1974年~1977年と紅白歌合戦の紅組司会を5回も担当しているように、NHK好みの「お茶の間」好感度が高い、スキャンダルとは縁遠い人物と思われていた。それだけにキャッシーの告発は衝撃的だった。
キャッシーの告白は、2人の馴れ初めから佐良家の「嫁」としての同居生活、「姑」(佐良の母)との関係の拗れが原因となった破局まで、3年間の愛情生活を詳細に語った上に、10数通の佐良からの手紙を証拠として添えたものだった(『週刊現代』1980年6月5日号)。
これに対して佐良は同性愛関係を全面否定し、手紙も偽造と決めつけた。両者それぞれ弁護士を立てての泥沼的な訴訟合戦になるかと思われたが、一転して5月末に和解となった。佐良本人は現在に至るまでレズビアン関係を完全に否定しているが、真相は「藪の中」である。
性的スキャンダル、しかもレズビアン・スキャンダルの影響は、両者の芸能界のポジションに格段の差があった分、佐良の方がずっと大きかった。それまでの優等生的なタレントイメージは大きく損なわれてしまった。その年の暮、佐良はデビュー以来13回連続出場を続けていたNHK紅白歌合戦に落選してしまう。確かにヒット曲には恵まれていなかったが、それまでの功績を考えれば唐突な感は否めず、やはりスキャンダルが理由と受け取る人が多かった。それ以降、佐良は徐々に芸能活動から遠ざかりテレビから消えて行った。
後年になって、佐良は芸能界から引退した理由を(レズビアン・スキャンダルではなく)恩師水島早苗の死(1978年)や声帯ポリープの手術(1987年)であると語っている(『東京スポーツ』2010年11月7日号「佐良直美が30年前のレズ騒動を語る」http://www.tokyo-sports.co.jp/entame/2238/)。おそらく事実はそうなのだろう。
しかし、同時代の多くの人は、私も含めそうは受け取らなかった。佐良直美ほどの一流歌手であってもレズビアンであることが世間に知られたら、芸能界から追放されてしまうのだ、と思った。
レズビアンの社会的隠蔽という現象を考える時、事実関係よりも、そうしたイメージが視聴者やテレビ業界に広まってしまったことの方が重要である。「佐良直美事件」によって、日本の芸能界においてレズビアンは絶対的なタブー(禁忌)と認識され、その後のテレビ業界のレズビアン忌避・隠蔽姿勢が決定づけられてしまった。
なお、1970~80年代は、日本でレズビアン・コミュニティが形成されていく時代である。その主体的な歴史については、杉浦郁子の一連の研究を参照されたい(杉浦2006、2008、2010a)。
4 『ラスト・フレンズ』問題 ―なぜレズビアンではいけないのか―
『ラスト・フレンズ』は、2008年(平成20)4月10日から6月19日まで全11回、毎週木曜22時台にフジテレビ系列で放送されたテレビドラマである。
あらすじは、児童虐待(ネグレクト、性的虐待)のトラウマに由来する自我の未確立が影響して家や職場でも居場所が得られず、区役所の児童福祉課で働く恋人宗佑(錦戸亮)からドメスティック・ヴァイオレンス(DV)を受けている藍田美知留(長澤まさみ)、モトクロス選手として全日本選手権優勝を目指す一方、自分の性別に悩みを抱える岸本瑠可(上野樹里)、女性たちの良き相談相手でありながら、過去のトラウマからセックス恐怖症に悩む水島タケル(瑛太)、恋多き女性である滝川えり(水川あさみ)の4人が、シェアハウスで共同生活を始めることで人と人との関わりの大切さを知り、前向きに生きようとする、というものだった。
DV、性同一性障害、セックス恐怖症など当時の社会の若者たちの間で社会問題化しつつあったテーマを取り入れ、主要キャストに旬な若手俳優を起用したこともあって若者たちの間で話題を呼び、高視聴率を記録した(最終回22.8%)。私が大学の講義で当時15~19歳だった受講生を対象に調査したところでは、その世代に限定すれば、視聴率は50%に迫っていたと思われる。また「第57回(2008年春クール)ドラマアカデミー賞」(テレビ雑誌『ザテレビジョン』主催)において、作品賞・助演男優賞(錦戸亮)・助演女優賞(上野樹里)など6冠を達成し、テレビ業界では高く評価された。その一方で、DV男性の美化、レズビアン(女性同性愛)とGIDの混乱などをめぐって、放送時から批判も多かった。
世間的にはハードなDVシーンが注目を集めたが、ここで問題にしたいのは、岸本瑠可の描かれ方である。瑠可は中学校時代の同級生であった美知留にずっと思いを寄せている。第1回のラスト、美知留が初めてシェアハウスに泊まった翌朝、ソファーで眠っている美知留の唇に瑠可がそっと唇を寄せるシーンは、瑠可がレズビアンである可能性を想起させるものだった。しかし、ドラマの中では、「レズビアン」という言葉は一度も使われない。さらに瑠可の性的指向は「男性を好きになれない」という形で表現され、より積極的な「女性が好き」という表現は意識して避けられている。このドラマでは女性が好きな女性を描きながら、レズビアン的なものが隠蔽されているのは明らかだろう。なぜ瑠可はレズビアンではいけないのだろうか。そこに「佐良直美事件」以来のテレビ業界のレズビアン忌避が影を落としているように思われる。
レズビアンが隠蔽される一方で、瑠可がインターネットで病院のサイトを密かに見ているシーンが伏線として描かれ、少し時を置いて瑠可が性同一性障害の診断を求めてメンタルクリニックを受診するシーンが出てくる。その場面にかぶせられた瑠可のモノローグは典型的な性同一性障害の語りであり、ここに至って、瑠可がFtM(Female to Male)の性同一性障害である可能性が視聴者に強く示唆される。
しかし、瑠可の場合、ジェンダー・アイデンティティ(性自認・性同一性)と深く結びついている自称(第一人称)は、ほぼ一貫して「私(わたし)」であり、時に「あたし」と聞こえる箇所もある。FtMは、女性性と関連づけられる「私」を自称として使うことを避ける傾向があり、まして女性性が明確な「あたし」と称することはまずない。FtMの自称としては「自分」「僕」「俺」が用いられることが多いが、瑠可はそうではない。
また、映像表現では、瑠可が女性的なジェンダー表現を好まないこと、男性を愛せないことは強調されているが、FtMに特徴的な女性としての身体に対する違和感は、メンタルクリニックのシーンで語りとして表現されるだけで、映像ではあまり表現されていない。
『ラスト・フレンズ』の脚本家、浅野妙子は、脚本をFtMの当事者にみせたところ、「これってレズビアンじゃん(笑)。レズビアンだと何でいけないの?」と即答されたことを語っている(Yuki Keiser2008)。まさにその通りで、FtMの性同一性障害者をよく知る者からしたら、瑠可がFtMであることはかなり疑問で、ボーイッシュなレズビアンにしか見えない。
ボーイッシュなレズビアンを思わせる瑠可に対して、性同一性障害のレッテルを無理やり貼り付けているのではないか、という疑問に答える場面がやってくる。それは瑠可の父親に対するカミングアウト・シーンだ。瑠可は「私は男の人を好きにならない。なれないんだ」と父親に告白する。ここで問題にされているのは性的指向であり、これは典型的なレズビアンのカミングアウトである。FtMのカミングアウトなら「自分(の心)は男なんだ。女じゃないんだ」というように性自認が問題にされるはずだからだ。
ところが、瑠可のレズビアン的なカミングアウトに対する父親の述懐シーンでは、男の子に混じって活発に遊んでいた瑠可の子供時代が語られる。これは、FtMの子供時代の典型的な語りである。
ここに至って、重大なことに気づく。脚本家が性的指向の問題であるレズビアンと性自認の問題である性同一性障害(FtM)とを混同している、あるいは意図的に混乱させていることに。
実際、脚本家の浅野妙子は、「性同一性障害という設定が最初に決まっていた」こと、その上で「FtMとレズビアンの間」の「グレーゾーン」として瑠可を設定したこと、「どっちともはっきりは言えないけれど」「性同一性障害のほうがレズビアンよりそういった面(「悩み」を連想するという点)で共感を得やすい」と思い、「まずは性同一性障害にしておこう」と考えたことを語っている(Yuki Keiser2008)。レズビアンが悩まないとでも思っているのだろうか。性的マイノリティに対する歪んだ思い込みに基づく安易なドラマ設定があったことがわかる。
「FtMとレズビアンの間」の「グレーゾーン」を描こうとした脚本家の意図が視聴者に伝わったとは思えない。むしろ、瑠可のような、女の子が好きな男っぽい女性は、性同一性障害(FtM)という病気で、メンタルクリニックに通院する必要がある、という誤った情報が視聴者に与えられた可能性が高いと思う。
そうであるならば、このドラマはレズビアンを隠蔽しただけでなく、FtMの性同一性障害のイメージをも歪めて流布し、現実世界に誤った印象・知識を与えたミスリードの事例ということになる。
実際、『ラスト・フレンズ』の放送があった2008年以降、全国のジェンダー・クリニックで10代~20代の若い女性の受診者が急増したことが報告されている。それについては第7節で詳しく述べるが、そこに「ラスフレを見て、自分もそうだと確信しました」というようなミスリードが作用している可能性は十分に考えられる。
5 1990年代以降のレズビアンをめぐる動向
1990年代になると欧米のゲイ・レボリューションの波がようやく日本にも到達する。そうした中で1992年に出版された掛札悠子『「レズビアン」である、ということ』(掛札1992)は、長らく沈黙を強いられてきたレズビアンが初めて堂々と自らの生き方を語ったものとして画期的なものだった。
しかし、それによってレズビアンを取り巻く状況が大きく改善されたかといえば、必ずしもそうとは言えない。掛札に続いてカミングアウトした人は少なく(笹野1995、池田1999)、掛札自身が筆を折ってしまったこともあり、レズビアン・ムーブメントは90年代末に始まる「性同一性障害」の大流行の波に埋もれてしまう(杉浦2010b)。
1990年代末から2000年代前半にマス・メディアによって流布された「性同一性障害」についての情報量は、同性愛のそれと比較できないほど多かった。同性愛の中でも、ゲイはすでに独自のコミュニティを確立し、専門の商業雑誌をもっていたが、コミュニティの規模が小さく商業雑誌がなかなか続かないレズビアンの情報量はさらに少なかった。インターネット時代になって若干改善されたものの、まだ十分と言うには程遠い。
一方、レズビアンの学術的研究としては、性意識調査グループ編の『310人の性意識―異性愛者ではない女たちのアンケート調査』(性意識調査1998)や、中央大学の矢島正見研究室がまとめた『女性同性愛者のライフヒストリー』(矢島1999)がひとつの方向性を示している。それは、ともかくレズビアンの話を聞き記録することで、その存在を顕在化することである。隠蔽されてきた日本のレズビアンを学問的な舞台に載せたという意味で、両書の意味は大きかったと思う。
しかし、同性愛の学術研究全体でみると、杉浦郁子や堀江有里の仕事はあるものの、まだまだ男性主導でアンバランスであることは否めない。たとえば、2010年に岩波書店から出版された風間孝・河口和也『同性愛と異性愛』は、同性愛の当事者が同性愛を書名に掲げて専論した初めての新書として注目されたが、共著者が当事者でないことを理由にレズビアンについてはほとんど触れていない。当事者主義にこだわるのなら、レズビアンの執筆者を招いて章を設けるべきだし、それができないのならば、書名は『男性同性愛と異性愛』にすべきだろう。書名に「同性愛」と銘打ちながらレズビアンについてほとんど記述をしないのは、単にアンバランスなだけでなく、レズビアンの疎外であり、結果的にレズビアンの隠蔽に加担していると言えなくもない。『同性愛と異性愛』という書名にひかれて手に取ったレズビアンが目次を通覧した時の疎外感と落胆を著者や編集者は想像しただろうか。
同性愛者の歴史的な歩みや現在直面している問題が、いつの間にか男性同性愛者(ゲイ)のそれにすり替えられてしまう現象は、この本だけではないように思う。
2005年、大阪府議会議員だった尾辻かな子がレズビアンであることをカミングアウトした(尾辻)。尾辻は2007年の参議院選挙(比例区)に民主党公認として立候補したものの当選ラインに遠く及ばず落選したが、2013年5月、繰り上げ当選によって参議院議員(民主党)となった。任期が僅か一カ月余だったこともあり、残念ながら十分な実績は残せなかったが、尾辻が日本初の性的マイノリティであることを公言した国会議員であることはまぎれもない事実である。
しかし、東京都豊島区議会議員で男性同性愛者(ゲイ)であることを公表している石川大我が2014年の衆議院総選挙で社会民主党の東京比例区名簿1位に登載されると、複数のネット・メディアが「日本初の同性愛者の国会議員を目指す」と報じ、尾辻の存在は「なかったこと」にされた。無知と言えばそれまでだが、石川事務所も「日本初のオープンリーゲイの国会議員」を目指すことをプロフィールに記していて、「日本初のオープンリー同性愛者国会議員」である尾辻への配慮に欠けていたことは否めない。
2000年代後半になると、レズビアン関係の出版も徐々に増えていく(堀江2006、飯野2008、牧村2013)。2013年には世界的な同性婚承認の流れの中で、レズビアン・カップルの東京ディズニーランドでの挙式が話題になった(東小雪+増原裕子2014)。
しかし、レズビアンの存在が日本社会の中で十分に認知され、レズビアンに関する情報が十分に流通し、レズビアンを取り巻く様々な困難な状況について地に足が着いた議論がなされる状況には、残念ながら至っていない。
6 レズビアン・ロールモデルの不在
レズビアンをめぐる現状を考えたとき、情報量の不足もだが、最大の問題はレズビアンのロールモデルの不在だと思う。その原因は、テレビをはじめとするマス・メディアがレズビアンの存在を徹底的に隠蔽してきたことにある。
2010年代になってさえ、日本のマス・メディアは「レズビアン疑惑」という言い方をしてはばからない。「疑惑」という言葉は「覚醒剤使用疑惑」など社会的に問題のある行為を疑う言葉だ。いったいなぜレズビアンであることが問題行為なのだろう。そうした「疑惑」をかけられた女優、女性歌手あるいは女性タレントは、必死に「疑惑」を否定しようとする。本人が沈黙していても事務所が否定に動く。なぜなら、現在の日本のテレビ業界では「レズビアン」であることは仕事を失うことにつながりかねず、デメリットが大きいからだ。その点で、レズビアンをカミングアウトした女優や女性アーティストが活躍する欧米と著しい違いがある。佐良直美事件の呪縛は30年以上たってもまだ解けていないのだ。
なぜ、これほどまでにテレビ・メディアはレズビアンの存在を忌避するのだろうか。その理由を端的に指摘すれば、すべての女性は男性の性的視線を受け止める存在でなければならないという、男性中心のヘテロセクシュアル原理がいまだに貫徹しているのがテレビ業界だということだ。そうした姿勢の背景にはスポンサーとしてテレビ番組を支えている日本の企業社会の男性中心のヘテロセクシャリズムがある。
このように、マス・メディアの隠蔽姿勢がレズビアンのvisibility(目に見えること)を著しく低下させ、魅力的なレズビアン・ロールモデルの出現を阻んでいる。そして、レズビアン・ロールモデルの不在が、レズビアンの自己肯定をいっそう困難にしている。
ところで、レストランでメニューにない料理を注文できる人はごく少ない。ほとんどの人はメニューの中から料理を選ぶ。それと同じで、人は目の前に並んでいる概念にしかアイデンティファイ(カテゴリーへの同一化)できない。私はこれを「メニュー理論」と言っている。
たとえば、20代の私の前に置かれていたメニューには、トランスジェンダーも性同一性障害も無く、ゲイボーイという概念しかなかった。「これは違う」と思ったから、それをつかまなかった。アマチュアの女装者という概念があることを知ったのは30代の初めで、やっとその言葉をつかむことができたが、トランスジェンダーという言葉を知って最終的にアイデンティファイできたのは40歳を過ぎてからだった。
レズビアンを抑圧し、存在を隠蔽してきた結果、レズビアンのロールモデルが提示されず、逆に性同一性障害(FtM)の情報が多く流布されている現状は、メニューに「今月のおすすめ」として「性同一性障害(FtM)」と大書されているのに対し、「レズビアン」は見えるか見えないかの小さい文字でしか書かれていない状態にたとえられる。自分の性的指向(Sexual Orientation)が典型的でないことに気づいた女性がメニューを見たとき、本来ならつかむべきレズビアンではなく、性同一性障害(FtM)をつかんでしまうのも無理からぬ状況がそこにある。
7 なぜ日本はFtM(Female to Male)が多いのか?
性同一性障害の性別比、つまりMtFとFtMの比率は、世界標準的には、2対1くらいでMtFが多いとされている。日本では1990年代末から2000年代中頃までは、MtFがやや多い状態からMtFとFtMの比率が拮抗する状況へと緩やかに推移していた。ところが、2008年以降、全国の複数の病院、クリニックで、若年(10代後半~20代前半)FtMの受診者が急増し、世界標準とは逆に、ほぼ1対2の比率でFtMの受診者が多くなった(2009年2月の第11回GID学会での報告。「関西医大病院ジェンダー・クリニック」MtF134、FtM270=33対67、「札幌医大GIDクリニック」MtF94、FtM220=30対70、「はりまメンタルクリニック」MtF229、FtM409=36対64)。
かつて私は、この現象をテレビドラマ『ラスト・フレンズ』の影響で、本来は、男性っぽいレズビアンの範疇でおさまるはずの(瑠可のような)女性が、性同一性障害(FtM)と自己認識して、ジェンダー・クリニックを受診している結果ではないかと考えていた。しかし、その後もFtMの増加傾向は止まらず、現在では1対3からさらに1対4に近づく状態になっている。
FtMの増加傾向は、受診者レベルではなく、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(GID特例法)」による戸籍の性別変更においても著しい。全国の家庭裁判所に提出される戸籍変更の診断書の約15%を書いている(2012~2014年平均)針間克己医師(はりまメンタルクリニック)によれば、2012年から2015年の戸籍変更診断書の累計はMtF119、FtM464≒1対4だった(「Anno job Log」2015年12月27日 http://d.hatena.ne.jp/annojo/20151227)。日本は世界で最も、そして格段にFtMの比率が高い国になっている。
こうなると、テレビドラマの影響だけとは言えず、それをきっかけとした、もっと大きな構造的な原因があると考えなければならない。生得的な体質、遺伝子的に日本人の女性がFtMになりやすいということはなさそうなので、その原因は社会的なものと考えられる。
そこで考えなければならないのは、世界標準より多い分のFtMがどこから来ているのか?ということだ。その際、ヘテロセクシュアルの女性がFtM化するということは考えにくい。女性に課せられた社会的制約から脱するために男装する女性は過去にはいたが、現代の日本は一般論的に言って女性が男体化しなければ社会活動が難しい状況にはない。また性的指向が男性に向かっているヘテロセクシュアルの女性がFtM化した場合、セクシュアリティ的なメリットはほとんどない。ゲイ男性はヘテロ男性よりずっと少ないからだ。
それに対して、レズビアンがFtM化しているという想定の方がずっと考えやすい。レズビアンがFtM化すれば、性愛対象のヘテロ女性はレズビアン女性よりずっと多いから、ターゲットはぐっと広がる。なにより戸籍の性別を男性に変更すれば、法的に女性と結婚できる。同性婚が法的に許可される見通しが立たない日本では、生得的な女性が女性と法的に婚姻するには、一方の女性がFtMの性同一性障害者として「GID特例法」によって、戸籍の性別を変更するのが唯一の方法だからだ。
このように考えると、日本におけるFtMの増加分はレズビアンからの流入を想定するのが、いちばん蓋然性が高いと思う。その原因として、前節で述べたような、自分の性的指向が典型的でないことに気づいた女性が本来ならアイデンティファイすべきレズビアンではなく、性同一性障害(FtM)として自己認識してしまう状況が存在し、さらに「GID特例法」による一種の「誘導」が作用していると考えられる。
次に考慮すべきは、レズビアンとFtMの比率である。本来、レズビアンは100人に数人いると考えるのが一般的だ。それに対して日本のFtMは10000人に数人と考えられる。つまり両者の人数は本来100倍ほども違う。ということは、レズビアンの1%がFtMに流入すればFtMは本来の数の倍になるし、2%流入すれば3倍に、9%が流入すれば10倍になる。このようにレズビアンからの流入モデルを考えることで、日本で世界標準よりFtMが著しく多い理由を容易に説明することができる。
ところで、レズビアンからFtMへという流入現象がかなりあると想定した場合、ゲイからMtFへの流入はそれに比してなぜ少ないのかという疑問が生じる。この点については次のように説明できると思う。
日本において、ゲイ・コミュニティとMtFのコミュニティは、性同一性障害概念が流布する1990年代後半以前に、すでにかなり明確に分離していた。その分離の時期は1970~1980年代と考えられる(三橋2008)。だから、性同一性障害概念はMtFだけに影響を与え、ゲイにはほとんど影響が及ばなかった(まったく流入がないわけではないが)。それに対して、レズビアン・コミュニティとFtMのコミュニティは分離が進まず混在した状態だったところに、性同一性障害概念が流布した。その結果、本来、性同一性障害概念の影響を受ける必要のないレズビアンにまでその影響が及んでしまい、混乱と流入が起こってしまったと考えられる。そして、レズビアン・コミュニティとFtMのコミュニティの未分離の原因にはレズビアンの隠蔽による情報不足がある。
非典型な性をもつ人たちがどのようにカテゴライズされ、自らをアイデンティファイしていくかは、今まで言われてきたほど固定的ではなく、与えられる情報によってかなり流動的であると私は考える。それゆえに、適切なアイデンティファイをするためには隠蔽や歪曲がない正しい情報提供、つまり、自分にふさわしい料理を選べる「メニュー」が必要なのである。
おわりに
ある年度、「ジェンダー論」の講義の単位レポートに、レズビアンであることの辛い思いを切々と記してきた学生がいた。好きな相手からもレズビアンの存在そのものを否定され、周囲の偏見の中で自己否定感にさいなまれる。なぜ、女性として女性が好きなだけでこんなに苦しまなければならないのか、単位レポートだから冷静に読んで評価しなければいけないのだが、「今まで書いてきたことはすべて事実です。でも、誰にも話したことはありません。やっとレポートという形ですが書くことができて、私は幸せです、ありがとうございました」という結びの文章を読んで、涙が流れるのを抑えることができなかった。
一方では、女性を愛するためには自分が男にならなければならないと思い込み、短命化の可能性が高い男性ホルモンを過剰に摂取し、身体にメスを入れて乳房、子宮・卵巣を摘出し、高額な費用をかけて(トラブルが多く機能的にも不十分な)擬似男性器を形成する人たちがいる。無惨な傷跡が残る症例写真を見るたびに、レズビアンの範疇に収まるのなら、その方がずっと身体リスクは少ないのに、なぜこんなことまでしなければならないのかと考えてしまう。
女性として女性を愛する女性たちが、適切な自己認識を形成するためには、レズビアンが隠蔽されることなく、レズビアンに関する情報が十分に流通し、女性として女性を愛する多様なロールモデルが社会の中で存在することが必要だと思う。さらに言えば、女性を愛する女性がレズビアンでなくFtMを選択する背景には、日本社会における女性の根本的な生きにくさが存在する。性的マイノリティだけの問題では済まないことを、性的マジョリティの人たちにも知って欲しいと思う。
文献
赤枝香奈子2011『近代日本における女同士の親密な関係』(角川学芸出版)
飯野由里子2008『レズビアンである〈わたしたち〉のストーリー』(生活書院)
池田久美子1999『先生のレズビアン宣言―つながるためのカムアウト』(かもがわ出版)
尾辻かな子2005『カミングアウト〜自分らしさを見つける旅』(講談社)
掛札悠子1992『「レズビアン」である、ということ』(河出書房新社)
風間孝・河口和也2010『同性愛と異性愛』(岩波新書)
桑谷定逸1911「戦慄す可き女性間の顚倒性慾」(『新公論』明治44年9月号)
小峰茂之・南孝夫1985『同性愛と同性心中の研究』(小峰研究所)
笹野みちる1995『Coming OUT!』(幻冬舎)
白倉敬彦2002『江戸の春画―それはポルノだったのか―』(洋泉社新書)
菅 聡子2006「女性同士の絆―近代日本の女性同性愛―」(『国文』106号)
杉浦郁子2006「1970、80年代の一般雑誌における『レズビアン』表象――レズビアンフェミニスト言説の登場まで」(矢島正見編著『戦後日本女装・同性愛研究』(中央大学出版部)
杉浦郁子2008「日本におけるレズビアン・フェミニズムの活動 -1970年代後半の黎明期における」 (『ジェンダー研究』11号)
杉浦郁子2010a「『レズビアン』の概念史――戦後、大衆娯楽雑誌における」(中村桃子編『ジェンダーで学ぶ言語学』世界思想社)
杉浦郁子2010b「レズビアンの欲望/主体/排除を不可視化する社会について―現代日本におけるレズビアン差別の特徴と現状―」(シリーズ「現代の差別と排除」第6巻『セクシュアリティ』明石書店)
性意識調査グループ編1998『310人の性意識―異性愛者ではない女たちのアンケート調査』(七つ森書館)
田中優子2004『張形と江戸をんな』(洋泉社新書)
東 小雪+増原裕子2014『レズビアン的結婚生活』(イースト・プレス)
肥留間由紀子2003「近代日本における女性同性愛の『発見』」(『解放社会学研究』17号)
古川 誠1994「セクシュアリティの変容:近代日本の同性愛をめぐる3つのコード」(『日米女性ジャーナル』17号)
堀江有里2006『「レズビアン」という生き方―キリスト教の異性愛主義を問う』(新教出版社)
堀江有里2015『レズビアン・アイデンティティーズ』(洛北出版)
牧村朝子2013『百合のリアル』(星海社新書)
三橋順子2008『女装と日本人』(講談社現代新書)
三橋順子2013「性と愛のはざま-近代的ジェンダー・セクシュアリティ観を疑う-」(『講座 日本の思想 第5巻 身と心』岩波書店)
三橋順子2015a「『台記』に見る藤原頼長のセクシュアリティの再検討」(倉本一宏編『日記・古記録の世界』思文閣出版)
三橋順子2015b「歴史の中の多様な『性』」(『アステイオン』83号 CCCメディアハウス)
矢島正見編著1999『女性同性愛者のライフヒストリー』(学文社)
Yuki Keiser2008「『ラスト・フレンズ』の脚本家・浅野妙子さんのインタビュー」
http://www.tokyowrestling.com/articles/2008/06/last_friends_3.html
【付記1】入稿後、杉浦郁子「『女性同性愛』言説をめぐる歴史的研究の展開と課題 」(『和光大学現代人間学部紀要』8号 2015年)に接した。本稿と関わるところ大であるが、内容に反映することができなかった。
【付記2】最終的な入稿(2015年2月)の直後、東京都渋谷区の「同性パートナー証明書」発行の条例化(2015年3月31日可決、11月5日実施)問題が浮上し、それをきっかけに「LGBTブーム」が一気に盛り上がり、マス・メディアにおけるレズビアンを含む同性愛関係報道が激増した。その結果、レズビアンのvisibilityは向上したように思われる。しかし、「LGBTブーム」の中で注目されているのは、裕福で、容姿に優れ、社会的地位のある「シャイニー(shiny)」な特定のレズビアンであり、一般のレズビアンが抱えるさまざまな生活の困難を改善していく視点は、まったく不十分である。これはブームの発端が政治的思惑(統一地方選挙)や経済的期待(LGBT消費需要)であり、必ずしも人権的観点でなかったためと思われる。今後、LGBTの人権擁護の論議が深まる中で、本当の意味でのレズビアンの社会的顕在化と生活改善がなされることを期待したい。
小林 富久子・村田 晶子・弓削 尚子編
『ジェンダー研究/教育の深化のために― 早稲田からの発信』

彩流社、2016年3月、474頁、定価4300円+税
ISBN-13: 978-4779121968
これからの「ジェンダー研究/教育」に向けて、文学、表象・メディア、歴史、法・社会などの専門領域の「ジェンダー研究の展開」と、教育実践をもとにした「ジェンダー教育のあり方」の二本立てで、計24編の論考を収録している。
私は、論文「日本におけるレズビアンの隠蔽とその影響」を執筆。
日本における女性同士の性愛の歴史をトピック的にたどり、その隠蔽の在り様を明らかにした上で、その現代における影響、具体的には「なぜ日本では女性から男性への性別移行者(Female to Male=FtM)が(国際比較で)突出的に多いのか?」を考えてみた。
論集では割愛した、図版を加えた。
-------------------------------------------------------------------------
日本におけるレズビアンの隠蔽とその影響
三橋順子(性社会・文化史研究者)
はじめに
「日本にもレズビアンがいると知って驚きました。テレビなどに出てこないのでいないものだと思っていました」
「今までレズビアンは性同一性障害の一種だと思っていましたが、今日の講義でレズビアンと性同一性障害は違うものだとわかりました」
いずれも、私の「ジェンダー論」の受講生のコメント票の記述である。読んで私は愕然とした。レズビアンへの認識不足は実感していたが、まさかこれほどとは……。しかし、学生の無知と笑って済ますことはできない。前者は教員養成で長い実績がある公立大学、後者は日本有数の私立大学の学生だ。つまり、レズビアンへの同様の認識不足は若者たち、いや世間に広く存在することを示しているからだ。
現代日本におけるレズビアン(Lesbian 女性同性愛)への認識と理解は、トランスジェンダー(Transgender性別越境者)の病理化概念である性同一性障害(Gender Identity Disorder=GID)や、同じ同性愛であるゲイ(Gay 男性同性愛)と比べて格段に低い。
その原因としては、学生が「テレビなどに出てこないので」と言っているように、一般の人が目にするところにレズビアンが存在しない(ように見える)ことが大きい。もちろん、現実には日本社会にはたくさんのレズビアンが生活している。その数は男性同性愛者とそれほど大きくは変わらないだろうし、性同一性障害の人よりずっと(おそらく2桁)多いはずだ。概数的に言えば、100人に2~3人いてもおかしくない。なのに、なぜ、目に見えないのか? それは隠されているからにほかならない。
日本におけるレズビアン差別については、杉浦郁子「レズビアンの欲望/主体/排除を不可視にする社会について―現代日本におけるレズビアン差別の特徴と現状―」(杉浦2010b)という優れた研究がある。男性ホモソーシャル体制を堅持するために、ホモフォビアを伴う異性愛主義を浸透させた、「女同士の絆」が未分化で曖昧なものとして構築されている現代日本社会の中で「男を望まない欲望」「男に望まれたくない欲望」を表出することは困難であり、それがレズビアンの不可視化、差別を招いているという杉浦の社会構造的な分析にほとんど異論はない。
しかし、杉浦はレズビアンが隠蔽されてきた個々の事例についてはあまり触れていない。そこで本稿では、不十分ながらレズビアンが隠蔽されてきた歴史をトピック的にたどり、それが現代日本社会にどんな影響を与えているかを考えてみたい。
1 レズビアンの前史 ―先行概念がない―
実態として、平安時代の後宮、江戸時代の将軍家大奥や大名家の奥向き、遊廓の妓楼など、女性が多く集まり暮らす場で、女性同士の性愛はあったと思われる。しかし、文献的に明確な例としては、『我身にたどる姫君』(鎌倉時代中期、1259~1278年頃)第6巻の主人公「前斎宮」(嵯峨院上皇の娘)が周囲の女性たちと次々に関係をもつ話があるくらいで数少ない。あるいは、江戸時代の性具の中に「互形(たがいがた)」と呼ばれた双頭の張形が残っていること(田中2004)や、同時期の春画の中に僅かながら女性同士の性愛を描いたものがあることなどからうかがえるに過ぎない。
このように女性同士の性愛を示す資料は、男と女の関係はもちろん、男と男(正確には男と若衆)の関係に比べても圧倒的に少ない。そもそも、女性同士の性愛を示す概念、言葉がなかった。「互形」を用いた女性同士の擬似性交を「互先(たがいせん)」と言い(田中2004)、女性同士の性愛を示す「貝合せ」とか「合淫(ともぐい)」という言葉があった(白倉2002)。あるいは、「といちはいち(ト一ハ一?)」という語源不詳(「上」「下」の意か?)の言い方もあった。これらは、いずれも卑語、隠語の類であり、世間に広く通用した言葉ではなかった。
これは江戸時代の「色」の概念が、男性から遊女に向かうものを「女色」、男性から若衆に向かうものを「男色」と言い、「色」の発信は常に男性が主体であるとされていたことによる(三橋2013)。つまり、女性が発信主体となることは想定されていないので、女と女の関係は概念として存在しないのだ。さらに、当時の著述・出版事業が圧倒的に男性支配下にあり、女性が自らの性愛を記録し刊行することが困難な事情もあった。
ところで、同性の間の性愛、あるいは性的指向(sexual orientation)が同性に向いていることを意味するhomosexualityという概念は、明治時代の末、1910年頃にドイツの精神医学者リヒャルト・フォン・クラフト=エビングの学説が日本に輸入され、「同性的情慾」「顚倒的同性間性慾」などの訳語で、精神疾患である「変態性慾」のひとつとして概念化された(古川1994)。日本において最初に「女性間の顚倒性慾」が「発見」されたのもこの時期だった(肥留間2003)。その後、訳語は「同性愛」に定着するが、同性愛という言葉が新聞・雑誌などで使用され、倒錯的な性愛として一般に広く知られるようになるのは、1920年代、大正末期から昭和初期のことである。
同性愛概念が導入される以前(明治時代以前)の日本では、同性愛という概念は存在しない。男性同士の性愛は「男色」として概念化されていたが、それは成人した男性と元服前の少年、あるいは年長の少年と年少の少年との関係に限定されていて、成人男性同士の性愛を含む「男性同性愛」とはかなり異なる(三橋2015a、2015b)。とはいえ、それでも類似の先行概念があるだけ男性同性愛という概念を受容しやすかっただろう。
これに対して、女性同士の性愛は、同性愛概念が導入される以前には概念化されていなかった。つまり、女性同性愛は類似の先行概念がなく、(前近代)「男色」→(近代)「男性同性愛」のような概念の継承、読み替えが成り立たず、大正~昭和初期にいきなり世の中に出てくることになる。
このことが、日本近代における女性同性愛の受容に大きく影響しているように思う。大衆は、よくわからないものには警戒的になる。女性同性愛が男性同性愛よりもさらに社会的に警戒されたのは、基本的には男尊女卑の社会構造が大きいが、先行概念の欠落にも理由があったのではないだろうか。
2 「富美子・エリ子事件」―「同性心中」と女性同性愛の危険視―
日本で女性同性愛が注目されたきっかけは、1911年(明治44)7月に新潟で起こった「令嬢風の二美人」の入水心中事件だった。東京の第二高等女学校(都立竹早高校の前身)の同級生だった二人は在学中から「非常の仲よし」だったが、卒業後は交際を控えるよう父親から注意されたのを悲観しての自殺だった。この事件に注目して日本最初の女性同性愛に関する論文、桑谷定逸「戦慄す可き女性間の顚倒性慾」が書かれる(桑谷1911)。日本における女性同性愛は最初から「戦慄すべき」ものだったのだ。
これ以降、昭和戦前期の新聞で、女性同士の「同性心中」がしばしば新聞報道されるようになり、女性同性愛のイメージを「危険」なものにしていった。「同性心中」なのだから男性同士の心中(自殺)もあるはずだが、実際に報道されたもののほとんどは女性同士の心中だった。また、女性同士の自殺だからといって、その二人が同性愛関係だったとは限らないのだが、イメージとして同性心中と女性同性愛が結び付けられ、ことさらに危険視されたことは間違いない。「同性心中」への注目と問題視は戦後期まで継続し、「危険な女性同性愛」のイメージを再生産していくことになる(小峰・南1985)。
ところで、日本で女学校が開設され、女学生が増えるとともに、女学生同士の親密な関係が社会的に浮上してくる。こうした一種の疑似恋愛関係は「エス」(Sisterの頭文字)と呼ばれ、1920年代には女学校文化として定着するようになった(赤枝2011)。それを危険視する見解がある一方で、親にしてみれば女学生の娘が男性と恋愛関係におちいるより、女学生同士の疑似恋愛に没頭している方が安全であり、「エス」の関係は卒業とともに終え、男性と結婚し良妻賢母になってくれればそれでいいという容認的な考えもあったようだ。
もちろん、親の思惑通りに行かない場合もあり、先の新潟の入水心中事件はその典型である。「エス」と女性同性愛の間に明確な線引きができるわけではないにもかかわらず、女学生同士の親密な関係である「エス」は許容され、女性同性愛は危険視されるというダブルスタンダードが生じていく。
一方、1933年(昭和8)に清朝皇室の粛親王善耆の第十四王女である川島芳子(愛新覺羅顯玗)をモデルにした小説、村松梢風『男装の麗人』が出版されたことをきっかけに「男装の麗人」ブームが起こる。その中心は、川島芳子と松竹歌劇団の男役スター「ターキー」こと水の江瀧子だった。当時の新聞は、川島とターキーの動静をしばしば伝えている。


(左)水の江瀧子(右)川島芳子
そんな時代を背景に、1935年(昭和10)1月末、「富美子・エリ子事件」が起こる。増田富美子は大阪の銀行頭取の令嬢ながら増田夷希(やすまれ)と名乗る「男装の麗人」で当時28歳、その恋人西條エリ子は「松竹少女歌劇」の女役トップスターだった人気映画女優で当時23歳。その二人の「女性同士の愛の逃避行」が新聞で大きく報道された。二人は「愛の逃避行」の末に1月28日夜、東京麹町区平河町の「万平ホテル」に同宿する。その夜、富美子はエリ子への遺書を残して睡眠薬自殺をはかり昏睡状態になってしまう。
.jpg)
↑ 増田夷希(やすまれ)と名乗った増田登美子(『読売新聞』1935年1月30日)
まるで犯罪者のように富美子たちの動向を追跡していた『読売新聞』は「『男装の麗人』富美子さん 萬平ホテルで服毒す 西條エリ子と共に投宿 遂に『死』への逃避行」という大見出しのもとに、男姿の富美子の写真と「本当いへば一緒に死んでほしかった」と記された遺書を掲載するなど、連日のようにセンセーショナルに伝えた。

↑ 『読売新聞』1935年1月29日
結局、富美子は一命をとりとめ、エリ子との関係を解消して大阪に帰り一件落着となった。この事件は「同性心中」としては不完全なものだったが、登場人物が著名人だっただけに大きな評判になり、「危険な女性同性愛」を世間にいっそう印象づける「事件」になってしまった。
「富美子・エリ子事件」が印象付けた女性同性愛の危険性とはなんだろう。それは第一に、本来、男性の性愛の対象になるべき女性が(富美子のように)「男を望まない欲望」「男に望まれたくない欲望」を抱くことで、男性の性愛対象から離脱してしまうことである。第二に「男を望まない欲望」が「女を望む欲望」に転化することで、男性の性愛の対象になるべき女性が(エリ子のように)女性同性愛者に奪われてしまうことである。そして、第三はそれらによって男性を主体として築かれた異性愛秩序が崩されかねない危険性を男性たちが感じるからである。
男性たちの女性同性愛への危険視には、本来自分たちのものであるべき女性が奪われることへの怒りが裏打ちされていると思う。
3 「佐良直美事件」―芸能界におけるレズビアン追放―
敗戦(1945年8月)直後の日本は、旧来の社会体制と倫理観の崩壊で、百花繚乱的に多様なセクシュアリティが展開していく。中でも男性同性愛(ゲイ)の顕在化は目覚しく、1950年代後半にはシスターボーイやゲイバーが話題になり、「第1次ゲイブーム」というべき現象が起こる。しかし、そうした社会状況の中でも、レズビアンの顕在化は進まなかった。
この時期の性風俗雑誌には、レズビアンについての記事が散見されるが、男性の興味本位の視点からのものがほとんどで、当事者性のある「語り」はきわめて少ない。そして、「男を望まない」「男に望まれたくない」はずのレズビアンに対して、男性の性的欲望の視線が向けられるようになる。こうして1950年代から60年代にかけて「危険な女性同性愛」は「ポルノグラフィーとしてのレズビアン」へと変化していく。
なぜ、男性の性的欲望を拒絶しているレズビアンに男性の性的視線が向けられるのだろうか。それはレズビアンが「性的快楽を貪欲に追求する」「性的に奔放な」女性としてイメージされたからである(杉浦2010b)。先に述べたように江戸時代において性的欲望の発信は男性に限定されてきた。近代以降の性慾学でも、性的欲望を抱き、性的快楽を追求する女性は「色情狂」であり、変態性慾のカテゴリーだった。同性愛の女性は、単に性愛対象が同性に向いているだけでなく、性的欲望を発信することにおいても変態とされたのだった。
こうした誤った認識がベースになり、性的に奔放な女性なら、男性の性的欲望にも応じるだろう、「レズビアンなんて俺(のペニス)が直してやる」というようなまったくお門違いの妄想がはびこることになる。そこまで愚かでなくても「レズビアン・ポルノビデオは、女性が2人出てくるので2倍おいしい」と言う男性は数多く実在した。
そうした性的奔放というイメージを付与されたレズビアンをめぐって、芸能界の大スキャンダルが勃発する。1980年(昭和55)5月19日、テレビ朝日のワイドショー番組『アフタヌーンショー』が「キャッシー涙の告白!! 佐良直美との愛の破局」と題して、女性歌手佐良直美と女性タレント、キャッシーのレズビアン関係を暴露した「佐良直美事件」である。
佐良直美は、1967年、デビュー曲「世界は二人のために」が120万枚の大ヒットとなり第9回日本レコード大賞の新人賞を受賞し、NHK紅白歌合戦に初出場を果たし、1969年には「いいじゃないの幸せならば」で第11回日本レコード大賞を受賞した。ショートヘアでスカートよりもパンタロンなどのスラックス姿を好み、若い女性にしては低音のハスキーボイスというマニッシュなイメージで、テレビのホームドラマ「ありがとう」(TBS、1970~74年)に出演するなど、歌手だけでなく女優や司会者など多方面で活躍する、押しも押されもせぬ一流歌手で、事件当時35歳だった。
それに対して、キャッシーは大阪弁でまくしたてるハーフのタレントとして注目され、テレビドラマにチョイ役で出演していた。佐良より6歳年下で事件当時は29歳だった。
佐良は、1972年、1974年~1977年と紅白歌合戦の紅組司会を5回も担当しているように、NHK好みの「お茶の間」好感度が高い、スキャンダルとは縁遠い人物と思われていた。それだけにキャッシーの告発は衝撃的だった。
キャッシーの告白は、2人の馴れ初めから佐良家の「嫁」としての同居生活、「姑」(佐良の母)との関係の拗れが原因となった破局まで、3年間の愛情生活を詳細に語った上に、10数通の佐良からの手紙を証拠として添えたものだった(『週刊現代』1980年6月5日号)。
これに対して佐良は同性愛関係を全面否定し、手紙も偽造と決めつけた。両者それぞれ弁護士を立てての泥沼的な訴訟合戦になるかと思われたが、一転して5月末に和解となった。佐良本人は現在に至るまでレズビアン関係を完全に否定しているが、真相は「藪の中」である。
性的スキャンダル、しかもレズビアン・スキャンダルの影響は、両者の芸能界のポジションに格段の差があった分、佐良の方がずっと大きかった。それまでの優等生的なタレントイメージは大きく損なわれてしまった。その年の暮、佐良はデビュー以来13回連続出場を続けていたNHK紅白歌合戦に落選してしまう。確かにヒット曲には恵まれていなかったが、それまでの功績を考えれば唐突な感は否めず、やはりスキャンダルが理由と受け取る人が多かった。それ以降、佐良は徐々に芸能活動から遠ざかりテレビから消えて行った。
後年になって、佐良は芸能界から引退した理由を(レズビアン・スキャンダルではなく)恩師水島早苗の死(1978年)や声帯ポリープの手術(1987年)であると語っている(『東京スポーツ』2010年11月7日号「佐良直美が30年前のレズ騒動を語る」http://www.tokyo-sports.co.jp/entame/2238/)。おそらく事実はそうなのだろう。
しかし、同時代の多くの人は、私も含めそうは受け取らなかった。佐良直美ほどの一流歌手であってもレズビアンであることが世間に知られたら、芸能界から追放されてしまうのだ、と思った。
レズビアンの社会的隠蔽という現象を考える時、事実関係よりも、そうしたイメージが視聴者やテレビ業界に広まってしまったことの方が重要である。「佐良直美事件」によって、日本の芸能界においてレズビアンは絶対的なタブー(禁忌)と認識され、その後のテレビ業界のレズビアン忌避・隠蔽姿勢が決定づけられてしまった。
なお、1970~80年代は、日本でレズビアン・コミュニティが形成されていく時代である。その主体的な歴史については、杉浦郁子の一連の研究を参照されたい(杉浦2006、2008、2010a)。
4 『ラスト・フレンズ』問題 ―なぜレズビアンではいけないのか―
『ラスト・フレンズ』は、2008年(平成20)4月10日から6月19日まで全11回、毎週木曜22時台にフジテレビ系列で放送されたテレビドラマである。
あらすじは、児童虐待(ネグレクト、性的虐待)のトラウマに由来する自我の未確立が影響して家や職場でも居場所が得られず、区役所の児童福祉課で働く恋人宗佑(錦戸亮)からドメスティック・ヴァイオレンス(DV)を受けている藍田美知留(長澤まさみ)、モトクロス選手として全日本選手権優勝を目指す一方、自分の性別に悩みを抱える岸本瑠可(上野樹里)、女性たちの良き相談相手でありながら、過去のトラウマからセックス恐怖症に悩む水島タケル(瑛太)、恋多き女性である滝川えり(水川あさみ)の4人が、シェアハウスで共同生活を始めることで人と人との関わりの大切さを知り、前向きに生きようとする、というものだった。
DV、性同一性障害、セックス恐怖症など当時の社会の若者たちの間で社会問題化しつつあったテーマを取り入れ、主要キャストに旬な若手俳優を起用したこともあって若者たちの間で話題を呼び、高視聴率を記録した(最終回22.8%)。私が大学の講義で当時15~19歳だった受講生を対象に調査したところでは、その世代に限定すれば、視聴率は50%に迫っていたと思われる。また「第57回(2008年春クール)ドラマアカデミー賞」(テレビ雑誌『ザテレビジョン』主催)において、作品賞・助演男優賞(錦戸亮)・助演女優賞(上野樹里)など6冠を達成し、テレビ業界では高く評価された。その一方で、DV男性の美化、レズビアン(女性同性愛)とGIDの混乱などをめぐって、放送時から批判も多かった。
世間的にはハードなDVシーンが注目を集めたが、ここで問題にしたいのは、岸本瑠可の描かれ方である。瑠可は中学校時代の同級生であった美知留にずっと思いを寄せている。第1回のラスト、美知留が初めてシェアハウスに泊まった翌朝、ソファーで眠っている美知留の唇に瑠可がそっと唇を寄せるシーンは、瑠可がレズビアンである可能性を想起させるものだった。しかし、ドラマの中では、「レズビアン」という言葉は一度も使われない。さらに瑠可の性的指向は「男性を好きになれない」という形で表現され、より積極的な「女性が好き」という表現は意識して避けられている。このドラマでは女性が好きな女性を描きながら、レズビアン的なものが隠蔽されているのは明らかだろう。なぜ瑠可はレズビアンではいけないのだろうか。そこに「佐良直美事件」以来のテレビ業界のレズビアン忌避が影を落としているように思われる。
レズビアンが隠蔽される一方で、瑠可がインターネットで病院のサイトを密かに見ているシーンが伏線として描かれ、少し時を置いて瑠可が性同一性障害の診断を求めてメンタルクリニックを受診するシーンが出てくる。その場面にかぶせられた瑠可のモノローグは典型的な性同一性障害の語りであり、ここに至って、瑠可がFtM(Female to Male)の性同一性障害である可能性が視聴者に強く示唆される。
しかし、瑠可の場合、ジェンダー・アイデンティティ(性自認・性同一性)と深く結びついている自称(第一人称)は、ほぼ一貫して「私(わたし)」であり、時に「あたし」と聞こえる箇所もある。FtMは、女性性と関連づけられる「私」を自称として使うことを避ける傾向があり、まして女性性が明確な「あたし」と称することはまずない。FtMの自称としては「自分」「僕」「俺」が用いられることが多いが、瑠可はそうではない。
また、映像表現では、瑠可が女性的なジェンダー表現を好まないこと、男性を愛せないことは強調されているが、FtMに特徴的な女性としての身体に対する違和感は、メンタルクリニックのシーンで語りとして表現されるだけで、映像ではあまり表現されていない。
『ラスト・フレンズ』の脚本家、浅野妙子は、脚本をFtMの当事者にみせたところ、「これってレズビアンじゃん(笑)。レズビアンだと何でいけないの?」と即答されたことを語っている(Yuki Keiser2008)。まさにその通りで、FtMの性同一性障害者をよく知る者からしたら、瑠可がFtMであることはかなり疑問で、ボーイッシュなレズビアンにしか見えない。
ボーイッシュなレズビアンを思わせる瑠可に対して、性同一性障害のレッテルを無理やり貼り付けているのではないか、という疑問に答える場面がやってくる。それは瑠可の父親に対するカミングアウト・シーンだ。瑠可は「私は男の人を好きにならない。なれないんだ」と父親に告白する。ここで問題にされているのは性的指向であり、これは典型的なレズビアンのカミングアウトである。FtMのカミングアウトなら「自分(の心)は男なんだ。女じゃないんだ」というように性自認が問題にされるはずだからだ。
ところが、瑠可のレズビアン的なカミングアウトに対する父親の述懐シーンでは、男の子に混じって活発に遊んでいた瑠可の子供時代が語られる。これは、FtMの子供時代の典型的な語りである。
ここに至って、重大なことに気づく。脚本家が性的指向の問題であるレズビアンと性自認の問題である性同一性障害(FtM)とを混同している、あるいは意図的に混乱させていることに。
実際、脚本家の浅野妙子は、「性同一性障害という設定が最初に決まっていた」こと、その上で「FtMとレズビアンの間」の「グレーゾーン」として瑠可を設定したこと、「どっちともはっきりは言えないけれど」「性同一性障害のほうがレズビアンよりそういった面(「悩み」を連想するという点)で共感を得やすい」と思い、「まずは性同一性障害にしておこう」と考えたことを語っている(Yuki Keiser2008)。レズビアンが悩まないとでも思っているのだろうか。性的マイノリティに対する歪んだ思い込みに基づく安易なドラマ設定があったことがわかる。
「FtMとレズビアンの間」の「グレーゾーン」を描こうとした脚本家の意図が視聴者に伝わったとは思えない。むしろ、瑠可のような、女の子が好きな男っぽい女性は、性同一性障害(FtM)という病気で、メンタルクリニックに通院する必要がある、という誤った情報が視聴者に与えられた可能性が高いと思う。
そうであるならば、このドラマはレズビアンを隠蔽しただけでなく、FtMの性同一性障害のイメージをも歪めて流布し、現実世界に誤った印象・知識を与えたミスリードの事例ということになる。
実際、『ラスト・フレンズ』の放送があった2008年以降、全国のジェンダー・クリニックで10代~20代の若い女性の受診者が急増したことが報告されている。それについては第7節で詳しく述べるが、そこに「ラスフレを見て、自分もそうだと確信しました」というようなミスリードが作用している可能性は十分に考えられる。
5 1990年代以降のレズビアンをめぐる動向
1990年代になると欧米のゲイ・レボリューションの波がようやく日本にも到達する。そうした中で1992年に出版された掛札悠子『「レズビアン」である、ということ』(掛札1992)は、長らく沈黙を強いられてきたレズビアンが初めて堂々と自らの生き方を語ったものとして画期的なものだった。
しかし、それによってレズビアンを取り巻く状況が大きく改善されたかといえば、必ずしもそうとは言えない。掛札に続いてカミングアウトした人は少なく(笹野1995、池田1999)、掛札自身が筆を折ってしまったこともあり、レズビアン・ムーブメントは90年代末に始まる「性同一性障害」の大流行の波に埋もれてしまう(杉浦2010b)。
1990年代末から2000年代前半にマス・メディアによって流布された「性同一性障害」についての情報量は、同性愛のそれと比較できないほど多かった。同性愛の中でも、ゲイはすでに独自のコミュニティを確立し、専門の商業雑誌をもっていたが、コミュニティの規模が小さく商業雑誌がなかなか続かないレズビアンの情報量はさらに少なかった。インターネット時代になって若干改善されたものの、まだ十分と言うには程遠い。
一方、レズビアンの学術的研究としては、性意識調査グループ編の『310人の性意識―異性愛者ではない女たちのアンケート調査』(性意識調査1998)や、中央大学の矢島正見研究室がまとめた『女性同性愛者のライフヒストリー』(矢島1999)がひとつの方向性を示している。それは、ともかくレズビアンの話を聞き記録することで、その存在を顕在化することである。隠蔽されてきた日本のレズビアンを学問的な舞台に載せたという意味で、両書の意味は大きかったと思う。
しかし、同性愛の学術研究全体でみると、杉浦郁子や堀江有里の仕事はあるものの、まだまだ男性主導でアンバランスであることは否めない。たとえば、2010年に岩波書店から出版された風間孝・河口和也『同性愛と異性愛』は、同性愛の当事者が同性愛を書名に掲げて専論した初めての新書として注目されたが、共著者が当事者でないことを理由にレズビアンについてはほとんど触れていない。当事者主義にこだわるのなら、レズビアンの執筆者を招いて章を設けるべきだし、それができないのならば、書名は『男性同性愛と異性愛』にすべきだろう。書名に「同性愛」と銘打ちながらレズビアンについてほとんど記述をしないのは、単にアンバランスなだけでなく、レズビアンの疎外であり、結果的にレズビアンの隠蔽に加担していると言えなくもない。『同性愛と異性愛』という書名にひかれて手に取ったレズビアンが目次を通覧した時の疎外感と落胆を著者や編集者は想像しただろうか。
同性愛者の歴史的な歩みや現在直面している問題が、いつの間にか男性同性愛者(ゲイ)のそれにすり替えられてしまう現象は、この本だけではないように思う。
2005年、大阪府議会議員だった尾辻かな子がレズビアンであることをカミングアウトした(尾辻)。尾辻は2007年の参議院選挙(比例区)に民主党公認として立候補したものの当選ラインに遠く及ばず落選したが、2013年5月、繰り上げ当選によって参議院議員(民主党)となった。任期が僅か一カ月余だったこともあり、残念ながら十分な実績は残せなかったが、尾辻が日本初の性的マイノリティであることを公言した国会議員であることはまぎれもない事実である。
しかし、東京都豊島区議会議員で男性同性愛者(ゲイ)であることを公表している石川大我が2014年の衆議院総選挙で社会民主党の東京比例区名簿1位に登載されると、複数のネット・メディアが「日本初の同性愛者の国会議員を目指す」と報じ、尾辻の存在は「なかったこと」にされた。無知と言えばそれまでだが、石川事務所も「日本初のオープンリーゲイの国会議員」を目指すことをプロフィールに記していて、「日本初のオープンリー同性愛者国会議員」である尾辻への配慮に欠けていたことは否めない。
2000年代後半になると、レズビアン関係の出版も徐々に増えていく(堀江2006、飯野2008、牧村2013)。2013年には世界的な同性婚承認の流れの中で、レズビアン・カップルの東京ディズニーランドでの挙式が話題になった(東小雪+増原裕子2014)。
しかし、レズビアンの存在が日本社会の中で十分に認知され、レズビアンに関する情報が十分に流通し、レズビアンを取り巻く様々な困難な状況について地に足が着いた議論がなされる状況には、残念ながら至っていない。
6 レズビアン・ロールモデルの不在
レズビアンをめぐる現状を考えたとき、情報量の不足もだが、最大の問題はレズビアンのロールモデルの不在だと思う。その原因は、テレビをはじめとするマス・メディアがレズビアンの存在を徹底的に隠蔽してきたことにある。
2010年代になってさえ、日本のマス・メディアは「レズビアン疑惑」という言い方をしてはばからない。「疑惑」という言葉は「覚醒剤使用疑惑」など社会的に問題のある行為を疑う言葉だ。いったいなぜレズビアンであることが問題行為なのだろう。そうした「疑惑」をかけられた女優、女性歌手あるいは女性タレントは、必死に「疑惑」を否定しようとする。本人が沈黙していても事務所が否定に動く。なぜなら、現在の日本のテレビ業界では「レズビアン」であることは仕事を失うことにつながりかねず、デメリットが大きいからだ。その点で、レズビアンをカミングアウトした女優や女性アーティストが活躍する欧米と著しい違いがある。佐良直美事件の呪縛は30年以上たってもまだ解けていないのだ。
なぜ、これほどまでにテレビ・メディアはレズビアンの存在を忌避するのだろうか。その理由を端的に指摘すれば、すべての女性は男性の性的視線を受け止める存在でなければならないという、男性中心のヘテロセクシュアル原理がいまだに貫徹しているのがテレビ業界だということだ。そうした姿勢の背景にはスポンサーとしてテレビ番組を支えている日本の企業社会の男性中心のヘテロセクシャリズムがある。
このように、マス・メディアの隠蔽姿勢がレズビアンのvisibility(目に見えること)を著しく低下させ、魅力的なレズビアン・ロールモデルの出現を阻んでいる。そして、レズビアン・ロールモデルの不在が、レズビアンの自己肯定をいっそう困難にしている。
ところで、レストランでメニューにない料理を注文できる人はごく少ない。ほとんどの人はメニューの中から料理を選ぶ。それと同じで、人は目の前に並んでいる概念にしかアイデンティファイ(カテゴリーへの同一化)できない。私はこれを「メニュー理論」と言っている。
たとえば、20代の私の前に置かれていたメニューには、トランスジェンダーも性同一性障害も無く、ゲイボーイという概念しかなかった。「これは違う」と思ったから、それをつかまなかった。アマチュアの女装者という概念があることを知ったのは30代の初めで、やっとその言葉をつかむことができたが、トランスジェンダーという言葉を知って最終的にアイデンティファイできたのは40歳を過ぎてからだった。
レズビアンを抑圧し、存在を隠蔽してきた結果、レズビアンのロールモデルが提示されず、逆に性同一性障害(FtM)の情報が多く流布されている現状は、メニューに「今月のおすすめ」として「性同一性障害(FtM)」と大書されているのに対し、「レズビアン」は見えるか見えないかの小さい文字でしか書かれていない状態にたとえられる。自分の性的指向(Sexual Orientation)が典型的でないことに気づいた女性がメニューを見たとき、本来ならつかむべきレズビアンではなく、性同一性障害(FtM)をつかんでしまうのも無理からぬ状況がそこにある。
7 なぜ日本はFtM(Female to Male)が多いのか?
性同一性障害の性別比、つまりMtFとFtMの比率は、世界標準的には、2対1くらいでMtFが多いとされている。日本では1990年代末から2000年代中頃までは、MtFがやや多い状態からMtFとFtMの比率が拮抗する状況へと緩やかに推移していた。ところが、2008年以降、全国の複数の病院、クリニックで、若年(10代後半~20代前半)FtMの受診者が急増し、世界標準とは逆に、ほぼ1対2の比率でFtMの受診者が多くなった(2009年2月の第11回GID学会での報告。「関西医大病院ジェンダー・クリニック」MtF134、FtM270=33対67、「札幌医大GIDクリニック」MtF94、FtM220=30対70、「はりまメンタルクリニック」MtF229、FtM409=36対64)。
かつて私は、この現象をテレビドラマ『ラスト・フレンズ』の影響で、本来は、男性っぽいレズビアンの範疇でおさまるはずの(瑠可のような)女性が、性同一性障害(FtM)と自己認識して、ジェンダー・クリニックを受診している結果ではないかと考えていた。しかし、その後もFtMの増加傾向は止まらず、現在では1対3からさらに1対4に近づく状態になっている。
FtMの増加傾向は、受診者レベルではなく、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(GID特例法)」による戸籍の性別変更においても著しい。全国の家庭裁判所に提出される戸籍変更の診断書の約15%を書いている(2012~2014年平均)針間克己医師(はりまメンタルクリニック)によれば、2012年から2015年の戸籍変更診断書の累計はMtF119、FtM464≒1対4だった(「Anno job Log」2015年12月27日 http://d.hatena.ne.jp/annojo/20151227)。日本は世界で最も、そして格段にFtMの比率が高い国になっている。
こうなると、テレビドラマの影響だけとは言えず、それをきっかけとした、もっと大きな構造的な原因があると考えなければならない。生得的な体質、遺伝子的に日本人の女性がFtMになりやすいということはなさそうなので、その原因は社会的なものと考えられる。
そこで考えなければならないのは、世界標準より多い分のFtMがどこから来ているのか?ということだ。その際、ヘテロセクシュアルの女性がFtM化するということは考えにくい。女性に課せられた社会的制約から脱するために男装する女性は過去にはいたが、現代の日本は一般論的に言って女性が男体化しなければ社会活動が難しい状況にはない。また性的指向が男性に向かっているヘテロセクシュアルの女性がFtM化した場合、セクシュアリティ的なメリットはほとんどない。ゲイ男性はヘテロ男性よりずっと少ないからだ。
それに対して、レズビアンがFtM化しているという想定の方がずっと考えやすい。レズビアンがFtM化すれば、性愛対象のヘテロ女性はレズビアン女性よりずっと多いから、ターゲットはぐっと広がる。なにより戸籍の性別を男性に変更すれば、法的に女性と結婚できる。同性婚が法的に許可される見通しが立たない日本では、生得的な女性が女性と法的に婚姻するには、一方の女性がFtMの性同一性障害者として「GID特例法」によって、戸籍の性別を変更するのが唯一の方法だからだ。
このように考えると、日本におけるFtMの増加分はレズビアンからの流入を想定するのが、いちばん蓋然性が高いと思う。その原因として、前節で述べたような、自分の性的指向が典型的でないことに気づいた女性が本来ならアイデンティファイすべきレズビアンではなく、性同一性障害(FtM)として自己認識してしまう状況が存在し、さらに「GID特例法」による一種の「誘導」が作用していると考えられる。
次に考慮すべきは、レズビアンとFtMの比率である。本来、レズビアンは100人に数人いると考えるのが一般的だ。それに対して日本のFtMは10000人に数人と考えられる。つまり両者の人数は本来100倍ほども違う。ということは、レズビアンの1%がFtMに流入すればFtMは本来の数の倍になるし、2%流入すれば3倍に、9%が流入すれば10倍になる。このようにレズビアンからの流入モデルを考えることで、日本で世界標準よりFtMが著しく多い理由を容易に説明することができる。
ところで、レズビアンからFtMへという流入現象がかなりあると想定した場合、ゲイからMtFへの流入はそれに比してなぜ少ないのかという疑問が生じる。この点については次のように説明できると思う。
日本において、ゲイ・コミュニティとMtFのコミュニティは、性同一性障害概念が流布する1990年代後半以前に、すでにかなり明確に分離していた。その分離の時期は1970~1980年代と考えられる(三橋2008)。だから、性同一性障害概念はMtFだけに影響を与え、ゲイにはほとんど影響が及ばなかった(まったく流入がないわけではないが)。それに対して、レズビアン・コミュニティとFtMのコミュニティは分離が進まず混在した状態だったところに、性同一性障害概念が流布した。その結果、本来、性同一性障害概念の影響を受ける必要のないレズビアンにまでその影響が及んでしまい、混乱と流入が起こってしまったと考えられる。そして、レズビアン・コミュニティとFtMのコミュニティの未分離の原因にはレズビアンの隠蔽による情報不足がある。
非典型な性をもつ人たちがどのようにカテゴライズされ、自らをアイデンティファイしていくかは、今まで言われてきたほど固定的ではなく、与えられる情報によってかなり流動的であると私は考える。それゆえに、適切なアイデンティファイをするためには隠蔽や歪曲がない正しい情報提供、つまり、自分にふさわしい料理を選べる「メニュー」が必要なのである。
おわりに
ある年度、「ジェンダー論」の講義の単位レポートに、レズビアンであることの辛い思いを切々と記してきた学生がいた。好きな相手からもレズビアンの存在そのものを否定され、周囲の偏見の中で自己否定感にさいなまれる。なぜ、女性として女性が好きなだけでこんなに苦しまなければならないのか、単位レポートだから冷静に読んで評価しなければいけないのだが、「今まで書いてきたことはすべて事実です。でも、誰にも話したことはありません。やっとレポートという形ですが書くことができて、私は幸せです、ありがとうございました」という結びの文章を読んで、涙が流れるのを抑えることができなかった。
一方では、女性を愛するためには自分が男にならなければならないと思い込み、短命化の可能性が高い男性ホルモンを過剰に摂取し、身体にメスを入れて乳房、子宮・卵巣を摘出し、高額な費用をかけて(トラブルが多く機能的にも不十分な)擬似男性器を形成する人たちがいる。無惨な傷跡が残る症例写真を見るたびに、レズビアンの範疇に収まるのなら、その方がずっと身体リスクは少ないのに、なぜこんなことまでしなければならないのかと考えてしまう。
女性として女性を愛する女性たちが、適切な自己認識を形成するためには、レズビアンが隠蔽されることなく、レズビアンに関する情報が十分に流通し、女性として女性を愛する多様なロールモデルが社会の中で存在することが必要だと思う。さらに言えば、女性を愛する女性がレズビアンでなくFtMを選択する背景には、日本社会における女性の根本的な生きにくさが存在する。性的マイノリティだけの問題では済まないことを、性的マジョリティの人たちにも知って欲しいと思う。
文献
赤枝香奈子2011『近代日本における女同士の親密な関係』(角川学芸出版)
飯野由里子2008『レズビアンである〈わたしたち〉のストーリー』(生活書院)
池田久美子1999『先生のレズビアン宣言―つながるためのカムアウト』(かもがわ出版)
尾辻かな子2005『カミングアウト〜自分らしさを見つける旅』(講談社)
掛札悠子1992『「レズビアン」である、ということ』(河出書房新社)
風間孝・河口和也2010『同性愛と異性愛』(岩波新書)
桑谷定逸1911「戦慄す可き女性間の顚倒性慾」(『新公論』明治44年9月号)
小峰茂之・南孝夫1985『同性愛と同性心中の研究』(小峰研究所)
笹野みちる1995『Coming OUT!』(幻冬舎)
白倉敬彦2002『江戸の春画―それはポルノだったのか―』(洋泉社新書)
菅 聡子2006「女性同士の絆―近代日本の女性同性愛―」(『国文』106号)
杉浦郁子2006「1970、80年代の一般雑誌における『レズビアン』表象――レズビアンフェミニスト言説の登場まで」(矢島正見編著『戦後日本女装・同性愛研究』(中央大学出版部)
杉浦郁子2008「日本におけるレズビアン・フェミニズムの活動 -1970年代後半の黎明期における」 (『ジェンダー研究』11号)
杉浦郁子2010a「『レズビアン』の概念史――戦後、大衆娯楽雑誌における」(中村桃子編『ジェンダーで学ぶ言語学』世界思想社)
杉浦郁子2010b「レズビアンの欲望/主体/排除を不可視化する社会について―現代日本におけるレズビアン差別の特徴と現状―」(シリーズ「現代の差別と排除」第6巻『セクシュアリティ』明石書店)
性意識調査グループ編1998『310人の性意識―異性愛者ではない女たちのアンケート調査』(七つ森書館)
田中優子2004『張形と江戸をんな』(洋泉社新書)
東 小雪+増原裕子2014『レズビアン的結婚生活』(イースト・プレス)
肥留間由紀子2003「近代日本における女性同性愛の『発見』」(『解放社会学研究』17号)
古川 誠1994「セクシュアリティの変容:近代日本の同性愛をめぐる3つのコード」(『日米女性ジャーナル』17号)
堀江有里2006『「レズビアン」という生き方―キリスト教の異性愛主義を問う』(新教出版社)
堀江有里2015『レズビアン・アイデンティティーズ』(洛北出版)
牧村朝子2013『百合のリアル』(星海社新書)
三橋順子2008『女装と日本人』(講談社現代新書)
三橋順子2013「性と愛のはざま-近代的ジェンダー・セクシュアリティ観を疑う-」(『講座 日本の思想 第5巻 身と心』岩波書店)
三橋順子2015a「『台記』に見る藤原頼長のセクシュアリティの再検討」(倉本一宏編『日記・古記録の世界』思文閣出版)
三橋順子2015b「歴史の中の多様な『性』」(『アステイオン』83号 CCCメディアハウス)
矢島正見編著1999『女性同性愛者のライフヒストリー』(学文社)
Yuki Keiser2008「『ラスト・フレンズ』の脚本家・浅野妙子さんのインタビュー」
http://www.tokyowrestling.com/articles/2008/06/last_friends_3.html
【付記1】入稿後、杉浦郁子「『女性同性愛』言説をめぐる歴史的研究の展開と課題 」(『和光大学現代人間学部紀要』8号 2015年)に接した。本稿と関わるところ大であるが、内容に反映することができなかった。
【付記2】最終的な入稿(2015年2月)の直後、東京都渋谷区の「同性パートナー証明書」発行の条例化(2015年3月31日可決、11月5日実施)問題が浮上し、それをきっかけに「LGBTブーム」が一気に盛り上がり、マス・メディアにおけるレズビアンを含む同性愛関係報道が激増した。その結果、レズビアンのvisibilityは向上したように思われる。しかし、「LGBTブーム」の中で注目されているのは、裕福で、容姿に優れ、社会的地位のある「シャイニー(shiny)」な特定のレズビアンであり、一般のレズビアンが抱えるさまざまな生活の困難を改善していく視点は、まったく不十分である。これはブームの発端が政治的思惑(統一地方選挙)や経済的期待(LGBT消費需要)であり、必ずしも人権的観点でなかったためと思われる。今後、LGBTの人権擁護の論議が深まる中で、本当の意味でのレズビアンの社会的顕在化と生活改善がなされることを期待したい。
【エッセー】「日本人は女装好き?」(講談社『本』2008年10月号) [論文・講演アーカイブ]
2008年9月に『女装と日本人』を講談社現代新書の1冊として刊行した際に、講談社の広報誌『本』2008年10月号に執筆したエッセーです。
『女装と日本人』で割愛した深川芸者と女装バレエ団を事例に、日本人の性別越境(女装・男装)への嗜好ついて書きました。
--------------------------------------------
日本人は女装好き?
三橋 順子
夏の終わりの夕べ、柳橋の舟宿から屋形舟をしたて、大川を下って、夜景が美しいお台場沖に泊まり、江戸前の天麩羅を食べながら、去り行く夏を送ってきました。
江戸時代の半ば過ぎた頃、大川の舟遊びといえば、芸者が付きものでした。川面を渡る三味線の音や、常磐津などの唄声は、さぞ風情があったことでしょう。私たちが舟を出した柳橋は、天保の取締り(一八四二)以降に隆盛を迎えた江戸においては新興の花街でしたが、それ以前に、大川の舟遊びの相手をもっぱら務めたのは深川の芸者たちでした。
深川の芸者の出で立ちの特色は、薄化粧で、鼠色など地味な長着に羽織を着ていることで、故に羽織芸者と呼ばれました。羽織は、現代の和装では、男女ともに用いますが、本来は男性のみが着用する衣料です。また深川芸者は、蔦吉とか、桃太郎とかいうような男名前(権兵衛名)を名乗り、しゃべり方も男っぽく威勢よく、気立ても「意気」と「張り」を看板にしていました。
今でこそ、芸者といえば古風な「女らしさ」の体現者としてイメージされますが、深川芸者は、男装、男名前、男言葉、気風(きっぷ)のよさというような男粧(おとこなり)、男振を売りにしていのです。現代に置き換えるならば、男物のスーツ姿で、大輔とか、拓也とか名乗って、「俺、○○なんすよ」みたいなしゃべり方をする女性だったことになります。現代の男性が、そうした女性にお金を払って、いっしょに遊ぼうとするでしょうか? とてもそうは思えません。しかし、江戸時代の男性は、そうした男っぽい女性を、好んで遊興の供としたのです。しかも金子を与えて。
話をまったく変えます。今年も「トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団」(アメリカ 一九七四年結成)の日本公演の広告が新聞に大きく出ていました。同バレエ団は、筋骨たくましい男性舞踊手が白いチュチュを着て「白鳥の湖」などを踊る男性だけで構成された女装バレエ団です。二〇〇八年には、六月六日から八月三日まで、東京新宿を中心に、北は秋田、南は鹿児島まで全国三〇都市を巡り三七回の公演が行われ、どこでも盛況だったようです。一九八二年の初来日以来、二四回目の来日公演ですから、ほとんど毎年のように来ていることになります。これほどの頻度で来日する海外のバレエ団が他にあるでしょうか? 頻繁に来日するということは、それだけ興行として成功しているということです。どうも、日本では、女性がプリマをつとめる海外の有名バレエ団の来日公演よりも、女装バレエ団の方が、はるかに興行成績が良いらしいのです。
後発の女装バレエ団「グランディーバ・バレエ団」(アメリカ 一九九六年結成)の場合、平均集客率は八割を超え、観客の九五%は女性というデータがあります。同バレエ団は日本公演をメインに活動していることからも明らかなように、女装バレエ団にとって日本は、とてもおいしい、最重要の市場であることは間違いありません。
男振を売りにした江戸時代の深川芸者と、女っぽさを売りにする現代の女装男性バレエ団と、どうつながるのか不思議に思う方も多いでしょうが、私は、そこに日本人の性別越境者、そうした人が担い手となる芸能への嗜好が見えるように思うのです。もう少し解りやすく言えば、日本人は、女装した男性や、男装した女性を好む文化を持っているということです。
そう書くと「いや、俺は、女装の男も、男装の女も大嫌いだ。とりわけ、女装した男なんて虫唾が走る」という人が出てくると思います。まあ、それは個人の好みの問題ですから結構です。
しかし、女装の演技者である女形が重要な役割をはたす歌舞伎は、日本を代表する伝統芸能です。歌舞伎とは逆に、男装の演技者(男役)がトップスターである宝塚歌劇も多くの熱狂的なファンを持っています。また、歌舞伎よりも古い起源をもつ古典芸能である能は、憑霊という仕組みと仮面という装置によって男性演技者がしばしば女性を演じます。
性別越境芸能の人気は、歌舞伎や宝塚のようなメジャーな演劇世界だけではありません。梅沢富美男や松井誠、最近では若手の早乙女太一の名が知られるように、大衆演劇の世界では、女形(をできる役者)が絶対的にスターで、女から男、男から女という性別越境は、最大の「ウケる」要素なのです。
このように見てくると、日本の演劇世界では、男から女(女装)、女から男(男装)のような異性装という要素が大きな役割を果たし、根強い人気を保っていることがわかります。観衆が性別越境(トランスジェンダー Transgender)的なものを好むという現象は、どうも過去から現代まで続く歴史的な伝統のようです。
演劇だけではありません。現代でも、女装した男性が一定の役割を果たす祭礼は日本各地に残っています。たとえば、東京江戸川区東葛西の雷不動真蔵院で毎年二月に行われる「雷の大般若」と呼ばれる行事では、お白粉に真っ赤な口紅、青のアイライン、頬紅という化粧をして女装した青年たちが大般若経の入った箱を担ぎ、家々の玄関口で悪魔払いをして無病息災を願います。ちなみに、お化粧は、地元の美容院に依頼するそうです。
また、一九六〇年代くらいまでは、花見や盆踊りの際に、一般の人々が女装・男装する習俗はあちこちで見られました。現在でも、大学や高校の学園祭でしばしば見られる女装コンテストなどは、そうした祝祭空間での女装習俗の名残でしょう。
日本人は、女装・男装を観るだけでなく、自らも楽しんでいたのです。こうなると、女装・男装への嗜好は、日本文化の基層に根差すものなのではないかと、私には思えるのです。
それでも中にはこう主張する人がいるかもしれません。「いや、男が女を演じるなんてどう考えたって不自然だ。そんな変態的な演劇は認められない」と。あるいは「女装する男なんて奴は、世の中の性別秩序を破壊する社会悪だ。そんな奴はとっ捕まえて、刑務所か精神病院へ叩き込め」と。
さすがに現代の日本では、そこまで言う人は稀でしょう(でも少数ですが確実にいます)。ですが、一昔前までは、けっして珍しい意見ではありませんでした。たとえば、評論家で近代演劇普及の旗手だった島村抱月は、一九一一年(明治四四)に「日本の旧歌舞伎といふ如きは変態芸術」と断じています。
こうした性別越境的なものを変態視して徹底的に忌避する考え方と、先に述べた女装・男装の演劇者に拍手する日本人の性別越境芸能への嗜好とは、どのような関係にあるのでしょうか?
結論だけを述べますと、性別越境的なものを「変態」として否定する考え方は、キリスト教文化に由来する西欧近代の産物で、明治時代以降に日本に移入されたものなのです。
結果として、現代の日本社会は、性別越境的なものを好む江戸時代以前からの基層文化の上に、そうしたものを変態視して忌避する西欧近代の思想が重なるという二重構造になっているように思います。それは、明治以降の日本の社会がずっと持ち続け悩んできた矛盾の投影なのです。
たかが、女装・男装の話が、ずいぶん大袈裟にことになってしまいましたが、このたび上梓した『女装と日本人』(講談社現代新書)ではそんなことをいろいろ考えてみました。
ところで、あなたは、女装した男性をどう思いますか?石をぶつけますか?「まあ、それもありかな」と思いますか? それとも好きですか? 後の二つの部類の方には、十分に楽しんでいただける内容だと思います。
(みつはし じゅんこ 国際日本文化研究センター共同研究員 性社会・文化史)
『女装と日本人』で割愛した深川芸者と女装バレエ団を事例に、日本人の性別越境(女装・男装)への嗜好ついて書きました。
--------------------------------------------
日本人は女装好き?
三橋 順子
夏の終わりの夕べ、柳橋の舟宿から屋形舟をしたて、大川を下って、夜景が美しいお台場沖に泊まり、江戸前の天麩羅を食べながら、去り行く夏を送ってきました。
江戸時代の半ば過ぎた頃、大川の舟遊びといえば、芸者が付きものでした。川面を渡る三味線の音や、常磐津などの唄声は、さぞ風情があったことでしょう。私たちが舟を出した柳橋は、天保の取締り(一八四二)以降に隆盛を迎えた江戸においては新興の花街でしたが、それ以前に、大川の舟遊びの相手をもっぱら務めたのは深川の芸者たちでした。
深川の芸者の出で立ちの特色は、薄化粧で、鼠色など地味な長着に羽織を着ていることで、故に羽織芸者と呼ばれました。羽織は、現代の和装では、男女ともに用いますが、本来は男性のみが着用する衣料です。また深川芸者は、蔦吉とか、桃太郎とかいうような男名前(権兵衛名)を名乗り、しゃべり方も男っぽく威勢よく、気立ても「意気」と「張り」を看板にしていました。
今でこそ、芸者といえば古風な「女らしさ」の体現者としてイメージされますが、深川芸者は、男装、男名前、男言葉、気風(きっぷ)のよさというような男粧(おとこなり)、男振を売りにしていのです。現代に置き換えるならば、男物のスーツ姿で、大輔とか、拓也とか名乗って、「俺、○○なんすよ」みたいなしゃべり方をする女性だったことになります。現代の男性が、そうした女性にお金を払って、いっしょに遊ぼうとするでしょうか? とてもそうは思えません。しかし、江戸時代の男性は、そうした男っぽい女性を、好んで遊興の供としたのです。しかも金子を与えて。
話をまったく変えます。今年も「トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団」(アメリカ 一九七四年結成)の日本公演の広告が新聞に大きく出ていました。同バレエ団は、筋骨たくましい男性舞踊手が白いチュチュを着て「白鳥の湖」などを踊る男性だけで構成された女装バレエ団です。二〇〇八年には、六月六日から八月三日まで、東京新宿を中心に、北は秋田、南は鹿児島まで全国三〇都市を巡り三七回の公演が行われ、どこでも盛況だったようです。一九八二年の初来日以来、二四回目の来日公演ですから、ほとんど毎年のように来ていることになります。これほどの頻度で来日する海外のバレエ団が他にあるでしょうか? 頻繁に来日するということは、それだけ興行として成功しているということです。どうも、日本では、女性がプリマをつとめる海外の有名バレエ団の来日公演よりも、女装バレエ団の方が、はるかに興行成績が良いらしいのです。
後発の女装バレエ団「グランディーバ・バレエ団」(アメリカ 一九九六年結成)の場合、平均集客率は八割を超え、観客の九五%は女性というデータがあります。同バレエ団は日本公演をメインに活動していることからも明らかなように、女装バレエ団にとって日本は、とてもおいしい、最重要の市場であることは間違いありません。
男振を売りにした江戸時代の深川芸者と、女っぽさを売りにする現代の女装男性バレエ団と、どうつながるのか不思議に思う方も多いでしょうが、私は、そこに日本人の性別越境者、そうした人が担い手となる芸能への嗜好が見えるように思うのです。もう少し解りやすく言えば、日本人は、女装した男性や、男装した女性を好む文化を持っているということです。
そう書くと「いや、俺は、女装の男も、男装の女も大嫌いだ。とりわけ、女装した男なんて虫唾が走る」という人が出てくると思います。まあ、それは個人の好みの問題ですから結構です。
しかし、女装の演技者である女形が重要な役割をはたす歌舞伎は、日本を代表する伝統芸能です。歌舞伎とは逆に、男装の演技者(男役)がトップスターである宝塚歌劇も多くの熱狂的なファンを持っています。また、歌舞伎よりも古い起源をもつ古典芸能である能は、憑霊という仕組みと仮面という装置によって男性演技者がしばしば女性を演じます。
性別越境芸能の人気は、歌舞伎や宝塚のようなメジャーな演劇世界だけではありません。梅沢富美男や松井誠、最近では若手の早乙女太一の名が知られるように、大衆演劇の世界では、女形(をできる役者)が絶対的にスターで、女から男、男から女という性別越境は、最大の「ウケる」要素なのです。
このように見てくると、日本の演劇世界では、男から女(女装)、女から男(男装)のような異性装という要素が大きな役割を果たし、根強い人気を保っていることがわかります。観衆が性別越境(トランスジェンダー Transgender)的なものを好むという現象は、どうも過去から現代まで続く歴史的な伝統のようです。
演劇だけではありません。現代でも、女装した男性が一定の役割を果たす祭礼は日本各地に残っています。たとえば、東京江戸川区東葛西の雷不動真蔵院で毎年二月に行われる「雷の大般若」と呼ばれる行事では、お白粉に真っ赤な口紅、青のアイライン、頬紅という化粧をして女装した青年たちが大般若経の入った箱を担ぎ、家々の玄関口で悪魔払いをして無病息災を願います。ちなみに、お化粧は、地元の美容院に依頼するそうです。
また、一九六〇年代くらいまでは、花見や盆踊りの際に、一般の人々が女装・男装する習俗はあちこちで見られました。現在でも、大学や高校の学園祭でしばしば見られる女装コンテストなどは、そうした祝祭空間での女装習俗の名残でしょう。
日本人は、女装・男装を観るだけでなく、自らも楽しんでいたのです。こうなると、女装・男装への嗜好は、日本文化の基層に根差すものなのではないかと、私には思えるのです。
それでも中にはこう主張する人がいるかもしれません。「いや、男が女を演じるなんてどう考えたって不自然だ。そんな変態的な演劇は認められない」と。あるいは「女装する男なんて奴は、世の中の性別秩序を破壊する社会悪だ。そんな奴はとっ捕まえて、刑務所か精神病院へ叩き込め」と。
さすがに現代の日本では、そこまで言う人は稀でしょう(でも少数ですが確実にいます)。ですが、一昔前までは、けっして珍しい意見ではありませんでした。たとえば、評論家で近代演劇普及の旗手だった島村抱月は、一九一一年(明治四四)に「日本の旧歌舞伎といふ如きは変態芸術」と断じています。
こうした性別越境的なものを変態視して徹底的に忌避する考え方と、先に述べた女装・男装の演劇者に拍手する日本人の性別越境芸能への嗜好とは、どのような関係にあるのでしょうか?
結論だけを述べますと、性別越境的なものを「変態」として否定する考え方は、キリスト教文化に由来する西欧近代の産物で、明治時代以降に日本に移入されたものなのです。
結果として、現代の日本社会は、性別越境的なものを好む江戸時代以前からの基層文化の上に、そうしたものを変態視して忌避する西欧近代の思想が重なるという二重構造になっているように思います。それは、明治以降の日本の社会がずっと持ち続け悩んできた矛盾の投影なのです。
たかが、女装・男装の話が、ずいぶん大袈裟にことになってしまいましたが、このたび上梓した『女装と日本人』(講談社現代新書)ではそんなことをいろいろ考えてみました。
ところで、あなたは、女装した男性をどう思いますか?石をぶつけますか?「まあ、それもありかな」と思いますか? それとも好きですか? 後の二つの部類の方には、十分に楽しんでいただける内容だと思います。
(みつはし じゅんこ 国際日本文化研究センター共同研究員 性社会・文化史)
【論文】「着物趣味」の成立 [論文・講演アーカイブ]
一般社団法人現代風俗研究会・東京の会の研究誌『現代風俗学研究』15号「趣味の風俗」(2014年3月 ISSN2188-482X)に掲載した論文「『着物趣味』の成立」のカラー画像入り全文。

日常衣料だった「着物」が非日常化し、さらに「趣味化」していく過程を、和装文化の展開を踏まえて、まとめてみた。
欲張った内容なので不十分な点は多々あるが、自分が考える和装文化の衰退と「着物趣味」の成立の流れを、まとめることができたと思っている。
------------------------------------------
「着物趣味」の成立 三橋 順子
【概要】
本来、日本人の日常の衣料であり、洋装化が進んだ戦後においても時と場を限定しながら衣料として機能していた着物(和装)の世界に、2000年頃からひとつの変化が現れる。それは着物の趣味化である。「着物趣味」は戦後の和装世界で形成されたさまざまな規範を超越しながら、ある種のコスチューム・プレイとして新たな展開をみせていく。本稿では、近代における和装文化の流れを踏まえながら、着物趣味の成立過程をたどってみたい。
キーワード 着物 趣味化 コスチューム・プレイ
はじめに
まず「趣味」とは何か、ということを考えておこう。「趣味」を辞書で引くと、「①仕事・職業としてでなく、個人が楽しみとしてしている事柄。②どういうものに美しさやおもしろさを感じるかという、その人の感覚のあり方。好みの傾向」(『大辞泉』)というように、だいたい2つの意味が出てくる。ここで論じる「着物趣味」の「趣味」は①である。さらに、人間だれしもが持っている時間に注目すれば、趣味とは、食事や睡眠などの生活必要時間、仕事や職業、家事などの労働時間以外の自由時間(余暇)に営まれるものと言うことができる。たとえば、私のように、ほぼ毎日、自分と家族のために食事を作っている人は「料理好き」かもしれないが、それは家事労働であって「料理趣味」ではない。料理趣味とは、日頃、家庭で料理をしない人が、休日などの余暇を利用して日常の食べ物とはちょっと違うレベルのものを料理することを言うのだと思う。
次に「着物趣味」の成立の要件を考えてみたい。着物が生活衣料である間は、着物を着ることは日常に必要な営みであって、趣味にはならない。私の明治生まれの祖母は2人とも、生涯、ほとんど和装しかしなかった人で、毎日、着物を着ていたが、それは「趣味」とはまったく遠い。そうした着物が日常衣料だった時代にも、裕福で高価な着物をたくさん誂える人はいたが、それは「着道楽」であって、「着物趣味」とは言わなかった。つまり、着物が趣味化して「着物趣味」が成立する前提、第1の要件として、着物が日常衣料としてのポジションを失うことが必要になる。
最初の辞書的定義のように「趣味」は本来、個人のものだ。しかし、個人が孤立している間は、ほとんど社会性を持たない。「趣味」がある程度の社会性をもつためには、同じ「趣味」をもつ「同好の士」が集まることが必要になる。つまり、「着物趣味」の同好の士が横のつながりをもって集うことが「着物趣味」の成立の第2の要件になると考える。
そして、その仲間たちの間で、「着物趣味とはこういうものだ」という意識、ある種の規範が共有される。その共有された規範が仲間としての意識を強化していく。こうした特有の規範の成立を第3の要件と考えたい。
Ⅰ 日常衣料としての和装の衰退 ―趣味化の前提として―
1 洋装化と和装の衰退
明治の文明開化とともに日本人の洋装化が始まる。西欧近代文化の輸入と模倣に懸命な新政府は鹿鳴館(1883)に象徴される洋風文化を演出するが根付かなかった。洋装化は軍人の軍服、巡査の制服、官公吏の上層部や洋行帰りの学者など、男性のごく一部に止まり、女性の洋装化はほとんど進展しなかった。
大正後期から昭和初期(1920~36)になると、洋服を着たモダンボーイ(モボ)とモダンガール(モガ)が最新の流行ファッションとして注目されるようになる。とりわけ、女性の洋装化の端緒となったモガへの社会的注目度は高かった。しかし、それは都市における尖端文化ではあったが、全国的・全階層的な広がりを持つものではなかった。
一方、この時代は和装にも大きな変化があった。化学染料と力織機の普及により銘仙やお召などの絹織物の大量生産が可能になり、それまで木綿の着物しか着られなかった階層にまで絹織物が普及していく。
昭和初期に大都市に出現するデパートは、絹織物としては安価な銘仙を衣料品売り場の目玉商品に据える。そして、産地と提携した展示会などを開催して積極的に「流行」を演出していった。
主要な産地(伊勢崎、秩父、足利、八王子など)は、デパートが演出する「流行」に応じるために熾烈な競争をしながら、デザインと技術のレベルを高めていった。その結果、アール・ヌーボーやアール・デコなどヨーロッパの新感覚デザインが取り入れられ、「解し織り」(経糸をざっくりと仮織りしてから型染め捺染した上で織機にかけて、仮糸を解しながら、緯糸を入れていく技法)など技術の進歩によって多彩な色柄を細かく織り出すことが可能になった。こうして、従来の着物とは感覚的に大きく異なる、華やかで斬新な色柄の銘仙が大量に市場に供給され、銘仙は都市大衆消費文化を代表する女性衣料としての地位を確立する(三橋2010)。


【写真1】銀座4丁目交差点(昭和7年=1932年)
出典:石川光陽『昭和の東京 ―あのころの街と風俗―』(朝日新聞社 1987年)

【写真1拡大】

【写真1拡大】
写真1は、1932年(昭和7)の銀座4丁目交差点である(石川1987)。男女とも和装・洋装さまざまな服装の人が行き交い、この時代の服飾文化の豊かさを思わせる。右側、仲良く連れ立った2人の女性の1人は、典型的なモガ・ファッションだが、もう1人は大きな麻の葉柄の振袖で、おそらく銘仙と思われる。また左側の袴姿の女子学生の着物は直線を交差させたアール・デコ風の銘仙だと思う。そしてその右の男の子を連れた母親は縞お召、もしくは縞銘仙を着ていると思われる。
この時代における銘仙・お召の流行が見て取れるが、日本近代の服飾史を洋装化の歴史としか見ない従来のファッション史のほとんどは、モガの出現に注目するあまり、この時代が大衆絹織物の普及による女性の和装文化の全盛期であったことを見落としている(註1)。
日中戦争から太平洋戦争の時代(1937~45)になると、軍服や国民服の着用によって男性の洋装化が進行する。また戦時体制への移行にともない繊維・衣服の統制が行われ、「贅沢は敵だ!」のスローガンのもと、女性の和装文化が抑圧されていった。また、戦地に赴く男性に代わる労働力として、「非常時」への対処として、女性の衣服にも活動性が求められ、そうした社会的要請から着物の上に履くズボン型衣料としての「もんぺ」が普及する。そして、戦争末期には、アメリカ軍の空襲によって繊維製品生産と流通機構が破壊されてしまう。
戦後混乱期(1945~51)は、戦災による物資の欠乏に始まり、繊維素材・製品の統制が衣料品の不足に輪をかけた。そうした中、日本を占領した進駐軍がもたらしたアメリカ文化への崇拝、日本の伝統文化否定の風潮が強まり、和装は旧態の象徴になっていく。その結果、戦時中に進行した男性の洋装化に加えて、女性の家庭外での洋装化が大きく進行する。
そして高度経済成長期(1960~75)になると、経済効率を優先した社会システムの画一化が進む。衣服における画一化はすなわち洋装化であり、企業にでも学校でも洋装が一般化・標準化する。同時に、家庭生活の洋風化も進行し、それまでは外では洋装、家では和装が主流だったのが、家庭内においても男女ともに洋装化が進んだ。
こうして、和装は生活衣料としてのポジションを失っていった。その時期は、地域によって差はあるが、東京などの大都市では1960年代後半から70年代前半の時期に押さえることができると思う。
2 女性着物の多層性の崩壊
1960年代後半から70年代前半に起こった注目すべき現象のひとつは、女性着物の多層性の崩壊である。
(表1)着物の階層性

着物を着る場が大きく狭まった結果、礼装・社交着としての着物は残ったものの、街着・家内着・労働着としての着物(お召・銘仙・木綿・麻)は洋装に取って代わられ衰退した。新たに茶道などの「お稽古着」が登場し、色無地や江戸小紋が好んで用いられるようになる。また、本来は家内着だった紬は高級化して社交着化する。階層性の崩壊と同時に、着物の材質も多様性が失われ、木綿・麻・ウールなどは、ごく一部が高級化して残った以外は姿を消し、着物と言えばほとんどが絹という状態になっていく。
3 「着付け教室」の登場と規範化
この時期に起こったもうひとつの注目すべき現象は「着付け教室」の登場である。1964年(昭和39)に「装道礼法きもの学院」が、1967年に「長沼静きもの学院」(当時は「長沼学園きもの着付け教室」)が、そして1969年には「ハクビ京都きもの学院」が創立され、「着付け教室」として全国的に展開していく。現在に続く大手の「着付け教室」が1960年代後半に創立されたことは偶然ではなく、それなりの社会的理由が有ったからだと思われる。
男性の着付けに比べて女性の着付けは帯結びが複雑・多様であるが、それにしても、着物の着付け、帯の結び方は、母や祖母から娘が生活の中で教わり習い覚えるもので、月謝を払って習うようなものではなかった。しかし、戦中・戦後混乱期に着物を思うように着られなかった女性が母親になった時、成長した娘に着物の着付けを伝授できない事態が発生したと思われる。
たとえば、1925年(大正14)生まれの女性は、戦間・戦後混乱期(1941~50)には16~25歳だった。23歳で娘を産めば、1967年には母親42歳、娘19歳である。成人式が間近になった娘に着付けを教えようと思っても、自分の和装経験が乏しく自信がないというようなケースである。祖母がいれば助けてもらえるだろうが、都会で核家族となると、そうもいかない。どこか教えてくれる所はないだろうか?
この時期に「着付け教室」が次々に創立された背景には、そうした戦争による母から娘へという和装文化の継承断絶が生んだ需要があったのではないだろうか。
着物の着付けは、いたって不器用な私の経験からして、単に着るだけなら、3日も習えば、なんとか着られるようになり、後は反復練習である。器用な人なら1日で覚えられるだろう。しかし、それでは月謝を取って教える「着付け教室」の経営は成り立たない。したがって、「着付け教室」では手っ取り早い簡便な着付けを教えず、いろいろと複雑な手順で教える。さらにごく日常的・庶民的な着付け法ではなく、戦前の上流階級の着付け法をベースにして伝授する。その方が付加価値が高いからである。
実際、この時期の著名な着付け指導者には、戦前の上流階級の女性が多かった。1970年にベストセラーになった『冠婚葬祭入門(正)』(カッパ・ホームス)で「着付け」法を広めた塩月弥栄子(1918~)は裏千家14世家元碩叟宗室の娘であり、1973年から「ハクビ総合学院」の学長を務めた酒井美意子(1926~99)は旧加賀藩主で侯爵の前田利為の娘で、旧姫路藩主で伯爵の酒井忠元の妻だった。
こうした戦前の上流階級の女性たちによって、自分で働かなくてよい上流階級の「奥様」「お嬢様」の非活動的な着付けがマニュアル化され、「着付け教室」で教えられ規範化していった。その結果、着物の着方がすっかり様式化し「こう着なければいけない」という形ができ上がる。
本来、生活衣料であった着物には、その状況に応じた着付け方があった。働く時には身体を動かしやすいように楽に緩めに着付けし、たくさん歩く時には裾がさばき易いように合わせを浅めにしてやや裾短かに着付けるなどといった着付けの融通性が失われてしまった。こうして、働けない、身動き不自由な、皺ひとつ許されないきっちりした、着ていて苦しい着物の着付けが成立する。
習わなければ自分で着られない衣服は、もう日常の生活衣料とは言えない。こうした過程をたどって、着物は日常の衣服としての機能を喪失していき、特別な場合、たとえば、お正月、冠婚葬祭(成人式、結婚式、葬儀、法事)などの非日常の衣服となり、あるいは特殊な職業の人(仲居、ホステスなど)の衣服になってしまった。
Ⅱ 「美しい着物世界」の成立
1 高級化と「美しい」の規範化
着物が生活衣料の地位を失い、特別な衣服になったことで、着物の生産・流通業界は、安価な大量生産中心から高価な少量生産へと転換していく。かっての主役だった銘仙やお召はまったく見捨てられ、手作業のため少量生産しかできなかった各地に残る紬が見出され、そのいくつかが付加価値がある織物として高級品化していった。
たとえば、1933年(昭和8)に秩父産の模様銘仙は5円80銭~6円50銭だった。当時の6円は現代の21000~24000円ほどと考えられ、中産階層なら1シーズン1着の購入が可能な値段だった(三橋2010)。ところが、1999年(平成11)に八丈島特産の黄八丈の反物は48万円もした。平均的な収入の人だったらローンでも組まない限り購入は難しい。
こうした着物の高級品化時代に主な情報媒体となったのが婦人画報社(現:ハースト婦人画報社)の『美しいキモノ』(1953年創刊・季刊)に代表される着物雑誌である。この種の着物雑誌の中身は、高価な着物のオン・パレードであり、安価な着物やまして古着などはけっして登場しない。高価な着物を売りたい着物業者と、そうした高価な着物を購入できる富裕な奥様・お嬢様の「美しい」「上品な」着物世界である。私はこれを「美しい着物世界」と呼んでいる。
「美しい着物世界」の特徴は、誌名通り「美しさ」と「着物」とが過度に結合したことである。『美しいキモノ』は、創刊以来毎号、高価な着物を着た女優さんが表紙を飾るのが通例で、中の誌面もほとんどがプロのモデルの着物姿である。その姿はたしかに美しく、なるほど誌名にふさわしい、と思ってしまう。しかし、着姿が美しいのはもともと美しい女優やモデルが着ているからであって、同じ着物を一般の女性が着ても必ずしも美しくなるとは限らない。
着物が日常の衣料であった時代、そんなことは考えるまでもなく誰もが解っていることだった。ところが、着物が非日常の衣服になるにつれて、わざわざ着物を着て特別の装いをするのだから、きっと美しくなるに違いない、というある種の期待が生まれてくる。実際にはそうなる場合もそうならない場合もあるわけだが、着物業界は、そうした期待感を利用して、着物雑誌の誌面を通じて「着物を着ている人は美しい」というイメージを流布し、「着物を着れば美しくなれる」さらに「高価な着物を着ればより美しくなれる」という幻想(錯覚)を喚起し、売り上げの向上につなげるという戦略をとった。
「着物を着ている人は美しい」というイメージは、やがて「着物を着ている人は美しくなければならない」という非現実的な意識に転化していき、必ずしもそうならない女性たちを着物世界から遠ざけることになった。
2 色・柄の衰退
日本の女性の和装文化は、江戸時代には遊廓の高級遊女(花魁)がファッションリーダーであり、明治以降も芸者をはじめとする玄人筋が大きな比重を保っていた。着物が生活衣料としての地位を失っていく時代になっても着物を着続け、着物業界の売り上げのかなりの部分を担ったのは銀座や北新地に代表されるクラブ・ホステスたちだった。にもかかわらず、「美しい着物世界」では、こうした玄人の着物は徹底的に無視・排除される。間違っても「銀座クラブママの着こなしに学ぶ」などという特集は組まれない。
「美しい着物世界」の着物のコンセプトは、あくまでも「上品」である。これを意訳すれば「玄人っぽくない」ということになる。具体的には、色味の弱い色、小さ目の柄、つまり自己主張の弱い「控えめ」が上品とされる。色については、原色や強い色は忌避され、薄い色、さらには無彩色(白・黒・グレーの濃淡、銀)が好まれる、柄は巨大柄・大柄が避けられ、比較的小さめの柄を反復する小紋や、細かな点で小さな意匠を全面に置く江戸小紋、さらには柄が消失した色無地が好まれるようになる。また、日本の伝統的な意匠である縞も、太縞や棒縞のようなシンプルで大胆なものは忌避され、細縞やよろけ縞のような控えめなものが好まれる。太縞や棒縞がもつ粋なイメージが玄人(粋筋)を連想させるためと思われる。
こうした傾向は着物の階層性が崩壊し、「お稽古着」の比重が増した結果、万事派手を嫌い、地味を上品とする茶道の世界の「趣味」が着物全体に影響を及ぼすようになったことが作用していると思われる。その結果、戦前の着物に比べて、現代の着物は、色は淡く、柄は小さく、色柄のバリエーションが少なくなり、創造性が失われ類型的となり、個性的でなく画一化が進んでしまった。服飾デザインという見地からすれば、明らかな退化であるが、商業的にはそうした無個性な無難な着物でないと売れなくなってしまったのである。
3 高級化の帰着と「趣味の着物」
こうした着物の高級化は、着物の世界をますます狭めていった。何10万円という衣料を次々に購入できるような富裕層がそんなに多いはずはない。「和装が好き、着物を着たいけど高くて手が出ない」という階層の方がずっと多かった。それでもバブル経済期(1980年代後半)はまだよかった。驚くほど高い着物が売れた。たとえば、染色家の久保田一竹(1917~2003)の一竹辻が花の訪問着が1200万円とか。しかし、購入された高価な着物が実際に着られたかというと必ずしもそうでもなく、多くは「箪笥の肥やし」と化し、着物世界が再び拡大することにはつながらなかった。そして、バブル崩壊後、着物業界は大量の在庫を抱えたことに加えて、バブル期の「箪笥の肥やし」がリサイクル市場に放出されることで、新規需要の落ち込みに苦しむことになる。
ところで、1980年代には「趣味の着物」を看板にする店が現れる。目の肥えた顧客を相手に、普及品ではなく高級紬や作家物など厳選された商品を扱う店である。しかし、この「趣味」は、「はじめに」で紹介した辞書の②の意味「どういうものに美しさやおもしろさを感じるかという、その人の感覚のあり方。好みの傾向」と解釈すべきだろう。「良いお着物の趣味でいらっしゃいますわね」の「趣味」である。この時点では、「仕事・職業としてでなく、個人が楽しみとしてしている事柄」という①の意味での「着物趣味」はまだ成立していなかった。
4 男性の和装の(ほぼ)絶滅
写真2は、1959(昭和34)正月のある一族(東京在住)の集合写真である(小泉2000)。
.jpg)
【写真2】ある一族のお正月(昭和34年=1959年)
出典:小泉和子『昭和のくらし博物館』(河出書房新社 2000年)
成年女性8人はすべて和装である。これに対して成年男性4人は家長と思われる1人が和装なだけで他の3人は洋装である。また子供たちも女児6人が和装4、洋装2であるのに対し男児2人はいずれも洋装だ。つまり、男性の和装はおじいちゃんだけという状態で、男性の洋装化=和装の衰退が女性のそれよりもかなり早く進行したことがはっきり見てとれる。
お正月ですらこの状態なのだから、平常時において男性が和装する機会はいよいよ乏しくなっていった。歌舞伎役者、茶道家、落語家、棋士など一部の限られた職業の男性の需要に応じた生産は続けられていたが、1970年代後半から80年代になると、男性の着物は高級品を除き店頭から姿を消していく。和装趣味の青年が着物を着たいと思っても、(彼の手が届く範囲では)「どこにも売っていない」状況になり、着付けのマニュアル本からも男性向けの記述はほとんどなくなってしまう(早坂2002)。こうして、1980年代後半から90年代前半には、男性着物はほぼ絶滅状態になり、着物は女性の物という社会認識が定着し、着物世界におけるジェンダー的な乖離は極限に達した。
こうして、着物趣味の成立の第1の要件である日常衣料としての地位の喪失は、少なくとも1980年代末には完全に達成されていた。しかし、まだこの時期には、着物世界の人間関係は、着物を売る着物屋と着物が好きで買う客の商業的関係であり、着物好きの客同士の横のつながりは、ほとんどなかった。第2の要件である着物好き同士の横のつながりができるまでには、もう一段階が必要だった。
Ⅲ 情報革命と着物世界 ―趣味化への胎動―
1 「着ていく場所がない」
着物を着て家を出ると、顔見知りの近所の奥さんに「あら、お着物でお出かけ? 今日は何かありますの?」と興味津々に尋ねられる。多くの着物好きの女性が経験したことだ(男性の場合はさらに不審がられて声も掛けられない)。1990年代になると、日常性を完全に喪失し衣服として特殊化してしまった着物には「着る理由」が必要とされるようになってしまった。「ただ着物を着たい」、「着て出かけたい」ができない状況が生じたのである。
「近所でジロジロ見られるので、着物で出掛けられない」、「変わり者扱いされるので(着物のことは)周囲の人に黙っている」、そんな話を聞いて「なんだ、女装と同じではないか?」と思ったことがある。冗談ではなく、1990年代には、着物のファッション・マイノリティ化はそこまで進行していた(三橋2006)。
実際、堂々と着物を「着られる場所」「着る機会」は少なかった。お正月は年に1度だし、結婚式に呼ばれる機会もそうはない。そうした状況の中で、「鈴乃屋」や「三松」のような大手の着物チェーンが「着物を着る場」としてイベントを企画・開催するようになる。しかし、お商売だから当然なのだが、そうしたイベントは着物展示会と併設されていたり、そうでなくても「お出かけ」の度に着物を作ることを勧められ、結局、多大の出費をすることになる。そうした制約なしに、「気楽に着物を着る場・機会があればいいのに」と、着物好きの多くが思うようになっていた。
2 パソコン通信からインターネットへ
1997年8月、パソコン通信「NIFTY-Serve」の中に「きものフォーラム」が開設される。「NIFTY-Serve」のサービス開始(1987年4月)から10年も後のことだった。そして11月25日には東京赤坂の「全日空ホテル」で「きものフォーラム」の「オフ会」(オフライン・ミーティング)が20名の参加者で開催された(早坂2002)。
これはパソコン通信と趣味の世界の結合としてはかなり遅い。たとえば女装趣味のパソコン通信「EON」(主宰:神名龍子)は1990年に創立され、その活動を通じて1995年頃にはすでに「電脳女装世界」ともいうべき女装仲間の横のつながりが形成されていた。1996年4月に開催された「EON」ボード上に設置された「クラブ・フェイクレディ(CFL)」(主宰:三橋順子)の「オフ会(FL3)」には77名が参加している。そんなものと比較するなと言われるかもしれないが、パソコン通信を通じての仲間の結合という点で、この時期の「着物仲間」は「女装仲間」よりもずっとマイナーな存在だったことがわかる。
1996~97年頃から日本でもようやくインターネットが盛んになると、1997年に秋田県在住の「澤井夫妻」がインターネット上に「きものくらぶ」を開設する。これが日本最初のインターネット着物サイトと思われ、私が最初にアクセスした着物サイトも「きものくらぶ」だった。同年12月には早坂伊織氏が「男のきもの大全」を立ち上げ、これが最初の「男着物」専門サイトになった。
こうして、パソコン通信、次いでインターネットを媒介にして、日本各地に孤立、散在していた「着物好き」が結びつき、仲間化していくことになる。
3 「男着物」の復活と男性主導の「オフ会」
パソコン通信時代から代表的な「着物好き」として活躍する早坂氏の本業が「富士通」のシステムエンジニアだったように、また「きものフォーラム」の中に「男のきもの」会議室が設置されたように、パソコンの普及度、パソコン通信やインターネットへのアクセス率は、その初期においては男性の方が圧倒的に高かった。したがって、インターネットによる仲間化や「オフ会」の開催は男性が先行する。
早坂氏が主催する男着物の「オフ会」である「男のきもの大全会」が開催されたのは1998年10月だった(参加者50名)。1999年12月には、毎週土曜日に着物男性が銀座に集まる「きものde銀座」の第1回が開催される(参加者14名)。この集まりは1999年11月に開催された第2回「男のきもの大全会」から派生したものだった(早坂2002)。
こうした経緯をたどって、1990年代末に、ほぼ絶滅状態だった男着物が復活し仲間同士の横のつながりが形成されていった。1990年代末から2000年代初頭にかけて、着物趣味成立の第2の要件が整ったことになる。
4 「ふだん着きもの」への志向
「インターネットきもの」の初期に多くのアクセスを集めたサイトに「あみさんのきもの」(主宰・鳥羽亜弓)があった。このサイトの特徴は、地方在住の子育て中の主婦が毎日着物を着て生活しているという「特異性」にあった(鳥羽2001)。着物で日常を過ごし、家事を行い、子供を育てるという戦前期の日本の多くの主婦がしていたことが、すっかり特異なことになってしまったのである。
2002年に『天使突抜一丁目―着物と自転車と―』を出版したマリンバ奏者の通崎睦美も、着物で自転車に乗るという「特異性」で注目された(通崎2002)。明治~大正期のハイカラ女学生がごく普通にしていたことなのに。
また、現代風俗研究会の古参会員である磯映美は、「華宵」の名義で、2001年から2003年にかけて、散歩きもの普及員会ニュースレターとして「着物で、ぶらぶら」を刊行した。
こうした「ふだん着着物」、あるいは日常的な「着物暮らし」への志向は、日常性を喪失した和装文化に反発・逆行するものであり、その方向性はその後の「趣味化」の中に受け継がれていくことになる。
Ⅳ アンティーク着物ブームと「着物趣味」の成立
1 女性主導の「オフ会」の盛行
当初、男性主導だった着物「オフ会」も、女性のインターネットアクセス率が上がるにつれて、女性の参加が増加していった。男性主導の「オフ会」には、男性だけで語り合いたいホモ・ソーシャルなタイプと、主催者が「女好き」で積極的に女性の参加を勧誘するタイプとがあった。2000年頃に何度か開催された村上酔魚堂の「オフ会」は後者のタイプだった。
.jpg)
【写真3】「村上酔魚堂・浅草オフ会」(2000年9月)。
ここで後の「うきうききもの」の初期中核メンバーが出会う
そうした場で着物好きの女性たちが知り合い、その横のつながりをベースに、2001年頃から女性主導の「オフ会」が盛んに開催されるようになる。その代表は、東京を中心とした首都圏では「うきうききもの」(主宰:古川阿津子、2001~10)、京都を中心とした関西圏では「夏海の遊び着」(主宰:夏海、2001~ )であり、最盛期には月に数回ペースで「オフ会」を開催した。
-5d3a9.jpg)
【写真4】「うきうききもの」秩父銘仙オフ会(2002年4月)。
中央が主宰の「あつこ女将」
こうした「オフ会」は心置きなく好きな着物を着られる場であり、着物に関する様々な情報や工夫が交換され、またお互いの着こなしが参照され相互に影響を与えあった。そして、「オフ会」の様子がインターネットサイトにレポートされることで、新しい参加者を引きつけていった。2000年代前半は、インターネットと「オフ会」を通じて、女性の着物仲間が横のつながりを形成していった時代だった。
私も参加した「うきうききもの」では、初期のメンバーの間には、既存の着物世界への飽き足らなさ、不満が共通意識としてあった。地味=上品に固定化され、「着付け教室」が作り上げた厳格な着用規範に反発し、「もっとどんどん、自由に、楽しく着物を着たい!」「(ミセスだって)派手な着物を着てもいいじゃない!」という思いである。「美しい着物世界」とまったく異なる着物への志向・嗜好がそこにはあった。
2 アンティーク着物ブーム
女性主導の「オフ会」の盛行とほぼ時を同じくして、アンティーク着物ブームが起こる。その火付け役は「別冊太陽」(平凡社)の「昔きもの」シリーズだった。2000年3月の『昔きものを楽しむ(1)』に始まり、『昔きものを楽しむ(2)』(2000年11月)、『昔きものと遊ぶ』(2001年8月)、『昔きものを買いに行く』(2002年12月)、『昔きものの着こなし』(2003年4月)、『昔きもの 私の着こなし』(2004年5月)とほぼ1年1冊ペースで計6冊が刊行された。
このシリーズ、最初は「骨董を楽しむ」シリーズの1冊として刊行されたように、骨董的な価値のあるアンティーク着物を「収集して楽しむ」というスタンスだった。ところが途中から、アンティーク着物を「着て楽しむ」という方向に変化していった。表紙も最初は着物の意匠だったのが、3冊目の『昔きものと遊ぶ』は着姿になっている。
「別冊太陽」の「昔きもの」シリーズによってアンティーク着物への関心が急速に高まり、骨董屋や骨董市の露店で、古い着物を漁る人々が出現するようになる。とくに現代の着物に比べてデザイン性に富み、派手な色柄の銘仙やお召が注目され、それまで二束三文(500円以下)だった銘仙の古着がたちまち値上がりしていった。
そうして探し出し手に入れた古着を洗い繕って、場合によっては仕立て直す。手間暇を惜しまない。そして、その着物を「オフ会」で仲間たちにお披露目する。すると、「わ~ぁ、すてき、どこで手に入れたの?」「いくらだった?」と仲間から質問が飛ぶ。「○○の露天市でね、500円だったの。けっこう汚れていたから(着られるようにするのが)大変だったけど…」。こう答えるとき、それまでの労苦が報われ、ある種の達成感がある。
探す→洗う・直す→着る→仲間に見せる、このサイクルが毎月のように繰り返される。傍目から見れば、いい大人の女性が古着を漁り集め、着ることに夢中になっているわけで、いったいウチの娘(もしくは妻)は何をしているのだ、と呆れられることになるが、まさにそれが「趣味」なのである。
2002年6月には、アンティーク着物に特化した着物雑誌『Kimono道』(祥伝社、後に『Kimono姫』と改題)が創刊される。そのコンセプトは「アンティーク&チープ」であり、表紙に記されたリードは「キモノのはじめてはアンティークから」だった。
アンティーク着物の場合、値上がりしたと言っても、せいぜい1000円から5000円程度で千の桁で納まり、万の桁になることは少なかった。稀に数万円という高級アンティーク着物もあったが、当時、市販の現代着物の多くは20~50万円の価格帯だったから、それでも10分の1である。30万円の現代着物1枚を買う値段で、露天商から3000円のアンティーク着物が約100枚買える計算になり、すさまじい価格破壊ということになる。
安価なアンティーク着物がブームになったことは、それまで経済的な理由で着物を思うように着られなかった「着物好き」にとっては大きな福音であり、とくに20代、30代の比較的若い人たちが着物世界に参入できるようになった。20世紀後半の50年間一貫して長期低落傾向にあった着物人口は、21世紀に入って一時的にせよ増加に転じたのである。これは「趣味化」というある種の「突然変異」かもしれないが、長い和装の歴史の中で、やはり画期的なことだと思う。
2000年代のアンティーク着物ブームによって、東京白金の「池田」、原宿の「壱の蔵」などのアンティーク着物専門店はおおいに賑わい、コレクターとしても知られた店主の池田重子(1925~)や弓岡勝美の名も高まった。とりわけ池田は、新宿伊勢丹や銀座松屋などで「池田重子コレクション―日本のおしゃれ展―」(1993~2011)を何度も開催し、アンティーク着物の社会的認知を高めた。池田のコレクションとコーディネートは、アンティーク着物ファンの垂涎の的になった。
また、リサイクル着物の「ながもち屋」や「たんす屋」がチェーン展開するのもこの時期である。しかし、アンティーク着物ブームは既存の着物業界にはほとんど影響しなかった。
3 銘仙への注目
アンティーク着物ブームの中で、とりわけ人気度が高かったのが銘仙だった。銘仙とは、先染(糸の段階で染める)、平織(経糸と緯糸の直交組織)の絹織物である。その詳細については別稿に譲るが(三橋2002,2010)、大正~昭和戦前期においては、安い価格と豊富な色柄が、中産階層のお嬢さんの普段着、女中さんの晴れ着、もしくは、女教師の銘仙+女袴(行燈袴)、牛鍋屋の仲居の赤銘仙、カフェの女給の銘仙+白エプロンといったような職業婦人の仕事着として好まれ大流行した。戦後も生産は続いたが、主な着用層だった「お嬢さん」や職業婦人が真っ先に洋装化したこと、粗悪品の流通によりイメージが低下したことで徐々に衰退した。それでも、大柄で色鮮やかな模様銘仙は、自分を「広告塔」にする女性、具体的には「赤線」(黙認買売春地区)の「女給」(実態は娼婦)たちに愛用された。
着尺としての銘仙の生産は、1960年代末までにほぼ途絶え、工場生産品ゆえに伝統工芸・美術品になることもなく、技術もほとんど断絶してしまった。つまり、銘仙はいったん滅んだ織物だった。
ところが、アンティーク着物ブームにより、女性の和装文化の最盛期だった大正・昭和初期の着物文化が再評価された結果、その最盛期を担った銘仙がにわかに注目されるようになる。2002年1月に主要産地だった埼玉県秩父市に初めての銘仙資料館「ちちぶ銘仙館」がオープンし、それを受けて2003年5月に三橋順子が「艶やかなる銘仙」を『Kimono姫』2号に執筆した(三橋2002)。2003年6月には銘仙コレクターの木村理恵と通崎睦美の「銘仙コレクション2人展」が東京中野の「シルクラブ」で開催される。そして2004年12月には秩父市在住の木村理恵のコレクションを紹介した『銘仙―大正・昭和のおしゃれ着―』が「別冊太陽」(平凡社)の1冊として刊行され、銘仙ブームはひとつの頂点を迎える。
その後も銘仙ブームは続き、銘仙をメインにした企画展が各地で立て続けに開催された(註2)。そして、2009年5月には銘仙を主な展示品とする「日本きもの文化美術館」が福島県郡山市にオープンし、2010年4月には同美術館から『ハイカラさんのおしゃれじょうず-銘仙きもの 多彩な世界』が刊行された。
こうした銘仙ブームは、現代の着物にはまったく失われてしまった大胆で前衛的な大柄と、原色を多用し多色を巧みに配した強烈な色彩感覚が作り出す華やかで艶やかなイメージに多くの着物好きが魅せられたからであり、銘仙そのものが現代着物へのアンチテーゼとなっている。銘仙のそうした性格は、2000年代に成立する「着物趣味」の方向性と合致し、それゆえに重要なアイテムとなったのである。
4 「規範」を越えて ―「着物趣味」の成立―
2000年代前半のアンティーク着物ブームの中で成立する「着物趣味」の基本コンセプトは、大正・昭和戦前期の着物文化の再評価とそれへの回帰である。それは、1970年代以降に形成された地味=上品に固定化された「美しい着物世界」や、「着付け教室」が流布する厳格な着用規範への反発と表裏一体だった。それはまた、すっかり特別な場の衣服になってしまった着物から、本来の日常性を取り戻す方向性だった。和装文化の伝統を意識しつつも、戦後の着物世界が作り上げた規範から自由に、好きな着物を着たいように着る、というスタンスだ。
日本の女性着物は、既婚か未婚かの区分が明瞭で、それが身分標識にもなっていたが、アンティーク系の場合、そうした境界も越えてしまう。ミセスであっても、派手な着物、目立つ帯を厭わない。振袖だって着てしまう。白半襟、白足袋という「美しい着物世界」の「常識」に対し、色半襟・刺繍半襟、色足袋・柄足袋が好まれる。着物と帯、そして小物類(半襟、帯揚、帯締、足袋)の色合わせ・柄合わせや帯結びに凝る。髪も、お正月やイベントには、すでに見かけることも稀になった日本髪を結う。
「美しい着物世界」の人に比べて行動性が高いので、着付けも前合わせは浅く、したがって襟のy字は深く半襟をたくさん露出し、襟もかなり抜く。「着付け教室」で「下品なのでやってはいけません」と教えられることばかりである。そして、いつでも(仕事以外)どこにでも着物で出掛ける。休日、近所に買い物に行くのも着物だし、国内旅行はもちろん、海外旅行も着物で行く。履物は、たくさん歩くので、草履より下駄が好まれる。なにより、着物も帯も「値段の高きをもって貴しとせず」で、その人の個性に合ったコーディネートや創意工夫が評価される。
こうした方向性・嗜好は、ほとんどすべて「美しい着物世界」への明確なアンチテーゼである。したがって、当然のことながら、従来の規範を順守する「美しい着物世界」の人たちからの反発も大きかった。ネット上で「ぼろ着て何が楽しいの?」「お女郎さんの集まり」「座敷牢から抜け出してきたみたい」と批判されるのは常のことで、銀座で集まっていた時、見知らぬ中年女性(洋装)にいきなり「ここは銀座なんだから、日本の恥になるようなみっともない着方はしないで!」と面と向かって言われたこともあった。単なる好奇の視線には慣れっこだが、さすがに「日本の恥」とまで言われるとは思っていなかった。
しかし、そこまで強く反発されるということは、従来の着物世界の規範を越えた、新しい、そして特有の方向性が成立したということである。既存の着物世界から批判されたことで逆に「私たちの着物趣味とはこうなんだ、これでいいんだ」という意識が仲間たちの間で共有化されていった。こうして、第3の要件が満たされ2000年代前半に新しい「着物趣味」の世界が成立した。
-9cd66.jpg)
【写真5】アンティーク銘仙のコーディネート。
モデル:(左)小紋、(右)YUKO
2人とも「アラフォー」のミセス(2005年3月)
Ⅳ 新しい着物世界
1 着物趣味イベントの開催
2000年代中頃になると、「着物趣味」の成立を背景に、従来の「オフ会」からさらに発展した着物趣味イベントが開催されるようになる。ここでは東京で開催され、私も参加したことがある代表的な2つの着物趣味イベントを紹介してみたい。
① 「きものde銀座」
「きものde銀座」は毎月1度銀座で開催される「着物好き」の集会イベントで、「男のきもの大全会」の派生イベントとして1999年12月に第1回が開催された。最初は毎週土曜日開催、着物男性だけの集いだったが、2000年2月からは月1回(毎月第2土曜)となり、着物女性も参加するようになった。主催者はなく、当初は「旦那さん」(牧田氏)が事務局を担当していたが、2006年以降は有志の当番制で運営している。着物で集まる人も会員制ではなく、まったくの任意参加である。
15時に銀座4丁目交差点「和光」前で待ち合わせ、「歩行者天国」の中央通りを1丁目方向に歩き「ティファニー」前で集合写真を撮影、その後は自由行動で、なにかイベントがあれば行きたい人はまとまって行く。17時半頃から「土風炉・銀座1丁目店」で懇親会(会費3000円)となり、20時前後にお開き、希望者は二次会へという毎回同じスケジュールで、途中参加・離脱も自由である。
コンセプトは文字通り「銀座で着物を着る」ということだけ。参加者の着物のスタイルもアンティーク系、「ふだん着着物」系から「美しい着物」系まで様々であり、どんな着方であっても批判しないことになっている。
2008年4月8日に第100回を迎え、2013年12月には168回となる。台風でも大雪でも中止せず(連絡方法がないため)、東日本太平洋沖大地震の翌日(2011年3月12日)にも20数名の参加者で開催された。最初期には参加者1名ということもあったが、近年は集合写真を見る限り40~60名くらいだろうか(註3)。
主催者がいない有志持ち回りの運営と、参加も着方も自由度が高い「緩い」形態が「着物趣味」のイベントとして最も長続きしている秘訣だと思う。
-944a6.jpg)
【写真6】第100回「きものde銀座」(2008年4月8日)
.jpg)
【写真7】2009年1月の「きものde銀座」。
日本髪を結い大振袖を着て築地・波除神社に初詣
② 「日本全国きもの日和」
「日本全国きもの日和」は、「きものであそぼう」をスローガンにした着物ファンの手作りイベントで、「玉龍」こと西脇龍二氏を中心とした「実行委員会」が運営している。メンバーの多くは「きものde銀座」で出会っている。11月3日を「きもの日和」として全国各地で着物イベントの開催を呼びかけ、第1回は7都市、第2回は20都市、第4回は25都市で「きもの日和」が開催され、「着物趣味」の地方への波及に大きな役割を果たした(註4)。
メイン会場である「きもの日和TOKYO」は、恵比寿のイベントホール「EBIS303」で2004年から2008年まで5回開催され、入場者は第1回が1500人、第3回(2日開催)は3000人だった。モデルもスタッフもすべて着物仲間で構成する本格的な「きものファッションショー」は観衆の注目の的だった。さらに、着物写真集『Kimono人』(2005、2006、2007の3冊)を自費出版した。
また、中心メンバーは、毎年5月に開催される静岡県下田市「黒船祭」に出張し、「賑わいパレード」に参加し、野外ファッションショーを開催している。
しかし、2007年の第4回から入場者、出店、広告が減少し赤字となり、経済不況(リーマン・ショック)もあって2009年11月に計画された「きもの日和TOKYO」は延期になってしまう。2010年3月に「きもの日和with目黒雅叙園」として開催されたが、2011年4月の開催予定が東日本大震災の影響で中止になった後は復活していない。
-5318c.jpg)
【写真8】「きもの日和TOKYO 2004」の冊子(2004年11月
-c5c3c.jpg)
【写真9】「きもの日和TOKYO」の「きものファッションショー」(2006年11月)
-c92c7.jpg)
【写真10】「下田黒船祭」の野外ファッションショー。
「ペリー・ロード」の橋の上が舞台(2007年5月)
-ddbca.jpg)
【写真11】「下田黒船祭」の賑わいパレード(2008年5月)
日本髪は美容院ではなく自分で結う
2 着物イベントの問題点
着物イベントに参加して、気付いた問題点を整理しておこう。第一はお金の問題である。「きもの日和TOKYO」のように、意欲的に活動を展開した結果、イベントの規模があまりに拡大してしまうと、集客や採算のような「趣味」とは性格が異なる要請が発生してしまう。また必要な経費が大きくなれば、経済・社会情勢の影響を大きく受けるようになる。「趣味」とは本来、浪費だが、あまり補填しなければならない金額が大きくなると、「趣味」の仲間では耐えられなくなる。といって、企業の協賛・支援を受ければ、商業資本の論理が入ってきて、ますます「趣味」の領域から外れてしまうジレンマがある。「趣味」としては拡大路線一筋ではなく適正規模を保つことも必要だと思う。
第2は、着物イベントのジェンダー的な構造問題である。端的に言えば、リーダーシップをとる男性、イベントの「華」としての女性という基本構造がそこにある。たとえば、ファッションショーやパレードで、男性リーダーの指示で若手の女性や美しい女性が目立つ場所に配される傾向は明らかにあった。それもまた社会的要請なのかもしれないが、必ずしもそうでない女性たちからは不満が出ることになる。
第3は、セクシュアリティの問題で、大人の男女が集まり、懇親会などでお酒が入ると、男性による女性へのセクシュアル・ハラスメントが発生する。その場合、運営側の男性のセクハラ認識が甘いと、結局は被害を受けた女性が泣くことになってしまう。
第4は、和装女装趣味の男性の問題で、近年は「女装」を禁止する着物イベントが増加している。和装文化に女形が貢献してきた度合いを考えれば、まったく理不尽と言いたくなる。そして、「女装禁止」の結果、日常的に女性として生活しているMtF(Male to Female)のトランスジェンダーまでが排除されることになってしまう。これは性的マイノリティに対する不当な社会的排除である。
第5は、高齢化の問題で、他の趣味の世界と同様に若い人がなかなか入ってこない。2000年代初頭のアンティークブームを担った30~40歳代は、10年たった現在40~50歳代であり、さらに10年たてば…である。今のままでは先細り傾向は免れないだろう。
これらの問題、とりわけ第2~5の問題は、着物趣味の世界だけの問題ではなく、日本社会が抱える問題の投影である。しかし、比較的柔構造な「趣味」の世界の特性を生かし、しっかりした認識をもって対応すれば、ある程度は改善可能な問題であると思う。
おわりに ―着物趣味の将来―
1 着たい着物がなくなる
現代の「着物趣味」、とりわけアンティーク派にとっての最大の不安は、近い将来、着たい着物がなくなってしまうのではないか、ということである。なんら特徴のない「つまらない」現代着物は巨大なデッドストックがあるのに、着たいと思うようなアンティーク系の着物はどんどん消えていく。和装文化の全盛期(1926~1936)に作られた銘仙・お召は、すでに80年前後が経過し耐用年数が過ぎつつあり、衣類としての寿命が尽きるのはもう遠いことではない。せめて、あと10年もってほしいと思うのだが。
また、現代女性の体格向上により、女性が小柄・低身長だった時代に作られたアンティーク着物を着られる人が減っている。こうした状況で頼りになったのは、2000年代の銘仙ブーム期に足利・伊勢崎などの旧産地で生産された復刻銘仙だった。復刻銘仙は、問屋価格で5~6万円、小売価格では8~10万円になってしまうので、かってのような普及は無理だったが、それでも、私のように身長が高い銘仙好きにはとてもありがたかった。しかし、わずかに残っていた職人さんの高齢化や逝去によって、2010年代初めに生産が途絶えてしまった(註4)。
先染め(糸を染めて柄を織り出す)の織物は技術的に難易度が高く、現状ではいったん絶えた技術の復活は望めそうにない。それが無理なら、せめて「全盛期(昭和戦前期)」のデザインを、後染め(糸を布に織った後で染める)の染物で再現してほしい。幸い現在ではアンティーク着物の色柄をコンピューターに取り込み、補修を加えた後に、インクジェット・プリンターで布地にプリントすることが容易になった。銘仙写しの浴衣や小紋が増えてくれればと思うのだが、現在の着物業界の沈滞した状況では、それも難しそうだ。
2 コスチューム・プレイとして
生産面では大きな不安があるが、着物をファッション・アイテムと考えた場合、その将来に希望はなくもない。
着物が日常の衣服としての機能を失い、着物を着る人がファッション・マイノリティになったことで、社会の服飾規範を超越する、ある種の自由を獲得できた。そもそも着物を着ていることが「変わり者」「外れ者」なのだから、細かな社会規範に縛られることはない。
そう思いきってしまえば、着物は自己主張、自己表現の手段として、そして変身のアイテムとして絶好である。コーディネートに工夫を凝らせば、立派な会社勤めの男性が任侠系の「あぶなそうな兄さん」に、まともな会社のOLさんや良家の奥様が芸者やお女郎上がりの「あやしい姐さん」に変身できる。背景や小道具に気を使えば、あっという間に昭和初期や昭和30年代にタイムワープした写真を撮ることも可能だ(三橋2006)。
-c2fb9.jpg)
【写真12】石仏に祈る村娘(昭和初期風)
モデル:YUKO
撮影:2008年2月、埼玉県秩父市金昌寺

【写真13】「赤線」の女(昭和28年設定)
モデル:YUKO
撮影:20010年10月、東京「鳩の街」旧「赤線」建物(娼館)をバックに
今や着物は、社会的立場を変え、年齢を化けて、時空すら超える力を持つようになった。それを活用しない手はない。21世紀の着物趣味は、こうした「着物で遊ぶ」、コスチューム・プレイとしての方向性をより強めていくことになると思う。
日本人の伝統衣装という路線では、美術工芸品としてはともかく、衣類としての着物はもう生き残れない段階になっている。「着物趣味」の仲間たちが目指してきた創造性のある自己表現のファッション・アイテムという方向こそが、着物という日本人の民族衣装を次の世代に伝える道だと私は思う。
(註1)村上信彦『服装の歴史2(キモノの時代)』(理論社、1974年)だけが、この時代の和装文化の発展に正当な評価を与えている。
(註2)主なものを掲げると、京都古布保存会「京都に残る100枚の銘仙展」(東京世田谷「キャロットタワー」、2005年3月)、須坂クラッシック美術館「大正浪漫のおしゃれ―銘仙着物―」(長野県、2007年8月)、京都府城陽市歴史民俗資料館「銘仙―レトロでモダンでおしゃれな着物―」(京都府、2008年8月)、神戸ファッション美術館「華やぐこころ―大正昭和のおでかけ着物―」(兵庫県、2008年11月)など。
(註3)の公式サイト「着物de銀座」(管理人:京屋悟雀氏)を参照
http://www.kimono-de-ginza.net/sub2.htm
(註4)2013年段階で継続しているものとして「着物日和in信州須坂」「奈良きもの日和」「きもの日和 in TOMO」(広島県福山市鞆の浦)などがある。また「群馬きもの復興委員会」「NPO法人川越きもの散歩」のように、それぞれの地域で積極的な着物普及活動をするグループも増えた。
(註5)京都の着物問屋「きものACT」が現地の職人さんに依頼して生産していた足利銘仙は2010年頃に、NHKの朝の連続ドラマ「カーネーション」(2011年度後期)で話題になった「木島織物」の伊勢崎銘仙は2012年末に生産が止まった。
文献
石川光陽1987『昭和の東京 ―あのころの街と風俗―』(朝日新聞社)
小泉和子2000『昭和のくらし博物館』(河出書房新社)
通崎睦美2002『天使突抜一丁目 ―着物と自転車と―』(淡交社)
鳥羽亜弓2001『浴衣の次に着るきもの(アミサンノキモノ)』(インデックス出版)
日本きもの文化美術館2010『ハイカラさんのおしゃれじょうず -銘仙きもの 多彩な世界-』(日本きもの文化美術館)
早坂伊織2002『男、はじめて和服を着る』(光文社新書)
別冊太陽2000a『昔きものを楽しむ(1)』(平凡社)
別冊太陽2000b『昔きものを楽しむ(2)』(平凡社)
別冊太陽2001『昔きものと遊ぶ』(平凡社)
別冊太陽2002『昔きものを買いに行く』(平凡社)
別冊太陽2003『昔きものの着こなし』(平凡社)
別冊太陽2004a『昔きもの 私の着こなし』(平凡社)
別冊太陽2004b『銘仙 ―大正・昭和のおしゃれ着物―』(平凡社)
村上信彦1974『服装の歴史2(キモノの時代)』(理論社)
三橋順子2002「艶やかなる銘仙」(『KIMONO道』2号、祥伝社。後に『KIMONO姫』2号、2003年、祥伝社、に拡大再掲)
三橋順子2006「着物マイノリティ論」(『Kimono人 2006』きもの日和実行委員会)
三橋順子2010「銘仙とその時代」(『ハイカラさんのおしゃれじょうず -銘仙きもの 多彩な世界-』日本きもの文化美術館)

日常衣料だった「着物」が非日常化し、さらに「趣味化」していく過程を、和装文化の展開を踏まえて、まとめてみた。
欲張った内容なので不十分な点は多々あるが、自分が考える和装文化の衰退と「着物趣味」の成立の流れを、まとめることができたと思っている。
------------------------------------------
「着物趣味」の成立 三橋 順子
【概要】
本来、日本人の日常の衣料であり、洋装化が進んだ戦後においても時と場を限定しながら衣料として機能していた着物(和装)の世界に、2000年頃からひとつの変化が現れる。それは着物の趣味化である。「着物趣味」は戦後の和装世界で形成されたさまざまな規範を超越しながら、ある種のコスチューム・プレイとして新たな展開をみせていく。本稿では、近代における和装文化の流れを踏まえながら、着物趣味の成立過程をたどってみたい。
キーワード 着物 趣味化 コスチューム・プレイ
はじめに
まず「趣味」とは何か、ということを考えておこう。「趣味」を辞書で引くと、「①仕事・職業としてでなく、個人が楽しみとしてしている事柄。②どういうものに美しさやおもしろさを感じるかという、その人の感覚のあり方。好みの傾向」(『大辞泉』)というように、だいたい2つの意味が出てくる。ここで論じる「着物趣味」の「趣味」は①である。さらに、人間だれしもが持っている時間に注目すれば、趣味とは、食事や睡眠などの生活必要時間、仕事や職業、家事などの労働時間以外の自由時間(余暇)に営まれるものと言うことができる。たとえば、私のように、ほぼ毎日、自分と家族のために食事を作っている人は「料理好き」かもしれないが、それは家事労働であって「料理趣味」ではない。料理趣味とは、日頃、家庭で料理をしない人が、休日などの余暇を利用して日常の食べ物とはちょっと違うレベルのものを料理することを言うのだと思う。
次に「着物趣味」の成立の要件を考えてみたい。着物が生活衣料である間は、着物を着ることは日常に必要な営みであって、趣味にはならない。私の明治生まれの祖母は2人とも、生涯、ほとんど和装しかしなかった人で、毎日、着物を着ていたが、それは「趣味」とはまったく遠い。そうした着物が日常衣料だった時代にも、裕福で高価な着物をたくさん誂える人はいたが、それは「着道楽」であって、「着物趣味」とは言わなかった。つまり、着物が趣味化して「着物趣味」が成立する前提、第1の要件として、着物が日常衣料としてのポジションを失うことが必要になる。
最初の辞書的定義のように「趣味」は本来、個人のものだ。しかし、個人が孤立している間は、ほとんど社会性を持たない。「趣味」がある程度の社会性をもつためには、同じ「趣味」をもつ「同好の士」が集まることが必要になる。つまり、「着物趣味」の同好の士が横のつながりをもって集うことが「着物趣味」の成立の第2の要件になると考える。
そして、その仲間たちの間で、「着物趣味とはこういうものだ」という意識、ある種の規範が共有される。その共有された規範が仲間としての意識を強化していく。こうした特有の規範の成立を第3の要件と考えたい。
Ⅰ 日常衣料としての和装の衰退 ―趣味化の前提として―
1 洋装化と和装の衰退
明治の文明開化とともに日本人の洋装化が始まる。西欧近代文化の輸入と模倣に懸命な新政府は鹿鳴館(1883)に象徴される洋風文化を演出するが根付かなかった。洋装化は軍人の軍服、巡査の制服、官公吏の上層部や洋行帰りの学者など、男性のごく一部に止まり、女性の洋装化はほとんど進展しなかった。
大正後期から昭和初期(1920~36)になると、洋服を着たモダンボーイ(モボ)とモダンガール(モガ)が最新の流行ファッションとして注目されるようになる。とりわけ、女性の洋装化の端緒となったモガへの社会的注目度は高かった。しかし、それは都市における尖端文化ではあったが、全国的・全階層的な広がりを持つものではなかった。
一方、この時代は和装にも大きな変化があった。化学染料と力織機の普及により銘仙やお召などの絹織物の大量生産が可能になり、それまで木綿の着物しか着られなかった階層にまで絹織物が普及していく。
昭和初期に大都市に出現するデパートは、絹織物としては安価な銘仙を衣料品売り場の目玉商品に据える。そして、産地と提携した展示会などを開催して積極的に「流行」を演出していった。
主要な産地(伊勢崎、秩父、足利、八王子など)は、デパートが演出する「流行」に応じるために熾烈な競争をしながら、デザインと技術のレベルを高めていった。その結果、アール・ヌーボーやアール・デコなどヨーロッパの新感覚デザインが取り入れられ、「解し織り」(経糸をざっくりと仮織りしてから型染め捺染した上で織機にかけて、仮糸を解しながら、緯糸を入れていく技法)など技術の進歩によって多彩な色柄を細かく織り出すことが可能になった。こうして、従来の着物とは感覚的に大きく異なる、華やかで斬新な色柄の銘仙が大量に市場に供給され、銘仙は都市大衆消費文化を代表する女性衣料としての地位を確立する(三橋2010)。


【写真1】銀座4丁目交差点(昭和7年=1932年)
出典:石川光陽『昭和の東京 ―あのころの街と風俗―』(朝日新聞社 1987年)

【写真1拡大】

【写真1拡大】
写真1は、1932年(昭和7)の銀座4丁目交差点である(石川1987)。男女とも和装・洋装さまざまな服装の人が行き交い、この時代の服飾文化の豊かさを思わせる。右側、仲良く連れ立った2人の女性の1人は、典型的なモガ・ファッションだが、もう1人は大きな麻の葉柄の振袖で、おそらく銘仙と思われる。また左側の袴姿の女子学生の着物は直線を交差させたアール・デコ風の銘仙だと思う。そしてその右の男の子を連れた母親は縞お召、もしくは縞銘仙を着ていると思われる。
この時代における銘仙・お召の流行が見て取れるが、日本近代の服飾史を洋装化の歴史としか見ない従来のファッション史のほとんどは、モガの出現に注目するあまり、この時代が大衆絹織物の普及による女性の和装文化の全盛期であったことを見落としている(註1)。
日中戦争から太平洋戦争の時代(1937~45)になると、軍服や国民服の着用によって男性の洋装化が進行する。また戦時体制への移行にともない繊維・衣服の統制が行われ、「贅沢は敵だ!」のスローガンのもと、女性の和装文化が抑圧されていった。また、戦地に赴く男性に代わる労働力として、「非常時」への対処として、女性の衣服にも活動性が求められ、そうした社会的要請から着物の上に履くズボン型衣料としての「もんぺ」が普及する。そして、戦争末期には、アメリカ軍の空襲によって繊維製品生産と流通機構が破壊されてしまう。
戦後混乱期(1945~51)は、戦災による物資の欠乏に始まり、繊維素材・製品の統制が衣料品の不足に輪をかけた。そうした中、日本を占領した進駐軍がもたらしたアメリカ文化への崇拝、日本の伝統文化否定の風潮が強まり、和装は旧態の象徴になっていく。その結果、戦時中に進行した男性の洋装化に加えて、女性の家庭外での洋装化が大きく進行する。
そして高度経済成長期(1960~75)になると、経済効率を優先した社会システムの画一化が進む。衣服における画一化はすなわち洋装化であり、企業にでも学校でも洋装が一般化・標準化する。同時に、家庭生活の洋風化も進行し、それまでは外では洋装、家では和装が主流だったのが、家庭内においても男女ともに洋装化が進んだ。
こうして、和装は生活衣料としてのポジションを失っていった。その時期は、地域によって差はあるが、東京などの大都市では1960年代後半から70年代前半の時期に押さえることができると思う。
2 女性着物の多層性の崩壊
1960年代後半から70年代前半に起こった注目すべき現象のひとつは、女性着物の多層性の崩壊である。
(表1)着物の階層性

着物を着る場が大きく狭まった結果、礼装・社交着としての着物は残ったものの、街着・家内着・労働着としての着物(お召・銘仙・木綿・麻)は洋装に取って代わられ衰退した。新たに茶道などの「お稽古着」が登場し、色無地や江戸小紋が好んで用いられるようになる。また、本来は家内着だった紬は高級化して社交着化する。階層性の崩壊と同時に、着物の材質も多様性が失われ、木綿・麻・ウールなどは、ごく一部が高級化して残った以外は姿を消し、着物と言えばほとんどが絹という状態になっていく。
3 「着付け教室」の登場と規範化
この時期に起こったもうひとつの注目すべき現象は「着付け教室」の登場である。1964年(昭和39)に「装道礼法きもの学院」が、1967年に「長沼静きもの学院」(当時は「長沼学園きもの着付け教室」)が、そして1969年には「ハクビ京都きもの学院」が創立され、「着付け教室」として全国的に展開していく。現在に続く大手の「着付け教室」が1960年代後半に創立されたことは偶然ではなく、それなりの社会的理由が有ったからだと思われる。
男性の着付けに比べて女性の着付けは帯結びが複雑・多様であるが、それにしても、着物の着付け、帯の結び方は、母や祖母から娘が生活の中で教わり習い覚えるもので、月謝を払って習うようなものではなかった。しかし、戦中・戦後混乱期に着物を思うように着られなかった女性が母親になった時、成長した娘に着物の着付けを伝授できない事態が発生したと思われる。
たとえば、1925年(大正14)生まれの女性は、戦間・戦後混乱期(1941~50)には16~25歳だった。23歳で娘を産めば、1967年には母親42歳、娘19歳である。成人式が間近になった娘に着付けを教えようと思っても、自分の和装経験が乏しく自信がないというようなケースである。祖母がいれば助けてもらえるだろうが、都会で核家族となると、そうもいかない。どこか教えてくれる所はないだろうか?
この時期に「着付け教室」が次々に創立された背景には、そうした戦争による母から娘へという和装文化の継承断絶が生んだ需要があったのではないだろうか。
着物の着付けは、いたって不器用な私の経験からして、単に着るだけなら、3日も習えば、なんとか着られるようになり、後は反復練習である。器用な人なら1日で覚えられるだろう。しかし、それでは月謝を取って教える「着付け教室」の経営は成り立たない。したがって、「着付け教室」では手っ取り早い簡便な着付けを教えず、いろいろと複雑な手順で教える。さらにごく日常的・庶民的な着付け法ではなく、戦前の上流階級の着付け法をベースにして伝授する。その方が付加価値が高いからである。
実際、この時期の著名な着付け指導者には、戦前の上流階級の女性が多かった。1970年にベストセラーになった『冠婚葬祭入門(正)』(カッパ・ホームス)で「着付け」法を広めた塩月弥栄子(1918~)は裏千家14世家元碩叟宗室の娘であり、1973年から「ハクビ総合学院」の学長を務めた酒井美意子(1926~99)は旧加賀藩主で侯爵の前田利為の娘で、旧姫路藩主で伯爵の酒井忠元の妻だった。
こうした戦前の上流階級の女性たちによって、自分で働かなくてよい上流階級の「奥様」「お嬢様」の非活動的な着付けがマニュアル化され、「着付け教室」で教えられ規範化していった。その結果、着物の着方がすっかり様式化し「こう着なければいけない」という形ができ上がる。
本来、生活衣料であった着物には、その状況に応じた着付け方があった。働く時には身体を動かしやすいように楽に緩めに着付けし、たくさん歩く時には裾がさばき易いように合わせを浅めにしてやや裾短かに着付けるなどといった着付けの融通性が失われてしまった。こうして、働けない、身動き不自由な、皺ひとつ許されないきっちりした、着ていて苦しい着物の着付けが成立する。
習わなければ自分で着られない衣服は、もう日常の生活衣料とは言えない。こうした過程をたどって、着物は日常の衣服としての機能を喪失していき、特別な場合、たとえば、お正月、冠婚葬祭(成人式、結婚式、葬儀、法事)などの非日常の衣服となり、あるいは特殊な職業の人(仲居、ホステスなど)の衣服になってしまった。
Ⅱ 「美しい着物世界」の成立
1 高級化と「美しい」の規範化
着物が生活衣料の地位を失い、特別な衣服になったことで、着物の生産・流通業界は、安価な大量生産中心から高価な少量生産へと転換していく。かっての主役だった銘仙やお召はまったく見捨てられ、手作業のため少量生産しかできなかった各地に残る紬が見出され、そのいくつかが付加価値がある織物として高級品化していった。
たとえば、1933年(昭和8)に秩父産の模様銘仙は5円80銭~6円50銭だった。当時の6円は現代の21000~24000円ほどと考えられ、中産階層なら1シーズン1着の購入が可能な値段だった(三橋2010)。ところが、1999年(平成11)に八丈島特産の黄八丈の反物は48万円もした。平均的な収入の人だったらローンでも組まない限り購入は難しい。
こうした着物の高級品化時代に主な情報媒体となったのが婦人画報社(現:ハースト婦人画報社)の『美しいキモノ』(1953年創刊・季刊)に代表される着物雑誌である。この種の着物雑誌の中身は、高価な着物のオン・パレードであり、安価な着物やまして古着などはけっして登場しない。高価な着物を売りたい着物業者と、そうした高価な着物を購入できる富裕な奥様・お嬢様の「美しい」「上品な」着物世界である。私はこれを「美しい着物世界」と呼んでいる。
「美しい着物世界」の特徴は、誌名通り「美しさ」と「着物」とが過度に結合したことである。『美しいキモノ』は、創刊以来毎号、高価な着物を着た女優さんが表紙を飾るのが通例で、中の誌面もほとんどがプロのモデルの着物姿である。その姿はたしかに美しく、なるほど誌名にふさわしい、と思ってしまう。しかし、着姿が美しいのはもともと美しい女優やモデルが着ているからであって、同じ着物を一般の女性が着ても必ずしも美しくなるとは限らない。
着物が日常の衣料であった時代、そんなことは考えるまでもなく誰もが解っていることだった。ところが、着物が非日常の衣服になるにつれて、わざわざ着物を着て特別の装いをするのだから、きっと美しくなるに違いない、というある種の期待が生まれてくる。実際にはそうなる場合もそうならない場合もあるわけだが、着物業界は、そうした期待感を利用して、着物雑誌の誌面を通じて「着物を着ている人は美しい」というイメージを流布し、「着物を着れば美しくなれる」さらに「高価な着物を着ればより美しくなれる」という幻想(錯覚)を喚起し、売り上げの向上につなげるという戦略をとった。
「着物を着ている人は美しい」というイメージは、やがて「着物を着ている人は美しくなければならない」という非現実的な意識に転化していき、必ずしもそうならない女性たちを着物世界から遠ざけることになった。
2 色・柄の衰退
日本の女性の和装文化は、江戸時代には遊廓の高級遊女(花魁)がファッションリーダーであり、明治以降も芸者をはじめとする玄人筋が大きな比重を保っていた。着物が生活衣料としての地位を失っていく時代になっても着物を着続け、着物業界の売り上げのかなりの部分を担ったのは銀座や北新地に代表されるクラブ・ホステスたちだった。にもかかわらず、「美しい着物世界」では、こうした玄人の着物は徹底的に無視・排除される。間違っても「銀座クラブママの着こなしに学ぶ」などという特集は組まれない。
「美しい着物世界」の着物のコンセプトは、あくまでも「上品」である。これを意訳すれば「玄人っぽくない」ということになる。具体的には、色味の弱い色、小さ目の柄、つまり自己主張の弱い「控えめ」が上品とされる。色については、原色や強い色は忌避され、薄い色、さらには無彩色(白・黒・グレーの濃淡、銀)が好まれる、柄は巨大柄・大柄が避けられ、比較的小さめの柄を反復する小紋や、細かな点で小さな意匠を全面に置く江戸小紋、さらには柄が消失した色無地が好まれるようになる。また、日本の伝統的な意匠である縞も、太縞や棒縞のようなシンプルで大胆なものは忌避され、細縞やよろけ縞のような控えめなものが好まれる。太縞や棒縞がもつ粋なイメージが玄人(粋筋)を連想させるためと思われる。
こうした傾向は着物の階層性が崩壊し、「お稽古着」の比重が増した結果、万事派手を嫌い、地味を上品とする茶道の世界の「趣味」が着物全体に影響を及ぼすようになったことが作用していると思われる。その結果、戦前の着物に比べて、現代の着物は、色は淡く、柄は小さく、色柄のバリエーションが少なくなり、創造性が失われ類型的となり、個性的でなく画一化が進んでしまった。服飾デザインという見地からすれば、明らかな退化であるが、商業的にはそうした無個性な無難な着物でないと売れなくなってしまったのである。
3 高級化の帰着と「趣味の着物」
こうした着物の高級化は、着物の世界をますます狭めていった。何10万円という衣料を次々に購入できるような富裕層がそんなに多いはずはない。「和装が好き、着物を着たいけど高くて手が出ない」という階層の方がずっと多かった。それでもバブル経済期(1980年代後半)はまだよかった。驚くほど高い着物が売れた。たとえば、染色家の久保田一竹(1917~2003)の一竹辻が花の訪問着が1200万円とか。しかし、購入された高価な着物が実際に着られたかというと必ずしもそうでもなく、多くは「箪笥の肥やし」と化し、着物世界が再び拡大することにはつながらなかった。そして、バブル崩壊後、着物業界は大量の在庫を抱えたことに加えて、バブル期の「箪笥の肥やし」がリサイクル市場に放出されることで、新規需要の落ち込みに苦しむことになる。
ところで、1980年代には「趣味の着物」を看板にする店が現れる。目の肥えた顧客を相手に、普及品ではなく高級紬や作家物など厳選された商品を扱う店である。しかし、この「趣味」は、「はじめに」で紹介した辞書の②の意味「どういうものに美しさやおもしろさを感じるかという、その人の感覚のあり方。好みの傾向」と解釈すべきだろう。「良いお着物の趣味でいらっしゃいますわね」の「趣味」である。この時点では、「仕事・職業としてでなく、個人が楽しみとしてしている事柄」という①の意味での「着物趣味」はまだ成立していなかった。
4 男性の和装の(ほぼ)絶滅
写真2は、1959(昭和34)正月のある一族(東京在住)の集合写真である(小泉2000)。
.jpg)
【写真2】ある一族のお正月(昭和34年=1959年)
出典:小泉和子『昭和のくらし博物館』(河出書房新社 2000年)
成年女性8人はすべて和装である。これに対して成年男性4人は家長と思われる1人が和装なだけで他の3人は洋装である。また子供たちも女児6人が和装4、洋装2であるのに対し男児2人はいずれも洋装だ。つまり、男性の和装はおじいちゃんだけという状態で、男性の洋装化=和装の衰退が女性のそれよりもかなり早く進行したことがはっきり見てとれる。
お正月ですらこの状態なのだから、平常時において男性が和装する機会はいよいよ乏しくなっていった。歌舞伎役者、茶道家、落語家、棋士など一部の限られた職業の男性の需要に応じた生産は続けられていたが、1970年代後半から80年代になると、男性の着物は高級品を除き店頭から姿を消していく。和装趣味の青年が着物を着たいと思っても、(彼の手が届く範囲では)「どこにも売っていない」状況になり、着付けのマニュアル本からも男性向けの記述はほとんどなくなってしまう(早坂2002)。こうして、1980年代後半から90年代前半には、男性着物はほぼ絶滅状態になり、着物は女性の物という社会認識が定着し、着物世界におけるジェンダー的な乖離は極限に達した。
こうして、着物趣味の成立の第1の要件である日常衣料としての地位の喪失は、少なくとも1980年代末には完全に達成されていた。しかし、まだこの時期には、着物世界の人間関係は、着物を売る着物屋と着物が好きで買う客の商業的関係であり、着物好きの客同士の横のつながりは、ほとんどなかった。第2の要件である着物好き同士の横のつながりができるまでには、もう一段階が必要だった。
Ⅲ 情報革命と着物世界 ―趣味化への胎動―
1 「着ていく場所がない」
着物を着て家を出ると、顔見知りの近所の奥さんに「あら、お着物でお出かけ? 今日は何かありますの?」と興味津々に尋ねられる。多くの着物好きの女性が経験したことだ(男性の場合はさらに不審がられて声も掛けられない)。1990年代になると、日常性を完全に喪失し衣服として特殊化してしまった着物には「着る理由」が必要とされるようになってしまった。「ただ着物を着たい」、「着て出かけたい」ができない状況が生じたのである。
「近所でジロジロ見られるので、着物で出掛けられない」、「変わり者扱いされるので(着物のことは)周囲の人に黙っている」、そんな話を聞いて「なんだ、女装と同じではないか?」と思ったことがある。冗談ではなく、1990年代には、着物のファッション・マイノリティ化はそこまで進行していた(三橋2006)。
実際、堂々と着物を「着られる場所」「着る機会」は少なかった。お正月は年に1度だし、結婚式に呼ばれる機会もそうはない。そうした状況の中で、「鈴乃屋」や「三松」のような大手の着物チェーンが「着物を着る場」としてイベントを企画・開催するようになる。しかし、お商売だから当然なのだが、そうしたイベントは着物展示会と併設されていたり、そうでなくても「お出かけ」の度に着物を作ることを勧められ、結局、多大の出費をすることになる。そうした制約なしに、「気楽に着物を着る場・機会があればいいのに」と、着物好きの多くが思うようになっていた。
2 パソコン通信からインターネットへ
1997年8月、パソコン通信「NIFTY-Serve」の中に「きものフォーラム」が開設される。「NIFTY-Serve」のサービス開始(1987年4月)から10年も後のことだった。そして11月25日には東京赤坂の「全日空ホテル」で「きものフォーラム」の「オフ会」(オフライン・ミーティング)が20名の参加者で開催された(早坂2002)。
これはパソコン通信と趣味の世界の結合としてはかなり遅い。たとえば女装趣味のパソコン通信「EON」(主宰:神名龍子)は1990年に創立され、その活動を通じて1995年頃にはすでに「電脳女装世界」ともいうべき女装仲間の横のつながりが形成されていた。1996年4月に開催された「EON」ボード上に設置された「クラブ・フェイクレディ(CFL)」(主宰:三橋順子)の「オフ会(FL3)」には77名が参加している。そんなものと比較するなと言われるかもしれないが、パソコン通信を通じての仲間の結合という点で、この時期の「着物仲間」は「女装仲間」よりもずっとマイナーな存在だったことがわかる。
1996~97年頃から日本でもようやくインターネットが盛んになると、1997年に秋田県在住の「澤井夫妻」がインターネット上に「きものくらぶ」を開設する。これが日本最初のインターネット着物サイトと思われ、私が最初にアクセスした着物サイトも「きものくらぶ」だった。同年12月には早坂伊織氏が「男のきもの大全」を立ち上げ、これが最初の「男着物」専門サイトになった。
こうして、パソコン通信、次いでインターネットを媒介にして、日本各地に孤立、散在していた「着物好き」が結びつき、仲間化していくことになる。
3 「男着物」の復活と男性主導の「オフ会」
パソコン通信時代から代表的な「着物好き」として活躍する早坂氏の本業が「富士通」のシステムエンジニアだったように、また「きものフォーラム」の中に「男のきもの」会議室が設置されたように、パソコンの普及度、パソコン通信やインターネットへのアクセス率は、その初期においては男性の方が圧倒的に高かった。したがって、インターネットによる仲間化や「オフ会」の開催は男性が先行する。
早坂氏が主催する男着物の「オフ会」である「男のきもの大全会」が開催されたのは1998年10月だった(参加者50名)。1999年12月には、毎週土曜日に着物男性が銀座に集まる「きものde銀座」の第1回が開催される(参加者14名)。この集まりは1999年11月に開催された第2回「男のきもの大全会」から派生したものだった(早坂2002)。
こうした経緯をたどって、1990年代末に、ほぼ絶滅状態だった男着物が復活し仲間同士の横のつながりが形成されていった。1990年代末から2000年代初頭にかけて、着物趣味成立の第2の要件が整ったことになる。
4 「ふだん着きもの」への志向
「インターネットきもの」の初期に多くのアクセスを集めたサイトに「あみさんのきもの」(主宰・鳥羽亜弓)があった。このサイトの特徴は、地方在住の子育て中の主婦が毎日着物を着て生活しているという「特異性」にあった(鳥羽2001)。着物で日常を過ごし、家事を行い、子供を育てるという戦前期の日本の多くの主婦がしていたことが、すっかり特異なことになってしまったのである。
2002年に『天使突抜一丁目―着物と自転車と―』を出版したマリンバ奏者の通崎睦美も、着物で自転車に乗るという「特異性」で注目された(通崎2002)。明治~大正期のハイカラ女学生がごく普通にしていたことなのに。
また、現代風俗研究会の古参会員である磯映美は、「華宵」の名義で、2001年から2003年にかけて、散歩きもの普及員会ニュースレターとして「着物で、ぶらぶら」を刊行した。
こうした「ふだん着着物」、あるいは日常的な「着物暮らし」への志向は、日常性を喪失した和装文化に反発・逆行するものであり、その方向性はその後の「趣味化」の中に受け継がれていくことになる。
Ⅳ アンティーク着物ブームと「着物趣味」の成立
1 女性主導の「オフ会」の盛行
当初、男性主導だった着物「オフ会」も、女性のインターネットアクセス率が上がるにつれて、女性の参加が増加していった。男性主導の「オフ会」には、男性だけで語り合いたいホモ・ソーシャルなタイプと、主催者が「女好き」で積極的に女性の参加を勧誘するタイプとがあった。2000年頃に何度か開催された村上酔魚堂の「オフ会」は後者のタイプだった。
.jpg)
【写真3】「村上酔魚堂・浅草オフ会」(2000年9月)。
ここで後の「うきうききもの」の初期中核メンバーが出会う
そうした場で着物好きの女性たちが知り合い、その横のつながりをベースに、2001年頃から女性主導の「オフ会」が盛んに開催されるようになる。その代表は、東京を中心とした首都圏では「うきうききもの」(主宰:古川阿津子、2001~10)、京都を中心とした関西圏では「夏海の遊び着」(主宰:夏海、2001~ )であり、最盛期には月に数回ペースで「オフ会」を開催した。
-5d3a9.jpg)
【写真4】「うきうききもの」秩父銘仙オフ会(2002年4月)。
中央が主宰の「あつこ女将」
こうした「オフ会」は心置きなく好きな着物を着られる場であり、着物に関する様々な情報や工夫が交換され、またお互いの着こなしが参照され相互に影響を与えあった。そして、「オフ会」の様子がインターネットサイトにレポートされることで、新しい参加者を引きつけていった。2000年代前半は、インターネットと「オフ会」を通じて、女性の着物仲間が横のつながりを形成していった時代だった。
私も参加した「うきうききもの」では、初期のメンバーの間には、既存の着物世界への飽き足らなさ、不満が共通意識としてあった。地味=上品に固定化され、「着付け教室」が作り上げた厳格な着用規範に反発し、「もっとどんどん、自由に、楽しく着物を着たい!」「(ミセスだって)派手な着物を着てもいいじゃない!」という思いである。「美しい着物世界」とまったく異なる着物への志向・嗜好がそこにはあった。
2 アンティーク着物ブーム
女性主導の「オフ会」の盛行とほぼ時を同じくして、アンティーク着物ブームが起こる。その火付け役は「別冊太陽」(平凡社)の「昔きもの」シリーズだった。2000年3月の『昔きものを楽しむ(1)』に始まり、『昔きものを楽しむ(2)』(2000年11月)、『昔きものと遊ぶ』(2001年8月)、『昔きものを買いに行く』(2002年12月)、『昔きものの着こなし』(2003年4月)、『昔きもの 私の着こなし』(2004年5月)とほぼ1年1冊ペースで計6冊が刊行された。
このシリーズ、最初は「骨董を楽しむ」シリーズの1冊として刊行されたように、骨董的な価値のあるアンティーク着物を「収集して楽しむ」というスタンスだった。ところが途中から、アンティーク着物を「着て楽しむ」という方向に変化していった。表紙も最初は着物の意匠だったのが、3冊目の『昔きものと遊ぶ』は着姿になっている。
「別冊太陽」の「昔きもの」シリーズによってアンティーク着物への関心が急速に高まり、骨董屋や骨董市の露店で、古い着物を漁る人々が出現するようになる。とくに現代の着物に比べてデザイン性に富み、派手な色柄の銘仙やお召が注目され、それまで二束三文(500円以下)だった銘仙の古着がたちまち値上がりしていった。
そうして探し出し手に入れた古着を洗い繕って、場合によっては仕立て直す。手間暇を惜しまない。そして、その着物を「オフ会」で仲間たちにお披露目する。すると、「わ~ぁ、すてき、どこで手に入れたの?」「いくらだった?」と仲間から質問が飛ぶ。「○○の露天市でね、500円だったの。けっこう汚れていたから(着られるようにするのが)大変だったけど…」。こう答えるとき、それまでの労苦が報われ、ある種の達成感がある。
探す→洗う・直す→着る→仲間に見せる、このサイクルが毎月のように繰り返される。傍目から見れば、いい大人の女性が古着を漁り集め、着ることに夢中になっているわけで、いったいウチの娘(もしくは妻)は何をしているのだ、と呆れられることになるが、まさにそれが「趣味」なのである。
2002年6月には、アンティーク着物に特化した着物雑誌『Kimono道』(祥伝社、後に『Kimono姫』と改題)が創刊される。そのコンセプトは「アンティーク&チープ」であり、表紙に記されたリードは「キモノのはじめてはアンティークから」だった。
アンティーク着物の場合、値上がりしたと言っても、せいぜい1000円から5000円程度で千の桁で納まり、万の桁になることは少なかった。稀に数万円という高級アンティーク着物もあったが、当時、市販の現代着物の多くは20~50万円の価格帯だったから、それでも10分の1である。30万円の現代着物1枚を買う値段で、露天商から3000円のアンティーク着物が約100枚買える計算になり、すさまじい価格破壊ということになる。
安価なアンティーク着物がブームになったことは、それまで経済的な理由で着物を思うように着られなかった「着物好き」にとっては大きな福音であり、とくに20代、30代の比較的若い人たちが着物世界に参入できるようになった。20世紀後半の50年間一貫して長期低落傾向にあった着物人口は、21世紀に入って一時的にせよ増加に転じたのである。これは「趣味化」というある種の「突然変異」かもしれないが、長い和装の歴史の中で、やはり画期的なことだと思う。
2000年代のアンティーク着物ブームによって、東京白金の「池田」、原宿の「壱の蔵」などのアンティーク着物専門店はおおいに賑わい、コレクターとしても知られた店主の池田重子(1925~)や弓岡勝美の名も高まった。とりわけ池田は、新宿伊勢丹や銀座松屋などで「池田重子コレクション―日本のおしゃれ展―」(1993~2011)を何度も開催し、アンティーク着物の社会的認知を高めた。池田のコレクションとコーディネートは、アンティーク着物ファンの垂涎の的になった。
また、リサイクル着物の「ながもち屋」や「たんす屋」がチェーン展開するのもこの時期である。しかし、アンティーク着物ブームは既存の着物業界にはほとんど影響しなかった。
3 銘仙への注目
アンティーク着物ブームの中で、とりわけ人気度が高かったのが銘仙だった。銘仙とは、先染(糸の段階で染める)、平織(経糸と緯糸の直交組織)の絹織物である。その詳細については別稿に譲るが(三橋2002,2010)、大正~昭和戦前期においては、安い価格と豊富な色柄が、中産階層のお嬢さんの普段着、女中さんの晴れ着、もしくは、女教師の銘仙+女袴(行燈袴)、牛鍋屋の仲居の赤銘仙、カフェの女給の銘仙+白エプロンといったような職業婦人の仕事着として好まれ大流行した。戦後も生産は続いたが、主な着用層だった「お嬢さん」や職業婦人が真っ先に洋装化したこと、粗悪品の流通によりイメージが低下したことで徐々に衰退した。それでも、大柄で色鮮やかな模様銘仙は、自分を「広告塔」にする女性、具体的には「赤線」(黙認買売春地区)の「女給」(実態は娼婦)たちに愛用された。
着尺としての銘仙の生産は、1960年代末までにほぼ途絶え、工場生産品ゆえに伝統工芸・美術品になることもなく、技術もほとんど断絶してしまった。つまり、銘仙はいったん滅んだ織物だった。
ところが、アンティーク着物ブームにより、女性の和装文化の最盛期だった大正・昭和初期の着物文化が再評価された結果、その最盛期を担った銘仙がにわかに注目されるようになる。2002年1月に主要産地だった埼玉県秩父市に初めての銘仙資料館「ちちぶ銘仙館」がオープンし、それを受けて2003年5月に三橋順子が「艶やかなる銘仙」を『Kimono姫』2号に執筆した(三橋2002)。2003年6月には銘仙コレクターの木村理恵と通崎睦美の「銘仙コレクション2人展」が東京中野の「シルクラブ」で開催される。そして2004年12月には秩父市在住の木村理恵のコレクションを紹介した『銘仙―大正・昭和のおしゃれ着―』が「別冊太陽」(平凡社)の1冊として刊行され、銘仙ブームはひとつの頂点を迎える。
その後も銘仙ブームは続き、銘仙をメインにした企画展が各地で立て続けに開催された(註2)。そして、2009年5月には銘仙を主な展示品とする「日本きもの文化美術館」が福島県郡山市にオープンし、2010年4月には同美術館から『ハイカラさんのおしゃれじょうず-銘仙きもの 多彩な世界』が刊行された。
こうした銘仙ブームは、現代の着物にはまったく失われてしまった大胆で前衛的な大柄と、原色を多用し多色を巧みに配した強烈な色彩感覚が作り出す華やかで艶やかなイメージに多くの着物好きが魅せられたからであり、銘仙そのものが現代着物へのアンチテーゼとなっている。銘仙のそうした性格は、2000年代に成立する「着物趣味」の方向性と合致し、それゆえに重要なアイテムとなったのである。
4 「規範」を越えて ―「着物趣味」の成立―
2000年代前半のアンティーク着物ブームの中で成立する「着物趣味」の基本コンセプトは、大正・昭和戦前期の着物文化の再評価とそれへの回帰である。それは、1970年代以降に形成された地味=上品に固定化された「美しい着物世界」や、「着付け教室」が流布する厳格な着用規範への反発と表裏一体だった。それはまた、すっかり特別な場の衣服になってしまった着物から、本来の日常性を取り戻す方向性だった。和装文化の伝統を意識しつつも、戦後の着物世界が作り上げた規範から自由に、好きな着物を着たいように着る、というスタンスだ。
日本の女性着物は、既婚か未婚かの区分が明瞭で、それが身分標識にもなっていたが、アンティーク系の場合、そうした境界も越えてしまう。ミセスであっても、派手な着物、目立つ帯を厭わない。振袖だって着てしまう。白半襟、白足袋という「美しい着物世界」の「常識」に対し、色半襟・刺繍半襟、色足袋・柄足袋が好まれる。着物と帯、そして小物類(半襟、帯揚、帯締、足袋)の色合わせ・柄合わせや帯結びに凝る。髪も、お正月やイベントには、すでに見かけることも稀になった日本髪を結う。
「美しい着物世界」の人に比べて行動性が高いので、着付けも前合わせは浅く、したがって襟のy字は深く半襟をたくさん露出し、襟もかなり抜く。「着付け教室」で「下品なのでやってはいけません」と教えられることばかりである。そして、いつでも(仕事以外)どこにでも着物で出掛ける。休日、近所に買い物に行くのも着物だし、国内旅行はもちろん、海外旅行も着物で行く。履物は、たくさん歩くので、草履より下駄が好まれる。なにより、着物も帯も「値段の高きをもって貴しとせず」で、その人の個性に合ったコーディネートや創意工夫が評価される。
こうした方向性・嗜好は、ほとんどすべて「美しい着物世界」への明確なアンチテーゼである。したがって、当然のことながら、従来の規範を順守する「美しい着物世界」の人たちからの反発も大きかった。ネット上で「ぼろ着て何が楽しいの?」「お女郎さんの集まり」「座敷牢から抜け出してきたみたい」と批判されるのは常のことで、銀座で集まっていた時、見知らぬ中年女性(洋装)にいきなり「ここは銀座なんだから、日本の恥になるようなみっともない着方はしないで!」と面と向かって言われたこともあった。単なる好奇の視線には慣れっこだが、さすがに「日本の恥」とまで言われるとは思っていなかった。
しかし、そこまで強く反発されるということは、従来の着物世界の規範を越えた、新しい、そして特有の方向性が成立したということである。既存の着物世界から批判されたことで逆に「私たちの着物趣味とはこうなんだ、これでいいんだ」という意識が仲間たちの間で共有化されていった。こうして、第3の要件が満たされ2000年代前半に新しい「着物趣味」の世界が成立した。
-9cd66.jpg)
【写真5】アンティーク銘仙のコーディネート。
モデル:(左)小紋、(右)YUKO
2人とも「アラフォー」のミセス(2005年3月)
Ⅳ 新しい着物世界
1 着物趣味イベントの開催
2000年代中頃になると、「着物趣味」の成立を背景に、従来の「オフ会」からさらに発展した着物趣味イベントが開催されるようになる。ここでは東京で開催され、私も参加したことがある代表的な2つの着物趣味イベントを紹介してみたい。
① 「きものde銀座」
「きものde銀座」は毎月1度銀座で開催される「着物好き」の集会イベントで、「男のきもの大全会」の派生イベントとして1999年12月に第1回が開催された。最初は毎週土曜日開催、着物男性だけの集いだったが、2000年2月からは月1回(毎月第2土曜)となり、着物女性も参加するようになった。主催者はなく、当初は「旦那さん」(牧田氏)が事務局を担当していたが、2006年以降は有志の当番制で運営している。着物で集まる人も会員制ではなく、まったくの任意参加である。
15時に銀座4丁目交差点「和光」前で待ち合わせ、「歩行者天国」の中央通りを1丁目方向に歩き「ティファニー」前で集合写真を撮影、その後は自由行動で、なにかイベントがあれば行きたい人はまとまって行く。17時半頃から「土風炉・銀座1丁目店」で懇親会(会費3000円)となり、20時前後にお開き、希望者は二次会へという毎回同じスケジュールで、途中参加・離脱も自由である。
コンセプトは文字通り「銀座で着物を着る」ということだけ。参加者の着物のスタイルもアンティーク系、「ふだん着着物」系から「美しい着物」系まで様々であり、どんな着方であっても批判しないことになっている。
2008年4月8日に第100回を迎え、2013年12月には168回となる。台風でも大雪でも中止せず(連絡方法がないため)、東日本太平洋沖大地震の翌日(2011年3月12日)にも20数名の参加者で開催された。最初期には参加者1名ということもあったが、近年は集合写真を見る限り40~60名くらいだろうか(註3)。
主催者がいない有志持ち回りの運営と、参加も着方も自由度が高い「緩い」形態が「着物趣味」のイベントとして最も長続きしている秘訣だと思う。
-944a6.jpg)
【写真6】第100回「きものde銀座」(2008年4月8日)
.jpg)
【写真7】2009年1月の「きものde銀座」。
日本髪を結い大振袖を着て築地・波除神社に初詣
② 「日本全国きもの日和」
「日本全国きもの日和」は、「きものであそぼう」をスローガンにした着物ファンの手作りイベントで、「玉龍」こと西脇龍二氏を中心とした「実行委員会」が運営している。メンバーの多くは「きものde銀座」で出会っている。11月3日を「きもの日和」として全国各地で着物イベントの開催を呼びかけ、第1回は7都市、第2回は20都市、第4回は25都市で「きもの日和」が開催され、「着物趣味」の地方への波及に大きな役割を果たした(註4)。
メイン会場である「きもの日和TOKYO」は、恵比寿のイベントホール「EBIS303」で2004年から2008年まで5回開催され、入場者は第1回が1500人、第3回(2日開催)は3000人だった。モデルもスタッフもすべて着物仲間で構成する本格的な「きものファッションショー」は観衆の注目の的だった。さらに、着物写真集『Kimono人』(2005、2006、2007の3冊)を自費出版した。
また、中心メンバーは、毎年5月に開催される静岡県下田市「黒船祭」に出張し、「賑わいパレード」に参加し、野外ファッションショーを開催している。
しかし、2007年の第4回から入場者、出店、広告が減少し赤字となり、経済不況(リーマン・ショック)もあって2009年11月に計画された「きもの日和TOKYO」は延期になってしまう。2010年3月に「きもの日和with目黒雅叙園」として開催されたが、2011年4月の開催予定が東日本大震災の影響で中止になった後は復活していない。
-5318c.jpg)
【写真8】「きもの日和TOKYO 2004」の冊子(2004年11月
-c5c3c.jpg)
【写真9】「きもの日和TOKYO」の「きものファッションショー」(2006年11月)
-c92c7.jpg)
【写真10】「下田黒船祭」の野外ファッションショー。
「ペリー・ロード」の橋の上が舞台(2007年5月)
-ddbca.jpg)
【写真11】「下田黒船祭」の賑わいパレード(2008年5月)
日本髪は美容院ではなく自分で結う
2 着物イベントの問題点
着物イベントに参加して、気付いた問題点を整理しておこう。第一はお金の問題である。「きもの日和TOKYO」のように、意欲的に活動を展開した結果、イベントの規模があまりに拡大してしまうと、集客や採算のような「趣味」とは性格が異なる要請が発生してしまう。また必要な経費が大きくなれば、経済・社会情勢の影響を大きく受けるようになる。「趣味」とは本来、浪費だが、あまり補填しなければならない金額が大きくなると、「趣味」の仲間では耐えられなくなる。といって、企業の協賛・支援を受ければ、商業資本の論理が入ってきて、ますます「趣味」の領域から外れてしまうジレンマがある。「趣味」としては拡大路線一筋ではなく適正規模を保つことも必要だと思う。
第2は、着物イベントのジェンダー的な構造問題である。端的に言えば、リーダーシップをとる男性、イベントの「華」としての女性という基本構造がそこにある。たとえば、ファッションショーやパレードで、男性リーダーの指示で若手の女性や美しい女性が目立つ場所に配される傾向は明らかにあった。それもまた社会的要請なのかもしれないが、必ずしもそうでない女性たちからは不満が出ることになる。
第3は、セクシュアリティの問題で、大人の男女が集まり、懇親会などでお酒が入ると、男性による女性へのセクシュアル・ハラスメントが発生する。その場合、運営側の男性のセクハラ認識が甘いと、結局は被害を受けた女性が泣くことになってしまう。
第4は、和装女装趣味の男性の問題で、近年は「女装」を禁止する着物イベントが増加している。和装文化に女形が貢献してきた度合いを考えれば、まったく理不尽と言いたくなる。そして、「女装禁止」の結果、日常的に女性として生活しているMtF(Male to Female)のトランスジェンダーまでが排除されることになってしまう。これは性的マイノリティに対する不当な社会的排除である。
第5は、高齢化の問題で、他の趣味の世界と同様に若い人がなかなか入ってこない。2000年代初頭のアンティークブームを担った30~40歳代は、10年たった現在40~50歳代であり、さらに10年たてば…である。今のままでは先細り傾向は免れないだろう。
これらの問題、とりわけ第2~5の問題は、着物趣味の世界だけの問題ではなく、日本社会が抱える問題の投影である。しかし、比較的柔構造な「趣味」の世界の特性を生かし、しっかりした認識をもって対応すれば、ある程度は改善可能な問題であると思う。
おわりに ―着物趣味の将来―
1 着たい着物がなくなる
現代の「着物趣味」、とりわけアンティーク派にとっての最大の不安は、近い将来、着たい着物がなくなってしまうのではないか、ということである。なんら特徴のない「つまらない」現代着物は巨大なデッドストックがあるのに、着たいと思うようなアンティーク系の着物はどんどん消えていく。和装文化の全盛期(1926~1936)に作られた銘仙・お召は、すでに80年前後が経過し耐用年数が過ぎつつあり、衣類としての寿命が尽きるのはもう遠いことではない。せめて、あと10年もってほしいと思うのだが。
また、現代女性の体格向上により、女性が小柄・低身長だった時代に作られたアンティーク着物を着られる人が減っている。こうした状況で頼りになったのは、2000年代の銘仙ブーム期に足利・伊勢崎などの旧産地で生産された復刻銘仙だった。復刻銘仙は、問屋価格で5~6万円、小売価格では8~10万円になってしまうので、かってのような普及は無理だったが、それでも、私のように身長が高い銘仙好きにはとてもありがたかった。しかし、わずかに残っていた職人さんの高齢化や逝去によって、2010年代初めに生産が途絶えてしまった(註4)。
先染め(糸を染めて柄を織り出す)の織物は技術的に難易度が高く、現状ではいったん絶えた技術の復活は望めそうにない。それが無理なら、せめて「全盛期(昭和戦前期)」のデザインを、後染め(糸を布に織った後で染める)の染物で再現してほしい。幸い現在ではアンティーク着物の色柄をコンピューターに取り込み、補修を加えた後に、インクジェット・プリンターで布地にプリントすることが容易になった。銘仙写しの浴衣や小紋が増えてくれればと思うのだが、現在の着物業界の沈滞した状況では、それも難しそうだ。
2 コスチューム・プレイとして
生産面では大きな不安があるが、着物をファッション・アイテムと考えた場合、その将来に希望はなくもない。
着物が日常の衣服としての機能を失い、着物を着る人がファッション・マイノリティになったことで、社会の服飾規範を超越する、ある種の自由を獲得できた。そもそも着物を着ていることが「変わり者」「外れ者」なのだから、細かな社会規範に縛られることはない。
そう思いきってしまえば、着物は自己主張、自己表現の手段として、そして変身のアイテムとして絶好である。コーディネートに工夫を凝らせば、立派な会社勤めの男性が任侠系の「あぶなそうな兄さん」に、まともな会社のOLさんや良家の奥様が芸者やお女郎上がりの「あやしい姐さん」に変身できる。背景や小道具に気を使えば、あっという間に昭和初期や昭和30年代にタイムワープした写真を撮ることも可能だ(三橋2006)。
-c2fb9.jpg)
【写真12】石仏に祈る村娘(昭和初期風)
モデル:YUKO
撮影:2008年2月、埼玉県秩父市金昌寺

【写真13】「赤線」の女(昭和28年設定)
モデル:YUKO
撮影:20010年10月、東京「鳩の街」旧「赤線」建物(娼館)をバックに
今や着物は、社会的立場を変え、年齢を化けて、時空すら超える力を持つようになった。それを活用しない手はない。21世紀の着物趣味は、こうした「着物で遊ぶ」、コスチューム・プレイとしての方向性をより強めていくことになると思う。
日本人の伝統衣装という路線では、美術工芸品としてはともかく、衣類としての着物はもう生き残れない段階になっている。「着物趣味」の仲間たちが目指してきた創造性のある自己表現のファッション・アイテムという方向こそが、着物という日本人の民族衣装を次の世代に伝える道だと私は思う。
(註1)村上信彦『服装の歴史2(キモノの時代)』(理論社、1974年)だけが、この時代の和装文化の発展に正当な評価を与えている。
(註2)主なものを掲げると、京都古布保存会「京都に残る100枚の銘仙展」(東京世田谷「キャロットタワー」、2005年3月)、須坂クラッシック美術館「大正浪漫のおしゃれ―銘仙着物―」(長野県、2007年8月)、京都府城陽市歴史民俗資料館「銘仙―レトロでモダンでおしゃれな着物―」(京都府、2008年8月)、神戸ファッション美術館「華やぐこころ―大正昭和のおでかけ着物―」(兵庫県、2008年11月)など。
(註3)の公式サイト「着物de銀座」(管理人:京屋悟雀氏)を参照
http://www.kimono-de-ginza.net/sub2.htm
(註4)2013年段階で継続しているものとして「着物日和in信州須坂」「奈良きもの日和」「きもの日和 in TOMO」(広島県福山市鞆の浦)などがある。また「群馬きもの復興委員会」「NPO法人川越きもの散歩」のように、それぞれの地域で積極的な着物普及活動をするグループも増えた。
(註5)京都の着物問屋「きものACT」が現地の職人さんに依頼して生産していた足利銘仙は2010年頃に、NHKの朝の連続ドラマ「カーネーション」(2011年度後期)で話題になった「木島織物」の伊勢崎銘仙は2012年末に生産が止まった。
文献
石川光陽1987『昭和の東京 ―あのころの街と風俗―』(朝日新聞社)
小泉和子2000『昭和のくらし博物館』(河出書房新社)
通崎睦美2002『天使突抜一丁目 ―着物と自転車と―』(淡交社)
鳥羽亜弓2001『浴衣の次に着るきもの(アミサンノキモノ)』(インデックス出版)
日本きもの文化美術館2010『ハイカラさんのおしゃれじょうず -銘仙きもの 多彩な世界-』(日本きもの文化美術館)
早坂伊織2002『男、はじめて和服を着る』(光文社新書)
別冊太陽2000a『昔きものを楽しむ(1)』(平凡社)
別冊太陽2000b『昔きものを楽しむ(2)』(平凡社)
別冊太陽2001『昔きものと遊ぶ』(平凡社)
別冊太陽2002『昔きものを買いに行く』(平凡社)
別冊太陽2003『昔きものの着こなし』(平凡社)
別冊太陽2004a『昔きもの 私の着こなし』(平凡社)
別冊太陽2004b『銘仙 ―大正・昭和のおしゃれ着物―』(平凡社)
村上信彦1974『服装の歴史2(キモノの時代)』(理論社)
三橋順子2002「艶やかなる銘仙」(『KIMONO道』2号、祥伝社。後に『KIMONO姫』2号、2003年、祥伝社、に拡大再掲)
三橋順子2006「着物マイノリティ論」(『Kimono人 2006』きもの日和実行委員会)
三橋順子2010「銘仙とその時代」(『ハイカラさんのおしゃれじょうず -銘仙きもの 多彩な世界-』日本きもの文化美術館)
【講演録】「男の娘(おとこのこ)」なるもの ―その今と昔・性別認識を考える― [論文・講演アーカイブ]
駒沢女子大学日本文化研究所『日本文化研究』第10号(2013年3月)掲載
.jpg)
---------------------------------------
平成24年(2012)度(駒沢女子大学)日本文化研究所主催講演会 2012年6月15日
「男の娘(おとこのこ)」なるもの
―その今と昔・性別認識を考える―
三橋 順子(性社会・文化史研究者 都留文科大学・明治大学非常勤講師)
皆さん、こんにちは。三橋でございます。このたびは私のような者をお招きいただき、大変うれしく思っております。自己紹介するとそれだけで持ち時間が終わってしまうようなややこしい人間なので、今、所長先生からお話がありましたように、適当に中に折り込んでいこうと思います。
最初にこちらにご縁をいただきましたことを少しお話ししておきます。以前、駒沢女子大学にいらした日本古代史の倉本一宏さんが京都の国際日本文化研究センターに着任をされました。私はもう10年ほど前から井上章一さんという建築史・風俗史の先生が主宰する「性欲の文化史」「性欲の社会史」の共同研究のメンバー(共同研究員)として年に5~6回、京都へ通っていました。
日文研は共同研究を重視する組織で専任の先生は他の先生の共同研究会にもいくつか出ないといけないというルールがあります。それで井上さんが倉本さんの研究会に出ることになりました。倉本さんが主宰されているのは主に平安、鎌倉の貴族の日記、そこから広げた日記の総合的研究という研究会です。井上さんが「僕、貴族の日記なんて読めないし、わからない。少しサポートしてもらえませんか」ということで、井上さんのお伴で私も倉本さんの研究会の共同研究員になりました。
その懇親会のときに、研究会の中核のメンバーの方たちは、日記のことばかりマニアックに話しています。その話についていけないメンバーは、端のほうに座っています。私も昔は平安時代の日記をやっていたのですが、もういいやと思っているので、隅っこのほうに座ります。そうすると、だいたい同じテーブルに池田先生、蘭先生、富田先生がいらっしゃる。そこでいろいろお話するようになったわけです。
そんな感じで、日文研の倉本さんの研究会つながりなのですが、お互い中核ではなく周辺、少し外れたところにいる者同士というつながりで、そう考えると、大変おもしろいご縁です。
ところで、私は都留文科大学で「ジェンダー研究」の講義を担当しているのですが、先ほど、佐々木先生とお話していて、先生が都留の方で、さらになんと都留市の谷村という町に嫁いだ私の叔母の菩提寺のご住職であることがわかり、本当にびっくりいたしました。人の縁(えにし)というものは実に不思議なものだと改めて感じております。
そんなご縁があって講演会に呼んでいただき、さて何をお話ししたらいいのだろうと悩みました。私は性社会・文化史という専門を名乗っております。日本におけるジェンダー&セクシャリティの歴史研究ということですが、もっぱら日本における性別越境、トランスジェンダーの研究をしております。お話をいただいたころに調べていたのは、昭和戦前期の大阪の女装男娼、つまり女装のセックスワーカーのことでした。それはいくら何でもあまりにもマニアックだろう、もう少し現代的なポピュラーな話題の方が興味をもっていただけるだろうと考えました。
そこで、こちらの研究所の総合テーマが「女性なるものと男性なるもの」とお聞きしていましたので、それでは、その間で行こう、女性なるものと男性なるものの境界領域をお話しようと、「『男の娘(おとこのこ)』なるもの」というテーマを思いつきました。ということで、今日は「男の娘」という最近の事象について、社会における性別認識という視点を絡めてお話することにいたします。
「男の娘(おとこのこ)」とは?
「男の娘」と書いて「おとこのこ」と読ませます。誰が考えたのかよくわからないのですが、なかなかしゃれたネーミングです。ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、なんのことやらわからないという方もいらっしゃると思います。その程度の社会的浸透度の新しい言葉です。
「男の娘」はまだ定義が固まっている言葉ではありません。いくつかご紹介しましょう。「まるで女の子のような男の子、女装している男性のこと」(『オトコの娘(こ)のための変身ガイド』)。「女の子のようにカワイイ女装少年のこと」(『わが輩は『男の娘』である!』)。あるいは、「二・五次元に生息する、(中略)女の子よりカワイイ男の子」(ニコニコ動画「男の娘ちゃんねる」)。二次元というのはいわゆる紙媒体、アニメの世界、そして三次元が現実世界ですから、二・五次元はその中間ということです。ウィキペディアは、「男性でありながら女性にしか見えない容姿と内面を持つ者」という定義です。これだと、それ以前の「女装」している人たちとの差違化が全くできていないので、あまりよろしくありません。
今、定義を四つ申しましたが、そのうちの二つに「カワイイ」という言葉が入っています。これが一つのキーワードだと思います。そこで、私なりの定義を示しますと「まるで女の子のようにカワイイ、女装した男の子」ということになります。
「男の娘」の出現
次に、「男の娘」というネーミングがいつ出てきたのかということをお話します。書籍でまず注目しておきたいのは、2007年9月に出た『オンナノコになりたい!』です。書名には「男の娘」とは入っていないのですが、帯の記述の中に「もっとかわいい男の娘になろう」と入っています。ただ帯は後からつけ替えられるので、少し不安があります。私の持っているのが第二刷で、初刷りではないので、余計に不安です。
書名に「男の娘」が入っているものとしては、2008年10月に女装普及委員会というところが出した『オトコの娘(こ)のための変身ガイド―カワイイは女の子だけのものじゃない―』(画像1)が最初だと思います。
E382AAE38388E382B3E381AEE5A898E381AEE3819FE38281E381AEEFBC882008E5B9B410E69C88EFBC89.jpg)
【画像1】
私は、2008年9月に『女装と日本人』という講談社現代新書を出しました。執筆は2007年です。その段階では、私の頭にはまだ「男の娘」という文字は入っていませんでした。ということは、「男の娘」というネーミングが社会の表面に浮上したのは、やはり2008年ではないか?と思います。
ところで、この『オトコの娘(こ)のための変身ガイド』という本は、男の子が女の子の格好をするためのテクニックやいろいろなアイテムに関して事細かに記している女装指南本です。こんな本が普通の書店で売られることすらびっくりしたのに、これ一冊だけで1万5000部以上、全4冊シリーズで6万部というかなりの売れ行きになったことも衝撃的でした。同時期に出た私の『女装と日本人』が1万部ぐらいしか売れないのに…、すごく悔しいです。
その後、2009年5月に『オトコノコ倶楽部』という女装美少年総合専門雑誌が三和出版から刊行されます。三和出版はもっぱら成人雑誌を出している出版社ですが、少し前まで『ニューハーフ倶楽部』(1995年3月~2007年8月)というニューハーフ(身体を女性化した男性、女装した男性であることをセールスポイントにした商業的なトランスジェンダー)をメインにした雑誌を出していました。私も連載コラムを2本持っていたのですが、コロッと宗旨替えして新しい流れに乗ったということです。このあたりまでくると、どうも様子がおかしいぞということに、私も気づいておりました。
その少し前、2008年の4月、私が銀座四丁目の「和光」の前におりましたら、背が高くてスタイルがいい振り袖のお嬢さんが、お母様らしき着物の女性と二人で、目の前を通過していったのです(画像2)。「あれ?」と思って、少し後をつけました。あれ?と思ったのは、スタイルが良すぎるというか、写真を見ればわかるように、少し袖で隠れていますが、お尻が小さいのです。つまり、女性ではないのではないか?ということを、直観的に感じたわけです。そこらへんの「目利き」は私のように女装業界に長くおりますと、自然と身についてきます。
E98A80E5BAA7E381AEE68CAFE3828AE8A296E3808CE5A898E3808DEFBC882008E5B9B44E69C88EFBC89.jpg)
【画像2】
後で、お話をうかがうと、やはり男性でした。左側の40歳ぐらいの女性が、右側の25歳ぐらいの男性に自分のお振り袖一式を着付けて、お化粧もしてあげて、銀座に連れ出したということでした。
そう言えば、少し前に新宿や渋谷で、「あれ、今の女の子の二人連れ、片一方は男の子じゃないかな?」と気づいたことが数回あったことを思い出しました。一見、女性の二人連れに見えるのですが、実は片方が女装した男の子というカップルです。そういう現象がひそかに増えていることに、私が気付いたのが、だいたい2008年の春ぐらいだったということです。たった4年前ぐらいのことです。
ちょうどその頃、今、京都造形芸術大学の成実弘至先生から、『コスプレする社会―サブカルチャーの身体文化』という本を一緒にやらないかというお話をいただきました。それで、『女装と日本人』に書いた後の女装世界の変化をフォローした「変容する女装文化」という論考を執筆しました。「男の娘」というネーミングは使いませんでしたが、後に「男の娘」とネーミングされるような若い女装者の意識の変化や、新しい現象として女性と女装した男性のカップルの話を取り上げたわけです。自画自賛になりますが、こうした女装文化の変化に真っ先に気づいて考察した論考が「変容する女装文化」ということになります。
マス・メディアへの登場
「変容する女装文化」を掲載した『コスプレする社会』は2009年6月に刊行されましたが、大手のメディアが「男の娘」現象に気づき始めたのは、その半年ほど後でした。12月に共同通信の記者から電話インタビューの依頼がありました。「おっ、やっと気付いたか」という感じでした。そのコメントが載ったのが、「きれいならOK?『女装男子』急増」という記事で(2009年12月22日配信)、こんな写真を載せていました(画像3)。秋葉原のメイドカフェで、メイドの格好をした女装の男の子が、本物の女性のお客さんに飲み物を運んでいる写真で、新しい現象のポイントをよく捉えています。つまり、後で詳しく申しますが、女装した男の子と女性との関係性です。
E794B7E381AEE5A8981-e63a3.jpg)
【画像3】
年末にはなんとNHKワールドからコメント出演の依頼がありました。NHKワールドは英語で世界百何十何カ国に放送している国際放送局ですが、NEWS LINEというニュース番組の中で現代日本の若者の女装文化を取り上げたいという話でした。私は驚いて「そんなことを取り上げて、世界に放送していいんですか」と問い返しました。そうしたら「実は、日本国内よりも外国で注目されているので、十分ニュース価値があるんです」というディレクターのお話でした。
年が明けた2010年の2月に「Boys Will Be Boys?」(少年は果たして男の子になるのでしょうか? もしかすると男の娘になっちゃうかもしれませんよ)という5分間ほどの特集で、現代日本の若者の一つのカルチャーとして「女装」する男の子現象が世界に紹介されました。DVDを持ってきましたので時間があったら、後でお見せします。
2010年8月には、共同通信がもっと本格的な「ニッポン解析:女装楽しむ『男の娘(こ)』」という記事を出しました(2010年8月25日配信)。銀座の街を歩いているのは二人とも「男の娘」です(画像4)。このような流れで、「男の娘」現象がマス・メディアで認知されたのは2010年ということになります。
E794B7E381AEE5A898EFBC93-168e0.jpg)
【画像4】
2011年11月には朝日新聞に、「『男の娘』(オトコノコ)になりたくて」という記事が出ました(2011年11月12日夕刊)。とうとう朝日新聞にまでと感慨深かったです。ついこの間、2012年5月には「男装大好き!」という題で、今度は女の子が男の子の格好をしているのが徐々にブーム化しているという記事が朝日新聞に載りました(2012年5月26日)。比べてみたら違う記者が書いているので、一人だけマニアックな記者がいるわけでもなさそうです。
男装のお話をする場がないので、ここでちょっとだけ触れておきますと、女性のファッションの範囲はとても広いので、極端に言えば、女性がどんな格好をしても、女性の幅広いファッション・カテゴリーの一部だと見なされてしまって、なかなか男装になりません。それこそ髭でもつけない限りは男装が成立しない、そういう意味で、男装の困難さがあるのです。朝日新聞の「男装大好き!」という記事の写真を見ますと、私からするとやはり女の子がボーイッシュなファッションをしているように見えてしまいます。ただし、本人たちは男装のつもりでやっている、そしてそこに「女子ファン増殖中」とあるように女の子が寄ってくる。男装女子がある種のアイドルとして、女の子にもてるという現象が社会の表面に出てきたというのは、なかなか興味深いことだと思います。
合わせて考えれば、コスチューム・プレイという感覚で、性別表現の転換が容易になっている。男女両方からの行き来がかなり自由になってきている。そして、そうした行為に対する評価が、以前のような「そんなことをするのは変態」というマイナスではなく、ある種のアイドル性を持った肯定的なプラス評価になってきている。そこが大きな変化、いちばん大事なポイントでだと思っています。
まとめますと、「男の娘」現象は、2008年ぐらいから社会の表面に浮上して、2010年にメディアに認知され、若者たちの間の異性装ブームは、現在進行中と言うことです。
「男の娘」の起源
もう少し掘り下げてみましょう。「男の娘」の定義のところで「二・五次元」云々という話が出てきましたが、「男の娘」の淵源は、二次元媒体、漫画、コミック、あるいはもっとローカルな、コミケ(コミック・マーケット。年二回開催される大規模な同人誌即売会)などで売られているコミック同人誌にあります。
確実なところでは、2006年9月に「男の娘 COS☆H」という名前の同人誌即売会が行われています。さらに、2000年の春頃、巨大インターネット掲示板で有名な「2ちゃんねる」の中で、「男の娘(おとこのこ)」という表現があったという話があります。ただこれは確認できていません。2000年代の前半、しかも早い時期に、マニアックな二次元媒体の中で「男の娘」というネーミングが生まれていたことは間違いなさそうです。
さらに、「男の娘」の元祖は、1980年代半ばにベストセラーになった江口寿史『ストップ ひばりくん!』の主人公大空ひばり(画像5)であるという説があります。『ストップ!! ひばりくん!』は、1981年~1983年の連載で、もう20年前の漫画です。私はリアルタイムで読んでいましたし、その世代の女装者には、やたらと「ひばり」という名前(女装名)の人が多くて、影響力があったことは間違いありません。しかし、これは「始祖伝説」のような話で、そういうふうに仮託されているということでして、日本最初の天皇は神武天皇というのと同様に歴史的事実として語れる話ではありません。
E382B9E38388E38383E38397E381B2E381B0E3828AE3818FE38293201-194cb.jpg)
【画像5】
「男の娘」の起源としていえることは、少なくとも2000年代の前半にコミック世界で女装した美しい男の子が「女装美少年」とか「化粧男子」とか、いろいろな名称で語られていて、それらのうちの一つが「男の娘」だったということです。
ところで、「娘」と書いて「こ」と読ませることですが、女装者を「女装娘」と書いて「じょそこ」と読ませることが、すでに1990年代前半の東京新宿の女装コミュニティで広く行われていました。その起源は1950年代に始まる男性同性愛者のコミュニティにおける女装する男性への侮蔑的な呼称である「女装子」にあります。男性同性愛者の世界は基本的に「男らしさ」を価値基準にする女性性嫌悪の強い世界ですから、「女らしい」人や女性の格好をする人は下位に位置づけられます。
ちなみに、なぜかゲイ業界では「〇〇子」という表現が好まれます。店で働いているゲイの人を「店子」と書いて「みせこ」と言います。「『店子』と書いたら普通は『たなこ』と読むのよ」などと言うと、「このばあさんは何を言っているんだ」と怪訝な顔をされるわけです。言葉としての「男の娘」、「娘」と書いて「こ」と読ませることには、そんな文化伝統があるわけです。
これまで述べたことをまとめますと、「男の娘」という言葉は、2000年代の前半、しかも早い時期に、マニアックなコミック世界で生まれ、最初はあくまでも二次元媒体の存在だったのが「コスプレ」などを通じて徐々に肉体を持った三次元キャラクターとして実体化していき、2008年ごろから社会の表面に現れてきて、2010年に「男の娘」現象としてマス・メディアの認知を得た、最初はある種のファッション・カテゴリーであったものが、ミニ流行化の中で次第にジェンダー・カテゴリーという感じになっていった、そんなところだと思います。
「男の娘」の実際
さて、二次元キャラクターの「男の娘」はいくらでも理想化が利きます。どんどん可愛く描けばいいわけです。ところが、三次元の「男の娘」はそうはいきません。皆さん、それなりに苦労しています。ここで、どんな「娘」がいるかちょっと見てみましょう。
この「娘」は、私の友人の吉野さやかさんです(画像6)。「彼女」に最初会った時、私ですらわかりませんでした。これはお友達の結婚パーティのときの写真を借りてきたのですが、本当に普通に女の子という感じで、こういう「娘」が現に存在しているのです。
E59089E9878EE38195E38284E3818B(2011E5B9B48E69C88)-2bd3c.jpg)
【画像6】
こちらの「娘」は、毎月、新宿歌舞伎町で「女装 ニューハーフプロパガンダ」というイベントを主催しているモカちゃんです(画像7)。彼女はイベントの主催者であると同時に、イベント最大のスターという存在です、この「娘」も、わかりませんでした。カワイイ女の子がいるなと思ったら「男の娘」で、びっくりでした。
E383A2E382AB20(2012E5B9B41E69C88)-19fc7.jpg)
【画像7】
これはテレビなどでときどき見かけるモデル兼タレントの佐藤かよさんです(画像8)。彼女は自分で「男の娘」とは名乗っていないと思いますが、世代的、容姿的、カワイイ系のファッションという点で、まさに最先端の「男の娘」だと思います。
E4BD90E897A4E3818BE38288(2011E5B9B4EFBC89-ca9d2.jpg)
【画像8】
こちらは、私の「娘分」的な存在の井上魅夜さんです(画像9)。以前は仲の良い後輩の女装者を「妹分」と言っていたのですが、もう無理です。どう考えても姉妹というより母と娘の年齢差ですから。この「娘」、身体的にまったく女の子サイズなので「男の娘」だとはまず気付かれません。黙っていればですが・・・。
E4BA95E4B88AE9AD85E5A49C.jpg)
【画像9】
2009年11月に、この井上魅夜さん主宰の「東京化粧男子宣言!」というイベントが行われました。早い話、化粧男子のミスコンです。これがそのポスターですが(画像10)、描いているのはいがらしゆみこさんという漫画家です。1970年代に「キャンディ・キャンディ」という大ヒット作がある方です。若い方はあまりなじみがないかもしれませんが……。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A880200920-2-d72ac.jpg)
【画像10】
では、なぜ、いがらし先生のような大家がポスターを描いてくださったのかといいますと、これは2010年12月に出た『わが輩は「男の娘」である!」という本です(画像11)。帯のところに、「こんな立派な『男の娘』になってくれて…… 母は嬉しいです!(実母・いがらしゆみこ)」と書いてあります。つまり、この本の著者いがらし奈波さんがいがらしゆみこ先生の息子さんなのです。
E794B7E381AEE5A898E381A7E38182E3828B(2010E5B9B412E69C88)-58968.jpg)
【画像11】
これは「東京化粧男子宣言!」のオープニングの写真です(画像12)。左側が主催者の井上魅夜さん、真ん中が審査員で「ニューハーフ女優」の月野姫さん、そして右側が司会のいがらし奈波さんです。つまり、司会の奈波さんの縁でいがらし先生にポスターを描いてくださったわけです。さらに、いがらし先生には審査委員長をお願いしました。審査員席で、私の隣がいがらし先生だったのですが、カワイイ「男の娘」になった息子さんの活躍を、本当にうれしそうに見ていました。まさに母親公認で、世の中つくづく変わったと実感したわけです。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A880200920-3-464b3.jpg)
【画像12】
さて、「東京化粧男子宣言!」の審査結果です。決勝進出の8人から審査員一致で(会場投票もトップ)グランプリに選ばれたのが、るるさんでした(画像13)。シャボン玉をふーっと吹くパフォーマンスで「男の娘」の最大のポイントである「カワイイ」を巧みに表現していました。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A880200920-5E584AAE58B9DE88085E3828BE3828B-8be4b.jpg)
【画像13】
これは優勝者を囲んだ審査員一同の写真です(画像14)。左からいがらし先生、グランプリのるるさん、月野姫さん、私です。全員女性のように見えますが、戸籍上の女性はいがらし先生だけという写真です。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A880200920-6E5AFA9E69FBBE593A1E381A8E584AAE58B9DE88085-9ca68.jpg)
【画像14】
るるさんにそっと「あなた、学生さんらしいけど、大学はどこ?」と聞いたら、「少し硬派なイメージがある、渋谷の……」という返事で、なんと私の後輩(笑)。またびっくりでした。要は、こんなかわいい「娘」がごく普通の男子大学生ということです。
「男の娘」を遡る
これが現代の状況です。しかし、こういうカワイイ女の子に見える男の子、「男の娘」的な存在が過去にいなかったかというと、そうでもありません。「男の娘」というネーミングは現代的なものですが、実態的に似たような「娘」が過去にも存在していました。そこで、次に「男の娘」的存在を過去に遡ってみましょう。
まず、1994年の浅草寺のほおずき市での写真です(画像15)。右側(私)は大貫録の姐さん風ですが、左側の岡野香菜さんは20代後半、当時江東区の亀戸にあったアマチュア女装クラブ「エリザベス会館」の若手スターです。
E9A086E5AD90EFBC881994E5B9B47E69C88EFBC89-1e0c5.jpg)
【画像15】
次は、20年ほど遡って1973年の中野のあるマンションのベランダで焼肉パーティをしている写真です(画像16)。写っているのは夢野すみれさんという女装秘密結社「富貴倶楽部」で若手ナンバーワンと呼ばれた方。大学を卒業して間もない20代前半だと思います。現在の「男の娘」と年齢的にはほとんど変わりありません。こういうカワイイ「娘」が1970年代にもいたのです。
E5A4A2E9878EE38199E381BFE3828CEFBC881973E5B9B4EFBC89-e03c4.jpg)
【画像16】
こちらは1969年、東京日比谷です(画像17)。お堀の石垣を背に大振袖で立つのは、佐々木涼子さんという方。実年齢は30代だと思いますが、やはり「富貴倶楽部」の有力メンバーで、振袖女装で有名だった方です。
E4BD90E38085E69CA8E6B6BCE5AD90EFBC881969E5B9B4EFBC89-10767.jpg)
【画像17】
次は、東京オリンピック直前の1964年6月の新宿駅東口駅前でのスナップです(画像18)。右側のお二人は少し年配、30代だと思います。左の横を向いている松葉ゆかりさんは、当時25歳で、今の「男の娘」と年齢的に変わりません。60年代の「富貴倶楽部」の若手花形で、私はこの方のロングインタビューを採ったことがあります。
E696B0E5AEBFE9A785E5898DE381AEE5A5B3E8A385E88085EFBC881964E5B9B46E69C88EFBC8920(2).jpg)
【画像18】
戦前に飛びます。横書きの文字が今と逆ですが、「これが男に見えますか」というキャッチコピーが入ったタブロイド判(夕刊フジの大きさ)の新聞号外です(『東京日日新聞』1937年3月31日特報)。写っているのは福島ゆみ子という24歳の人です(画像19)。風紀係の私服刑事が、銀座七丁目の資生堂の前で声をかけてきた女性を「密淫売」(無届売春)の容疑で逮捕して築地署に連行し取り調べたら、なんと女性ではなく女装の男性だったという事件を報じたものです。
E7A68FE5B3B6E38286E381BFEFBC881937E5B9B4EFBC8920(2)-0f5c0.jpg)
【画像19】
ちなみに、現在の売春防止法もそうですが、戦前の売春関係の法律も売春の行為主体を女性に限定していますので、男性だとわかった途端に罪状が消えてしまい、仕方なく(厳重説諭の上)釈放になります。ゆみ子さん、釈放になるので余裕でポーズを作っています。違う新聞の写真には「男なんて甘いわ」というセリフがついています。昭和戦前期には、非合法売春の容疑で捕まった女装男娼が何人か新聞報道されていますが、私が見る限り彼女がいちばんの美形です。
さらに時を遡りましょう。これは江戸時代中期、18世紀後半に活躍した鈴木春信(1725?~70)の作品です(画像20)。春信は錦絵の大成者として知られる浮世絵師で教科書にも出てくるとても有名な人です。前を歩いているのはもちろん男性で、後ろを歩いている華麗な大振袖、島田髷の人は、今の私たちの目には娘に見えますが、当時「陰間」と呼ばれた、芸能・飲食接客・セックスワークを職業にした女装の少年です。これから贔屓筋の座敷に出勤するところです。
E6B19FE688B8E69982E4BBA3E999B0E996931-fd07f.jpg)
【画像20】
こちらは、少し後の浮世絵師、北尾重政(1739~1820)の「東西南北美人」シリーズの「西方の美人 堺町」です(画像21)。江戸の東西南北の美人を2人ずつ描いた4枚のセットですが、残念ながら全部残っていないようです。確認できる「東方」は深川の芸者を描いていて、たぶん「北方」は吉原の遊女、「南方」は品川の飯盛女(実態は遊女)でしょう。どれもまちがいなく女性ですが問題はこの「西方」です。立ち姿が橘屋の三喜蔵、座っているのが天王寺屋の松之丞という子で、松之丞は江戸の町娘のあこがれだった黄八丈の振袖姿です。もうあらためて言うまでもないと思いますが、「西方の美人」は女性ではなく、女装の少年なのです。
E6B19FE688B8E69982E4BBA3E999B0E9969324-cdde8.jpg)
【画像21】
このようにさかのぼっていくと、「男の娘」的存在がぞろぞろと出てくるわけです。なぜ前近代の日本にそういう「娘」がたくさん出てくるのか、そこら辺のことは私の『女装と日本人』に詳しく書いてありますので、ご参照いただければ幸いです。
もう一息です。これは鎌倉時代末期に描かれた『石山寺縁起絵巻』です(画像22)。この子が着ている橙色の衣服、肩が割れていないので少年が着る水干ではなく、女性が着る袿(うちき)です。履物もけばけばしています。藺げげ(いげげ)という当時の若い女性の履き物です。後にお坊さんがいます。首が切れていますが…。この時代、僧侶は戒律で女性と行動を共にしてはいけません。お坊さんの連れが少女ではまずいのです。つまり、この子は女装の稚児です。きっと後ろにいる師匠のお坊さんが(性的にも)可愛がっている「娘」なのでしょう。
E98E8CE58089E69982E4BBA3E7A89AE585901-42089.jpg)
【画像22】
これで最後です(画像23)。私の話を何度も聞いてくださっている方は「またか」と思われるかもしれませんが、やはり行き着くところは女装の建国英雄・ヤマトタケルになってしまいます。これは三重県鈴鹿市の加佐登神社に奉納されている大きな絵馬です。ヤマトタケルは少女の姿になって九州の豪族クマソタケル兄弟の館に入り込み、その美少女ぶりで兄弟を魅了します。絵馬は長い垂れ髪に緋色の裳の女姿のヤマトタケルがクマソタケル兄弟をやっつける場面を描いています。ヤマトタケルの右手に握られた剣はすでに血にまみれていて。すでにクマソタケル兄の方を殺し、これから青い衣の髭面のクマソタケル弟を刺そうとするところです。ヤマトタケルはこのとき16歳。まさに元祖「男の娘」です。
E383A4E3839EE38388E382BFE382B1E383AB-5fd8c.jpg)
【画像23】
こうして歴史を遡ってみますと、「男の娘」的存在は日本の長い歴史の中に常に存在していたことがわかります。言葉を変えるならば、現在、ミニブームになっている「男の娘」も、男でもあり女でもある双性、ダブルジェンダー的な存在への強い嗜好に支えられた日本の性別越境文化の末裔であり、決して現代の特異現象ではないということです。メディアは新しいものが大好きなので、最新の社会現象だと騒ぎますが、実は根っこはずっと続いているのです。「男の娘」は、2000年の長い歴史を持つ日本の女装文化の21世紀リニューアルバージョンだと、私は理解をしています。
「男の娘」出現の背景
さて、再び現代の「男の娘」に戻って、もう少し深く考えてみましょう。まず「男の娘」がクローズアップされてきた背景です。1990年代後半から2000年代前半は、性別を越えて生きたいと考えることを「病」、精神疾患だと考える性同一性障害という概念が大流行した時代です。メディアの報道も性同一性障害一色でした。こうした性同一性障害の概念の大流行で、従来の女装世界、例えば女装スナックやバーを拠点に形成されている新宿の女装コミュニティは、長年培ってきた人的資源をごっそり奪われて大打撃を受けました。わかりやすく言えば、「女になりたい」と思う人は、それまではお店に来ていたのが、病院に行くようになってしまったわけです。
私は1995年から2001年まで6年間、新宿歌舞伎町の老舗の女装スナック「ジュネ」やニューハーフ・パブ「MISTY」でお手伝いホステス(ゲスト・スタッフ)をしていていました。ちょうど性同一性障害の概念が流行していった時期です。『女装と日本人』を書いた理由の一つは、性別を越えて生きることが精神疾患であるという病理化の思想が社会に蔓延してしまうと、ヤマトタケル以来連綿と続いてきた日本の女装文化は終わりになってしまう、ならば、こういう世界があったんだということをちゃんと調べて書き残そう、そう思って、1998年頃から歴史学や社会学の勉強をし直して学術的な女装文化の研究を始めたわけです。つまり、日本の女装文化の遺言を書くようなすごく悲観的な気持ちで書き始めたのですが、先ほど述べましたように、執筆しているうちにあれ、何か様子が変だぞ、流れが微妙に変わりつつあるぞ、という感じになったのです。
性同一性障害の概念には、医療によって身体の女性化を進めていくことを重視して、性別表現、ファッションや化粧というものを軽視する傾向があります。そのアンチテーゼとして、性別表現を重視した自己表現的な性別越境の形が復活してきた。「男の娘」現象の背景には、そうした性別越境をめぐる大きな流れの転換があると考えています。
メディアも、性同一性障害を10年間も報道すると、もう番組の作り方がなくなってきます。さらに言えば、重苦しさがつきまとう性同一性障害の報道にそろそろ嫌気が差していた。「また性同一性障害かよ、もうちょっと飽きてきたな」と思い始めていたところに、もっと楽しく気軽に性別を越えようという「男の娘」が浮上してきたわけです。メディアは、何度も言うように新しいものが大好きですから、そちらに飛びついた。そういうメディアの視点の転換も、「男の娘」がクローズアップされた背景にあったと思います。
ただし、性同一性障害概念の流布以前に戻ったわけではなく、「男の娘」たちの多くは1990年代まで主流だった新宿の女装コミュニティとは一線を画しています。そもそもエリアが違います。新宿ではなく秋葉原、中心が東京の東側へ動きました。「東京化粧男子宣言」の井上魅夜さんは、2011年12月に「若衆バー 化粧男子」という店を出したのですが、場所は新宿ではなく秋葉原の北の湯島でした。
もっとも、女装世界の中心は、新宿に移る前は上野や浅草でした。戦後最初の女装した女将さんがいるバーは「湯島」という名で、その名の通り湯島天神の男坂の下にありました。さらに言えば、江戸時代、女装の少年が接客する陰間茶屋の江戸における三大密集地の一つが湯島天神界隈でした。徳川将軍家の菩提寺である上野寛永寺のお坊さんが最大の客筋でした。そういう意味では、「男の娘」の拠点が秋葉原や湯島になったのは、先祖返りとも言えます。
「男の娘」の内実
次に「男の娘」の内実です。これはけっこう複雑で、趣味のコスチューム・プレイ(コスプレ)としてやっている女装者から、将来的には女性への性別越境を考えている、つまり戸籍まで女性に変えたいという子までかなり幅広いです。性同一性障害の診断書を持っている子も少なくありません。ですから、身体の女性化の程度も様々で、ほとんど何もしていない人もいれば、女性ホルモン継続の投与だけという人もいれば、外性器の手術(睾丸摘出手術や造膣手術)までしてしまっている人もいます。「男の娘」と言っても中身はいろいろなのです。
性的指向(セクシュアル・オリエンテーション)も一定ではありません。「女好き」、つまり、女の子の格好で女の子が好きという見かけ上レズビアンも多いですが、「男好き」(見かけヘテロセクシャル)もいます。バイセクシャルもいます。
1990年代後半から2000年代にかけては、女装あるいはトランスジェンダーというカテゴリーと、性同一性障害というカテゴリーの間に、かなり強烈な対立がありました。「あなたはどっちなの?」という感じ。ところが「男の娘」は、そうした対立、境界にこだわらない傾向があります。「そんなのどっちだっていいじゃないですか」という感じ。そうした概念へのこだわりのなさも新しいところです。つまり、「男の娘」の内実はかなり多様であり、良く言えばそうした幅広さ、悪く言えばとらえどころのなさ、無思想性が特色になっていると言えます。
「男の娘」出現の条件
次に、「男の娘」出現の条件です。なぜ「男の娘」が出てきたのですか?という質問はメディアの取材で必ず聞かれます。
第一に大きいのは情報流通の変化、具体的に言うとインターネットの普及です。インターネットの普及以前、女装やニューハーフの世界は、まさに閉ざされた世界でした。
先ほどお話した歌舞伎町の女装スナック「ジュネ」)の先輩で、200軒以上の飲み屋が集まっている新宿のゴールデン街を端から飲みまくって、10万円ぐらい飲んだところでやっと女装の店の情報に行き着いたという人がいます。1980年代後半、もう25年くらい前の話ですが、世の中にほとんど情報が回ってなく、伝手をたどってその種のお店を探すしかなかったわけです。どうやったら化粧ができるか、そういう情報もありません。女装やニューハーフの世界になんとかしてたどり着かないと、いくら女の子になりたくても始まりませんでした。
今は、インターネットでいくらでもお店の情報や女装テクニックが簡単に得られるようになりました。初めの方で紹介したように女装指南本が一般の本屋で売られている時代です。昔は女装の専門雑誌を買うのもけっこう大変で、どこに行けば売っているのか、なかなかわかりません。売っている場所に行っても、買うのにすごいドキドキでした。どうしても勇気が出なくて店の前を何度も往復してとうとう買えなかった、なんて話もあります。ともかく、ものすごく敷居が高い世界でした。それが今はもうまったく違います。
第二は男の子たちの顔や体形の変化です。私、今はすっかり太って丸顔ですが、若いころは1000人に1人の女顎、つまり三角顎だと言われたことがあったのですが、悔しいことに今、私レベルの三角顎の男の子はごろごろいます。そのくらい日本人の男性の顔立ちは変わってきています。フーテンの寅さん、渥美清さんのようなエラが張っているホームベース型の顔で、髭の剃り跡が青く見えるような男の子は本当に少なくなっています。顎のラインがすっきりした、髭もあまり濃くないような子が増えています。体形も手足が長く、骨格がずいぶん華奢になり、女物の9号の服が着られるような男の子が増加しています。つまり、男の子の顔立ちや体型が女装向きに変化してきています。昔に比べて「女の子になる」ベースに恵まれている男の子が多くなっているわけです。
第三に社会環境の変化があります。男の子が髪を長くのばしたり、眉を細く手入れしたり、髭や手足の体毛を脱毛していることが、それほど奇異に見られなくなっています。別に女の子になりたいわけでなくても、身体のメンテナンスに気を遣うおしゃれな男の子が増えていますから、そういう女装のための身体条件を整えることをしても、あまり目立ちません。
社会全体として性別の越境に対する許容度・自由度が以前に比べればだいぶ緩くなっています。コスチューム・プレイという感覚で、男性と女性の間を行って戻ってみたいなことがかなり自由になっている。社会環境として性別の越境、性別表現の転換が容易になっているということです。昔はそこに乗り越えなければならない高い壁のようなもの厳としてありましたったのが、私の世代だと、女装すること自体がものすごく大変で、そこに至るのに何年かかるという世界だったわけです。たとえば、私は振袖を着たいと思ってから実際に振袖姿で外へ出るまで20年近くかかっています。ところが最初に紹介した銀座の振袖「男の娘」は、2回目の女装でした。それほど違うのです。心理的な、もしくは社会的な、越えなければいけない障壁がとても低くなっています。
第四は、女性が男の子の女装を受け入れるようになったことです。女装した男性と一緒に遊ぶ、さらには積極的に女装に協力するような女性が確実に増えてきています。化粧にしてもファッション・コーディネートにしても、男の子が一から独力で覚えるのと、女性が協力してくれるのとでは、進度も到達レベルもまったく違います。こうした関係性の変化については、また後で詳しく述べます。
第五は、これがいちばん重要なことですが、価値観の変化です。昔は男が女の格好をする、女装することは、男性上位社会において明らかな社会的下降でした。よりによって「女『なんか』になる」という感じです。ですから、女装にはしばしばマゾヒズムが伴っていました。マゾヒズムについては、富田先生がここでお話になったと思うのですが、わざわざ女という低い身分になる、「あたし、とうとう女に墜ちちゃったわ」というような被虐的な陶酔にひたる女装者は少なくありませんでした。
ところが、今の「男の娘」たちはまったく違います。現代の男の子は同世代の女の子のライフスタイルに、かなり強いあこがれを持っています。男の子のライフスタイルは冴えないけれども、女の子たちはとても輝いている」。あくまでも見えるだけで、必ずしも実際はそうでないのですが、ともかく女の子ライフが素敵に見える。自分もああなりたいと思うわけです。つまり、「女になる」ということ下降ではなく、明らかに上昇志向なのです。より輝いているあこがれの女の子ライフに近づいていくという意識です。そこが、昔とまったく違います。
性別表現の転換に対する評価が、以前のような「そんなことをするのは変態」というマイナスではなく、ある種のアイドル性を持った肯定的なプラス評価になってきています。そこが大きな変化、大事なポイントだと思います。
今の若い女性の最大の価値観はカワイイです。カワイイものがいちばん価値がある。それに近づいていくための自己表現が「男の娘」になることなのです。だから、「男の娘」の世界では、カワイイことが基準化され重視されます。残念ながら誰でもカワイクなれるわけではないですから、そこに淘汰が生じます。カワイクない「男の娘」は女性に受け入れられません。
それと、年齢を重ねると、どうしてもカワイイが似合わなくなってきます。ですから、「男の娘」は年齢的な制約がとてもにきつい。当人たちに言わせると「10代から20代で20代が中心。アラサー(30歳前後)はもう辛いですね」ということになります。
従来の女装コミュニティでは、30代、40代が中核でした。これは、ある程度の経済的余力がないと、化粧品や服、さらにそれらの隠し場所である変身部屋(仕度部屋)にお金がかかる女装という遊びができなかったからです。20代だと独力では経済的に難しい、男性のお世話(援助)がないとそれなりのレベルの女装は無理でした。
男性主導から女性主導へ
男性のお世話になると言いましたが、伝統的な女装世界では、自分は女装しないけれど女装者が大好きな男性、私は「女装者愛好男性」名付けているのですが、そういう人たちが大きな役割を果たしていました。女装者愛好男性が若い女装者を「育てる」、経済的に援助することはしばしば行われていました。前に出てきた女装秘密結社「富貴倶楽部」はそうした援助がシステム化されたものと言えます。
援助の見返りとして女装者は、女装者愛好男性に性的に従属することが当然視されました。つまり、女装して女になることは男に抱かれるということと全く同義で、女装とセクシャリティが表裏一体でした。
それが徐々に変わっていきます。1979年創業のアマチュア女装クラブ「エリザベス会館」では女装者愛好男性を出入禁止にします。女性スタッフと女装者だけの空間で、セクシャリティを基本的に排除したのです。
私は1990年から4年半「エリザベス会館」に通って、本格的な女装の技術を習得し、その後、1995年から新宿歌舞伎町の女装ホステスになりました。今述べた歴史的な流れとは逆のコースだったので、女装者が女装者愛好男性に抱かれることが当然視されていることに驚きました。店で男性客に「ホテルに行こう」と誘われても、私は「嫌」と言うので、「あいつは生意気だ」とずいぶん言われたものです。
そうした女性と女装者の空間という形は、2000年代に登場してくる女性が経営するハイスペック、ハイレベルな、ただし費用も高い女装スタジオにも受け継がれます。これはそうした高級女装スタジオのひとつ、早乙女麗子さん主宰の「R’s(アールズ)」(曙橋から新宿御苑前に移転)の作品です(画像24)。モデルは前に出てきた吉野さやかさんですが、まったく男性らしさの欠片も感じられません。
E59089E9878EE38195E38284E3818BEFBC882009E5B9B4EFBC89-94b07.jpg)
【画像24】
先ほど本物の女の子と「男の娘」とが一緒に遊ぶと言いましたが、この写真がそれです(画像25)。やはり早乙女さんの作品ですが、一見、どっちがどっちだかわかりません。右側がSakiさんという「男の娘」で、左側が生まれつき本物の女の子です。こういう形で「男の娘」と女の子が仲よく一緒に遊んでいる世界になると、もう女装者愛好男性が入り込む余地はありません。
Saki26E7B494E5A5B3-c34db.jpg)
【画像25】
これは「東京化粧男子宣言」ポスターですが、このシルエット画像がなかなか象徴的です。左のお化粧されているのが男の子で、右のメーキャップしているのが女性です(画像26)。先ほど言い忘れましたが、「東京化粧男子宣言」は、モデルの男の子と、ファッション・コーディネート&メイク担当の女の子が男女ペアで競うコンセプトのコンテストです。このシルエット画像は、現在の女装が、かっての男性主導から女性主導へと変わってきていることをよく示しています。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A8802009-1-2714c.jpg)
【画像26】
そうなると評価の基準も変わってきます。以前の男性目線の評価だと、きれい、色っぽい、おとなしい(従順)が評価基準でした。どれだけ男性の性欲をそそるかが価値基準だったわけです。それが同世代の女性目線の評価になるとカワイイが絶対的な価値基準です。女の子にカワイイと承認されるかどうかが、「男の娘」の最大のポイントになる、そういう世界です。
こうした変化の背景には、2000年代においてさまざまな分野で女性の社会的進出が進み、社会の中で女性の嗜好が重視されるようになり、相対的に男性の影響力が減少したことがあるのだろうと思います。
性別認識をめぐって
さて、そろそろ与えられた時間が尽きそうです。最後に「男の娘」をめぐる性別認識についてお話します。
湯島の「若衆バー 化粧男子」でこんなことがありました。ある「男の娘」、なかなかカワイイ子なのですが、店に入ってくるなり「今日ここに来る前に、男の人に声かけられて、ナンパだったんですよぉ。ああ、キモ!(気持ち悪い)」と言っています。そこで私が「それはあなた、どう見ても女の子なんだから、男の人が寄ってくるのは当然でしょう」と言ったら、「でも、自分、男ですよ」と(笑)。
どう見ても女の子に見える「娘」が、「えー、でも自分、男ですよ」と言っている。この「男の娘」の性自認(ジェンダー・アイデンティティ)は、女性ではなく男性で、しかも性的指向(セクシュアル・オリエンテーション)は男性には向いていないということです。私は他者から与えられる性別認識を、性自認に対して「性他認」と言っています。たぶん私の造語だと思うのですが…。この「男の娘」の場合、性自認は男性だけど性他認は女性で両者が一致していません。それで男性にナンパされるという性的指向に沿わない不快な経験をしてしまったということです。
ところで、性同一性障害の世界では、これと逆の現象がしばしば見られます。MtF(Male to Female 男から女へ)の方で、性自認が女性で「私は女なんです」と主張しているのに、周囲から「あなた、女に見えないよ」と言われてしまうケースが問題になっています。性自認は女性なのに、性他認は男性という不一致です。
つまり、「男の娘」の世界と性同一性障害の世界でパターンは逆ですが、同じような性自認と性他認の不一致による混乱が起こっているということです。「男の娘」の方は遊びの要素が強いですから笑って済ませられますが、性同一性障害の方のパターンは、社会生活にいろいろ支障をきたし、よほど深刻です。性自認が女性であるにもかかわらず女性の性他認が得られないのは、女性としての性別表現が不十分なことに原因があることが多いので、私は機会があるとそういう方たちのために、女性的なしぐさや歩き方のレッスンをしていますが、男性としての生活が長かった中高年の性同一性障害の方の場合、なかなか大変なのが実際です。
それはともかく、現代の日本では、男に見えるから男、女に見えるから女というふうに、もう単純に言えなくなってきているということです。「男なるもの」と「女なるもの」の境界がかなりぼやけてきて、境界領域が幅広くなっている。社会の中で自明と思われていた性別認識が、実はかなり揺らいできているということ、それが大事なポイントではないかと思うわけです。
「男の娘」の可能性
最後に「男の娘」の可能性です。「男の娘」というネーミングがいつまで続くかわからないので、「男の娘」を含むトランスジェンダーの可能性ということになると思いますが、21世紀の日本におけるの「男なるもの」と「女なるもの」の境界に位置するサード・ジェンダー的存在として、世の中には男と女しかいないのだという性別二元制、あるいは体が男なら男、体が女なら女というような身体構造を絶対視する性別決定論、さらには。男なら女が好き、女なら男が好き、そうでなければいけないというような異性愛絶対主義などを揺るがしていく存在になる、そんな可能性、期待感を持っています。
話し始めて1時間たちましたので時間切れですが、せっかくなので最後にNHKワールドの「(NEWS LINE)Boys Will Be Boys?」をご覧いただきましょう。
(5分間ほど番組視聴)
なにやら怪しい着物の先生が今日お話したようなことをコメントしていましたが、番組の後半は、早稲田大学の男子学生さんが卒業記念に横浜の「アルテミス」という高級女装スタジオに行ってドレスアップした卒業記念写真を撮るという話です。私、この番組の収録の時に、その早稲田の学生さんに「あなた、素顔を出しちゃって大丈夫なの?」と尋ねました。彼はある地方の公務員に採用が決まっていると聞いていましたので、昔ならこんな形で番組に出てしまったら採用取り消しになりかねません。それで、心配して「(素顔に)モザイクかけなくていいの?」と言ったわけです。そうしたら「私、面接のときに『趣味は女装です』と言って合格していますから、問題ありません」という返事でした。ここでも、世の中つくづく変わったなと思ったわけです。
今日は、日本の長いトランスジェンダーの歴史の中の、いちばん新しい現象である「男の娘」についてお話しました。ご清聴ありがとうございました。(拍手)
【追記・「男の娘」をめぐるその後の動向】
2012年11月20日、男の娘を主人公にした映画『僕の中のオトコの娘』(窪田將治監督、12月1日公開)公開記念イベント「オトコの娘サミット2012」が開催された(東京新宿歌舞伎町「ロフトプラスワン」)。
.jpg)
年が明けた2013年2月17日には『毎日新聞』が「S ストーリー」という企画記事で「月一度『封印』を解くー女子化する男たちー」(鈴木敦子記者)と題して社会的視点から「男の娘」問題を1面の一部と4面の全部を使って大きく取り上げた(http://junko-mitsuhashi.blog.so-net.ne.jp/2013-02-18)。
【参考文献】
三橋順子「現代日本のトランスジェンダー世界 -東京新宿の女装コミュニティを中心に-」
三橋順子「『女装者』概念の成立」
三橋順子「女装者愛好男性という存在」
(以上、矢島正見編著『戦後日本女装・同性愛研究』中央大学出版部 2006年)
三橋順子「往還するジェンダーと身体-トランスジェンダーを生きる-」
(鷲田清一編『身体をめぐるレッスン 1 夢みる身体 Fantasy』 岩波書店 2006年)
三橋順子『女装と日本人』(講談社現代新書 2008年)
三橋順子「変容する女装文化 -異性装と自己表現-」
(成実弘至編著『コスプレする社会 -サブカルチャーの身体文化-』せりか書房 2009年)
三橋順子「異性装と身体意識 -女装と女体化の間-」
(武田佐知子編『着衣する身体と女性の周縁化』思文閣出版 2012年)
.jpg)
---------------------------------------
平成24年(2012)度(駒沢女子大学)日本文化研究所主催講演会 2012年6月15日
「男の娘(おとこのこ)」なるもの
―その今と昔・性別認識を考える―
三橋 順子(性社会・文化史研究者 都留文科大学・明治大学非常勤講師)
皆さん、こんにちは。三橋でございます。このたびは私のような者をお招きいただき、大変うれしく思っております。自己紹介するとそれだけで持ち時間が終わってしまうようなややこしい人間なので、今、所長先生からお話がありましたように、適当に中に折り込んでいこうと思います。
最初にこちらにご縁をいただきましたことを少しお話ししておきます。以前、駒沢女子大学にいらした日本古代史の倉本一宏さんが京都の国際日本文化研究センターに着任をされました。私はもう10年ほど前から井上章一さんという建築史・風俗史の先生が主宰する「性欲の文化史」「性欲の社会史」の共同研究のメンバー(共同研究員)として年に5~6回、京都へ通っていました。
日文研は共同研究を重視する組織で専任の先生は他の先生の共同研究会にもいくつか出ないといけないというルールがあります。それで井上さんが倉本さんの研究会に出ることになりました。倉本さんが主宰されているのは主に平安、鎌倉の貴族の日記、そこから広げた日記の総合的研究という研究会です。井上さんが「僕、貴族の日記なんて読めないし、わからない。少しサポートしてもらえませんか」ということで、井上さんのお伴で私も倉本さんの研究会の共同研究員になりました。
その懇親会のときに、研究会の中核のメンバーの方たちは、日記のことばかりマニアックに話しています。その話についていけないメンバーは、端のほうに座っています。私も昔は平安時代の日記をやっていたのですが、もういいやと思っているので、隅っこのほうに座ります。そうすると、だいたい同じテーブルに池田先生、蘭先生、富田先生がいらっしゃる。そこでいろいろお話するようになったわけです。
そんな感じで、日文研の倉本さんの研究会つながりなのですが、お互い中核ではなく周辺、少し外れたところにいる者同士というつながりで、そう考えると、大変おもしろいご縁です。
ところで、私は都留文科大学で「ジェンダー研究」の講義を担当しているのですが、先ほど、佐々木先生とお話していて、先生が都留の方で、さらになんと都留市の谷村という町に嫁いだ私の叔母の菩提寺のご住職であることがわかり、本当にびっくりいたしました。人の縁(えにし)というものは実に不思議なものだと改めて感じております。
そんなご縁があって講演会に呼んでいただき、さて何をお話ししたらいいのだろうと悩みました。私は性社会・文化史という専門を名乗っております。日本におけるジェンダー&セクシャリティの歴史研究ということですが、もっぱら日本における性別越境、トランスジェンダーの研究をしております。お話をいただいたころに調べていたのは、昭和戦前期の大阪の女装男娼、つまり女装のセックスワーカーのことでした。それはいくら何でもあまりにもマニアックだろう、もう少し現代的なポピュラーな話題の方が興味をもっていただけるだろうと考えました。
そこで、こちらの研究所の総合テーマが「女性なるものと男性なるもの」とお聞きしていましたので、それでは、その間で行こう、女性なるものと男性なるものの境界領域をお話しようと、「『男の娘(おとこのこ)』なるもの」というテーマを思いつきました。ということで、今日は「男の娘」という最近の事象について、社会における性別認識という視点を絡めてお話することにいたします。
「男の娘(おとこのこ)」とは?
「男の娘」と書いて「おとこのこ」と読ませます。誰が考えたのかよくわからないのですが、なかなかしゃれたネーミングです。ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、なんのことやらわからないという方もいらっしゃると思います。その程度の社会的浸透度の新しい言葉です。
「男の娘」はまだ定義が固まっている言葉ではありません。いくつかご紹介しましょう。「まるで女の子のような男の子、女装している男性のこと」(『オトコの娘(こ)のための変身ガイド』)。「女の子のようにカワイイ女装少年のこと」(『わが輩は『男の娘』である!』)。あるいは、「二・五次元に生息する、(中略)女の子よりカワイイ男の子」(ニコニコ動画「男の娘ちゃんねる」)。二次元というのはいわゆる紙媒体、アニメの世界、そして三次元が現実世界ですから、二・五次元はその中間ということです。ウィキペディアは、「男性でありながら女性にしか見えない容姿と内面を持つ者」という定義です。これだと、それ以前の「女装」している人たちとの差違化が全くできていないので、あまりよろしくありません。
今、定義を四つ申しましたが、そのうちの二つに「カワイイ」という言葉が入っています。これが一つのキーワードだと思います。そこで、私なりの定義を示しますと「まるで女の子のようにカワイイ、女装した男の子」ということになります。
「男の娘」の出現
次に、「男の娘」というネーミングがいつ出てきたのかということをお話します。書籍でまず注目しておきたいのは、2007年9月に出た『オンナノコになりたい!』です。書名には「男の娘」とは入っていないのですが、帯の記述の中に「もっとかわいい男の娘になろう」と入っています。ただ帯は後からつけ替えられるので、少し不安があります。私の持っているのが第二刷で、初刷りではないので、余計に不安です。
書名に「男の娘」が入っているものとしては、2008年10月に女装普及委員会というところが出した『オトコの娘(こ)のための変身ガイド―カワイイは女の子だけのものじゃない―』(画像1)が最初だと思います。
E382AAE38388E382B3E381AEE5A898E381AEE3819FE38281E381AEEFBC882008E5B9B410E69C88EFBC89.jpg)
【画像1】
私は、2008年9月に『女装と日本人』という講談社現代新書を出しました。執筆は2007年です。その段階では、私の頭にはまだ「男の娘」という文字は入っていませんでした。ということは、「男の娘」というネーミングが社会の表面に浮上したのは、やはり2008年ではないか?と思います。
ところで、この『オトコの娘(こ)のための変身ガイド』という本は、男の子が女の子の格好をするためのテクニックやいろいろなアイテムに関して事細かに記している女装指南本です。こんな本が普通の書店で売られることすらびっくりしたのに、これ一冊だけで1万5000部以上、全4冊シリーズで6万部というかなりの売れ行きになったことも衝撃的でした。同時期に出た私の『女装と日本人』が1万部ぐらいしか売れないのに…、すごく悔しいです。
その後、2009年5月に『オトコノコ倶楽部』という女装美少年総合専門雑誌が三和出版から刊行されます。三和出版はもっぱら成人雑誌を出している出版社ですが、少し前まで『ニューハーフ倶楽部』(1995年3月~2007年8月)というニューハーフ(身体を女性化した男性、女装した男性であることをセールスポイントにした商業的なトランスジェンダー)をメインにした雑誌を出していました。私も連載コラムを2本持っていたのですが、コロッと宗旨替えして新しい流れに乗ったということです。このあたりまでくると、どうも様子がおかしいぞということに、私も気づいておりました。
その少し前、2008年の4月、私が銀座四丁目の「和光」の前におりましたら、背が高くてスタイルがいい振り袖のお嬢さんが、お母様らしき着物の女性と二人で、目の前を通過していったのです(画像2)。「あれ?」と思って、少し後をつけました。あれ?と思ったのは、スタイルが良すぎるというか、写真を見ればわかるように、少し袖で隠れていますが、お尻が小さいのです。つまり、女性ではないのではないか?ということを、直観的に感じたわけです。そこらへんの「目利き」は私のように女装業界に長くおりますと、自然と身についてきます。
E98A80E5BAA7E381AEE68CAFE3828AE8A296E3808CE5A898E3808DEFBC882008E5B9B44E69C88EFBC89.jpg)
【画像2】
後で、お話をうかがうと、やはり男性でした。左側の40歳ぐらいの女性が、右側の25歳ぐらいの男性に自分のお振り袖一式を着付けて、お化粧もしてあげて、銀座に連れ出したということでした。
そう言えば、少し前に新宿や渋谷で、「あれ、今の女の子の二人連れ、片一方は男の子じゃないかな?」と気づいたことが数回あったことを思い出しました。一見、女性の二人連れに見えるのですが、実は片方が女装した男の子というカップルです。そういう現象がひそかに増えていることに、私が気付いたのが、だいたい2008年の春ぐらいだったということです。たった4年前ぐらいのことです。
ちょうどその頃、今、京都造形芸術大学の成実弘至先生から、『コスプレする社会―サブカルチャーの身体文化』という本を一緒にやらないかというお話をいただきました。それで、『女装と日本人』に書いた後の女装世界の変化をフォローした「変容する女装文化」という論考を執筆しました。「男の娘」というネーミングは使いませんでしたが、後に「男の娘」とネーミングされるような若い女装者の意識の変化や、新しい現象として女性と女装した男性のカップルの話を取り上げたわけです。自画自賛になりますが、こうした女装文化の変化に真っ先に気づいて考察した論考が「変容する女装文化」ということになります。
マス・メディアへの登場
「変容する女装文化」を掲載した『コスプレする社会』は2009年6月に刊行されましたが、大手のメディアが「男の娘」現象に気づき始めたのは、その半年ほど後でした。12月に共同通信の記者から電話インタビューの依頼がありました。「おっ、やっと気付いたか」という感じでした。そのコメントが載ったのが、「きれいならOK?『女装男子』急増」という記事で(2009年12月22日配信)、こんな写真を載せていました(画像3)。秋葉原のメイドカフェで、メイドの格好をした女装の男の子が、本物の女性のお客さんに飲み物を運んでいる写真で、新しい現象のポイントをよく捉えています。つまり、後で詳しく申しますが、女装した男の子と女性との関係性です。
E794B7E381AEE5A8981-e63a3.jpg)
【画像3】
年末にはなんとNHKワールドからコメント出演の依頼がありました。NHKワールドは英語で世界百何十何カ国に放送している国際放送局ですが、NEWS LINEというニュース番組の中で現代日本の若者の女装文化を取り上げたいという話でした。私は驚いて「そんなことを取り上げて、世界に放送していいんですか」と問い返しました。そうしたら「実は、日本国内よりも外国で注目されているので、十分ニュース価値があるんです」というディレクターのお話でした。
年が明けた2010年の2月に「Boys Will Be Boys?」(少年は果たして男の子になるのでしょうか? もしかすると男の娘になっちゃうかもしれませんよ)という5分間ほどの特集で、現代日本の若者の一つのカルチャーとして「女装」する男の子現象が世界に紹介されました。DVDを持ってきましたので時間があったら、後でお見せします。
2010年8月には、共同通信がもっと本格的な「ニッポン解析:女装楽しむ『男の娘(こ)』」という記事を出しました(2010年8月25日配信)。銀座の街を歩いているのは二人とも「男の娘」です(画像4)。このような流れで、「男の娘」現象がマス・メディアで認知されたのは2010年ということになります。
E794B7E381AEE5A898EFBC93-168e0.jpg)
【画像4】
2011年11月には朝日新聞に、「『男の娘』(オトコノコ)になりたくて」という記事が出ました(2011年11月12日夕刊)。とうとう朝日新聞にまでと感慨深かったです。ついこの間、2012年5月には「男装大好き!」という題で、今度は女の子が男の子の格好をしているのが徐々にブーム化しているという記事が朝日新聞に載りました(2012年5月26日)。比べてみたら違う記者が書いているので、一人だけマニアックな記者がいるわけでもなさそうです。
男装のお話をする場がないので、ここでちょっとだけ触れておきますと、女性のファッションの範囲はとても広いので、極端に言えば、女性がどんな格好をしても、女性の幅広いファッション・カテゴリーの一部だと見なされてしまって、なかなか男装になりません。それこそ髭でもつけない限りは男装が成立しない、そういう意味で、男装の困難さがあるのです。朝日新聞の「男装大好き!」という記事の写真を見ますと、私からするとやはり女の子がボーイッシュなファッションをしているように見えてしまいます。ただし、本人たちは男装のつもりでやっている、そしてそこに「女子ファン増殖中」とあるように女の子が寄ってくる。男装女子がある種のアイドルとして、女の子にもてるという現象が社会の表面に出てきたというのは、なかなか興味深いことだと思います。
合わせて考えれば、コスチューム・プレイという感覚で、性別表現の転換が容易になっている。男女両方からの行き来がかなり自由になってきている。そして、そうした行為に対する評価が、以前のような「そんなことをするのは変態」というマイナスではなく、ある種のアイドル性を持った肯定的なプラス評価になってきている。そこが大きな変化、いちばん大事なポイントでだと思っています。
まとめますと、「男の娘」現象は、2008年ぐらいから社会の表面に浮上して、2010年にメディアに認知され、若者たちの間の異性装ブームは、現在進行中と言うことです。
「男の娘」の起源
もう少し掘り下げてみましょう。「男の娘」の定義のところで「二・五次元」云々という話が出てきましたが、「男の娘」の淵源は、二次元媒体、漫画、コミック、あるいはもっとローカルな、コミケ(コミック・マーケット。年二回開催される大規模な同人誌即売会)などで売られているコミック同人誌にあります。
確実なところでは、2006年9月に「男の娘 COS☆H」という名前の同人誌即売会が行われています。さらに、2000年の春頃、巨大インターネット掲示板で有名な「2ちゃんねる」の中で、「男の娘(おとこのこ)」という表現があったという話があります。ただこれは確認できていません。2000年代の前半、しかも早い時期に、マニアックな二次元媒体の中で「男の娘」というネーミングが生まれていたことは間違いなさそうです。
さらに、「男の娘」の元祖は、1980年代半ばにベストセラーになった江口寿史『ストップ ひばりくん!』の主人公大空ひばり(画像5)であるという説があります。『ストップ!! ひばりくん!』は、1981年~1983年の連載で、もう20年前の漫画です。私はリアルタイムで読んでいましたし、その世代の女装者には、やたらと「ひばり」という名前(女装名)の人が多くて、影響力があったことは間違いありません。しかし、これは「始祖伝説」のような話で、そういうふうに仮託されているということでして、日本最初の天皇は神武天皇というのと同様に歴史的事実として語れる話ではありません。
E382B9E38388E38383E38397E381B2E381B0E3828AE3818FE38293201-194cb.jpg)
【画像5】
「男の娘」の起源としていえることは、少なくとも2000年代の前半にコミック世界で女装した美しい男の子が「女装美少年」とか「化粧男子」とか、いろいろな名称で語られていて、それらのうちの一つが「男の娘」だったということです。
ところで、「娘」と書いて「こ」と読ませることですが、女装者を「女装娘」と書いて「じょそこ」と読ませることが、すでに1990年代前半の東京新宿の女装コミュニティで広く行われていました。その起源は1950年代に始まる男性同性愛者のコミュニティにおける女装する男性への侮蔑的な呼称である「女装子」にあります。男性同性愛者の世界は基本的に「男らしさ」を価値基準にする女性性嫌悪の強い世界ですから、「女らしい」人や女性の格好をする人は下位に位置づけられます。
ちなみに、なぜかゲイ業界では「〇〇子」という表現が好まれます。店で働いているゲイの人を「店子」と書いて「みせこ」と言います。「『店子』と書いたら普通は『たなこ』と読むのよ」などと言うと、「このばあさんは何を言っているんだ」と怪訝な顔をされるわけです。言葉としての「男の娘」、「娘」と書いて「こ」と読ませることには、そんな文化伝統があるわけです。
これまで述べたことをまとめますと、「男の娘」という言葉は、2000年代の前半、しかも早い時期に、マニアックなコミック世界で生まれ、最初はあくまでも二次元媒体の存在だったのが「コスプレ」などを通じて徐々に肉体を持った三次元キャラクターとして実体化していき、2008年ごろから社会の表面に現れてきて、2010年に「男の娘」現象としてマス・メディアの認知を得た、最初はある種のファッション・カテゴリーであったものが、ミニ流行化の中で次第にジェンダー・カテゴリーという感じになっていった、そんなところだと思います。
「男の娘」の実際
さて、二次元キャラクターの「男の娘」はいくらでも理想化が利きます。どんどん可愛く描けばいいわけです。ところが、三次元の「男の娘」はそうはいきません。皆さん、それなりに苦労しています。ここで、どんな「娘」がいるかちょっと見てみましょう。
この「娘」は、私の友人の吉野さやかさんです(画像6)。「彼女」に最初会った時、私ですらわかりませんでした。これはお友達の結婚パーティのときの写真を借りてきたのですが、本当に普通に女の子という感じで、こういう「娘」が現に存在しているのです。
E59089E9878EE38195E38284E3818B(2011E5B9B48E69C88)-2bd3c.jpg)
【画像6】
こちらの「娘」は、毎月、新宿歌舞伎町で「女装 ニューハーフプロパガンダ」というイベントを主催しているモカちゃんです(画像7)。彼女はイベントの主催者であると同時に、イベント最大のスターという存在です、この「娘」も、わかりませんでした。カワイイ女の子がいるなと思ったら「男の娘」で、びっくりでした。
E383A2E382AB20(2012E5B9B41E69C88)-19fc7.jpg)
【画像7】
これはテレビなどでときどき見かけるモデル兼タレントの佐藤かよさんです(画像8)。彼女は自分で「男の娘」とは名乗っていないと思いますが、世代的、容姿的、カワイイ系のファッションという点で、まさに最先端の「男の娘」だと思います。
E4BD90E897A4E3818BE38288(2011E5B9B4EFBC89-ca9d2.jpg)
【画像8】
こちらは、私の「娘分」的な存在の井上魅夜さんです(画像9)。以前は仲の良い後輩の女装者を「妹分」と言っていたのですが、もう無理です。どう考えても姉妹というより母と娘の年齢差ですから。この「娘」、身体的にまったく女の子サイズなので「男の娘」だとはまず気付かれません。黙っていればですが・・・。
E4BA95E4B88AE9AD85E5A49C.jpg)
【画像9】
2009年11月に、この井上魅夜さん主宰の「東京化粧男子宣言!」というイベントが行われました。早い話、化粧男子のミスコンです。これがそのポスターですが(画像10)、描いているのはいがらしゆみこさんという漫画家です。1970年代に「キャンディ・キャンディ」という大ヒット作がある方です。若い方はあまりなじみがないかもしれませんが……。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A880200920-2-d72ac.jpg)
【画像10】
では、なぜ、いがらし先生のような大家がポスターを描いてくださったのかといいますと、これは2010年12月に出た『わが輩は「男の娘」である!」という本です(画像11)。帯のところに、「こんな立派な『男の娘』になってくれて…… 母は嬉しいです!(実母・いがらしゆみこ)」と書いてあります。つまり、この本の著者いがらし奈波さんがいがらしゆみこ先生の息子さんなのです。
E794B7E381AEE5A898E381A7E38182E3828B(2010E5B9B412E69C88)-58968.jpg)
【画像11】
これは「東京化粧男子宣言!」のオープニングの写真です(画像12)。左側が主催者の井上魅夜さん、真ん中が審査員で「ニューハーフ女優」の月野姫さん、そして右側が司会のいがらし奈波さんです。つまり、司会の奈波さんの縁でいがらし先生にポスターを描いてくださったわけです。さらに、いがらし先生には審査委員長をお願いしました。審査員席で、私の隣がいがらし先生だったのですが、カワイイ「男の娘」になった息子さんの活躍を、本当にうれしそうに見ていました。まさに母親公認で、世の中つくづく変わったと実感したわけです。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A880200920-3-464b3.jpg)
【画像12】
さて、「東京化粧男子宣言!」の審査結果です。決勝進出の8人から審査員一致で(会場投票もトップ)グランプリに選ばれたのが、るるさんでした(画像13)。シャボン玉をふーっと吹くパフォーマンスで「男の娘」の最大のポイントである「カワイイ」を巧みに表現していました。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A880200920-5E584AAE58B9DE88085E3828BE3828B-8be4b.jpg)
【画像13】
これは優勝者を囲んだ審査員一同の写真です(画像14)。左からいがらし先生、グランプリのるるさん、月野姫さん、私です。全員女性のように見えますが、戸籍上の女性はいがらし先生だけという写真です。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A880200920-6E5AFA9E69FBBE593A1E381A8E584AAE58B9DE88085-9ca68.jpg)
【画像14】
るるさんにそっと「あなた、学生さんらしいけど、大学はどこ?」と聞いたら、「少し硬派なイメージがある、渋谷の……」という返事で、なんと私の後輩(笑)。またびっくりでした。要は、こんなかわいい「娘」がごく普通の男子大学生ということです。
「男の娘」を遡る
これが現代の状況です。しかし、こういうカワイイ女の子に見える男の子、「男の娘」的な存在が過去にいなかったかというと、そうでもありません。「男の娘」というネーミングは現代的なものですが、実態的に似たような「娘」が過去にも存在していました。そこで、次に「男の娘」的存在を過去に遡ってみましょう。
まず、1994年の浅草寺のほおずき市での写真です(画像15)。右側(私)は大貫録の姐さん風ですが、左側の岡野香菜さんは20代後半、当時江東区の亀戸にあったアマチュア女装クラブ「エリザベス会館」の若手スターです。
E9A086E5AD90EFBC881994E5B9B47E69C88EFBC89-1e0c5.jpg)
【画像15】
次は、20年ほど遡って1973年の中野のあるマンションのベランダで焼肉パーティをしている写真です(画像16)。写っているのは夢野すみれさんという女装秘密結社「富貴倶楽部」で若手ナンバーワンと呼ばれた方。大学を卒業して間もない20代前半だと思います。現在の「男の娘」と年齢的にはほとんど変わりありません。こういうカワイイ「娘」が1970年代にもいたのです。
E5A4A2E9878EE38199E381BFE3828CEFBC881973E5B9B4EFBC89-e03c4.jpg)
【画像16】
こちらは1969年、東京日比谷です(画像17)。お堀の石垣を背に大振袖で立つのは、佐々木涼子さんという方。実年齢は30代だと思いますが、やはり「富貴倶楽部」の有力メンバーで、振袖女装で有名だった方です。
E4BD90E38085E69CA8E6B6BCE5AD90EFBC881969E5B9B4EFBC89-10767.jpg)
【画像17】
次は、東京オリンピック直前の1964年6月の新宿駅東口駅前でのスナップです(画像18)。右側のお二人は少し年配、30代だと思います。左の横を向いている松葉ゆかりさんは、当時25歳で、今の「男の娘」と年齢的に変わりません。60年代の「富貴倶楽部」の若手花形で、私はこの方のロングインタビューを採ったことがあります。
E696B0E5AEBFE9A785E5898DE381AEE5A5B3E8A385E88085EFBC881964E5B9B46E69C88EFBC8920(2).jpg)
【画像18】
戦前に飛びます。横書きの文字が今と逆ですが、「これが男に見えますか」というキャッチコピーが入ったタブロイド判(夕刊フジの大きさ)の新聞号外です(『東京日日新聞』1937年3月31日特報)。写っているのは福島ゆみ子という24歳の人です(画像19)。風紀係の私服刑事が、銀座七丁目の資生堂の前で声をかけてきた女性を「密淫売」(無届売春)の容疑で逮捕して築地署に連行し取り調べたら、なんと女性ではなく女装の男性だったという事件を報じたものです。
E7A68FE5B3B6E38286E381BFEFBC881937E5B9B4EFBC8920(2)-0f5c0.jpg)
【画像19】
ちなみに、現在の売春防止法もそうですが、戦前の売春関係の法律も売春の行為主体を女性に限定していますので、男性だとわかった途端に罪状が消えてしまい、仕方なく(厳重説諭の上)釈放になります。ゆみ子さん、釈放になるので余裕でポーズを作っています。違う新聞の写真には「男なんて甘いわ」というセリフがついています。昭和戦前期には、非合法売春の容疑で捕まった女装男娼が何人か新聞報道されていますが、私が見る限り彼女がいちばんの美形です。
さらに時を遡りましょう。これは江戸時代中期、18世紀後半に活躍した鈴木春信(1725?~70)の作品です(画像20)。春信は錦絵の大成者として知られる浮世絵師で教科書にも出てくるとても有名な人です。前を歩いているのはもちろん男性で、後ろを歩いている華麗な大振袖、島田髷の人は、今の私たちの目には娘に見えますが、当時「陰間」と呼ばれた、芸能・飲食接客・セックスワークを職業にした女装の少年です。これから贔屓筋の座敷に出勤するところです。
E6B19FE688B8E69982E4BBA3E999B0E996931-fd07f.jpg)
【画像20】
こちらは、少し後の浮世絵師、北尾重政(1739~1820)の「東西南北美人」シリーズの「西方の美人 堺町」です(画像21)。江戸の東西南北の美人を2人ずつ描いた4枚のセットですが、残念ながら全部残っていないようです。確認できる「東方」は深川の芸者を描いていて、たぶん「北方」は吉原の遊女、「南方」は品川の飯盛女(実態は遊女)でしょう。どれもまちがいなく女性ですが問題はこの「西方」です。立ち姿が橘屋の三喜蔵、座っているのが天王寺屋の松之丞という子で、松之丞は江戸の町娘のあこがれだった黄八丈の振袖姿です。もうあらためて言うまでもないと思いますが、「西方の美人」は女性ではなく、女装の少年なのです。
E6B19FE688B8E69982E4BBA3E999B0E9969324-cdde8.jpg)
【画像21】
このようにさかのぼっていくと、「男の娘」的存在がぞろぞろと出てくるわけです。なぜ前近代の日本にそういう「娘」がたくさん出てくるのか、そこら辺のことは私の『女装と日本人』に詳しく書いてありますので、ご参照いただければ幸いです。
もう一息です。これは鎌倉時代末期に描かれた『石山寺縁起絵巻』です(画像22)。この子が着ている橙色の衣服、肩が割れていないので少年が着る水干ではなく、女性が着る袿(うちき)です。履物もけばけばしています。藺げげ(いげげ)という当時の若い女性の履き物です。後にお坊さんがいます。首が切れていますが…。この時代、僧侶は戒律で女性と行動を共にしてはいけません。お坊さんの連れが少女ではまずいのです。つまり、この子は女装の稚児です。きっと後ろにいる師匠のお坊さんが(性的にも)可愛がっている「娘」なのでしょう。
E98E8CE58089E69982E4BBA3E7A89AE585901-42089.jpg)
【画像22】
これで最後です(画像23)。私の話を何度も聞いてくださっている方は「またか」と思われるかもしれませんが、やはり行き着くところは女装の建国英雄・ヤマトタケルになってしまいます。これは三重県鈴鹿市の加佐登神社に奉納されている大きな絵馬です。ヤマトタケルは少女の姿になって九州の豪族クマソタケル兄弟の館に入り込み、その美少女ぶりで兄弟を魅了します。絵馬は長い垂れ髪に緋色の裳の女姿のヤマトタケルがクマソタケル兄弟をやっつける場面を描いています。ヤマトタケルの右手に握られた剣はすでに血にまみれていて。すでにクマソタケル兄の方を殺し、これから青い衣の髭面のクマソタケル弟を刺そうとするところです。ヤマトタケルはこのとき16歳。まさに元祖「男の娘」です。
E383A4E3839EE38388E382BFE382B1E383AB-5fd8c.jpg)
【画像23】
こうして歴史を遡ってみますと、「男の娘」的存在は日本の長い歴史の中に常に存在していたことがわかります。言葉を変えるならば、現在、ミニブームになっている「男の娘」も、男でもあり女でもある双性、ダブルジェンダー的な存在への強い嗜好に支えられた日本の性別越境文化の末裔であり、決して現代の特異現象ではないということです。メディアは新しいものが大好きなので、最新の社会現象だと騒ぎますが、実は根っこはずっと続いているのです。「男の娘」は、2000年の長い歴史を持つ日本の女装文化の21世紀リニューアルバージョンだと、私は理解をしています。
「男の娘」出現の背景
さて、再び現代の「男の娘」に戻って、もう少し深く考えてみましょう。まず「男の娘」がクローズアップされてきた背景です。1990年代後半から2000年代前半は、性別を越えて生きたいと考えることを「病」、精神疾患だと考える性同一性障害という概念が大流行した時代です。メディアの報道も性同一性障害一色でした。こうした性同一性障害の概念の大流行で、従来の女装世界、例えば女装スナックやバーを拠点に形成されている新宿の女装コミュニティは、長年培ってきた人的資源をごっそり奪われて大打撃を受けました。わかりやすく言えば、「女になりたい」と思う人は、それまではお店に来ていたのが、病院に行くようになってしまったわけです。
私は1995年から2001年まで6年間、新宿歌舞伎町の老舗の女装スナック「ジュネ」やニューハーフ・パブ「MISTY」でお手伝いホステス(ゲスト・スタッフ)をしていていました。ちょうど性同一性障害の概念が流行していった時期です。『女装と日本人』を書いた理由の一つは、性別を越えて生きることが精神疾患であるという病理化の思想が社会に蔓延してしまうと、ヤマトタケル以来連綿と続いてきた日本の女装文化は終わりになってしまう、ならば、こういう世界があったんだということをちゃんと調べて書き残そう、そう思って、1998年頃から歴史学や社会学の勉強をし直して学術的な女装文化の研究を始めたわけです。つまり、日本の女装文化の遺言を書くようなすごく悲観的な気持ちで書き始めたのですが、先ほど述べましたように、執筆しているうちにあれ、何か様子が変だぞ、流れが微妙に変わりつつあるぞ、という感じになったのです。
性同一性障害の概念には、医療によって身体の女性化を進めていくことを重視して、性別表現、ファッションや化粧というものを軽視する傾向があります。そのアンチテーゼとして、性別表現を重視した自己表現的な性別越境の形が復活してきた。「男の娘」現象の背景には、そうした性別越境をめぐる大きな流れの転換があると考えています。
メディアも、性同一性障害を10年間も報道すると、もう番組の作り方がなくなってきます。さらに言えば、重苦しさがつきまとう性同一性障害の報道にそろそろ嫌気が差していた。「また性同一性障害かよ、もうちょっと飽きてきたな」と思い始めていたところに、もっと楽しく気軽に性別を越えようという「男の娘」が浮上してきたわけです。メディアは、何度も言うように新しいものが大好きですから、そちらに飛びついた。そういうメディアの視点の転換も、「男の娘」がクローズアップされた背景にあったと思います。
ただし、性同一性障害概念の流布以前に戻ったわけではなく、「男の娘」たちの多くは1990年代まで主流だった新宿の女装コミュニティとは一線を画しています。そもそもエリアが違います。新宿ではなく秋葉原、中心が東京の東側へ動きました。「東京化粧男子宣言」の井上魅夜さんは、2011年12月に「若衆バー 化粧男子」という店を出したのですが、場所は新宿ではなく秋葉原の北の湯島でした。
もっとも、女装世界の中心は、新宿に移る前は上野や浅草でした。戦後最初の女装した女将さんがいるバーは「湯島」という名で、その名の通り湯島天神の男坂の下にありました。さらに言えば、江戸時代、女装の少年が接客する陰間茶屋の江戸における三大密集地の一つが湯島天神界隈でした。徳川将軍家の菩提寺である上野寛永寺のお坊さんが最大の客筋でした。そういう意味では、「男の娘」の拠点が秋葉原や湯島になったのは、先祖返りとも言えます。
「男の娘」の内実
次に「男の娘」の内実です。これはけっこう複雑で、趣味のコスチューム・プレイ(コスプレ)としてやっている女装者から、将来的には女性への性別越境を考えている、つまり戸籍まで女性に変えたいという子までかなり幅広いです。性同一性障害の診断書を持っている子も少なくありません。ですから、身体の女性化の程度も様々で、ほとんど何もしていない人もいれば、女性ホルモン継続の投与だけという人もいれば、外性器の手術(睾丸摘出手術や造膣手術)までしてしまっている人もいます。「男の娘」と言っても中身はいろいろなのです。
性的指向(セクシュアル・オリエンテーション)も一定ではありません。「女好き」、つまり、女の子の格好で女の子が好きという見かけ上レズビアンも多いですが、「男好き」(見かけヘテロセクシャル)もいます。バイセクシャルもいます。
1990年代後半から2000年代にかけては、女装あるいはトランスジェンダーというカテゴリーと、性同一性障害というカテゴリーの間に、かなり強烈な対立がありました。「あなたはどっちなの?」という感じ。ところが「男の娘」は、そうした対立、境界にこだわらない傾向があります。「そんなのどっちだっていいじゃないですか」という感じ。そうした概念へのこだわりのなさも新しいところです。つまり、「男の娘」の内実はかなり多様であり、良く言えばそうした幅広さ、悪く言えばとらえどころのなさ、無思想性が特色になっていると言えます。
「男の娘」出現の条件
次に、「男の娘」出現の条件です。なぜ「男の娘」が出てきたのですか?という質問はメディアの取材で必ず聞かれます。
第一に大きいのは情報流通の変化、具体的に言うとインターネットの普及です。インターネットの普及以前、女装やニューハーフの世界は、まさに閉ざされた世界でした。
先ほどお話した歌舞伎町の女装スナック「ジュネ」)の先輩で、200軒以上の飲み屋が集まっている新宿のゴールデン街を端から飲みまくって、10万円ぐらい飲んだところでやっと女装の店の情報に行き着いたという人がいます。1980年代後半、もう25年くらい前の話ですが、世の中にほとんど情報が回ってなく、伝手をたどってその種のお店を探すしかなかったわけです。どうやったら化粧ができるか、そういう情報もありません。女装やニューハーフの世界になんとかしてたどり着かないと、いくら女の子になりたくても始まりませんでした。
今は、インターネットでいくらでもお店の情報や女装テクニックが簡単に得られるようになりました。初めの方で紹介したように女装指南本が一般の本屋で売られている時代です。昔は女装の専門雑誌を買うのもけっこう大変で、どこに行けば売っているのか、なかなかわかりません。売っている場所に行っても、買うのにすごいドキドキでした。どうしても勇気が出なくて店の前を何度も往復してとうとう買えなかった、なんて話もあります。ともかく、ものすごく敷居が高い世界でした。それが今はもうまったく違います。
第二は男の子たちの顔や体形の変化です。私、今はすっかり太って丸顔ですが、若いころは1000人に1人の女顎、つまり三角顎だと言われたことがあったのですが、悔しいことに今、私レベルの三角顎の男の子はごろごろいます。そのくらい日本人の男性の顔立ちは変わってきています。フーテンの寅さん、渥美清さんのようなエラが張っているホームベース型の顔で、髭の剃り跡が青く見えるような男の子は本当に少なくなっています。顎のラインがすっきりした、髭もあまり濃くないような子が増えています。体形も手足が長く、骨格がずいぶん華奢になり、女物の9号の服が着られるような男の子が増加しています。つまり、男の子の顔立ちや体型が女装向きに変化してきています。昔に比べて「女の子になる」ベースに恵まれている男の子が多くなっているわけです。
第三に社会環境の変化があります。男の子が髪を長くのばしたり、眉を細く手入れしたり、髭や手足の体毛を脱毛していることが、それほど奇異に見られなくなっています。別に女の子になりたいわけでなくても、身体のメンテナンスに気を遣うおしゃれな男の子が増えていますから、そういう女装のための身体条件を整えることをしても、あまり目立ちません。
社会全体として性別の越境に対する許容度・自由度が以前に比べればだいぶ緩くなっています。コスチューム・プレイという感覚で、男性と女性の間を行って戻ってみたいなことがかなり自由になっている。社会環境として性別の越境、性別表現の転換が容易になっているということです。昔はそこに乗り越えなければならない高い壁のようなもの厳としてありましたったのが、私の世代だと、女装すること自体がものすごく大変で、そこに至るのに何年かかるという世界だったわけです。たとえば、私は振袖を着たいと思ってから実際に振袖姿で外へ出るまで20年近くかかっています。ところが最初に紹介した銀座の振袖「男の娘」は、2回目の女装でした。それほど違うのです。心理的な、もしくは社会的な、越えなければいけない障壁がとても低くなっています。
第四は、女性が男の子の女装を受け入れるようになったことです。女装した男性と一緒に遊ぶ、さらには積極的に女装に協力するような女性が確実に増えてきています。化粧にしてもファッション・コーディネートにしても、男の子が一から独力で覚えるのと、女性が協力してくれるのとでは、進度も到達レベルもまったく違います。こうした関係性の変化については、また後で詳しく述べます。
第五は、これがいちばん重要なことですが、価値観の変化です。昔は男が女の格好をする、女装することは、男性上位社会において明らかな社会的下降でした。よりによって「女『なんか』になる」という感じです。ですから、女装にはしばしばマゾヒズムが伴っていました。マゾヒズムについては、富田先生がここでお話になったと思うのですが、わざわざ女という低い身分になる、「あたし、とうとう女に墜ちちゃったわ」というような被虐的な陶酔にひたる女装者は少なくありませんでした。
ところが、今の「男の娘」たちはまったく違います。現代の男の子は同世代の女の子のライフスタイルに、かなり強いあこがれを持っています。男の子のライフスタイルは冴えないけれども、女の子たちはとても輝いている」。あくまでも見えるだけで、必ずしも実際はそうでないのですが、ともかく女の子ライフが素敵に見える。自分もああなりたいと思うわけです。つまり、「女になる」ということ下降ではなく、明らかに上昇志向なのです。より輝いているあこがれの女の子ライフに近づいていくという意識です。そこが、昔とまったく違います。
性別表現の転換に対する評価が、以前のような「そんなことをするのは変態」というマイナスではなく、ある種のアイドル性を持った肯定的なプラス評価になってきています。そこが大きな変化、大事なポイントだと思います。
今の若い女性の最大の価値観はカワイイです。カワイイものがいちばん価値がある。それに近づいていくための自己表現が「男の娘」になることなのです。だから、「男の娘」の世界では、カワイイことが基準化され重視されます。残念ながら誰でもカワイクなれるわけではないですから、そこに淘汰が生じます。カワイクない「男の娘」は女性に受け入れられません。
それと、年齢を重ねると、どうしてもカワイイが似合わなくなってきます。ですから、「男の娘」は年齢的な制約がとてもにきつい。当人たちに言わせると「10代から20代で20代が中心。アラサー(30歳前後)はもう辛いですね」ということになります。
従来の女装コミュニティでは、30代、40代が中核でした。これは、ある程度の経済的余力がないと、化粧品や服、さらにそれらの隠し場所である変身部屋(仕度部屋)にお金がかかる女装という遊びができなかったからです。20代だと独力では経済的に難しい、男性のお世話(援助)がないとそれなりのレベルの女装は無理でした。
男性主導から女性主導へ
男性のお世話になると言いましたが、伝統的な女装世界では、自分は女装しないけれど女装者が大好きな男性、私は「女装者愛好男性」名付けているのですが、そういう人たちが大きな役割を果たしていました。女装者愛好男性が若い女装者を「育てる」、経済的に援助することはしばしば行われていました。前に出てきた女装秘密結社「富貴倶楽部」はそうした援助がシステム化されたものと言えます。
援助の見返りとして女装者は、女装者愛好男性に性的に従属することが当然視されました。つまり、女装して女になることは男に抱かれるということと全く同義で、女装とセクシャリティが表裏一体でした。
それが徐々に変わっていきます。1979年創業のアマチュア女装クラブ「エリザベス会館」では女装者愛好男性を出入禁止にします。女性スタッフと女装者だけの空間で、セクシャリティを基本的に排除したのです。
私は1990年から4年半「エリザベス会館」に通って、本格的な女装の技術を習得し、その後、1995年から新宿歌舞伎町の女装ホステスになりました。今述べた歴史的な流れとは逆のコースだったので、女装者が女装者愛好男性に抱かれることが当然視されていることに驚きました。店で男性客に「ホテルに行こう」と誘われても、私は「嫌」と言うので、「あいつは生意気だ」とずいぶん言われたものです。
そうした女性と女装者の空間という形は、2000年代に登場してくる女性が経営するハイスペック、ハイレベルな、ただし費用も高い女装スタジオにも受け継がれます。これはそうした高級女装スタジオのひとつ、早乙女麗子さん主宰の「R’s(アールズ)」(曙橋から新宿御苑前に移転)の作品です(画像24)。モデルは前に出てきた吉野さやかさんですが、まったく男性らしさの欠片も感じられません。
E59089E9878EE38195E38284E3818BEFBC882009E5B9B4EFBC89-94b07.jpg)
【画像24】
先ほど本物の女の子と「男の娘」とが一緒に遊ぶと言いましたが、この写真がそれです(画像25)。やはり早乙女さんの作品ですが、一見、どっちがどっちだかわかりません。右側がSakiさんという「男の娘」で、左側が生まれつき本物の女の子です。こういう形で「男の娘」と女の子が仲よく一緒に遊んでいる世界になると、もう女装者愛好男性が入り込む余地はありません。
Saki26E7B494E5A5B3-c34db.jpg)
【画像25】
これは「東京化粧男子宣言」ポスターですが、このシルエット画像がなかなか象徴的です。左のお化粧されているのが男の子で、右のメーキャップしているのが女性です(画像26)。先ほど言い忘れましたが、「東京化粧男子宣言」は、モデルの男の子と、ファッション・コーディネート&メイク担当の女の子が男女ペアで競うコンセプトのコンテストです。このシルエット画像は、現在の女装が、かっての男性主導から女性主導へと変わってきていることをよく示しています。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A8802009-1-2714c.jpg)
【画像26】
そうなると評価の基準も変わってきます。以前の男性目線の評価だと、きれい、色っぽい、おとなしい(従順)が評価基準でした。どれだけ男性の性欲をそそるかが価値基準だったわけです。それが同世代の女性目線の評価になるとカワイイが絶対的な価値基準です。女の子にカワイイと承認されるかどうかが、「男の娘」の最大のポイントになる、そういう世界です。
こうした変化の背景には、2000年代においてさまざまな分野で女性の社会的進出が進み、社会の中で女性の嗜好が重視されるようになり、相対的に男性の影響力が減少したことがあるのだろうと思います。
性別認識をめぐって
さて、そろそろ与えられた時間が尽きそうです。最後に「男の娘」をめぐる性別認識についてお話します。
湯島の「若衆バー 化粧男子」でこんなことがありました。ある「男の娘」、なかなかカワイイ子なのですが、店に入ってくるなり「今日ここに来る前に、男の人に声かけられて、ナンパだったんですよぉ。ああ、キモ!(気持ち悪い)」と言っています。そこで私が「それはあなた、どう見ても女の子なんだから、男の人が寄ってくるのは当然でしょう」と言ったら、「でも、自分、男ですよ」と(笑)。
どう見ても女の子に見える「娘」が、「えー、でも自分、男ですよ」と言っている。この「男の娘」の性自認(ジェンダー・アイデンティティ)は、女性ではなく男性で、しかも性的指向(セクシュアル・オリエンテーション)は男性には向いていないということです。私は他者から与えられる性別認識を、性自認に対して「性他認」と言っています。たぶん私の造語だと思うのですが…。この「男の娘」の場合、性自認は男性だけど性他認は女性で両者が一致していません。それで男性にナンパされるという性的指向に沿わない不快な経験をしてしまったということです。
ところで、性同一性障害の世界では、これと逆の現象がしばしば見られます。MtF(Male to Female 男から女へ)の方で、性自認が女性で「私は女なんです」と主張しているのに、周囲から「あなた、女に見えないよ」と言われてしまうケースが問題になっています。性自認は女性なのに、性他認は男性という不一致です。
つまり、「男の娘」の世界と性同一性障害の世界でパターンは逆ですが、同じような性自認と性他認の不一致による混乱が起こっているということです。「男の娘」の方は遊びの要素が強いですから笑って済ませられますが、性同一性障害の方のパターンは、社会生活にいろいろ支障をきたし、よほど深刻です。性自認が女性であるにもかかわらず女性の性他認が得られないのは、女性としての性別表現が不十分なことに原因があることが多いので、私は機会があるとそういう方たちのために、女性的なしぐさや歩き方のレッスンをしていますが、男性としての生活が長かった中高年の性同一性障害の方の場合、なかなか大変なのが実際です。
それはともかく、現代の日本では、男に見えるから男、女に見えるから女というふうに、もう単純に言えなくなってきているということです。「男なるもの」と「女なるもの」の境界がかなりぼやけてきて、境界領域が幅広くなっている。社会の中で自明と思われていた性別認識が、実はかなり揺らいできているということ、それが大事なポイントではないかと思うわけです。
「男の娘」の可能性
最後に「男の娘」の可能性です。「男の娘」というネーミングがいつまで続くかわからないので、「男の娘」を含むトランスジェンダーの可能性ということになると思いますが、21世紀の日本におけるの「男なるもの」と「女なるもの」の境界に位置するサード・ジェンダー的存在として、世の中には男と女しかいないのだという性別二元制、あるいは体が男なら男、体が女なら女というような身体構造を絶対視する性別決定論、さらには。男なら女が好き、女なら男が好き、そうでなければいけないというような異性愛絶対主義などを揺るがしていく存在になる、そんな可能性、期待感を持っています。
話し始めて1時間たちましたので時間切れですが、せっかくなので最後にNHKワールドの「(NEWS LINE)Boys Will Be Boys?」をご覧いただきましょう。
(5分間ほど番組視聴)
なにやら怪しい着物の先生が今日お話したようなことをコメントしていましたが、番組の後半は、早稲田大学の男子学生さんが卒業記念に横浜の「アルテミス」という高級女装スタジオに行ってドレスアップした卒業記念写真を撮るという話です。私、この番組の収録の時に、その早稲田の学生さんに「あなた、素顔を出しちゃって大丈夫なの?」と尋ねました。彼はある地方の公務員に採用が決まっていると聞いていましたので、昔ならこんな形で番組に出てしまったら採用取り消しになりかねません。それで、心配して「(素顔に)モザイクかけなくていいの?」と言ったわけです。そうしたら「私、面接のときに『趣味は女装です』と言って合格していますから、問題ありません」という返事でした。ここでも、世の中つくづく変わったなと思ったわけです。
今日は、日本の長いトランスジェンダーの歴史の中の、いちばん新しい現象である「男の娘」についてお話しました。ご清聴ありがとうございました。(拍手)
【追記・「男の娘」をめぐるその後の動向】
2012年11月20日、男の娘を主人公にした映画『僕の中のオトコの娘』(窪田將治監督、12月1日公開)公開記念イベント「オトコの娘サミット2012」が開催された(東京新宿歌舞伎町「ロフトプラスワン」)。
.jpg)
年が明けた2013年2月17日には『毎日新聞』が「S ストーリー」という企画記事で「月一度『封印』を解くー女子化する男たちー」(鈴木敦子記者)と題して社会的視点から「男の娘」問題を1面の一部と4面の全部を使って大きく取り上げた(http://junko-mitsuhashi.blog.so-net.ne.jp/2013-02-18)。
【参考文献】
三橋順子「現代日本のトランスジェンダー世界 -東京新宿の女装コミュニティを中心に-」
三橋順子「『女装者』概念の成立」
三橋順子「女装者愛好男性という存在」
(以上、矢島正見編著『戦後日本女装・同性愛研究』中央大学出版部 2006年)
三橋順子「往還するジェンダーと身体-トランスジェンダーを生きる-」
(鷲田清一編『身体をめぐるレッスン 1 夢みる身体 Fantasy』 岩波書店 2006年)
三橋順子『女装と日本人』(講談社現代新書 2008年)
三橋順子「変容する女装文化 -異性装と自己表現-」
(成実弘至編著『コスプレする社会 -サブカルチャーの身体文化-』せりか書房 2009年)
三橋順子「異性装と身体意識 -女装と女体化の間-」
(武田佐知子編『着衣する身体と女性の周縁化』思文閣出版 2012年)
【講演録】性別違和感を抱く学生に教職員はどう対応していくか [論文・講演アーカイブ]
2014年7月27日、明治大学(駿河台)で開催された「第53回学生相談室夏期セミナー」に呼んでいただき、「性別違和感を抱く学生に教職員はどう対応していくか」というテーマでお話しました。
その記録が『学生相談 2014年度 学生相談室報告』(明治大学学生支援部 2015年6月)に掲載されました。
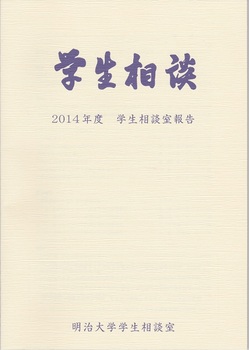
学外者には入手が難しい学内誌なので、全文をここに掲載します。
--------------------------------------
明治大学 第53回学生相談室夏期セミナー 講演
「性別違和感を抱く学生に教職員はどう対応していくか」
2014年7月27日(日)
文学部 兼任講師 三橋 順子
はじめに
皆さん、こんにちは。三橋順子です。明治大学に非常勤講師で呼んでいただいて3年目になります。簡単に自己紹介しますと、私は、男性から女性へのトランスジェンダーですが、戸籍は生まれたときの性別、名前で変えておりません。1995年くらいから社会的には女性として、講演、著述、あるいは教育活動をしてきました。女性としてそれなりに実績はあったわけですが、実は、明治大学から講師のオファーがあったとき、すんなりとはいきませんでした。「お引き受けします」とお返事した後、履歴書段階で1~2カ月ほど手続きが止まってしまったのです。理由は履歴書の性別欄の記載です。私は履歴書の性別欄を空欄で提出しました。私の性自認からして「男」とは書けませんし、男女雇用機会均等法の趣旨からして性別の記載は強要されるべきではないと考えますので。それに対して人事課は「性別欄が空欄なのは前例が無い。戸籍通りちゃんと男性と記載してください」ということでした。私から明大で講義をさせてくれとお願いしたわけではなく、明大から依頼してきたことですので、「それなら結構です」と申しましたら、やっと人事が動いたということがありました。性別記載で引っ掛かってしまうということが、まだまだ日本の現実としてあるということです。明治大学だけが理解がないわけではなくて、日本社会のシステムが男女二元で、しかも硬直的で融通が利かない。それが性別を越えて生きるトランスジェンダーの人たちをどれだけ生きにくくしているかという事例としてお話しました。今日はそうした問題をどのようにクリアしていけばよいかというお話をいたします。
1 基礎知識として
今日のテーマは「性別違和感を抱く学生に」ということですが、最初に基礎知識的なことを、三つお話をしておきましょう。
(1) 同性愛とトランスジェンダー
一つ目は、同性愛とトランスジェンダーの違いです。学生も一番ここが分からないと言うので、こんな説明をします。同性愛は、男が好きか女が好きかという性的指向sexual orientation問題であって、自分が男であるか女であるかというgender identity性自認(性同一性)の問題ではありません。誰を好きになるかという相手の性別がマジョリティーの人と違っているのが同性愛です。トランスジェンダーは自分が男であるか女であるかという性自認gender identityの問題で、男が好きか女が好きかというsexual orientationの問題ではありません。男として生きるか女として生きるかという自分の性別の在り方の問題です。
(2) 性別違和感(Gender Dysphoria=GD)とは?
基礎知識の二つ目は、性別違和感gender dysphoriaとは何かということです。一般的には、自分の性別に対する心理的な違和感が性別違和感です。性別違和感を考える場合、基本になるのは自分の性自認、自分を男と思うか、女と思うかということです。自分は男だと思っているのに、身体が女である、生理が来る。あるいは、自分が女だと思っているのに、男性の身体である、声変わりをしてしまう、髭が生えてくるというような性自認と身体の性のズレが身体違和です。
ズレ(違和感)はそれだけでなく、性自認と社会的性(ジェンダー)の間にも生じます。自分が女だと思っているのに、世の中からは男として扱われる。「あなたは、戸籍は男でしょう。だから男として扱いますよ」ということです。自分は男だと思っているのに、「あなた、戸籍上は女でしょう。女性のほうに入りなさい」と言われてしまう。性別違和感は性自認と身体の間、性自認と社会的な扱いの2カ所で生じます。ここがポイントです。身体のほうの違和感は大学でどうこうできる話ではありませんので、医学的な対処が必要になりますが、社会的な扱いに関しては、世の中の一部である大学でも対応できる問題ということになります。
心が女なのに身体が男であるというのはやはり辛いわけで、何とかズレを直そう、整合性を回復しようとします。自分は女だと思っているのに世の中から男として扱われるというのはとてもきついことです。さっきの私の履歴書の話ですが、あの時は精神的に相当きつかった、かなり落ち込みました。そのあたりは、性別違和感がない方にはなかなか理解をしていただけないと思いますが。性別違和感というのは、ギザギザ、トゲトゲした、やっかいな嫌なものなので、何とかそれを解消しようと努力します。つまり、性別違和感は、性別を移行していく原動力になるわけです。
(3) 性同一性障害(Gender Identity Disorder=GID)とは?
基礎知識の三つ目は、性同一性障害とは何かということです。性同一性障害は、Gender Identity Disorderという英語の疾患名の日本語訳です。先ほど、性別違和感は性自認(性同一性)gender identityと身体的性sex、性自認と社会的役割gender roleの2カ所で生じると申しましたが、その2カ所の不一致に起因する性別違和感がどんどんひどくなっていった結果、著しい精神的苦痛や、社会生活・職場における機能障害、つまり、社会生活がうまくいかない、あるいは学校や職場でそこにうまく身をおけないという形になって、医療のサポートが必要になった状態をいう精神疾患概念です。「性同一性障害は病気ではないと思います」という学生がときどきいますが、「性同一性障害というのは精神疾患の名称なので、それを病気でないというのは概念矛盾で、成り立ちませんよ」と説明します。ただし、性同一性障害というのは性別違和感を原因とする社会的不適応の病であって、性別違和感を持っていること自体は病気ではないということです。ここはマスメディアが心の性と身体の性がズレていることが病気だというような説明をすることが多いのですが、それは間違いです。実は、自分の性の在り様が何かズレている、違和感があるという人は、けっこう多いのです。それは違和感の程度の問題でして、違和感があること自体を病にしてしまうのは、問題があると思います。そのような状態をとても苦痛を感じていて、社会生活上、不適応を起こしていることが病であると捉えないといけないと思います。
2 「性別違和」の現在
(1) この15年間の流れと最新の動向
次に、日本で性別移行の問題が社会的に浮上したこの15年ぐらいの流れをざっとおさらいしておきます。もちろんそれ以前から、性別を変えようと努力したいろいろな人がいたわけですが、やはり起点は1996年です。私立の埼玉医科大学の倫理委員会が、形成外科の教授から申請があったSex Reassignment Surgery、「性転換手術」、現在で言う「性別適合手術」を正当な医療行為として承認したことがニュースになりました。これはあくまでも一大学の倫理委員会の判断で、本来はそんなに大げさに報道することではないと思うのですが。それを受けて97年の5月に、日本精神神経学会が「性同一性障害に関する答申と提言」という、私たちが「ガイドライン」と呼んでいるものを出しました。これもかなり大きなニュースになって、このあたりから性同一性障害という病名が『現代用語の基礎知識』などにも載るようになってきました。98年10月に埼玉医科大学が「ガイドライン」に基づいたものとして初めての性別適合手術を実施しました。あくまでもガイドラインに基づいたものとしては初めての手術であって、性別適合手術自体は日本では1951年、世界でも指折りに早い時期からやっています。これは私が調べたことですが。
そんな流れの中で2002年の8月に六大学「学生相談」連絡会議で「性別違和を抱える学生をどう受け入れるか」という講演をさせていただきました。会場は中央大学で、私は中央大学の社会科学研究所の研究員という立場でした。その、きっかけは明治大学だったように覚えています。明大で、自分は男ですという女子学生、つまりFtM(Female to Male)の学生さんが出てきて、教授会で問題になったというお話でした。「問題になったというのは、対策が問題になったのですか」とうかがったら、そうではなく、「『明治大学の学生ともあろうものがけしからん』とある教授が言い出した」というお話でした。今からすると、とんでもない無理解ですが、この頃は、明大だけがそうだったわけではありません。
早稲田の学生部の方が「うちはいないと思います」と言ってきたので、「早稲田大学の学生数って6万人でしたよね。6万人いていなかったら、それはそういう人たちを選別して落としているという意味ですか」と尋ねたら「いや、そんなことしていません」と言う。「だったら、いるに決まっているんです。プライバシーの問題があるから誰ということは言えませんが、早稲田大はニューハーフ業界でもかなり名門ですよ」とお返事しました。法政大はカルーセル麻紀さんのお師匠さんの「青江のママ」さんが法政大の学徒出陣ですからもっと名門ですね。後でまた申しますが、性別の悩みを持った学生さんというのは、東京の私立の大きな大学だったら確率的に必ずいるのです。ただ、それがきちんと認識されていない、あるいは本人が隠しているというだけの話なのです、ということをそのときの講演で、お話しました。
あの講演、少しは効果があったかなと思います。例えば慶應義塾大学で、MtF(Male to Female)の学生さんの就職がなかなかきついということで、大学の職員として雇用してくださった例がありました。もちろん、本人にそれだけの能力があったからでしょうが。
大きく流れが変わったのは、2003年です。7月に「性同一性障害者の性別取り扱いの特例法」(GID特例法)が成立し、翌年の7月に実施されました。この7月でちょうど実施10周年になります。これを大学に関係させて言うと、大学の学部あるいは大学院在学中に学生・院生が性別の変更を行うことが合法的に現実のものになったということです。あるいは、教職員の方で性別を変更する方が出てくるかもしれないということです。
少し飛びますが、2013年、文部科学省が全国の小中高校と支援学級を対象に、いわゆる性別違和に悩む児童、生徒の一斉調査というものをやりました。本当に一斉調査なのかという疑問もあるのですけれども、私は良い面と問題な面と両方を感じています。結果的に性別違和を持つ児童、生徒は606人。うち性同一性障害の診断をすでに受けている児童、生徒が165人という結果が出ました。実際はもっといるはずです。ただこれも、どの範囲を性別違和と捉えるかによってだいぶ人数が違ってきます。何度も言いますが、この問題がとてもややこしいのは、どの程度の性別違和感までを病理として把握するかということです。
例えば、私は明大で260人ぐらい受講生がいます。後期、山梨の都留文科大学でも240人ぐらいを持っています。だいたいその200人越えぐらいの人数で、コメントシートやレポートなどで、自分の性別違和を書いてくる学生がだいたい毎年2~3人はいます。不思議なことになぜか女子学生が多いのですが。周囲が女の子扱いするのが嫌で学校に行きたくなかったというような、かなり辛い性別違和を経験している例もあります。その時点で診断を受けたら、多分、性同一性障害の診断が出るだろうと思います。ところが、その学生とたまたま面談すると、一応女子学生で適応していたりします。本人は「まだ今でも違和感があります、すっきりしない部分はあります。だから先生の授業を取りました。でも何とか女子大生でやっています」という感じですね。そういう学生たちは、今後、病院へはたぶん行かないでしょう。だからそこまでを病理の範囲に入れるか入れないかで、かなり話は違ってくるのです。
最新の状況についてもお話ししておきましょう。実は今、国際的な動きがいろいろあります。2013年5月にアメリカ精神医学会のマニュアル「精神疾患の分類と診断の手引き」の改定が行われ、「DSM-5」と言われる第5版が施行されました。そこで、gender identity disorder、日本語でいう性同一性障害をgender dysphoria性別違和という病名に置き換えました。ただ病名を変更しただけではなく、診断基準も手直ししているので、置き換えたという言い方をしています。その結果、アメリカでは、すでにgender identity disorder、性同一性障害という病名はなくなりました。やはり「disorder」という部分に抵抗感を強く持つ当事者が多いのです。これはアメリカの診断基準ですから、どう変えようが、本来なら日本は関係ないはずなのですが、実際には日本の精神科医もかなり影響を受けています。日本のメンタルクリニックや心療内科へ行くと、「どうされました?」と尋ねる先生の後ろの書棚に分厚いDSMのマニュアルが飾ってあることが多いのです。ちゃんと読んでいるかどうかは知りませんが、影響力はすごくあるのです。
さらに、日本は国際連合に加盟していて、国連の専門機関である世界保健機関WHOのメンバーです。WHOにはICDと言う疾患リストがありまして、本来はこちらが日本で診断マニュアル化されるべきものです。そのICDの改訂作業が現在進行中で、新しい第11版、ICD-11の施行が2017年に予定されています。性別違和に関して、かなり大きな改訂になりそうで、まず確定的なのは、gender identity disorder性同一性障害はなくなります。何という病名に置き換えるかまだ決定ではないのですが、どうもgender incongruence、性別不一致という病名に置き換えられそうです。さらに重要な変更は、今までの精神疾患のカテゴリーから「その他の疾患」のカテゴリーに移す案が有力視されています。そこらへんの情報は2014年2月にバンコクの国際学会で仕入れてきた最新のもので、日本で知っている人はまだそんなに多くありません。
このまま実現すれば、gender identity disorder性同一性障害という病名は、国際的な疾患リストから完全に消えます。ですから、日本でも病名を変えなければなりませんし、「性同一性障害者の性別取り扱いの特例法」という法律名も変えなければいけなくなります。そして性別移行の脱精神疾患化が達成されることになりますが、この点はまだ少し不確定な要素があります。
ということで、現在は過渡期でありまして、2000年代に入って高まってきた性別移行の脱精神疾患化という世界的な流れが結実するかどうか、微妙なところに来ています。日本はそういう世界的な潮流にはまったく鈍感ですが、いずれそういう方向に行かざるを得ない、行くべきだということです。
(2) 性別移行システムの問題点
問題点を整理しておきましょう。2000年代、「GID特例法」制定の前後からにメディアが活発に性同一性障害について報道をしました。しかし、その報道は医療側の言説をそのまま流すという形で、病気だから仕方ないから戸籍を変えるのだという流れになってしまい、本来、考えなければいけない性的マイノリティの人権という視点が希薄化してしまいました。病気ということなら認めましょうという流れ、性別移行の病理化が一気に進行してしまったのです。それでうまくいった人もいるわけで、それはそれで結構なのですが、世界の流れは、2000年代に入って、むしろ病理化ではなく脱病理化、具体的には、性別移行を精神疾患概念からどうやって外していくかという脱精神疾患化の方向に向かっていました。ところが、日本は世界的な潮流とまったく逆行して、この10年間に病理化を推進してきたわけで、大学も「対応しますから、診断書を出しなさい」、さらに高校や中・小学校まで「診断書を出しなさい、診断書を出したら対応しますよ」という、形になってしまいました。性同一性障害概念の流布によって、性別移行の病理化が極端に進みすぎてしまい、病理を前提にしないと社会的対応ができないような仕組みができてしまいました。これは大きな問題です。今後、こうした病理を前提にしたやり方を人権を前提にした考え方に変えていかなければなりません。
先ほど申しましたように、弱い性別違和を持つ人は、けっこうたくさんいます。おそらく100人に数人レベルでいると思います。弱い性別違和をもつ人たちの多くは自然に解消する、あるいは自分で折り合いがつく可能性があるわけで、病理化する必要はないのです。ところが、医者の中には、性別違和感を持つ人すべてを病理化しようとする、性同一性障害の診断基準から外れるような弱い違和の人までを性別違和症候群として把握するような形が理想とする医師もいます。病理化の徹底ですね。そこには、自分にふさわしい性の在り様を自分で選んで決定するのは人権の一つであるという発想がないわけで、まったく困ったものです。
性別移行の当事者の方も、戸籍の性別変更が目的化してしまって、「GID特例法」の要件をクリアするため、ともかく性別適合手術をするという状況が生じています。必ずしもしなくてもいい手術まで受けてしまう過剰な医療化です。今、世界的にはIDカードなどの性別の書き換えに手術を要件とするのは人権侵害だという方向になっています。つい1カ月ほど前に、WHOが性別の移行に関して性別適合手術を要件化するのは人権侵害という勧告を出しました。日本の「GID特例法」は手術して生殖機能を喪失しないと性別の変更は認めない形ですから、WHOの勧告に完全に抵触します。日本の現状は、世界の性転換法の中で人権意識の低い、遅れた形になってしまっています。
病理化の徹底、過剰な医療化を進めながら、実は国内の医療施設がまったく足りません。患者は激増したのに、医療施設が増えないのです。だから手術をするのにみんな海外、主にタイへ行かざるを得ない。日本の医療というのは、面倒くさいことは全部外注してしまう傾向がありますが、まさにその典型です。
過剰な医療化、あるいはアンバランスな医療化の弊害が実際に出てきています。性同一性障害の診断を受けたのにジェンダーの移行がなかなか進まない。これは何か違う精神的な原因で引っ掛かっていると思われます。さらには、性別適合手術を受けて戸籍変更までしながら、新しい性別で社会適応ができない。たとえば、身体の外形も戸籍も女になりました。だけれど女性として社会適応ができませんというケースが増えているように思います。大学でこういう形が出てくると、なかなか対応が難しいことになります。
(3) 性別違和の人口比
性別違和を抱える人はだいたいどのぐらいの比率なのか、皆さんけっこう気になるのではないかと思いますので、その話をしましょう。
もともと欧米では、私のような男性から女性への移行を望むMtFが3万人に1人、逆に女性から男性への移行を望むFTMが10万人、つまり、MtFとFtMの比率は3対1と言われていました。このデータ、実はあまり信用度が高くないのですが、日本で90年代末に性同一性障害の問題が浮上したとき、どうも日本はFTMが少し多いのではないか、MtFが1~2万人に1人、FtMが3万人に1人、MtF対FtMの比率は2対1くらいに考える人が多かったと思います。ところが、どんどんどんどん差が詰まっていきまして、2000年代の初めぐらいには、MtF、FtMを通じてだいたい1~2万人に1人、MtF対FtMは1対1に近い。もうこの時点で、世界の研究者から「日本のデータが変じゃないか?」と言われ始めていました。さらに2008年ぐらいから、中高大学生ぐらいの若いFtMが急増して、MtFとFtMの比率が1対1.5~2と完全に逆転してしまいます。
私の授業では、2008年に放送された「ラストフレンズ」というテレビドラマの中で、ボーイッシュなレズビアンっぽい女性が性同一性障害だと思ってメンタルクリニックに行くシーンを学生に見せて、メディアのミスリードが現実世界に影響しているのではないかという話をするのですが、2008年ぐらいから様子ががらっと変わってきました。その後も女性から男性になりたい若い人の増加傾向がずっと続いていて、現状MtFとFtMの比率は1対3、90年代とは完全に裏返しになっています。人口比で言うと、MtFが1万人に1人か2人。MtFはあまり変わっていません。FtMが1万人に3人くらいという状況です。現状、日本は世界で最も顕著にFtMの比率が高い国になっています。
性別違和が重く性別適合手術をして戸籍の性別変更をした人が、2013年12月末現在で、全国で4353人というデータが出ています。このペースだと2014年末には5000人を超えるのは確実ですので、だいたい2万人に1人が戸籍の性別を変更しているということになります。
10年前に法律ができたときには、こんなに多いとは思いませんでした。年間50人ぐらいだろうと予想していました。年間50人だと10年で500人ですから、10倍ぐらい予想より多いというのが今の状況です。
なぜ、こんなに多いのか、そしてFtMの比率がこんなに高いのか。とても重要な問題なのですが、誰もきちんとした説を出していません。私が頑張って考えているのですが…。要は、全体に増加傾向にあるということと、特にFtMが増えているということを頭に置いておいてください。
それから、2010年代に入ると、あるお医者さんの言い方で「確信的でない受診者」が増えています。以前、メンタルクリニックに来る人は、かなり確信的に「私は、心は女なのに、男性なのです」とか、逆に「俺は絶対男だと思うんだけど、女なんで何とかしてください」というタイプが圧倒的でした。ところが最近は、「自分の性別がよく分からない」とい言う人が増えてきています。これをXジェンダーといいます。数学で不明数をXとするのと同じです。そういう人たちは「自分はXです」と言います。男ではないと思うけれども女でもないMtX。女ではないけれども男でもないFtXというタイプです。これが現実にかなり増えていて、理由を考えなければと思うのですが、まだ調査が進んでいません。私は弱い性別違和までを病理化してしまった結果、本来だったら男女どちらかに折り合いをつけるべきところを折り合いがつけられない人が増えてきているのだろうと思っています。それから女性に多いと思うのですが、いわゆる成熟拒否、大人の女性になりたくない。できるだけ猶予期間を長引かせたいという人も含んでいると思います。
こういう現状で、数値モデルを整理しておきますと、弱い性別違和を持つ人が100人に2~3人、医療が必要な強い性別違和を持つ人がそのうちの100人に1人ぐらい、つまり1万人に2~3人という話になります。さらに戸籍変更に至るまでの人は、そのうちの8~9人で、10万人に5人、2万人に1人。ここはかなり確定的なデータが出ていますので、こんなモデルが作られるわけです。私はどちらかと言うと少なめに見積もっていますが、そんなに違ってはいないと思います。
明治大学の学生数は2万9千人だそうです。このモデルに合わせると、強い性別違和を持つ学生は1万人に2~3人ですから、6~9人ぐらいいて当たり前ということです。1万人に2~3人というのは全人口比ですから、大学在学年齢だともっと多いと思います。何10人ということではありませんが10数人いてもおかしくないということです。何度も申しますが、いて当たり前だという認識がとても大事です。
さらに言うと、まさに10代後半ぐらいの年齢層では、自分の性別がよく分かりませんというXジェンダー的な学生がだいぶ増えているはずです。おそらく「性同一性障害」のカテゴリーに入る学生と同じくらいいるかもしれません、かなり強い性別違和を持つ学生が仮に10人いたとしたら、曖昧な形で何か性別に悩んでいるような学生も、もう10人ぐらいはいるという勘定です。これだけいたらもう珍しい話ではありませんので、そういう学生が相談に来た時の対応マニュアルをきちんと作っておくべきです。ただし、マニュアルは、個々のケースに応じて弾力的に運用することが大事です。
3 大学はどう対応すべきか
では、大学は具体的にどういう対応をしていけばいいのかについてお話しします。ここからは私の主観的な意見になっていくわけですが、実を言うと12年前にお話ししたことと基本は変わっていません。自分でも頑固だなとは思いますが、12年前から言ってきたことが今、現実になっている感じがありますので、少し自信を持っています。
① いて当たり前という基本認識
先ほども申しましたように、ある程度の規模の大学なら強い性別違和感を持つ学生が在籍しているのは確率的に当然で、まったく特異なことではありません。いて当たり前だという基本認識を持ち、いると思って対応すべきなのです。不思議なことでも特異なことでもないということです。
② 基本的には本人の自主性に任せる(放っておく)
異性装、身体の性別とは違う服装をするとか、性別を越えて生きるということ自体は、病でも性的逸脱でもありません。客観的には「変わり者」かもしれませんが、現在の日本では法律で禁止されているわけでもありません。日本で異性装が違法だったのは、明治5~6年から14年(1881)までの約10年間、文明開花期だけです。基本的に、服装表現、性別表現、ジェンダーの選択は個人の自由で、人権として認められるべきものです。つまり、本人の自主性にまかせるべき問題で、そうした学生がいたからといって、大学のほうから積極的に介入する必要はありません。基本的には放っておくべきことなのです。性同一性障害なんていう話が出てくる以前にも、書類上は男子学生だけどずっと女の格好で大学に通っていましたという人は実際にいます。もちろん大学側は気付いていたはずですけど、処分するようなことはできませんし、結局そのまま「あいつは変わっているな」で卒業してしまったという話です。基本的には放っておく、でも、なにか困って相談に来たら、ちゃんと対応するということが大事なところです。
③ 環境整備に努める
性別を移行したい学生にとって一番困るのは、学生名簿の男女欄など、学内における性別記載です。日本の大学、例えば文学部だったら文学士という学位を出します。文学士男とか、文学士女という学位ではないわけで、男だろうが女だろうが……女子大は別ですが、明大は共学なので、いちいち学生名簿に男女欄とか男女の識別記号はいらないはずです。学生証の性別記載欄も同様です。性別で引っ掛かってしまう学生にとっては、引っ掛かる場所がたくさんあるのは辛いものなのです。
これは何も大学だけではなく、世の中がそういう方向に向かわないといけません。たとえば住民票の申請をするのに何でいちいち男女欄に丸を付けなければいけないのか。あるいは選挙で投票するのに、なぜいちいち投票場の入場券に男女と書いてあるのか。そういう問題を私たちトランスジェンダーは、10年以上、いろいろ問題化して社会に働きかけてきました。実際、ずいぶん減っているのです。私が住んでいる川崎市では、投票場の入場券に以前は男・女とはっきり書いてあったのが、記号化されてあまり目立たなくなっています。大学も同じように、環境整備としてそうした必ずしも必要でない性別記載欄を減らしていく方向で行くべきだと思います。
今ちょうどレポートの採点時期で、昨日も履修者名簿を見ていたのですが、明大の名簿には、名前の欄の尻尾のところに、女子学生だけ「F」という記号が付いています。これは必要でしょうか。前もそんなお話をしたら、名前を呼ぶ先生が、男なら何とか君、女なら何とかさんと、敬称を変える必要があるからというお話でした。でも、1回目の授業のときに先生が「この学生は女子」と個人的にチェックしていけばいいわけで、公的な名簿で性別表記をする必要があるのかということです。そもそもなぜ男子と女子で敬称を変えなければいけないのでしょうか。全員「さん」で問題ないでしょう。私が関わっている大学では、都留文科大学と東京経済大学の名簿には、性別を示す記号はありません。こういうことは慣例でずっとやってきたことなので、それに慣れているとなかなか変えにくいのかもしれませんが、本質的によく考えていただきたいと思います。実際に男女の別が必要なのはごくごく限られた、例えば体育実技などだけだと思います。体育実技だって男女一緒のスポーツでやっている場合は、そんなに必要もありませんね。
④ 何が障害になっているのかを聞く
先ほど申しましたように、基本的には放っておくべきなのですが、性別に悩みがある学生が相談に訪れた場合は、何が問題なのかをきちんと聞くことが大切です。この場合、悩みが性自認の問題なのか、あるいは性的指向の問題なのか、分別すること必要です。ただし、相談に来ている学生自身がよく分かっていないことがけっこうありますから、相談を受ける側がそこらへんを整理しながら聞いていくことが必要になります。その学生にとって何が一番の問題なのか。たとえば、自分は男なのに男が好きということで悩んでいるのか、自分は男なのだけど、どうもそれに馴染めない、自分の中身が女のほうにズレているという悩みなのか、ということです。
実は、前に触れた文科省の全国一斉調査は、この部分の指示がないのです。つまり、性に違和感がある、友達と性のあり方が違うという子供が、それは性的指向が違っているのか、それとも自分の性別に対する違和感なのか、小学校段階できちんと分別がつくはずがないのです。中学生だってあやしいです。それを一緒にして、あたかも性同一性障害の予備軍的に見るのは大きな間違いです。人数的には性同一性障害よりも同性愛のほうが圧倒的に多いはずですから。
先日、朝日新聞の教育欄に、大学におけるLGBT――レズビアン、ゲイ、バイ・セクシャル、トランスジェンダーの学生のサークルがすいぶん増えてきたというニュースが載っていました。明大の私の受講生にも、そういうサークルを立ち上げて熱心に活動しているレズビアンの女子学生がいます。各大学を結ぶインターカレッジ的なつながりもできてきているようです。
ゲイ、レズビアンの学生たちは、自分たちで何とかやっていける人も多いのです。それに対して、性別違和を抱える学生は、身体の問題もありますので、悩みを内に抱えてしまう傾向があり、そういう学生が相談に来る可能性が高いと思います。その場合、最初から性同一性障害という病気と決め付けるのではなくて、何に困っているのかから入るべきです。例えばトイレ。性別の問題が引っ掛かる人には、いわゆる「誰でもトイレ」(多目的トイレ)を使うようにアドバイスするのが一般的ですが、私の講師控室があるリバティタワーの3階は、少し進みすぎていて、車椅子でも入れるトイレが男女別に…女子トイレの中にあるのです。そうなると、またややこしい状況が出てくるわけです。トイレの問題は、性別に悩みがある学生には切実な問題なので、大学のどこかに誰でも使えるユニバーサルなトイレが確保されていることが必要です。
⑤ 知識を提供する
性の問題というのは多様ですので、適当な参考書を紹介して知識を提供して、その多様な性の形態の中からもっとも自分にふさわしいジェンダー&セクシュアリティのあり方を自分で選択させることが大事です。具体的には野宮亜紀、針間克己ほか著『性同一性障害って何? ―一人一人の性のありようを大切にするために (プロブレムQ&A)』(緑風書房、2011年増補改訂版)などがよいでしょう。私もジェンダー論の授業の最初と最後に、「この授業が皆さんにとって一番心地よいジェンダー・セクシュアリティのあり方を見つけるための手がかりになればうれしいです」という話をします。これは性的なマイノリティの人たちも全く同じで、自分が何なのだということをきちんと自分なりに理解をしていかないと、自己肯定感が生まれないのです。セクシュアル・マイノリティはゲイ、レズビアンでもトランスジェンダーでもそうなのですが、最終的にはマジョリティーとは違う自分の性のあり方を、私はこうなのだ、私はこれでいいのだと自己肯定できないと、悩みはいつまでも続いてします。私などもある程度の自己肯定はできても、なかなか100パーセントの自己肯定には至りません。その難しい自己肯定の材料をどう与えていくか、サジェスチョンをしていくか、とても大事だと思うのです。
⑥ 必要な場合は専門医を紹介する
自分の体が嫌で嫌で仕方がないというような強い身体違和、FtMだったら生理が来るたびに死にたくなるとか、MtFだったらシャワーを浴びるたびに自分のペニスを切断したくなるようなケース。あるいは、ジェンダー違和が強くて、家から出られない、学校にも行けないような性別違和感に由来する社会的不適応を訴える学生は、放置できません。放置をすると本当に自殺を企ててしまうか、修学が継続できなくなってしまいます。そういうケースでは、性同一性障害の専門医を紹介して、専門的なカウンセリングを受けるように方向付けることが必要です。
この点については、明治大学駿河台校舎は日本一恵まれています。日本における精神科領域の性別違和、性同一性障害問題の第一人者である針間克己先生が2008年に神田小川町3‐24‐1に「はりまメンタルクリニック」を開院したからです。私はリバティホールで授業をやっていますが、リバティホールからだと信号に引っ掛からなければ3分で行ける距離で、本当にすぐそこです。私が明大で初めて講義を持った2012年前期、「あれ?何か社会人学生にしてもばかにひねた大人が後ろのほうで聞いているな」と思ったら針間先生でした。たまたま先生のクリニックは火曜日の午後が休診で、私の講義が火曜日の午後の1コマ目だったので聴講していたのです。東京大学医学部を出た先生が、私なんかの講義を聞いて少しでも勉強しよういう謙虚な姿勢、すばらしいです。ただ、明大の授業をただ聞きしていたわけですから、何かあったときに少し無理を頼んでも嫌とは言えない立場です。専門的なカウンセリングが必要な学生がいたら、ぜひ紹介してください。残念ながら、性同一性障害の診察で、私が自信を持ってご紹介ができるメンタルクリニックは、東京近辺に3つしかありません。他に千葉県浦安市の阿部輝夫先生の「あべメンタルクリニック」、埼玉県さいたま市の塚田攻先生の「彩の国みなみのクリニック」ですが、針間先生のところが一番近いです。
⑦ 学内で可能な限り対応措置をとる
MtFが学内での女性扱い、FtMが男性扱いを希望する場合は、通称名の学内使用をはじめ可能な限り対応措置をとっていただきたいと思います。ただ、なかなかやっかいなのは、希望する性別への適合度です。一目見て、「あなた、どう見たってそれで男子学生は無理でしょう、女子学生の方が自然でしょう」というようなMtF、あるいは「それで女子学生は無理でしょう」というようなFtMの学生だったら大きな問題はないと思います。しかし「う~ん、微妙と」というケースもしばしばあります。そうしたケースは、ある程度、1年くらいの観察期間が必要だと思います。中には精神的に不安定な学生もいて、ガーッとどちらかの性別に偏って、少しすると熱が冷めるというようなケースもあります。あまり性別をコロコロ変えられるのは、大学の事務としては困るでしょうから、基本的には、4年間、卒業までの継続性を前提に、学生が求める措置を取って欲しいと思います。
⑧ 性別移行プロセスへの協力
在学中に戸籍名を望みの性別にふさわしいものに改名したり、戸籍の性別を変更したりする学生、院生が出てくることは、現在の性別移行システムで十分にありうることです。現在のガイドラインでは、クロスホルモン―男性だった人に女性ホルモンを投与、女性だった人に男性ホルモンを投与すること―は、場合によっては16歳から可能です。戸籍の変更要件は20歳以上になっていますが、外国で性別適合手術を受けるだけならその前でも可能です。つまり、入学以前からクロスホルモン投与を受け、在学中に性別適合手術をして、戸籍の性別を変更して、卒業証書は新しい名前と性別でもらって、望みの性別で社会に巣立つという人生計画を立てる学生が出てくるということです。それは現在、認められている性別移行システムに沿ったものなので、そうした性別移行のプロセスに、大学はできるだけ協力をしてあげてください。
⑨ いっそうの就労支援
問題は、戸籍の性別変更がまだ済んでいない学生、あるいは、性別は移行するけども戸籍の性別まで変えるつもりはない学生の場合です。そうした学生の場合、最大の難関は望みの性別での就労です。私もそれでさんざんそれで引っ掛かってきたわけです。日本の大学は非常勤でトランスジェンダーの教員を任用するところまでは来ていますが、常勤ではまず採らないでしょう。それが日本の現実です。ただ、この点に関しては、日本が遅れているわけではなく、外国だと非常勤でもトランスジェンダーは採用しない国はけっこうあります。日本は非常勤ではあるけれど、トランスジェンダーを大学教員に採用していますという話をしたら、外国の研究者に「great、素晴らしい」言われたことがあります。私の場合、年齢的にもう仕方がないなと諦めていますが、若いトランスジェンダーの学生にとっては、やはり就職が最大の難関です。前から言っていることですが、就職課が格別の配慮、一般学生に不平等にならない程度にできるだけのバックアップをしていただきたい。能力が十分にあるトランスジェンダー学生が性別の問題だけで就職ができないということは、その学生だけでなく、社会全体にとっても損失ですし、それは何とか避けたいと思うわけです。
性同一性障害の場合、会社に入ってから性別移行をしたとして、それを理由にした解雇は違法という判例が固まっていますので、入社してからは首を切れません。性同一性障害を理由に解雇して裁判になったらほぼ確実に会社側が負けます。さすがだなと思ったのは、判例が出た頃に企業の総務課や人事課の人たちが読む専門雑誌に、さっそくその判例が紹介されていました。きちんと勉強している企業の労務管理担当者は知っているはずです。ですが、採用段階での就労差別はかなりあります。「戸籍を変更されてからもう一度当社をご受験ください」という形で門前払いするケースです。ですから、学生にしてみると、とりあえ生得的な性別で入社して、入ってから性別を移行するという手もなくはないです。でも、「就職のときは、そのことを隠していたのか」という信義の問題になりかねませんので、なかなか難しいところです。何度も言いますが、就労問題が最大のネックですので、何とかバックアップしていただきたいと思います。
⑩ 望みの性別で生きて行くための社会訓練の場としての大学
実は今、小・中学校では、性別違和を抱える児童、生徒がいると、隔離的、特別に扱って「どこどこの病院へ行って診断書を取って来てください」というように、問題を性同一性障害医療に委ねてしまう形がけっこう多くなっています。大学レベル、ましてや明治大学みたいなトップクラスの大学だったら、そんな安易な方法は採らないと思います。医療の手に委ねてしまうのではなく、大学という一つの社会で性別違和を抱える学生を受け入れていくという姿勢が望まれるわけです。トランスジェンダーの学生が望みの性別での生活を円滑にできるようになるためには、トレーニング期間が必要です。いずれ望みの性別で社会に出て行かなければならない学生にとって、大学の4年間プラスアルファが、トレーニング、社会訓練の場になるわけです。大学はそれをサポートする方向で対応してほしい、そうした姿勢を持って欲しいということです。
私は2002年に「トランスジェンダーと学校教育」という論文を書いているのですが、私が書いた論文の中で一番読まれません。どうしてなのだろうと思うのですが、どうも、現実の学校現場の先生とだいぶ意識が違うようなのです。たとえば、先生方は「男女別に並べるときにどうしたらいいのですか?」と質問してきます。私が「男女別に並べること自体を考え直した方がよろしいのではないですか」と返事をすると、ものすごく不満な顔をされてしまいます。前例が無いケースが出て来た時には、前例に合わせようとするのではなく、従来のシステムを再検討して新例を開くという姿勢が大事だと思います。
おわりに
2014年2月にタイのバンコクでWPATH2014という国際会議が開催されました。WPATHというのはWorld Professional Association for Transgender Health、トランスジェンダーの健康のための世界専門家会議という団体です。今回が第23回でしたが、今までずっと欧米で開催されていて、今回が初めてのアジア開催でした。そこでアジア・太平洋地域のトランスジェンダーをできるだけ集めて「Trans People in Asia and Pacific」というシンポジウムをやろうということになりました。とはいえ、これがなかなか大変で、トランスジェンダーは、お金持ちではない人がほとんどなので、飛行機代、滞在費を世界開発機構、世界エイズ会議など国際連合の4機関が資金提供して、アジア・パシフィック10カ国、最終的は日本も入って11カ国のトランスジェンダーがバンコクに集まりました。私も招待状をもらったのですが、日本はOECD加盟国で、世界開発機構ではお金を出す立場でお金をもらう立場ではない、だから日本の研究者には資金提供はできないから旅費と滞在費は自分持ちで来てくれ、というという話で、「それはあんまりな・・・」と思いました。お金のことはともかく、世界のどの国にも、トランスジェンダーはいるということです。いろいろ困難な状況はあるけれども、それぞれの国でそれぞれの社会の中で頑張って生きているわけです。
そうしたシンポジウムで、とても考えさせられたことがありました。全部で12人が各国の事情を報告したのですが、12人のうち11人がMtFなのです。私以外のMtFは、フィリピン、インドネシア、タイ、ネパール、インド、そしてトンガ、みんな英語がペラペラで、パワーポイントできちんと資料を作ってきて、しっかりプレゼンテーションをできる能力があります。ところが、FtMの人はそうしたプレゼンテーションができないのです。12人中1人だけ、しかもニュージーランドの活動家でしたから、少し事情が違います。
どういうことかと言いますと、アジアの国で、女性として生まれて女性としての教育を受けてきた人は、開発途上国における男女の教育格差を被ってしまうのです。女で育てられると、なかなか十分な教育が受けられない。それで男になっても、一定の知的レベルが求められる社会的活動がなかなか難しいのです。
この例のように、性別を変えて生きる人たちにとって、大事なのは教育なのです。社会に出て一般の人よりももっと厳しい状況の中で生き抜いていくための力になるのは教育です。教育をきちんと受けられるかどうかが鍵なのです。実は、日本もそういう傾向があって、日本で今FtMがこんなに多くなっているのに、日本から参加して報告したメンバーは2人ともMtFでした。残念ながら、国際学会で通用するレベルのプレゼンテーションができるFtMは、日本ではほとんどいません。なぜかというと、FtMの最終学歴は、MtFに比べて明らかに低く、高校中退レベルの人がかなりいます。そうした状況は徐々に改善されてきていますが、制服とかいろいろなことで引っ掛かってしまって修学が継続できず、その結果、低学歴で終わってしまって、学力やスキルが伴わないFtMがまだかなりいるのです。
社会の中でより良く生きていくための力を大学教育の中で身に着ける必要性は、一般学生でもトランスジェンダーの学生でもまったく変わりません。むしろトランスジェンダーであるがゆえにその必要性は高いのです。そのためには、何度も言うように修学が継続できる……きちんと卒業ができて、できることなら望む方面に就職ができるようなバックアップを、明治大学だけではなく全国の大学でぜひとっていただきたいと思います。
だいたい予定の時間になりました。3年前、明大に非常勤で呼んでいただいた時から、いつか講義以外でもお役に立てる機会があればと思っていましたので、今日はこういう機会をいただいて、とてもうれしかったです。どうもありがとうございました。
(紙幅の都合により、講師紹介及び質疑応答は割愛させていただきました。)
【参考文献】
三橋順子「『性』を考える-トランスジェンダーの視点から-」
(シリーズ 女性と心理 第2巻『セクシュアリティをめぐって』 新水社 1998年)
三橋順子「トランスジェンダーと学校教育」
(『アソシエ』8号 御茶の水書房 2002年)
三橋順子「トランスジェンダーをめぐる疎外・差異化・差別」
(シリーズ「現代の差別と排除」第6巻『セクシュアリティ』明石書店 2010年)
その記録が『学生相談 2014年度 学生相談室報告』(明治大学学生支援部 2015年6月)に掲載されました。
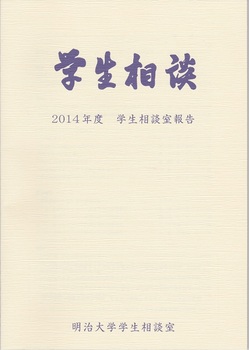
学外者には入手が難しい学内誌なので、全文をここに掲載します。
--------------------------------------
明治大学 第53回学生相談室夏期セミナー 講演
「性別違和感を抱く学生に教職員はどう対応していくか」
2014年7月27日(日)
文学部 兼任講師 三橋 順子
はじめに
皆さん、こんにちは。三橋順子です。明治大学に非常勤講師で呼んでいただいて3年目になります。簡単に自己紹介しますと、私は、男性から女性へのトランスジェンダーですが、戸籍は生まれたときの性別、名前で変えておりません。1995年くらいから社会的には女性として、講演、著述、あるいは教育活動をしてきました。女性としてそれなりに実績はあったわけですが、実は、明治大学から講師のオファーがあったとき、すんなりとはいきませんでした。「お引き受けします」とお返事した後、履歴書段階で1~2カ月ほど手続きが止まってしまったのです。理由は履歴書の性別欄の記載です。私は履歴書の性別欄を空欄で提出しました。私の性自認からして「男」とは書けませんし、男女雇用機会均等法の趣旨からして性別の記載は強要されるべきではないと考えますので。それに対して人事課は「性別欄が空欄なのは前例が無い。戸籍通りちゃんと男性と記載してください」ということでした。私から明大で講義をさせてくれとお願いしたわけではなく、明大から依頼してきたことですので、「それなら結構です」と申しましたら、やっと人事が動いたということがありました。性別記載で引っ掛かってしまうということが、まだまだ日本の現実としてあるということです。明治大学だけが理解がないわけではなくて、日本社会のシステムが男女二元で、しかも硬直的で融通が利かない。それが性別を越えて生きるトランスジェンダーの人たちをどれだけ生きにくくしているかという事例としてお話しました。今日はそうした問題をどのようにクリアしていけばよいかというお話をいたします。
1 基礎知識として
今日のテーマは「性別違和感を抱く学生に」ということですが、最初に基礎知識的なことを、三つお話をしておきましょう。
(1) 同性愛とトランスジェンダー
一つ目は、同性愛とトランスジェンダーの違いです。学生も一番ここが分からないと言うので、こんな説明をします。同性愛は、男が好きか女が好きかという性的指向sexual orientation問題であって、自分が男であるか女であるかというgender identity性自認(性同一性)の問題ではありません。誰を好きになるかという相手の性別がマジョリティーの人と違っているのが同性愛です。トランスジェンダーは自分が男であるか女であるかという性自認gender identityの問題で、男が好きか女が好きかというsexual orientationの問題ではありません。男として生きるか女として生きるかという自分の性別の在り方の問題です。
(2) 性別違和感(Gender Dysphoria=GD)とは?
基礎知識の二つ目は、性別違和感gender dysphoriaとは何かということです。一般的には、自分の性別に対する心理的な違和感が性別違和感です。性別違和感を考える場合、基本になるのは自分の性自認、自分を男と思うか、女と思うかということです。自分は男だと思っているのに、身体が女である、生理が来る。あるいは、自分が女だと思っているのに、男性の身体である、声変わりをしてしまう、髭が生えてくるというような性自認と身体の性のズレが身体違和です。
ズレ(違和感)はそれだけでなく、性自認と社会的性(ジェンダー)の間にも生じます。自分が女だと思っているのに、世の中からは男として扱われる。「あなたは、戸籍は男でしょう。だから男として扱いますよ」ということです。自分は男だと思っているのに、「あなた、戸籍上は女でしょう。女性のほうに入りなさい」と言われてしまう。性別違和感は性自認と身体の間、性自認と社会的な扱いの2カ所で生じます。ここがポイントです。身体のほうの違和感は大学でどうこうできる話ではありませんので、医学的な対処が必要になりますが、社会的な扱いに関しては、世の中の一部である大学でも対応できる問題ということになります。
心が女なのに身体が男であるというのはやはり辛いわけで、何とかズレを直そう、整合性を回復しようとします。自分は女だと思っているのに世の中から男として扱われるというのはとてもきついことです。さっきの私の履歴書の話ですが、あの時は精神的に相当きつかった、かなり落ち込みました。そのあたりは、性別違和感がない方にはなかなか理解をしていただけないと思いますが。性別違和感というのは、ギザギザ、トゲトゲした、やっかいな嫌なものなので、何とかそれを解消しようと努力します。つまり、性別違和感は、性別を移行していく原動力になるわけです。
(3) 性同一性障害(Gender Identity Disorder=GID)とは?
基礎知識の三つ目は、性同一性障害とは何かということです。性同一性障害は、Gender Identity Disorderという英語の疾患名の日本語訳です。先ほど、性別違和感は性自認(性同一性)gender identityと身体的性sex、性自認と社会的役割gender roleの2カ所で生じると申しましたが、その2カ所の不一致に起因する性別違和感がどんどんひどくなっていった結果、著しい精神的苦痛や、社会生活・職場における機能障害、つまり、社会生活がうまくいかない、あるいは学校や職場でそこにうまく身をおけないという形になって、医療のサポートが必要になった状態をいう精神疾患概念です。「性同一性障害は病気ではないと思います」という学生がときどきいますが、「性同一性障害というのは精神疾患の名称なので、それを病気でないというのは概念矛盾で、成り立ちませんよ」と説明します。ただし、性同一性障害というのは性別違和感を原因とする社会的不適応の病であって、性別違和感を持っていること自体は病気ではないということです。ここはマスメディアが心の性と身体の性がズレていることが病気だというような説明をすることが多いのですが、それは間違いです。実は、自分の性の在り様が何かズレている、違和感があるという人は、けっこう多いのです。それは違和感の程度の問題でして、違和感があること自体を病にしてしまうのは、問題があると思います。そのような状態をとても苦痛を感じていて、社会生活上、不適応を起こしていることが病であると捉えないといけないと思います。
2 「性別違和」の現在
(1) この15年間の流れと最新の動向
次に、日本で性別移行の問題が社会的に浮上したこの15年ぐらいの流れをざっとおさらいしておきます。もちろんそれ以前から、性別を変えようと努力したいろいろな人がいたわけですが、やはり起点は1996年です。私立の埼玉医科大学の倫理委員会が、形成外科の教授から申請があったSex Reassignment Surgery、「性転換手術」、現在で言う「性別適合手術」を正当な医療行為として承認したことがニュースになりました。これはあくまでも一大学の倫理委員会の判断で、本来はそんなに大げさに報道することではないと思うのですが。それを受けて97年の5月に、日本精神神経学会が「性同一性障害に関する答申と提言」という、私たちが「ガイドライン」と呼んでいるものを出しました。これもかなり大きなニュースになって、このあたりから性同一性障害という病名が『現代用語の基礎知識』などにも載るようになってきました。98年10月に埼玉医科大学が「ガイドライン」に基づいたものとして初めての性別適合手術を実施しました。あくまでもガイドラインに基づいたものとしては初めての手術であって、性別適合手術自体は日本では1951年、世界でも指折りに早い時期からやっています。これは私が調べたことですが。
そんな流れの中で2002年の8月に六大学「学生相談」連絡会議で「性別違和を抱える学生をどう受け入れるか」という講演をさせていただきました。会場は中央大学で、私は中央大学の社会科学研究所の研究員という立場でした。その、きっかけは明治大学だったように覚えています。明大で、自分は男ですという女子学生、つまりFtM(Female to Male)の学生さんが出てきて、教授会で問題になったというお話でした。「問題になったというのは、対策が問題になったのですか」とうかがったら、そうではなく、「『明治大学の学生ともあろうものがけしからん』とある教授が言い出した」というお話でした。今からすると、とんでもない無理解ですが、この頃は、明大だけがそうだったわけではありません。
早稲田の学生部の方が「うちはいないと思います」と言ってきたので、「早稲田大学の学生数って6万人でしたよね。6万人いていなかったら、それはそういう人たちを選別して落としているという意味ですか」と尋ねたら「いや、そんなことしていません」と言う。「だったら、いるに決まっているんです。プライバシーの問題があるから誰ということは言えませんが、早稲田大はニューハーフ業界でもかなり名門ですよ」とお返事しました。法政大はカルーセル麻紀さんのお師匠さんの「青江のママ」さんが法政大の学徒出陣ですからもっと名門ですね。後でまた申しますが、性別の悩みを持った学生さんというのは、東京の私立の大きな大学だったら確率的に必ずいるのです。ただ、それがきちんと認識されていない、あるいは本人が隠しているというだけの話なのです、ということをそのときの講演で、お話しました。
あの講演、少しは効果があったかなと思います。例えば慶應義塾大学で、MtF(Male to Female)の学生さんの就職がなかなかきついということで、大学の職員として雇用してくださった例がありました。もちろん、本人にそれだけの能力があったからでしょうが。
大きく流れが変わったのは、2003年です。7月に「性同一性障害者の性別取り扱いの特例法」(GID特例法)が成立し、翌年の7月に実施されました。この7月でちょうど実施10周年になります。これを大学に関係させて言うと、大学の学部あるいは大学院在学中に学生・院生が性別の変更を行うことが合法的に現実のものになったということです。あるいは、教職員の方で性別を変更する方が出てくるかもしれないということです。
少し飛びますが、2013年、文部科学省が全国の小中高校と支援学級を対象に、いわゆる性別違和に悩む児童、生徒の一斉調査というものをやりました。本当に一斉調査なのかという疑問もあるのですけれども、私は良い面と問題な面と両方を感じています。結果的に性別違和を持つ児童、生徒は606人。うち性同一性障害の診断をすでに受けている児童、生徒が165人という結果が出ました。実際はもっといるはずです。ただこれも、どの範囲を性別違和と捉えるかによってだいぶ人数が違ってきます。何度も言いますが、この問題がとてもややこしいのは、どの程度の性別違和感までを病理として把握するかということです。
例えば、私は明大で260人ぐらい受講生がいます。後期、山梨の都留文科大学でも240人ぐらいを持っています。だいたいその200人越えぐらいの人数で、コメントシートやレポートなどで、自分の性別違和を書いてくる学生がだいたい毎年2~3人はいます。不思議なことになぜか女子学生が多いのですが。周囲が女の子扱いするのが嫌で学校に行きたくなかったというような、かなり辛い性別違和を経験している例もあります。その時点で診断を受けたら、多分、性同一性障害の診断が出るだろうと思います。ところが、その学生とたまたま面談すると、一応女子学生で適応していたりします。本人は「まだ今でも違和感があります、すっきりしない部分はあります。だから先生の授業を取りました。でも何とか女子大生でやっています」という感じですね。そういう学生たちは、今後、病院へはたぶん行かないでしょう。だからそこまでを病理の範囲に入れるか入れないかで、かなり話は違ってくるのです。
最新の状況についてもお話ししておきましょう。実は今、国際的な動きがいろいろあります。2013年5月にアメリカ精神医学会のマニュアル「精神疾患の分類と診断の手引き」の改定が行われ、「DSM-5」と言われる第5版が施行されました。そこで、gender identity disorder、日本語でいう性同一性障害をgender dysphoria性別違和という病名に置き換えました。ただ病名を変更しただけではなく、診断基準も手直ししているので、置き換えたという言い方をしています。その結果、アメリカでは、すでにgender identity disorder、性同一性障害という病名はなくなりました。やはり「disorder」という部分に抵抗感を強く持つ当事者が多いのです。これはアメリカの診断基準ですから、どう変えようが、本来なら日本は関係ないはずなのですが、実際には日本の精神科医もかなり影響を受けています。日本のメンタルクリニックや心療内科へ行くと、「どうされました?」と尋ねる先生の後ろの書棚に分厚いDSMのマニュアルが飾ってあることが多いのです。ちゃんと読んでいるかどうかは知りませんが、影響力はすごくあるのです。
さらに、日本は国際連合に加盟していて、国連の専門機関である世界保健機関WHOのメンバーです。WHOにはICDと言う疾患リストがありまして、本来はこちらが日本で診断マニュアル化されるべきものです。そのICDの改訂作業が現在進行中で、新しい第11版、ICD-11の施行が2017年に予定されています。性別違和に関して、かなり大きな改訂になりそうで、まず確定的なのは、gender identity disorder性同一性障害はなくなります。何という病名に置き換えるかまだ決定ではないのですが、どうもgender incongruence、性別不一致という病名に置き換えられそうです。さらに重要な変更は、今までの精神疾患のカテゴリーから「その他の疾患」のカテゴリーに移す案が有力視されています。そこらへんの情報は2014年2月にバンコクの国際学会で仕入れてきた最新のもので、日本で知っている人はまだそんなに多くありません。
このまま実現すれば、gender identity disorder性同一性障害という病名は、国際的な疾患リストから完全に消えます。ですから、日本でも病名を変えなければなりませんし、「性同一性障害者の性別取り扱いの特例法」という法律名も変えなければいけなくなります。そして性別移行の脱精神疾患化が達成されることになりますが、この点はまだ少し不確定な要素があります。
ということで、現在は過渡期でありまして、2000年代に入って高まってきた性別移行の脱精神疾患化という世界的な流れが結実するかどうか、微妙なところに来ています。日本はそういう世界的な潮流にはまったく鈍感ですが、いずれそういう方向に行かざるを得ない、行くべきだということです。
(2) 性別移行システムの問題点
問題点を整理しておきましょう。2000年代、「GID特例法」制定の前後からにメディアが活発に性同一性障害について報道をしました。しかし、その報道は医療側の言説をそのまま流すという形で、病気だから仕方ないから戸籍を変えるのだという流れになってしまい、本来、考えなければいけない性的マイノリティの人権という視点が希薄化してしまいました。病気ということなら認めましょうという流れ、性別移行の病理化が一気に進行してしまったのです。それでうまくいった人もいるわけで、それはそれで結構なのですが、世界の流れは、2000年代に入って、むしろ病理化ではなく脱病理化、具体的には、性別移行を精神疾患概念からどうやって外していくかという脱精神疾患化の方向に向かっていました。ところが、日本は世界的な潮流とまったく逆行して、この10年間に病理化を推進してきたわけで、大学も「対応しますから、診断書を出しなさい」、さらに高校や中・小学校まで「診断書を出しなさい、診断書を出したら対応しますよ」という、形になってしまいました。性同一性障害概念の流布によって、性別移行の病理化が極端に進みすぎてしまい、病理を前提にしないと社会的対応ができないような仕組みができてしまいました。これは大きな問題です。今後、こうした病理を前提にしたやり方を人権を前提にした考え方に変えていかなければなりません。
先ほど申しましたように、弱い性別違和を持つ人は、けっこうたくさんいます。おそらく100人に数人レベルでいると思います。弱い性別違和をもつ人たちの多くは自然に解消する、あるいは自分で折り合いがつく可能性があるわけで、病理化する必要はないのです。ところが、医者の中には、性別違和感を持つ人すべてを病理化しようとする、性同一性障害の診断基準から外れるような弱い違和の人までを性別違和症候群として把握するような形が理想とする医師もいます。病理化の徹底ですね。そこには、自分にふさわしい性の在り様を自分で選んで決定するのは人権の一つであるという発想がないわけで、まったく困ったものです。
性別移行の当事者の方も、戸籍の性別変更が目的化してしまって、「GID特例法」の要件をクリアするため、ともかく性別適合手術をするという状況が生じています。必ずしもしなくてもいい手術まで受けてしまう過剰な医療化です。今、世界的にはIDカードなどの性別の書き換えに手術を要件とするのは人権侵害だという方向になっています。つい1カ月ほど前に、WHOが性別の移行に関して性別適合手術を要件化するのは人権侵害という勧告を出しました。日本の「GID特例法」は手術して生殖機能を喪失しないと性別の変更は認めない形ですから、WHOの勧告に完全に抵触します。日本の現状は、世界の性転換法の中で人権意識の低い、遅れた形になってしまっています。
病理化の徹底、過剰な医療化を進めながら、実は国内の医療施設がまったく足りません。患者は激増したのに、医療施設が増えないのです。だから手術をするのにみんな海外、主にタイへ行かざるを得ない。日本の医療というのは、面倒くさいことは全部外注してしまう傾向がありますが、まさにその典型です。
過剰な医療化、あるいはアンバランスな医療化の弊害が実際に出てきています。性同一性障害の診断を受けたのにジェンダーの移行がなかなか進まない。これは何か違う精神的な原因で引っ掛かっていると思われます。さらには、性別適合手術を受けて戸籍変更までしながら、新しい性別で社会適応ができない。たとえば、身体の外形も戸籍も女になりました。だけれど女性として社会適応ができませんというケースが増えているように思います。大学でこういう形が出てくると、なかなか対応が難しいことになります。
(3) 性別違和の人口比
性別違和を抱える人はだいたいどのぐらいの比率なのか、皆さんけっこう気になるのではないかと思いますので、その話をしましょう。
もともと欧米では、私のような男性から女性への移行を望むMtFが3万人に1人、逆に女性から男性への移行を望むFTMが10万人、つまり、MtFとFtMの比率は3対1と言われていました。このデータ、実はあまり信用度が高くないのですが、日本で90年代末に性同一性障害の問題が浮上したとき、どうも日本はFTMが少し多いのではないか、MtFが1~2万人に1人、FtMが3万人に1人、MtF対FtMの比率は2対1くらいに考える人が多かったと思います。ところが、どんどんどんどん差が詰まっていきまして、2000年代の初めぐらいには、MtF、FtMを通じてだいたい1~2万人に1人、MtF対FtMは1対1に近い。もうこの時点で、世界の研究者から「日本のデータが変じゃないか?」と言われ始めていました。さらに2008年ぐらいから、中高大学生ぐらいの若いFtMが急増して、MtFとFtMの比率が1対1.5~2と完全に逆転してしまいます。
私の授業では、2008年に放送された「ラストフレンズ」というテレビドラマの中で、ボーイッシュなレズビアンっぽい女性が性同一性障害だと思ってメンタルクリニックに行くシーンを学生に見せて、メディアのミスリードが現実世界に影響しているのではないかという話をするのですが、2008年ぐらいから様子ががらっと変わってきました。その後も女性から男性になりたい若い人の増加傾向がずっと続いていて、現状MtFとFtMの比率は1対3、90年代とは完全に裏返しになっています。人口比で言うと、MtFが1万人に1人か2人。MtFはあまり変わっていません。FtMが1万人に3人くらいという状況です。現状、日本は世界で最も顕著にFtMの比率が高い国になっています。
性別違和が重く性別適合手術をして戸籍の性別変更をした人が、2013年12月末現在で、全国で4353人というデータが出ています。このペースだと2014年末には5000人を超えるのは確実ですので、だいたい2万人に1人が戸籍の性別を変更しているということになります。
10年前に法律ができたときには、こんなに多いとは思いませんでした。年間50人ぐらいだろうと予想していました。年間50人だと10年で500人ですから、10倍ぐらい予想より多いというのが今の状況です。
なぜ、こんなに多いのか、そしてFtMの比率がこんなに高いのか。とても重要な問題なのですが、誰もきちんとした説を出していません。私が頑張って考えているのですが…。要は、全体に増加傾向にあるということと、特にFtMが増えているということを頭に置いておいてください。
それから、2010年代に入ると、あるお医者さんの言い方で「確信的でない受診者」が増えています。以前、メンタルクリニックに来る人は、かなり確信的に「私は、心は女なのに、男性なのです」とか、逆に「俺は絶対男だと思うんだけど、女なんで何とかしてください」というタイプが圧倒的でした。ところが最近は、「自分の性別がよく分からない」とい言う人が増えてきています。これをXジェンダーといいます。数学で不明数をXとするのと同じです。そういう人たちは「自分はXです」と言います。男ではないと思うけれども女でもないMtX。女ではないけれども男でもないFtXというタイプです。これが現実にかなり増えていて、理由を考えなければと思うのですが、まだ調査が進んでいません。私は弱い性別違和までを病理化してしまった結果、本来だったら男女どちらかに折り合いをつけるべきところを折り合いがつけられない人が増えてきているのだろうと思っています。それから女性に多いと思うのですが、いわゆる成熟拒否、大人の女性になりたくない。できるだけ猶予期間を長引かせたいという人も含んでいると思います。
こういう現状で、数値モデルを整理しておきますと、弱い性別違和を持つ人が100人に2~3人、医療が必要な強い性別違和を持つ人がそのうちの100人に1人ぐらい、つまり1万人に2~3人という話になります。さらに戸籍変更に至るまでの人は、そのうちの8~9人で、10万人に5人、2万人に1人。ここはかなり確定的なデータが出ていますので、こんなモデルが作られるわけです。私はどちらかと言うと少なめに見積もっていますが、そんなに違ってはいないと思います。
明治大学の学生数は2万9千人だそうです。このモデルに合わせると、強い性別違和を持つ学生は1万人に2~3人ですから、6~9人ぐらいいて当たり前ということです。1万人に2~3人というのは全人口比ですから、大学在学年齢だともっと多いと思います。何10人ということではありませんが10数人いてもおかしくないということです。何度も申しますが、いて当たり前だという認識がとても大事です。
さらに言うと、まさに10代後半ぐらいの年齢層では、自分の性別がよく分かりませんというXジェンダー的な学生がだいぶ増えているはずです。おそらく「性同一性障害」のカテゴリーに入る学生と同じくらいいるかもしれません、かなり強い性別違和を持つ学生が仮に10人いたとしたら、曖昧な形で何か性別に悩んでいるような学生も、もう10人ぐらいはいるという勘定です。これだけいたらもう珍しい話ではありませんので、そういう学生が相談に来た時の対応マニュアルをきちんと作っておくべきです。ただし、マニュアルは、個々のケースに応じて弾力的に運用することが大事です。
3 大学はどう対応すべきか
では、大学は具体的にどういう対応をしていけばいいのかについてお話しします。ここからは私の主観的な意見になっていくわけですが、実を言うと12年前にお話ししたことと基本は変わっていません。自分でも頑固だなとは思いますが、12年前から言ってきたことが今、現実になっている感じがありますので、少し自信を持っています。
① いて当たり前という基本認識
先ほども申しましたように、ある程度の規模の大学なら強い性別違和感を持つ学生が在籍しているのは確率的に当然で、まったく特異なことではありません。いて当たり前だという基本認識を持ち、いると思って対応すべきなのです。不思議なことでも特異なことでもないということです。
② 基本的には本人の自主性に任せる(放っておく)
異性装、身体の性別とは違う服装をするとか、性別を越えて生きるということ自体は、病でも性的逸脱でもありません。客観的には「変わり者」かもしれませんが、現在の日本では法律で禁止されているわけでもありません。日本で異性装が違法だったのは、明治5~6年から14年(1881)までの約10年間、文明開花期だけです。基本的に、服装表現、性別表現、ジェンダーの選択は個人の自由で、人権として認められるべきものです。つまり、本人の自主性にまかせるべき問題で、そうした学生がいたからといって、大学のほうから積極的に介入する必要はありません。基本的には放っておくべきことなのです。性同一性障害なんていう話が出てくる以前にも、書類上は男子学生だけどずっと女の格好で大学に通っていましたという人は実際にいます。もちろん大学側は気付いていたはずですけど、処分するようなことはできませんし、結局そのまま「あいつは変わっているな」で卒業してしまったという話です。基本的には放っておく、でも、なにか困って相談に来たら、ちゃんと対応するということが大事なところです。
③ 環境整備に努める
性別を移行したい学生にとって一番困るのは、学生名簿の男女欄など、学内における性別記載です。日本の大学、例えば文学部だったら文学士という学位を出します。文学士男とか、文学士女という学位ではないわけで、男だろうが女だろうが……女子大は別ですが、明大は共学なので、いちいち学生名簿に男女欄とか男女の識別記号はいらないはずです。学生証の性別記載欄も同様です。性別で引っ掛かってしまう学生にとっては、引っ掛かる場所がたくさんあるのは辛いものなのです。
これは何も大学だけではなく、世の中がそういう方向に向かわないといけません。たとえば住民票の申請をするのに何でいちいち男女欄に丸を付けなければいけないのか。あるいは選挙で投票するのに、なぜいちいち投票場の入場券に男女と書いてあるのか。そういう問題を私たちトランスジェンダーは、10年以上、いろいろ問題化して社会に働きかけてきました。実際、ずいぶん減っているのです。私が住んでいる川崎市では、投票場の入場券に以前は男・女とはっきり書いてあったのが、記号化されてあまり目立たなくなっています。大学も同じように、環境整備としてそうした必ずしも必要でない性別記載欄を減らしていく方向で行くべきだと思います。
今ちょうどレポートの採点時期で、昨日も履修者名簿を見ていたのですが、明大の名簿には、名前の欄の尻尾のところに、女子学生だけ「F」という記号が付いています。これは必要でしょうか。前もそんなお話をしたら、名前を呼ぶ先生が、男なら何とか君、女なら何とかさんと、敬称を変える必要があるからというお話でした。でも、1回目の授業のときに先生が「この学生は女子」と個人的にチェックしていけばいいわけで、公的な名簿で性別表記をする必要があるのかということです。そもそもなぜ男子と女子で敬称を変えなければいけないのでしょうか。全員「さん」で問題ないでしょう。私が関わっている大学では、都留文科大学と東京経済大学の名簿には、性別を示す記号はありません。こういうことは慣例でずっとやってきたことなので、それに慣れているとなかなか変えにくいのかもしれませんが、本質的によく考えていただきたいと思います。実際に男女の別が必要なのはごくごく限られた、例えば体育実技などだけだと思います。体育実技だって男女一緒のスポーツでやっている場合は、そんなに必要もありませんね。
④ 何が障害になっているのかを聞く
先ほど申しましたように、基本的には放っておくべきなのですが、性別に悩みがある学生が相談に訪れた場合は、何が問題なのかをきちんと聞くことが大切です。この場合、悩みが性自認の問題なのか、あるいは性的指向の問題なのか、分別すること必要です。ただし、相談に来ている学生自身がよく分かっていないことがけっこうありますから、相談を受ける側がそこらへんを整理しながら聞いていくことが必要になります。その学生にとって何が一番の問題なのか。たとえば、自分は男なのに男が好きということで悩んでいるのか、自分は男なのだけど、どうもそれに馴染めない、自分の中身が女のほうにズレているという悩みなのか、ということです。
実は、前に触れた文科省の全国一斉調査は、この部分の指示がないのです。つまり、性に違和感がある、友達と性のあり方が違うという子供が、それは性的指向が違っているのか、それとも自分の性別に対する違和感なのか、小学校段階できちんと分別がつくはずがないのです。中学生だってあやしいです。それを一緒にして、あたかも性同一性障害の予備軍的に見るのは大きな間違いです。人数的には性同一性障害よりも同性愛のほうが圧倒的に多いはずですから。
先日、朝日新聞の教育欄に、大学におけるLGBT――レズビアン、ゲイ、バイ・セクシャル、トランスジェンダーの学生のサークルがすいぶん増えてきたというニュースが載っていました。明大の私の受講生にも、そういうサークルを立ち上げて熱心に活動しているレズビアンの女子学生がいます。各大学を結ぶインターカレッジ的なつながりもできてきているようです。
ゲイ、レズビアンの学生たちは、自分たちで何とかやっていける人も多いのです。それに対して、性別違和を抱える学生は、身体の問題もありますので、悩みを内に抱えてしまう傾向があり、そういう学生が相談に来る可能性が高いと思います。その場合、最初から性同一性障害という病気と決め付けるのではなくて、何に困っているのかから入るべきです。例えばトイレ。性別の問題が引っ掛かる人には、いわゆる「誰でもトイレ」(多目的トイレ)を使うようにアドバイスするのが一般的ですが、私の講師控室があるリバティタワーの3階は、少し進みすぎていて、車椅子でも入れるトイレが男女別に…女子トイレの中にあるのです。そうなると、またややこしい状況が出てくるわけです。トイレの問題は、性別に悩みがある学生には切実な問題なので、大学のどこかに誰でも使えるユニバーサルなトイレが確保されていることが必要です。
⑤ 知識を提供する
性の問題というのは多様ですので、適当な参考書を紹介して知識を提供して、その多様な性の形態の中からもっとも自分にふさわしいジェンダー&セクシュアリティのあり方を自分で選択させることが大事です。具体的には野宮亜紀、針間克己ほか著『性同一性障害って何? ―一人一人の性のありようを大切にするために (プロブレムQ&A)』(緑風書房、2011年増補改訂版)などがよいでしょう。私もジェンダー論の授業の最初と最後に、「この授業が皆さんにとって一番心地よいジェンダー・セクシュアリティのあり方を見つけるための手がかりになればうれしいです」という話をします。これは性的なマイノリティの人たちも全く同じで、自分が何なのだということをきちんと自分なりに理解をしていかないと、自己肯定感が生まれないのです。セクシュアル・マイノリティはゲイ、レズビアンでもトランスジェンダーでもそうなのですが、最終的にはマジョリティーとは違う自分の性のあり方を、私はこうなのだ、私はこれでいいのだと自己肯定できないと、悩みはいつまでも続いてします。私などもある程度の自己肯定はできても、なかなか100パーセントの自己肯定には至りません。その難しい自己肯定の材料をどう与えていくか、サジェスチョンをしていくか、とても大事だと思うのです。
⑥ 必要な場合は専門医を紹介する
自分の体が嫌で嫌で仕方がないというような強い身体違和、FtMだったら生理が来るたびに死にたくなるとか、MtFだったらシャワーを浴びるたびに自分のペニスを切断したくなるようなケース。あるいは、ジェンダー違和が強くて、家から出られない、学校にも行けないような性別違和感に由来する社会的不適応を訴える学生は、放置できません。放置をすると本当に自殺を企ててしまうか、修学が継続できなくなってしまいます。そういうケースでは、性同一性障害の専門医を紹介して、専門的なカウンセリングを受けるように方向付けることが必要です。
この点については、明治大学駿河台校舎は日本一恵まれています。日本における精神科領域の性別違和、性同一性障害問題の第一人者である針間克己先生が2008年に神田小川町3‐24‐1に「はりまメンタルクリニック」を開院したからです。私はリバティホールで授業をやっていますが、リバティホールからだと信号に引っ掛からなければ3分で行ける距離で、本当にすぐそこです。私が明大で初めて講義を持った2012年前期、「あれ?何か社会人学生にしてもばかにひねた大人が後ろのほうで聞いているな」と思ったら針間先生でした。たまたま先生のクリニックは火曜日の午後が休診で、私の講義が火曜日の午後の1コマ目だったので聴講していたのです。東京大学医学部を出た先生が、私なんかの講義を聞いて少しでも勉強しよういう謙虚な姿勢、すばらしいです。ただ、明大の授業をただ聞きしていたわけですから、何かあったときに少し無理を頼んでも嫌とは言えない立場です。専門的なカウンセリングが必要な学生がいたら、ぜひ紹介してください。残念ながら、性同一性障害の診察で、私が自信を持ってご紹介ができるメンタルクリニックは、東京近辺に3つしかありません。他に千葉県浦安市の阿部輝夫先生の「あべメンタルクリニック」、埼玉県さいたま市の塚田攻先生の「彩の国みなみのクリニック」ですが、針間先生のところが一番近いです。
⑦ 学内で可能な限り対応措置をとる
MtFが学内での女性扱い、FtMが男性扱いを希望する場合は、通称名の学内使用をはじめ可能な限り対応措置をとっていただきたいと思います。ただ、なかなかやっかいなのは、希望する性別への適合度です。一目見て、「あなた、どう見たってそれで男子学生は無理でしょう、女子学生の方が自然でしょう」というようなMtF、あるいは「それで女子学生は無理でしょう」というようなFtMの学生だったら大きな問題はないと思います。しかし「う~ん、微妙と」というケースもしばしばあります。そうしたケースは、ある程度、1年くらいの観察期間が必要だと思います。中には精神的に不安定な学生もいて、ガーッとどちらかの性別に偏って、少しすると熱が冷めるというようなケースもあります。あまり性別をコロコロ変えられるのは、大学の事務としては困るでしょうから、基本的には、4年間、卒業までの継続性を前提に、学生が求める措置を取って欲しいと思います。
⑧ 性別移行プロセスへの協力
在学中に戸籍名を望みの性別にふさわしいものに改名したり、戸籍の性別を変更したりする学生、院生が出てくることは、現在の性別移行システムで十分にありうることです。現在のガイドラインでは、クロスホルモン―男性だった人に女性ホルモンを投与、女性だった人に男性ホルモンを投与すること―は、場合によっては16歳から可能です。戸籍の変更要件は20歳以上になっていますが、外国で性別適合手術を受けるだけならその前でも可能です。つまり、入学以前からクロスホルモン投与を受け、在学中に性別適合手術をして、戸籍の性別を変更して、卒業証書は新しい名前と性別でもらって、望みの性別で社会に巣立つという人生計画を立てる学生が出てくるということです。それは現在、認められている性別移行システムに沿ったものなので、そうした性別移行のプロセスに、大学はできるだけ協力をしてあげてください。
⑨ いっそうの就労支援
問題は、戸籍の性別変更がまだ済んでいない学生、あるいは、性別は移行するけども戸籍の性別まで変えるつもりはない学生の場合です。そうした学生の場合、最大の難関は望みの性別での就労です。私もそれでさんざんそれで引っ掛かってきたわけです。日本の大学は非常勤でトランスジェンダーの教員を任用するところまでは来ていますが、常勤ではまず採らないでしょう。それが日本の現実です。ただ、この点に関しては、日本が遅れているわけではなく、外国だと非常勤でもトランスジェンダーは採用しない国はけっこうあります。日本は非常勤ではあるけれど、トランスジェンダーを大学教員に採用していますという話をしたら、外国の研究者に「great、素晴らしい」言われたことがあります。私の場合、年齢的にもう仕方がないなと諦めていますが、若いトランスジェンダーの学生にとっては、やはり就職が最大の難関です。前から言っていることですが、就職課が格別の配慮、一般学生に不平等にならない程度にできるだけのバックアップをしていただきたい。能力が十分にあるトランスジェンダー学生が性別の問題だけで就職ができないということは、その学生だけでなく、社会全体にとっても損失ですし、それは何とか避けたいと思うわけです。
性同一性障害の場合、会社に入ってから性別移行をしたとして、それを理由にした解雇は違法という判例が固まっていますので、入社してからは首を切れません。性同一性障害を理由に解雇して裁判になったらほぼ確実に会社側が負けます。さすがだなと思ったのは、判例が出た頃に企業の総務課や人事課の人たちが読む専門雑誌に、さっそくその判例が紹介されていました。きちんと勉強している企業の労務管理担当者は知っているはずです。ですが、採用段階での就労差別はかなりあります。「戸籍を変更されてからもう一度当社をご受験ください」という形で門前払いするケースです。ですから、学生にしてみると、とりあえ生得的な性別で入社して、入ってから性別を移行するという手もなくはないです。でも、「就職のときは、そのことを隠していたのか」という信義の問題になりかねませんので、なかなか難しいところです。何度も言いますが、就労問題が最大のネックですので、何とかバックアップしていただきたいと思います。
⑩ 望みの性別で生きて行くための社会訓練の場としての大学
実は今、小・中学校では、性別違和を抱える児童、生徒がいると、隔離的、特別に扱って「どこどこの病院へ行って診断書を取って来てください」というように、問題を性同一性障害医療に委ねてしまう形がけっこう多くなっています。大学レベル、ましてや明治大学みたいなトップクラスの大学だったら、そんな安易な方法は採らないと思います。医療の手に委ねてしまうのではなく、大学という一つの社会で性別違和を抱える学生を受け入れていくという姿勢が望まれるわけです。トランスジェンダーの学生が望みの性別での生活を円滑にできるようになるためには、トレーニング期間が必要です。いずれ望みの性別で社会に出て行かなければならない学生にとって、大学の4年間プラスアルファが、トレーニング、社会訓練の場になるわけです。大学はそれをサポートする方向で対応してほしい、そうした姿勢を持って欲しいということです。
私は2002年に「トランスジェンダーと学校教育」という論文を書いているのですが、私が書いた論文の中で一番読まれません。どうしてなのだろうと思うのですが、どうも、現実の学校現場の先生とだいぶ意識が違うようなのです。たとえば、先生方は「男女別に並べるときにどうしたらいいのですか?」と質問してきます。私が「男女別に並べること自体を考え直した方がよろしいのではないですか」と返事をすると、ものすごく不満な顔をされてしまいます。前例が無いケースが出て来た時には、前例に合わせようとするのではなく、従来のシステムを再検討して新例を開くという姿勢が大事だと思います。
おわりに
2014年2月にタイのバンコクでWPATH2014という国際会議が開催されました。WPATHというのはWorld Professional Association for Transgender Health、トランスジェンダーの健康のための世界専門家会議という団体です。今回が第23回でしたが、今までずっと欧米で開催されていて、今回が初めてのアジア開催でした。そこでアジア・太平洋地域のトランスジェンダーをできるだけ集めて「Trans People in Asia and Pacific」というシンポジウムをやろうということになりました。とはいえ、これがなかなか大変で、トランスジェンダーは、お金持ちではない人がほとんどなので、飛行機代、滞在費を世界開発機構、世界エイズ会議など国際連合の4機関が資金提供して、アジア・パシフィック10カ国、最終的は日本も入って11カ国のトランスジェンダーがバンコクに集まりました。私も招待状をもらったのですが、日本はOECD加盟国で、世界開発機構ではお金を出す立場でお金をもらう立場ではない、だから日本の研究者には資金提供はできないから旅費と滞在費は自分持ちで来てくれ、というという話で、「それはあんまりな・・・」と思いました。お金のことはともかく、世界のどの国にも、トランスジェンダーはいるということです。いろいろ困難な状況はあるけれども、それぞれの国でそれぞれの社会の中で頑張って生きているわけです。
そうしたシンポジウムで、とても考えさせられたことがありました。全部で12人が各国の事情を報告したのですが、12人のうち11人がMtFなのです。私以外のMtFは、フィリピン、インドネシア、タイ、ネパール、インド、そしてトンガ、みんな英語がペラペラで、パワーポイントできちんと資料を作ってきて、しっかりプレゼンテーションをできる能力があります。ところが、FtMの人はそうしたプレゼンテーションができないのです。12人中1人だけ、しかもニュージーランドの活動家でしたから、少し事情が違います。
どういうことかと言いますと、アジアの国で、女性として生まれて女性としての教育を受けてきた人は、開発途上国における男女の教育格差を被ってしまうのです。女で育てられると、なかなか十分な教育が受けられない。それで男になっても、一定の知的レベルが求められる社会的活動がなかなか難しいのです。
この例のように、性別を変えて生きる人たちにとって、大事なのは教育なのです。社会に出て一般の人よりももっと厳しい状況の中で生き抜いていくための力になるのは教育です。教育をきちんと受けられるかどうかが鍵なのです。実は、日本もそういう傾向があって、日本で今FtMがこんなに多くなっているのに、日本から参加して報告したメンバーは2人ともMtFでした。残念ながら、国際学会で通用するレベルのプレゼンテーションができるFtMは、日本ではほとんどいません。なぜかというと、FtMの最終学歴は、MtFに比べて明らかに低く、高校中退レベルの人がかなりいます。そうした状況は徐々に改善されてきていますが、制服とかいろいろなことで引っ掛かってしまって修学が継続できず、その結果、低学歴で終わってしまって、学力やスキルが伴わないFtMがまだかなりいるのです。
社会の中でより良く生きていくための力を大学教育の中で身に着ける必要性は、一般学生でもトランスジェンダーの学生でもまったく変わりません。むしろトランスジェンダーであるがゆえにその必要性は高いのです。そのためには、何度も言うように修学が継続できる……きちんと卒業ができて、できることなら望む方面に就職ができるようなバックアップを、明治大学だけではなく全国の大学でぜひとっていただきたいと思います。
だいたい予定の時間になりました。3年前、明大に非常勤で呼んでいただいた時から、いつか講義以外でもお役に立てる機会があればと思っていましたので、今日はこういう機会をいただいて、とてもうれしかったです。どうもありがとうございました。
(紙幅の都合により、講師紹介及び質疑応答は割愛させていただきました。)
【参考文献】
三橋順子「『性』を考える-トランスジェンダーの視点から-」
(シリーズ 女性と心理 第2巻『セクシュアリティをめぐって』 新水社 1998年)
三橋順子「トランスジェンダーと学校教育」
(『アソシエ』8号 御茶の水書房 2002年)
三橋順子「トランスジェンダーをめぐる疎外・差異化・差別」
(シリーズ「現代の差別と排除」第6巻『セクシュアリティ』明石書店 2010年)



