【インタビュー】「わたしの光になった表現」(聞き手:外山雄太) [論文・講演アーカイブ]
集英社の文芸誌『すばる』2016年8月号は「特集・LGBT-海の向こうから-」。

虹色の表紙が目印。
インタビュー記事「わたしの光になった表現」(聞き手:外山雄太)は、牧村朝子・杉山文野・中村キヨ・マーガレット・田亀源五郎・橋口亮輔という豪華なメンバーが「人生の大切な局面をともにした三つの作品」を語る。
その他、海外のLGBT関係の評論・エッセイ8本を掲載。
東京の主要書店では、7月6日発売(税込950円)。
インタビューは、5月31日(火)。
明治大学(駿河台)での講義の後、17時少し前、神田神保町三丁目の「集英社」へ。
インタビュアーは外山雄太さん。
昨年3月、『朝日新聞』の原田朱美記者の紹介で知り合った方。
ご縁が形になってうれしい。
最初に撮影。
簡単な撮影かと思ったら、ちゃんとプロのカメラマンが待機していて、まず室内で、さらに、屋外に出て撮影。
着物、着てきてよかった。

↑ 撮影:隼田大輔氏
その後、2時間半ほど、「わたしの光となった表現」というテーマであれこれしゃべる。
まず、1980年代までに青年期を過ごした私の世代は、そもそも世の中に性別越境についての情報が乏しく、それを見つける(実際には、偶然、出会う)ことがたいへんだったことを話す。
「性別違和」という自分の状況を説明する言葉も、「性同一性障害」という概念も日本には入っていなかった。
そんな状況の中で「自分を見つける」導きになった書籍として、
(1)存在への気づき、(2)「成りたい」自己イメージの形成、(3)自己肯定化の理論、という観点で3冊を挙げた。
----------------------------
今回、豪華なメンバーの驥尾に付して出していただいたが、いろいろな意味で、トランスジェンダーとしての私の社会的な役割は終わったのかなと思う、今日この頃。
たくさんの方に「まだまだ」と言っていただけるのは励みにはなるけど、もう表舞台に出るのは心身ともに辛くなってきた。
あと何年生きられるかわからないが、残りの人生は研究生活、とりわけ、自分の著述のまとめに専念しようと思う。
『すばる』は創刊(1970年)から数年間、高校生の頃に購読していた思い出のある雑誌で、そこに出られたのは、そういう意味で良い記念になった。
-----------------------------------------------------
わたしの光となった表現
「あなたはどのような表現に影響を受け、また、支えられてきましたか?」
セクシュアリティー/世代/職業の異なる七名に、
人生の大切な局面をともにした三つの作品との出会いと、
その魅力についてうかがった。
探すものではなく、出会うもの
三橋順子
「二〇〇〇年、初めて大学の教壇に立った最初の講義の日、忘れもしません。週刊誌が三誌も取材に来たんです。日本で最初の、トランスジェンダーの大学教員。いったいそれ何? というまったく興味本位な反応でした」
三橋順子さんは、日本における性別越境、トランスジェンダーの社会・文化史研究家だ。歴史学的な手法で調査対象に取り組み、トランスジェンダーおよびセクシャルマイノリティーの歴史を探求してきた。
「自分が〝ふつう〟の男子と違うかも? と気づいたのは遅かったです。高校生のころ、おぼろげにそうかもしれない……と思ったくらいで、それ以前はとくになにも感じていませんでした。少なくとも、自分としては気づていないことになってました。のちのち専門の精神科医の先生にカウンセリングしてもらうと、どうも〝ふつう〟でない、記憶に蓋をしていたエピソードがたくさん出てきましたが。
自分のなかに別の人格がいて、それが女性だったと気づいたのは二十一歳のころ。性同一性障害とか、性別違和とか、そういう概念がない時代です。すてきな女性に対して、『付き合いたい』よりも、『ああいうふうになりたい』という気持ちを抱きました。
そんな自分が不可解で、図書館で精神分析学の本を読んだけど、答えは見つかりません。二十代後半が、自分がなぜこうなのか、よく分からず、つらかった時期でした。
そんな田舎から東京に出てきた青年が、いちばん最初に共鳴したのが『別冊SMスナイパー』一九八〇年十一月号に掲載されていた館淳一さんの「ナイロンの罠」という小説。一九八三年に単行本が刊行されますが、雑誌掲載時に読んで、これだ……! と思いました。自分の姉と義兄の手によって女性化されていく男子予備校生のお話。 女装の道に引き摺りこまれる美少年に自分を重ねたんですね。この作品は、二十五歳だったわたしのセクシュアル・ファンタジーの形成に多大な影響を与えました。三十数年後、著者の館淳一さんにお会いしたときは、大感激でした。

↑ 館 淳一『ナイロンの罠』(ミリオン出版 1983年)

↑ 初出の『別冊SMスナイパー』1980年11月号。
ほぼ時期を同じくして存在を知ったのが、土田ヒロミ撮影『青い花――東京ドール――』(世文社、一九八一年)でした。これは、一九七〇年代の東京のゲイボーイを主題にした写真集です。ゲイボーイというのは、当時は女装した男性のことを指しました。いまのゲイということばと、、八〇年代までのゲイとでは意味のズレがあるんです。
トランスジェンダー的な人物をテーマに撮影した日本初の写真集の存在は、スポーツ新聞で見て知っていましたが、当時二八〇〇円もする本なんて手が出ませんでした。あるとき、たまたま立ち寄った神保町の古本屋さんでめぐり会ったんです。店の前側には真面目な古本が、奥にSMやポルノ雑誌が置かれているような、お堅い本でエロをカムフラージュした本屋さんでした。そこで、『青い花』をやっと手に入れました。当時は、今のように情報が流通していませんから、こういった本は、探してもなかなか見つかるものではありません。存在が隠されているから探しようがなく、偶然出会うものだったんです。
写真集を見て、それまでぼんやりとしたイメージでしかなかった〝女装〟というものが、明確に可視化されました。「東京のどこかに、こうやって美しく着飾ったゲイボーイがいるんだ!」という強い実感。見えること、視覚的にイメージ化できることはそれだけ重要なんです。被写体になっていた〝お姉さん〟たちは、たぶん、赤坂、六本木あたりでお勤めの方々だったと思います。記載がないから、確かではないけれど。でも、自分と似たような感じの人がこれだけいるということを知って、なりたいわたしのイメージはより強固なものになっていきました」
.jpg)
-a7dc7.jpg)
↑ 土田ヒロミ撮影『青い花ー東京ドールー』(世文社 1981年)
しかし、そんなイメージを頼りに女装をし始めた八〇年代の終わりごろ、また別の問題が浮上したのだという。
「自己イメージは定まってきたけれど、それを言語化することがなかなかできませんでした。そんなときに出会ったのが、渡辺恒夫先生の『脱男性の時代――アンドロジナスを目指す文明学――』(勁草書房、一九八六年)でした。女装、性転換、アンドロジナス(両性具有)の世界を探求した評論集で、 女装者としての私の形成に際して、理論的な面で大きな影響を受けました。
評論として高く評価された『脱男性の時代』以外にも、二冊ほど同じような内容の本を書かれていて、『精神科治療か服装革命か』なんて、いまにも通じる問いを投じられました。〝トランスジェンダー〟というワードを書名にした日本最初の本の著者は、渡辺先生なんです(『トランス・ジェンダーの文化―異世界へ越境する知―』勁草書房、一九八九年)。
でも、その後はトランスジェンダーについては事実上、筆を折っちゃったんです。詳しい事情はよくわかりませんが、「おかしな研究をしている」というような社会的な圧力があったのではないでしょうか。いずれにせよ、日本にトランスジェンダリズムの原点をつくった重要な研究者であることは間違いありません」
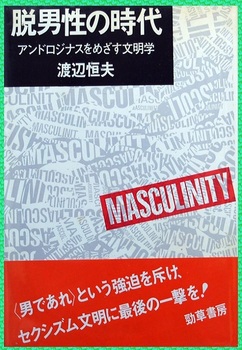
↑ 渡辺恒夫『脱男性の時代ーアンドロジナスを目指す文明学ー』(勁草書房 1986年)
九〇年代に入り、一九七九年創業の女装メイクルーム&サロン「エリザベス会館」に所属、自己流の女装から、本格的な技術を学んで女装をするようになった。のちに新宿歌舞伎町の女装スナック「ジュネ」でホステスとして働きはじめる。現在につながる〝研究〟を本格的に始められたきっかけは、何だったんだろう。
「九六、七年くらいに、〝性同一性障害〟ということばが一気に広まりました。「性同一性障害のあとに、トランスジェンダーということばが入ってきた」と言う人もいるけど、それは事実誤認です。トランスジェンダーが先にあって、その概念こそが性別を越えて生きようというわたしたちの自己肯定の出発点になっていたんです。
〝性同一性障害〟という概念の登場によって、新宿の女装世界はものすごく影響を受けました。分かりやすく言うと、いままでお店のドアを叩いていた女の子になりたい願望を持つ子たちが、みんな病院に行くようになってしまったんです。性別を越えて生きたいと思うのは障害であり、治療すべき病気だという考えが広まるにつれて、ずいぶんお客さんが減りました。
ある常連さんからは、「おまえたちが病気ってことは、俺は病気の人間と、病気をネタに酒を飲んでいるのか? そんなことする俺って人でなしじゃないか」と言われて。「そうじゃないのよ。楽しく飲めばいいじゃない」となだめても、一度落ちた気分は直りません。
そんななか、ママや古いお客さんからお店の昔話を聞くのが好きだったわたしに、先輩ホステスがこんなふうに言いました。
「わたしたちが作ってきた女装世界は、近い将来になくなっちゃうかもしれない。こんな世界があったことを、記録して残すことが、歴史学を勉強した順ちゃんの役目よ」
それ以来、研究者というよりは当事者として、調べて記録しなくてはならないという強い意識を持つようになりました。「ジュネ」という店の歴史、それを中核とした新宿の女装世界の成り立ちを遡って調べていきました。そんな調査をより社会史的な研究にしていこうと思い始めた時期に、中央大学の矢島正見先生(社会学)から声をかけられて、一九九九年に「戦後日本〈トランスジェンダー〉社会史研究会」を立ち上げ、歴史学と社会学の二つの手法で研究をしていくことになりました」
二〇〇〇年代初頭から、「性別を越えて生きることは病ではない」と一貫して性別越境の病理化を批判しつづけ、性同一性障害という病理概念に絡めとられることを拒否してきた三橋さん。ようやく時代の流れが変わりつつあるようだ。
「来年か、再来年かに実施されるWHOの国際疾病分類(ICD)の改訂にともなって、性別越境が精神疾患でなくなる見通しなんです。性同一性障害という病名も国際的には消えることになります。同性愛の脱病理化に遅れること二十七、八年、自分が唱えてきたことが実現することへ期待と喜びはもちろんあります。
「研究ができる女装者がいたんだ!」と驚かれたり、「病気と認められて良かったですね」と善意の人に言われた時代もありました。当時とくらべれば、ずいぶんトランスジェンダーが生きやすい世の中になったと思います。でも、まだまだ調べて記録しなければならないことはたくさんあります」
着物の襟を正しながら、まっすぐ前を見据える三橋さん。
「トランスジェンダー研究をきちんと引き継いでくれるひとが現われるまで、わたしもがんばりますよ」
虹色の表紙が目印。
インタビュー記事「わたしの光になった表現」(聞き手:外山雄太)は、牧村朝子・杉山文野・中村キヨ・マーガレット・田亀源五郎・橋口亮輔という豪華なメンバーが「人生の大切な局面をともにした三つの作品」を語る。
その他、海外のLGBT関係の評論・エッセイ8本を掲載。
東京の主要書店では、7月6日発売(税込950円)。
インタビューは、5月31日(火)。
明治大学(駿河台)での講義の後、17時少し前、神田神保町三丁目の「集英社」へ。
インタビュアーは外山雄太さん。
昨年3月、『朝日新聞』の原田朱美記者の紹介で知り合った方。
ご縁が形になってうれしい。
最初に撮影。
簡単な撮影かと思ったら、ちゃんとプロのカメラマンが待機していて、まず室内で、さらに、屋外に出て撮影。
着物、着てきてよかった。
↑ 撮影:隼田大輔氏
その後、2時間半ほど、「わたしの光となった表現」というテーマであれこれしゃべる。
まず、1980年代までに青年期を過ごした私の世代は、そもそも世の中に性別越境についての情報が乏しく、それを見つける(実際には、偶然、出会う)ことがたいへんだったことを話す。
「性別違和」という自分の状況を説明する言葉も、「性同一性障害」という概念も日本には入っていなかった。
そんな状況の中で「自分を見つける」導きになった書籍として、
(1)存在への気づき、(2)「成りたい」自己イメージの形成、(3)自己肯定化の理論、という観点で3冊を挙げた。
----------------------------
今回、豪華なメンバーの驥尾に付して出していただいたが、いろいろな意味で、トランスジェンダーとしての私の社会的な役割は終わったのかなと思う、今日この頃。
たくさんの方に「まだまだ」と言っていただけるのは励みにはなるけど、もう表舞台に出るのは心身ともに辛くなってきた。
あと何年生きられるかわからないが、残りの人生は研究生活、とりわけ、自分の著述のまとめに専念しようと思う。
『すばる』は創刊(1970年)から数年間、高校生の頃に購読していた思い出のある雑誌で、そこに出られたのは、そういう意味で良い記念になった。
-----------------------------------------------------
わたしの光となった表現
「あなたはどのような表現に影響を受け、また、支えられてきましたか?」
セクシュアリティー/世代/職業の異なる七名に、
人生の大切な局面をともにした三つの作品との出会いと、
その魅力についてうかがった。
探すものではなく、出会うもの
三橋順子
「二〇〇〇年、初めて大学の教壇に立った最初の講義の日、忘れもしません。週刊誌が三誌も取材に来たんです。日本で最初の、トランスジェンダーの大学教員。いったいそれ何? というまったく興味本位な反応でした」
三橋順子さんは、日本における性別越境、トランスジェンダーの社会・文化史研究家だ。歴史学的な手法で調査対象に取り組み、トランスジェンダーおよびセクシャルマイノリティーの歴史を探求してきた。
「自分が〝ふつう〟の男子と違うかも? と気づいたのは遅かったです。高校生のころ、おぼろげにそうかもしれない……と思ったくらいで、それ以前はとくになにも感じていませんでした。少なくとも、自分としては気づていないことになってました。のちのち専門の精神科医の先生にカウンセリングしてもらうと、どうも〝ふつう〟でない、記憶に蓋をしていたエピソードがたくさん出てきましたが。
自分のなかに別の人格がいて、それが女性だったと気づいたのは二十一歳のころ。性同一性障害とか、性別違和とか、そういう概念がない時代です。すてきな女性に対して、『付き合いたい』よりも、『ああいうふうになりたい』という気持ちを抱きました。
そんな自分が不可解で、図書館で精神分析学の本を読んだけど、答えは見つかりません。二十代後半が、自分がなぜこうなのか、よく分からず、つらかった時期でした。
そんな田舎から東京に出てきた青年が、いちばん最初に共鳴したのが『別冊SMスナイパー』一九八〇年十一月号に掲載されていた館淳一さんの「ナイロンの罠」という小説。一九八三年に単行本が刊行されますが、雑誌掲載時に読んで、これだ……! と思いました。自分の姉と義兄の手によって女性化されていく男子予備校生のお話。 女装の道に引き摺りこまれる美少年に自分を重ねたんですね。この作品は、二十五歳だったわたしのセクシュアル・ファンタジーの形成に多大な影響を与えました。三十数年後、著者の館淳一さんにお会いしたときは、大感激でした。

↑ 館 淳一『ナイロンの罠』(ミリオン出版 1983年)

↑ 初出の『別冊SMスナイパー』1980年11月号。
ほぼ時期を同じくして存在を知ったのが、土田ヒロミ撮影『青い花――東京ドール――』(世文社、一九八一年)でした。これは、一九七〇年代の東京のゲイボーイを主題にした写真集です。ゲイボーイというのは、当時は女装した男性のことを指しました。いまのゲイということばと、、八〇年代までのゲイとでは意味のズレがあるんです。
トランスジェンダー的な人物をテーマに撮影した日本初の写真集の存在は、スポーツ新聞で見て知っていましたが、当時二八〇〇円もする本なんて手が出ませんでした。あるとき、たまたま立ち寄った神保町の古本屋さんでめぐり会ったんです。店の前側には真面目な古本が、奥にSMやポルノ雑誌が置かれているような、お堅い本でエロをカムフラージュした本屋さんでした。そこで、『青い花』をやっと手に入れました。当時は、今のように情報が流通していませんから、こういった本は、探してもなかなか見つかるものではありません。存在が隠されているから探しようがなく、偶然出会うものだったんです。
写真集を見て、それまでぼんやりとしたイメージでしかなかった〝女装〟というものが、明確に可視化されました。「東京のどこかに、こうやって美しく着飾ったゲイボーイがいるんだ!」という強い実感。見えること、視覚的にイメージ化できることはそれだけ重要なんです。被写体になっていた〝お姉さん〟たちは、たぶん、赤坂、六本木あたりでお勤めの方々だったと思います。記載がないから、確かではないけれど。でも、自分と似たような感じの人がこれだけいるということを知って、なりたいわたしのイメージはより強固なものになっていきました」
.jpg)
-a7dc7.jpg)
↑ 土田ヒロミ撮影『青い花ー東京ドールー』(世文社 1981年)
しかし、そんなイメージを頼りに女装をし始めた八〇年代の終わりごろ、また別の問題が浮上したのだという。
「自己イメージは定まってきたけれど、それを言語化することがなかなかできませんでした。そんなときに出会ったのが、渡辺恒夫先生の『脱男性の時代――アンドロジナスを目指す文明学――』(勁草書房、一九八六年)でした。女装、性転換、アンドロジナス(両性具有)の世界を探求した評論集で、 女装者としての私の形成に際して、理論的な面で大きな影響を受けました。
評論として高く評価された『脱男性の時代』以外にも、二冊ほど同じような内容の本を書かれていて、『精神科治療か服装革命か』なんて、いまにも通じる問いを投じられました。〝トランスジェンダー〟というワードを書名にした日本最初の本の著者は、渡辺先生なんです(『トランス・ジェンダーの文化―異世界へ越境する知―』勁草書房、一九八九年)。
でも、その後はトランスジェンダーについては事実上、筆を折っちゃったんです。詳しい事情はよくわかりませんが、「おかしな研究をしている」というような社会的な圧力があったのではないでしょうか。いずれにせよ、日本にトランスジェンダリズムの原点をつくった重要な研究者であることは間違いありません」
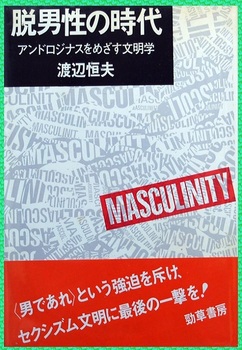
↑ 渡辺恒夫『脱男性の時代ーアンドロジナスを目指す文明学ー』(勁草書房 1986年)
九〇年代に入り、一九七九年創業の女装メイクルーム&サロン「エリザベス会館」に所属、自己流の女装から、本格的な技術を学んで女装をするようになった。のちに新宿歌舞伎町の女装スナック「ジュネ」でホステスとして働きはじめる。現在につながる〝研究〟を本格的に始められたきっかけは、何だったんだろう。
「九六、七年くらいに、〝性同一性障害〟ということばが一気に広まりました。「性同一性障害のあとに、トランスジェンダーということばが入ってきた」と言う人もいるけど、それは事実誤認です。トランスジェンダーが先にあって、その概念こそが性別を越えて生きようというわたしたちの自己肯定の出発点になっていたんです。
〝性同一性障害〟という概念の登場によって、新宿の女装世界はものすごく影響を受けました。分かりやすく言うと、いままでお店のドアを叩いていた女の子になりたい願望を持つ子たちが、みんな病院に行くようになってしまったんです。性別を越えて生きたいと思うのは障害であり、治療すべき病気だという考えが広まるにつれて、ずいぶんお客さんが減りました。
ある常連さんからは、「おまえたちが病気ってことは、俺は病気の人間と、病気をネタに酒を飲んでいるのか? そんなことする俺って人でなしじゃないか」と言われて。「そうじゃないのよ。楽しく飲めばいいじゃない」となだめても、一度落ちた気分は直りません。
そんななか、ママや古いお客さんからお店の昔話を聞くのが好きだったわたしに、先輩ホステスがこんなふうに言いました。
「わたしたちが作ってきた女装世界は、近い将来になくなっちゃうかもしれない。こんな世界があったことを、記録して残すことが、歴史学を勉強した順ちゃんの役目よ」
それ以来、研究者というよりは当事者として、調べて記録しなくてはならないという強い意識を持つようになりました。「ジュネ」という店の歴史、それを中核とした新宿の女装世界の成り立ちを遡って調べていきました。そんな調査をより社会史的な研究にしていこうと思い始めた時期に、中央大学の矢島正見先生(社会学)から声をかけられて、一九九九年に「戦後日本〈トランスジェンダー〉社会史研究会」を立ち上げ、歴史学と社会学の二つの手法で研究をしていくことになりました」
二〇〇〇年代初頭から、「性別を越えて生きることは病ではない」と一貫して性別越境の病理化を批判しつづけ、性同一性障害という病理概念に絡めとられることを拒否してきた三橋さん。ようやく時代の流れが変わりつつあるようだ。
「来年か、再来年かに実施されるWHOの国際疾病分類(ICD)の改訂にともなって、性別越境が精神疾患でなくなる見通しなんです。性同一性障害という病名も国際的には消えることになります。同性愛の脱病理化に遅れること二十七、八年、自分が唱えてきたことが実現することへ期待と喜びはもちろんあります。
「研究ができる女装者がいたんだ!」と驚かれたり、「病気と認められて良かったですね」と善意の人に言われた時代もありました。当時とくらべれば、ずいぶんトランスジェンダーが生きやすい世の中になったと思います。でも、まだまだ調べて記録しなければならないことはたくさんあります」
着物の襟を正しながら、まっすぐ前を見据える三橋さん。
「トランスジェンダー研究をきちんと引き継いでくれるひとが現われるまで、わたしもがんばりますよ」
【論文】「日本におけるレズビアンの隠蔽とその影響」 [論文・講演アーカイブ]
2016年3月末に刊行された「早稲田大学ジェンダー研究所」の創立15周年記念論集
小林 富久子・村田 晶子・弓削 尚子編
『ジェンダー研究/教育の深化のために― 早稲田からの発信』

彩流社、2016年3月、474頁、定価4300円+税
ISBN-13: 978-4779121968
これからの「ジェンダー研究/教育」に向けて、文学、表象・メディア、歴史、法・社会などの専門領域の「ジェンダー研究の展開」と、教育実践をもとにした「ジェンダー教育のあり方」の二本立てで、計24編の論考を収録している。
私は、論文「日本におけるレズビアンの隠蔽とその影響」を執筆。
日本における女性同士の性愛の歴史をトピック的にたどり、その隠蔽の在り様を明らかにした上で、その現代における影響、具体的には「なぜ日本では女性から男性への性別移行者(Female to Male=FtM)が(国際比較で)突出的に多いのか?」を考えてみた。
論集では割愛した、図版を加えた。
-------------------------------------------------------------------------
日本におけるレズビアンの隠蔽とその影響
三橋順子(性社会・文化史研究者)
はじめに
「日本にもレズビアンがいると知って驚きました。テレビなどに出てこないのでいないものだと思っていました」
「今までレズビアンは性同一性障害の一種だと思っていましたが、今日の講義でレズビアンと性同一性障害は違うものだとわかりました」
いずれも、私の「ジェンダー論」の受講生のコメント票の記述である。読んで私は愕然とした。レズビアンへの認識不足は実感していたが、まさかこれほどとは……。しかし、学生の無知と笑って済ますことはできない。前者は教員養成で長い実績がある公立大学、後者は日本有数の私立大学の学生だ。つまり、レズビアンへの同様の認識不足は若者たち、いや世間に広く存在することを示しているからだ。
現代日本におけるレズビアン(Lesbian 女性同性愛)への認識と理解は、トランスジェンダー(Transgender性別越境者)の病理化概念である性同一性障害(Gender Identity Disorder=GID)や、同じ同性愛であるゲイ(Gay 男性同性愛)と比べて格段に低い。
その原因としては、学生が「テレビなどに出てこないので」と言っているように、一般の人が目にするところにレズビアンが存在しない(ように見える)ことが大きい。もちろん、現実には日本社会にはたくさんのレズビアンが生活している。その数は男性同性愛者とそれほど大きくは変わらないだろうし、性同一性障害の人よりずっと(おそらく2桁)多いはずだ。概数的に言えば、100人に2~3人いてもおかしくない。なのに、なぜ、目に見えないのか? それは隠されているからにほかならない。
日本におけるレズビアン差別については、杉浦郁子「レズビアンの欲望/主体/排除を不可視にする社会について―現代日本におけるレズビアン差別の特徴と現状―」(杉浦2010b)という優れた研究がある。男性ホモソーシャル体制を堅持するために、ホモフォビアを伴う異性愛主義を浸透させた、「女同士の絆」が未分化で曖昧なものとして構築されている現代日本社会の中で「男を望まない欲望」「男に望まれたくない欲望」を表出することは困難であり、それがレズビアンの不可視化、差別を招いているという杉浦の社会構造的な分析にほとんど異論はない。
しかし、杉浦はレズビアンが隠蔽されてきた個々の事例についてはあまり触れていない。そこで本稿では、不十分ながらレズビアンが隠蔽されてきた歴史をトピック的にたどり、それが現代日本社会にどんな影響を与えているかを考えてみたい。
1 レズビアンの前史 ―先行概念がない―
実態として、平安時代の後宮、江戸時代の将軍家大奥や大名家の奥向き、遊廓の妓楼など、女性が多く集まり暮らす場で、女性同士の性愛はあったと思われる。しかし、文献的に明確な例としては、『我身にたどる姫君』(鎌倉時代中期、1259~1278年頃)第6巻の主人公「前斎宮」(嵯峨院上皇の娘)が周囲の女性たちと次々に関係をもつ話があるくらいで数少ない。あるいは、江戸時代の性具の中に「互形(たがいがた)」と呼ばれた双頭の張形が残っていること(田中2004)や、同時期の春画の中に僅かながら女性同士の性愛を描いたものがあることなどからうかがえるに過ぎない。
このように女性同士の性愛を示す資料は、男と女の関係はもちろん、男と男(正確には男と若衆)の関係に比べても圧倒的に少ない。そもそも、女性同士の性愛を示す概念、言葉がなかった。「互形」を用いた女性同士の擬似性交を「互先(たがいせん)」と言い(田中2004)、女性同士の性愛を示す「貝合せ」とか「合淫(ともぐい)」という言葉があった(白倉2002)。あるいは、「といちはいち(ト一ハ一?)」という語源不詳(「上」「下」の意か?)の言い方もあった。これらは、いずれも卑語、隠語の類であり、世間に広く通用した言葉ではなかった。
これは江戸時代の「色」の概念が、男性から遊女に向かうものを「女色」、男性から若衆に向かうものを「男色」と言い、「色」の発信は常に男性が主体であるとされていたことによる(三橋2013)。つまり、女性が発信主体となることは想定されていないので、女と女の関係は概念として存在しないのだ。さらに、当時の著述・出版事業が圧倒的に男性支配下にあり、女性が自らの性愛を記録し刊行することが困難な事情もあった。
ところで、同性の間の性愛、あるいは性的指向(sexual orientation)が同性に向いていることを意味するhomosexualityという概念は、明治時代の末、1910年頃にドイツの精神医学者リヒャルト・フォン・クラフト=エビングの学説が日本に輸入され、「同性的情慾」「顚倒的同性間性慾」などの訳語で、精神疾患である「変態性慾」のひとつとして概念化された(古川1994)。日本において最初に「女性間の顚倒性慾」が「発見」されたのもこの時期だった(肥留間2003)。その後、訳語は「同性愛」に定着するが、同性愛という言葉が新聞・雑誌などで使用され、倒錯的な性愛として一般に広く知られるようになるのは、1920年代、大正末期から昭和初期のことである。
同性愛概念が導入される以前(明治時代以前)の日本では、同性愛という概念は存在しない。男性同士の性愛は「男色」として概念化されていたが、それは成人した男性と元服前の少年、あるいは年長の少年と年少の少年との関係に限定されていて、成人男性同士の性愛を含む「男性同性愛」とはかなり異なる(三橋2015a、2015b)。とはいえ、それでも類似の先行概念があるだけ男性同性愛という概念を受容しやすかっただろう。
これに対して、女性同士の性愛は、同性愛概念が導入される以前には概念化されていなかった。つまり、女性同性愛は類似の先行概念がなく、(前近代)「男色」→(近代)「男性同性愛」のような概念の継承、読み替えが成り立たず、大正~昭和初期にいきなり世の中に出てくることになる。
このことが、日本近代における女性同性愛の受容に大きく影響しているように思う。大衆は、よくわからないものには警戒的になる。女性同性愛が男性同性愛よりもさらに社会的に警戒されたのは、基本的には男尊女卑の社会構造が大きいが、先行概念の欠落にも理由があったのではないだろうか。
2 「富美子・エリ子事件」―「同性心中」と女性同性愛の危険視―
日本で女性同性愛が注目されたきっかけは、1911年(明治44)7月に新潟で起こった「令嬢風の二美人」の入水心中事件だった。東京の第二高等女学校(都立竹早高校の前身)の同級生だった二人は在学中から「非常の仲よし」だったが、卒業後は交際を控えるよう父親から注意されたのを悲観しての自殺だった。この事件に注目して日本最初の女性同性愛に関する論文、桑谷定逸「戦慄す可き女性間の顚倒性慾」が書かれる(桑谷1911)。日本における女性同性愛は最初から「戦慄すべき」ものだったのだ。
これ以降、昭和戦前期の新聞で、女性同士の「同性心中」がしばしば新聞報道されるようになり、女性同性愛のイメージを「危険」なものにしていった。「同性心中」なのだから男性同士の心中(自殺)もあるはずだが、実際に報道されたもののほとんどは女性同士の心中だった。また、女性同士の自殺だからといって、その二人が同性愛関係だったとは限らないのだが、イメージとして同性心中と女性同性愛が結び付けられ、ことさらに危険視されたことは間違いない。「同性心中」への注目と問題視は戦後期まで継続し、「危険な女性同性愛」のイメージを再生産していくことになる(小峰・南1985)。
ところで、日本で女学校が開設され、女学生が増えるとともに、女学生同士の親密な関係が社会的に浮上してくる。こうした一種の疑似恋愛関係は「エス」(Sisterの頭文字)と呼ばれ、1920年代には女学校文化として定着するようになった(赤枝2011)。それを危険視する見解がある一方で、親にしてみれば女学生の娘が男性と恋愛関係におちいるより、女学生同士の疑似恋愛に没頭している方が安全であり、「エス」の関係は卒業とともに終え、男性と結婚し良妻賢母になってくれればそれでいいという容認的な考えもあったようだ。
もちろん、親の思惑通りに行かない場合もあり、先の新潟の入水心中事件はその典型である。「エス」と女性同性愛の間に明確な線引きができるわけではないにもかかわらず、女学生同士の親密な関係である「エス」は許容され、女性同性愛は危険視されるというダブルスタンダードが生じていく。
一方、1933年(昭和8)に清朝皇室の粛親王善耆の第十四王女である川島芳子(愛新覺羅顯玗)をモデルにした小説、村松梢風『男装の麗人』が出版されたことをきっかけに「男装の麗人」ブームが起こる。その中心は、川島芳子と松竹歌劇団の男役スター「ターキー」こと水の江瀧子だった。当時の新聞は、川島とターキーの動静をしばしば伝えている。


(左)水の江瀧子(右)川島芳子
そんな時代を背景に、1935年(昭和10)1月末、「富美子・エリ子事件」が起こる。増田富美子は大阪の銀行頭取の令嬢ながら増田夷希(やすまれ)と名乗る「男装の麗人」で当時28歳、その恋人西條エリ子は「松竹少女歌劇」の女役トップスターだった人気映画女優で当時23歳。その二人の「女性同士の愛の逃避行」が新聞で大きく報道された。二人は「愛の逃避行」の末に1月28日夜、東京麹町区平河町の「万平ホテル」に同宿する。その夜、富美子はエリ子への遺書を残して睡眠薬自殺をはかり昏睡状態になってしまう。
.jpg)
↑ 増田夷希(やすまれ)と名乗った増田登美子(『読売新聞』1935年1月30日)
まるで犯罪者のように富美子たちの動向を追跡していた『読売新聞』は「『男装の麗人』富美子さん 萬平ホテルで服毒す 西條エリ子と共に投宿 遂に『死』への逃避行」という大見出しのもとに、男姿の富美子の写真と「本当いへば一緒に死んでほしかった」と記された遺書を掲載するなど、連日のようにセンセーショナルに伝えた。

↑ 『読売新聞』1935年1月29日
結局、富美子は一命をとりとめ、エリ子との関係を解消して大阪に帰り一件落着となった。この事件は「同性心中」としては不完全なものだったが、登場人物が著名人だっただけに大きな評判になり、「危険な女性同性愛」を世間にいっそう印象づける「事件」になってしまった。
「富美子・エリ子事件」が印象付けた女性同性愛の危険性とはなんだろう。それは第一に、本来、男性の性愛の対象になるべき女性が(富美子のように)「男を望まない欲望」「男に望まれたくない欲望」を抱くことで、男性の性愛対象から離脱してしまうことである。第二に「男を望まない欲望」が「女を望む欲望」に転化することで、男性の性愛の対象になるべき女性が(エリ子のように)女性同性愛者に奪われてしまうことである。そして、第三はそれらによって男性を主体として築かれた異性愛秩序が崩されかねない危険性を男性たちが感じるからである。
男性たちの女性同性愛への危険視には、本来自分たちのものであるべき女性が奪われることへの怒りが裏打ちされていると思う。
3 「佐良直美事件」―芸能界におけるレズビアン追放―
敗戦(1945年8月)直後の日本は、旧来の社会体制と倫理観の崩壊で、百花繚乱的に多様なセクシュアリティが展開していく。中でも男性同性愛(ゲイ)の顕在化は目覚しく、1950年代後半にはシスターボーイやゲイバーが話題になり、「第1次ゲイブーム」というべき現象が起こる。しかし、そうした社会状況の中でも、レズビアンの顕在化は進まなかった。
この時期の性風俗雑誌には、レズビアンについての記事が散見されるが、男性の興味本位の視点からのものがほとんどで、当事者性のある「語り」はきわめて少ない。そして、「男を望まない」「男に望まれたくない」はずのレズビアンに対して、男性の性的欲望の視線が向けられるようになる。こうして1950年代から60年代にかけて「危険な女性同性愛」は「ポルノグラフィーとしてのレズビアン」へと変化していく。
なぜ、男性の性的欲望を拒絶しているレズビアンに男性の性的視線が向けられるのだろうか。それはレズビアンが「性的快楽を貪欲に追求する」「性的に奔放な」女性としてイメージされたからである(杉浦2010b)。先に述べたように江戸時代において性的欲望の発信は男性に限定されてきた。近代以降の性慾学でも、性的欲望を抱き、性的快楽を追求する女性は「色情狂」であり、変態性慾のカテゴリーだった。同性愛の女性は、単に性愛対象が同性に向いているだけでなく、性的欲望を発信することにおいても変態とされたのだった。
こうした誤った認識がベースになり、性的に奔放な女性なら、男性の性的欲望にも応じるだろう、「レズビアンなんて俺(のペニス)が直してやる」というようなまったくお門違いの妄想がはびこることになる。そこまで愚かでなくても「レズビアン・ポルノビデオは、女性が2人出てくるので2倍おいしい」と言う男性は数多く実在した。
そうした性的奔放というイメージを付与されたレズビアンをめぐって、芸能界の大スキャンダルが勃発する。1980年(昭和55)5月19日、テレビ朝日のワイドショー番組『アフタヌーンショー』が「キャッシー涙の告白!! 佐良直美との愛の破局」と題して、女性歌手佐良直美と女性タレント、キャッシーのレズビアン関係を暴露した「佐良直美事件」である。
佐良直美は、1967年、デビュー曲「世界は二人のために」が120万枚の大ヒットとなり第9回日本レコード大賞の新人賞を受賞し、NHK紅白歌合戦に初出場を果たし、1969年には「いいじゃないの幸せならば」で第11回日本レコード大賞を受賞した。ショートヘアでスカートよりもパンタロンなどのスラックス姿を好み、若い女性にしては低音のハスキーボイスというマニッシュなイメージで、テレビのホームドラマ「ありがとう」(TBS、1970~74年)に出演するなど、歌手だけでなく女優や司会者など多方面で活躍する、押しも押されもせぬ一流歌手で、事件当時35歳だった。
それに対して、キャッシーは大阪弁でまくしたてるハーフのタレントとして注目され、テレビドラマにチョイ役で出演していた。佐良より6歳年下で事件当時は29歳だった。
佐良は、1972年、1974年~1977年と紅白歌合戦の紅組司会を5回も担当しているように、NHK好みの「お茶の間」好感度が高い、スキャンダルとは縁遠い人物と思われていた。それだけにキャッシーの告発は衝撃的だった。
キャッシーの告白は、2人の馴れ初めから佐良家の「嫁」としての同居生活、「姑」(佐良の母)との関係の拗れが原因となった破局まで、3年間の愛情生活を詳細に語った上に、10数通の佐良からの手紙を証拠として添えたものだった(『週刊現代』1980年6月5日号)。
これに対して佐良は同性愛関係を全面否定し、手紙も偽造と決めつけた。両者それぞれ弁護士を立てての泥沼的な訴訟合戦になるかと思われたが、一転して5月末に和解となった。佐良本人は現在に至るまでレズビアン関係を完全に否定しているが、真相は「藪の中」である。
性的スキャンダル、しかもレズビアン・スキャンダルの影響は、両者の芸能界のポジションに格段の差があった分、佐良の方がずっと大きかった。それまでの優等生的なタレントイメージは大きく損なわれてしまった。その年の暮、佐良はデビュー以来13回連続出場を続けていたNHK紅白歌合戦に落選してしまう。確かにヒット曲には恵まれていなかったが、それまでの功績を考えれば唐突な感は否めず、やはりスキャンダルが理由と受け取る人が多かった。それ以降、佐良は徐々に芸能活動から遠ざかりテレビから消えて行った。
後年になって、佐良は芸能界から引退した理由を(レズビアン・スキャンダルではなく)恩師水島早苗の死(1978年)や声帯ポリープの手術(1987年)であると語っている(『東京スポーツ』2010年11月7日号「佐良直美が30年前のレズ騒動を語る」http://www.tokyo-sports.co.jp/entame/2238/)。おそらく事実はそうなのだろう。
しかし、同時代の多くの人は、私も含めそうは受け取らなかった。佐良直美ほどの一流歌手であってもレズビアンであることが世間に知られたら、芸能界から追放されてしまうのだ、と思った。
レズビアンの社会的隠蔽という現象を考える時、事実関係よりも、そうしたイメージが視聴者やテレビ業界に広まってしまったことの方が重要である。「佐良直美事件」によって、日本の芸能界においてレズビアンは絶対的なタブー(禁忌)と認識され、その後のテレビ業界のレズビアン忌避・隠蔽姿勢が決定づけられてしまった。
なお、1970~80年代は、日本でレズビアン・コミュニティが形成されていく時代である。その主体的な歴史については、杉浦郁子の一連の研究を参照されたい(杉浦2006、2008、2010a)。
4 『ラスト・フレンズ』問題 ―なぜレズビアンではいけないのか―
『ラスト・フレンズ』は、2008年(平成20)4月10日から6月19日まで全11回、毎週木曜22時台にフジテレビ系列で放送されたテレビドラマである。
あらすじは、児童虐待(ネグレクト、性的虐待)のトラウマに由来する自我の未確立が影響して家や職場でも居場所が得られず、区役所の児童福祉課で働く恋人宗佑(錦戸亮)からドメスティック・ヴァイオレンス(DV)を受けている藍田美知留(長澤まさみ)、モトクロス選手として全日本選手権優勝を目指す一方、自分の性別に悩みを抱える岸本瑠可(上野樹里)、女性たちの良き相談相手でありながら、過去のトラウマからセックス恐怖症に悩む水島タケル(瑛太)、恋多き女性である滝川えり(水川あさみ)の4人が、シェアハウスで共同生活を始めることで人と人との関わりの大切さを知り、前向きに生きようとする、というものだった。
DV、性同一性障害、セックス恐怖症など当時の社会の若者たちの間で社会問題化しつつあったテーマを取り入れ、主要キャストに旬な若手俳優を起用したこともあって若者たちの間で話題を呼び、高視聴率を記録した(最終回22.8%)。私が大学の講義で当時15~19歳だった受講生を対象に調査したところでは、その世代に限定すれば、視聴率は50%に迫っていたと思われる。また「第57回(2008年春クール)ドラマアカデミー賞」(テレビ雑誌『ザテレビジョン』主催)において、作品賞・助演男優賞(錦戸亮)・助演女優賞(上野樹里)など6冠を達成し、テレビ業界では高く評価された。その一方で、DV男性の美化、レズビアン(女性同性愛)とGIDの混乱などをめぐって、放送時から批判も多かった。
世間的にはハードなDVシーンが注目を集めたが、ここで問題にしたいのは、岸本瑠可の描かれ方である。瑠可は中学校時代の同級生であった美知留にずっと思いを寄せている。第1回のラスト、美知留が初めてシェアハウスに泊まった翌朝、ソファーで眠っている美知留の唇に瑠可がそっと唇を寄せるシーンは、瑠可がレズビアンである可能性を想起させるものだった。しかし、ドラマの中では、「レズビアン」という言葉は一度も使われない。さらに瑠可の性的指向は「男性を好きになれない」という形で表現され、より積極的な「女性が好き」という表現は意識して避けられている。このドラマでは女性が好きな女性を描きながら、レズビアン的なものが隠蔽されているのは明らかだろう。なぜ瑠可はレズビアンではいけないのだろうか。そこに「佐良直美事件」以来のテレビ業界のレズビアン忌避が影を落としているように思われる。
レズビアンが隠蔽される一方で、瑠可がインターネットで病院のサイトを密かに見ているシーンが伏線として描かれ、少し時を置いて瑠可が性同一性障害の診断を求めてメンタルクリニックを受診するシーンが出てくる。その場面にかぶせられた瑠可のモノローグは典型的な性同一性障害の語りであり、ここに至って、瑠可がFtM(Female to Male)の性同一性障害である可能性が視聴者に強く示唆される。
しかし、瑠可の場合、ジェンダー・アイデンティティ(性自認・性同一性)と深く結びついている自称(第一人称)は、ほぼ一貫して「私(わたし)」であり、時に「あたし」と聞こえる箇所もある。FtMは、女性性と関連づけられる「私」を自称として使うことを避ける傾向があり、まして女性性が明確な「あたし」と称することはまずない。FtMの自称としては「自分」「僕」「俺」が用いられることが多いが、瑠可はそうではない。
また、映像表現では、瑠可が女性的なジェンダー表現を好まないこと、男性を愛せないことは強調されているが、FtMに特徴的な女性としての身体に対する違和感は、メンタルクリニックのシーンで語りとして表現されるだけで、映像ではあまり表現されていない。
『ラスト・フレンズ』の脚本家、浅野妙子は、脚本をFtMの当事者にみせたところ、「これってレズビアンじゃん(笑)。レズビアンだと何でいけないの?」と即答されたことを語っている(Yuki Keiser2008)。まさにその通りで、FtMの性同一性障害者をよく知る者からしたら、瑠可がFtMであることはかなり疑問で、ボーイッシュなレズビアンにしか見えない。
ボーイッシュなレズビアンを思わせる瑠可に対して、性同一性障害のレッテルを無理やり貼り付けているのではないか、という疑問に答える場面がやってくる。それは瑠可の父親に対するカミングアウト・シーンだ。瑠可は「私は男の人を好きにならない。なれないんだ」と父親に告白する。ここで問題にされているのは性的指向であり、これは典型的なレズビアンのカミングアウトである。FtMのカミングアウトなら「自分(の心)は男なんだ。女じゃないんだ」というように性自認が問題にされるはずだからだ。
ところが、瑠可のレズビアン的なカミングアウトに対する父親の述懐シーンでは、男の子に混じって活発に遊んでいた瑠可の子供時代が語られる。これは、FtMの子供時代の典型的な語りである。
ここに至って、重大なことに気づく。脚本家が性的指向の問題であるレズビアンと性自認の問題である性同一性障害(FtM)とを混同している、あるいは意図的に混乱させていることに。
実際、脚本家の浅野妙子は、「性同一性障害という設定が最初に決まっていた」こと、その上で「FtMとレズビアンの間」の「グレーゾーン」として瑠可を設定したこと、「どっちともはっきりは言えないけれど」「性同一性障害のほうがレズビアンよりそういった面(「悩み」を連想するという点)で共感を得やすい」と思い、「まずは性同一性障害にしておこう」と考えたことを語っている(Yuki Keiser2008)。レズビアンが悩まないとでも思っているのだろうか。性的マイノリティに対する歪んだ思い込みに基づく安易なドラマ設定があったことがわかる。
「FtMとレズビアンの間」の「グレーゾーン」を描こうとした脚本家の意図が視聴者に伝わったとは思えない。むしろ、瑠可のような、女の子が好きな男っぽい女性は、性同一性障害(FtM)という病気で、メンタルクリニックに通院する必要がある、という誤った情報が視聴者に与えられた可能性が高いと思う。
そうであるならば、このドラマはレズビアンを隠蔽しただけでなく、FtMの性同一性障害のイメージをも歪めて流布し、現実世界に誤った印象・知識を与えたミスリードの事例ということになる。
実際、『ラスト・フレンズ』の放送があった2008年以降、全国のジェンダー・クリニックで10代~20代の若い女性の受診者が急増したことが報告されている。それについては第7節で詳しく述べるが、そこに「ラスフレを見て、自分もそうだと確信しました」というようなミスリードが作用している可能性は十分に考えられる。
5 1990年代以降のレズビアンをめぐる動向
1990年代になると欧米のゲイ・レボリューションの波がようやく日本にも到達する。そうした中で1992年に出版された掛札悠子『「レズビアン」である、ということ』(掛札1992)は、長らく沈黙を強いられてきたレズビアンが初めて堂々と自らの生き方を語ったものとして画期的なものだった。
しかし、それによってレズビアンを取り巻く状況が大きく改善されたかといえば、必ずしもそうとは言えない。掛札に続いてカミングアウトした人は少なく(笹野1995、池田1999)、掛札自身が筆を折ってしまったこともあり、レズビアン・ムーブメントは90年代末に始まる「性同一性障害」の大流行の波に埋もれてしまう(杉浦2010b)。
1990年代末から2000年代前半にマス・メディアによって流布された「性同一性障害」についての情報量は、同性愛のそれと比較できないほど多かった。同性愛の中でも、ゲイはすでに独自のコミュニティを確立し、専門の商業雑誌をもっていたが、コミュニティの規模が小さく商業雑誌がなかなか続かないレズビアンの情報量はさらに少なかった。インターネット時代になって若干改善されたものの、まだ十分と言うには程遠い。
一方、レズビアンの学術的研究としては、性意識調査グループ編の『310人の性意識―異性愛者ではない女たちのアンケート調査』(性意識調査1998)や、中央大学の矢島正見研究室がまとめた『女性同性愛者のライフヒストリー』(矢島1999)がひとつの方向性を示している。それは、ともかくレズビアンの話を聞き記録することで、その存在を顕在化することである。隠蔽されてきた日本のレズビアンを学問的な舞台に載せたという意味で、両書の意味は大きかったと思う。
しかし、同性愛の学術研究全体でみると、杉浦郁子や堀江有里の仕事はあるものの、まだまだ男性主導でアンバランスであることは否めない。たとえば、2010年に岩波書店から出版された風間孝・河口和也『同性愛と異性愛』は、同性愛の当事者が同性愛を書名に掲げて専論した初めての新書として注目されたが、共著者が当事者でないことを理由にレズビアンについてはほとんど触れていない。当事者主義にこだわるのなら、レズビアンの執筆者を招いて章を設けるべきだし、それができないのならば、書名は『男性同性愛と異性愛』にすべきだろう。書名に「同性愛」と銘打ちながらレズビアンについてほとんど記述をしないのは、単にアンバランスなだけでなく、レズビアンの疎外であり、結果的にレズビアンの隠蔽に加担していると言えなくもない。『同性愛と異性愛』という書名にひかれて手に取ったレズビアンが目次を通覧した時の疎外感と落胆を著者や編集者は想像しただろうか。
同性愛者の歴史的な歩みや現在直面している問題が、いつの間にか男性同性愛者(ゲイ)のそれにすり替えられてしまう現象は、この本だけではないように思う。
2005年、大阪府議会議員だった尾辻かな子がレズビアンであることをカミングアウトした(尾辻)。尾辻は2007年の参議院選挙(比例区)に民主党公認として立候補したものの当選ラインに遠く及ばず落選したが、2013年5月、繰り上げ当選によって参議院議員(民主党)となった。任期が僅か一カ月余だったこともあり、残念ながら十分な実績は残せなかったが、尾辻が日本初の性的マイノリティであることを公言した国会議員であることはまぎれもない事実である。
しかし、東京都豊島区議会議員で男性同性愛者(ゲイ)であることを公表している石川大我が2014年の衆議院総選挙で社会民主党の東京比例区名簿1位に登載されると、複数のネット・メディアが「日本初の同性愛者の国会議員を目指す」と報じ、尾辻の存在は「なかったこと」にされた。無知と言えばそれまでだが、石川事務所も「日本初のオープンリーゲイの国会議員」を目指すことをプロフィールに記していて、「日本初のオープンリー同性愛者国会議員」である尾辻への配慮に欠けていたことは否めない。
2000年代後半になると、レズビアン関係の出版も徐々に増えていく(堀江2006、飯野2008、牧村2013)。2013年には世界的な同性婚承認の流れの中で、レズビアン・カップルの東京ディズニーランドでの挙式が話題になった(東小雪+増原裕子2014)。
しかし、レズビアンの存在が日本社会の中で十分に認知され、レズビアンに関する情報が十分に流通し、レズビアンを取り巻く様々な困難な状況について地に足が着いた議論がなされる状況には、残念ながら至っていない。
6 レズビアン・ロールモデルの不在
レズビアンをめぐる現状を考えたとき、情報量の不足もだが、最大の問題はレズビアンのロールモデルの不在だと思う。その原因は、テレビをはじめとするマス・メディアがレズビアンの存在を徹底的に隠蔽してきたことにある。
2010年代になってさえ、日本のマス・メディアは「レズビアン疑惑」という言い方をしてはばからない。「疑惑」という言葉は「覚醒剤使用疑惑」など社会的に問題のある行為を疑う言葉だ。いったいなぜレズビアンであることが問題行為なのだろう。そうした「疑惑」をかけられた女優、女性歌手あるいは女性タレントは、必死に「疑惑」を否定しようとする。本人が沈黙していても事務所が否定に動く。なぜなら、現在の日本のテレビ業界では「レズビアン」であることは仕事を失うことにつながりかねず、デメリットが大きいからだ。その点で、レズビアンをカミングアウトした女優や女性アーティストが活躍する欧米と著しい違いがある。佐良直美事件の呪縛は30年以上たってもまだ解けていないのだ。
なぜ、これほどまでにテレビ・メディアはレズビアンの存在を忌避するのだろうか。その理由を端的に指摘すれば、すべての女性は男性の性的視線を受け止める存在でなければならないという、男性中心のヘテロセクシュアル原理がいまだに貫徹しているのがテレビ業界だということだ。そうした姿勢の背景にはスポンサーとしてテレビ番組を支えている日本の企業社会の男性中心のヘテロセクシャリズムがある。
このように、マス・メディアの隠蔽姿勢がレズビアンのvisibility(目に見えること)を著しく低下させ、魅力的なレズビアン・ロールモデルの出現を阻んでいる。そして、レズビアン・ロールモデルの不在が、レズビアンの自己肯定をいっそう困難にしている。
ところで、レストランでメニューにない料理を注文できる人はごく少ない。ほとんどの人はメニューの中から料理を選ぶ。それと同じで、人は目の前に並んでいる概念にしかアイデンティファイ(カテゴリーへの同一化)できない。私はこれを「メニュー理論」と言っている。
たとえば、20代の私の前に置かれていたメニューには、トランスジェンダーも性同一性障害も無く、ゲイボーイという概念しかなかった。「これは違う」と思ったから、それをつかまなかった。アマチュアの女装者という概念があることを知ったのは30代の初めで、やっとその言葉をつかむことができたが、トランスジェンダーという言葉を知って最終的にアイデンティファイできたのは40歳を過ぎてからだった。
レズビアンを抑圧し、存在を隠蔽してきた結果、レズビアンのロールモデルが提示されず、逆に性同一性障害(FtM)の情報が多く流布されている現状は、メニューに「今月のおすすめ」として「性同一性障害(FtM)」と大書されているのに対し、「レズビアン」は見えるか見えないかの小さい文字でしか書かれていない状態にたとえられる。自分の性的指向(Sexual Orientation)が典型的でないことに気づいた女性がメニューを見たとき、本来ならつかむべきレズビアンではなく、性同一性障害(FtM)をつかんでしまうのも無理からぬ状況がそこにある。
7 なぜ日本はFtM(Female to Male)が多いのか?
性同一性障害の性別比、つまりMtFとFtMの比率は、世界標準的には、2対1くらいでMtFが多いとされている。日本では1990年代末から2000年代中頃までは、MtFがやや多い状態からMtFとFtMの比率が拮抗する状況へと緩やかに推移していた。ところが、2008年以降、全国の複数の病院、クリニックで、若年(10代後半~20代前半)FtMの受診者が急増し、世界標準とは逆に、ほぼ1対2の比率でFtMの受診者が多くなった(2009年2月の第11回GID学会での報告。「関西医大病院ジェンダー・クリニック」MtF134、FtM270=33対67、「札幌医大GIDクリニック」MtF94、FtM220=30対70、「はりまメンタルクリニック」MtF229、FtM409=36対64)。
かつて私は、この現象をテレビドラマ『ラスト・フレンズ』の影響で、本来は、男性っぽいレズビアンの範疇でおさまるはずの(瑠可のような)女性が、性同一性障害(FtM)と自己認識して、ジェンダー・クリニックを受診している結果ではないかと考えていた。しかし、その後もFtMの増加傾向は止まらず、現在では1対3からさらに1対4に近づく状態になっている。
FtMの増加傾向は、受診者レベルではなく、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(GID特例法)」による戸籍の性別変更においても著しい。全国の家庭裁判所に提出される戸籍変更の診断書の約15%を書いている(2012~2014年平均)針間克己医師(はりまメンタルクリニック)によれば、2012年から2015年の戸籍変更診断書の累計はMtF119、FtM464≒1対4だった(「Anno job Log」2015年12月27日 http://d.hatena.ne.jp/annojo/20151227)。日本は世界で最も、そして格段にFtMの比率が高い国になっている。
こうなると、テレビドラマの影響だけとは言えず、それをきっかけとした、もっと大きな構造的な原因があると考えなければならない。生得的な体質、遺伝子的に日本人の女性がFtMになりやすいということはなさそうなので、その原因は社会的なものと考えられる。
そこで考えなければならないのは、世界標準より多い分のFtMがどこから来ているのか?ということだ。その際、ヘテロセクシュアルの女性がFtM化するということは考えにくい。女性に課せられた社会的制約から脱するために男装する女性は過去にはいたが、現代の日本は一般論的に言って女性が男体化しなければ社会活動が難しい状況にはない。また性的指向が男性に向かっているヘテロセクシュアルの女性がFtM化した場合、セクシュアリティ的なメリットはほとんどない。ゲイ男性はヘテロ男性よりずっと少ないからだ。
それに対して、レズビアンがFtM化しているという想定の方がずっと考えやすい。レズビアンがFtM化すれば、性愛対象のヘテロ女性はレズビアン女性よりずっと多いから、ターゲットはぐっと広がる。なにより戸籍の性別を男性に変更すれば、法的に女性と結婚できる。同性婚が法的に許可される見通しが立たない日本では、生得的な女性が女性と法的に婚姻するには、一方の女性がFtMの性同一性障害者として「GID特例法」によって、戸籍の性別を変更するのが唯一の方法だからだ。
このように考えると、日本におけるFtMの増加分はレズビアンからの流入を想定するのが、いちばん蓋然性が高いと思う。その原因として、前節で述べたような、自分の性的指向が典型的でないことに気づいた女性が本来ならアイデンティファイすべきレズビアンではなく、性同一性障害(FtM)として自己認識してしまう状況が存在し、さらに「GID特例法」による一種の「誘導」が作用していると考えられる。
次に考慮すべきは、レズビアンとFtMの比率である。本来、レズビアンは100人に数人いると考えるのが一般的だ。それに対して日本のFtMは10000人に数人と考えられる。つまり両者の人数は本来100倍ほども違う。ということは、レズビアンの1%がFtMに流入すればFtMは本来の数の倍になるし、2%流入すれば3倍に、9%が流入すれば10倍になる。このようにレズビアンからの流入モデルを考えることで、日本で世界標準よりFtMが著しく多い理由を容易に説明することができる。
ところで、レズビアンからFtMへという流入現象がかなりあると想定した場合、ゲイからMtFへの流入はそれに比してなぜ少ないのかという疑問が生じる。この点については次のように説明できると思う。
日本において、ゲイ・コミュニティとMtFのコミュニティは、性同一性障害概念が流布する1990年代後半以前に、すでにかなり明確に分離していた。その分離の時期は1970~1980年代と考えられる(三橋2008)。だから、性同一性障害概念はMtFだけに影響を与え、ゲイにはほとんど影響が及ばなかった(まったく流入がないわけではないが)。それに対して、レズビアン・コミュニティとFtMのコミュニティは分離が進まず混在した状態だったところに、性同一性障害概念が流布した。その結果、本来、性同一性障害概念の影響を受ける必要のないレズビアンにまでその影響が及んでしまい、混乱と流入が起こってしまったと考えられる。そして、レズビアン・コミュニティとFtMのコミュニティの未分離の原因にはレズビアンの隠蔽による情報不足がある。
非典型な性をもつ人たちがどのようにカテゴライズされ、自らをアイデンティファイしていくかは、今まで言われてきたほど固定的ではなく、与えられる情報によってかなり流動的であると私は考える。それゆえに、適切なアイデンティファイをするためには隠蔽や歪曲がない正しい情報提供、つまり、自分にふさわしい料理を選べる「メニュー」が必要なのである。
おわりに
ある年度、「ジェンダー論」の講義の単位レポートに、レズビアンであることの辛い思いを切々と記してきた学生がいた。好きな相手からもレズビアンの存在そのものを否定され、周囲の偏見の中で自己否定感にさいなまれる。なぜ、女性として女性が好きなだけでこんなに苦しまなければならないのか、単位レポートだから冷静に読んで評価しなければいけないのだが、「今まで書いてきたことはすべて事実です。でも、誰にも話したことはありません。やっとレポートという形ですが書くことができて、私は幸せです、ありがとうございました」という結びの文章を読んで、涙が流れるのを抑えることができなかった。
一方では、女性を愛するためには自分が男にならなければならないと思い込み、短命化の可能性が高い男性ホルモンを過剰に摂取し、身体にメスを入れて乳房、子宮・卵巣を摘出し、高額な費用をかけて(トラブルが多く機能的にも不十分な)擬似男性器を形成する人たちがいる。無惨な傷跡が残る症例写真を見るたびに、レズビアンの範疇に収まるのなら、その方がずっと身体リスクは少ないのに、なぜこんなことまでしなければならないのかと考えてしまう。
女性として女性を愛する女性たちが、適切な自己認識を形成するためには、レズビアンが隠蔽されることなく、レズビアンに関する情報が十分に流通し、女性として女性を愛する多様なロールモデルが社会の中で存在することが必要だと思う。さらに言えば、女性を愛する女性がレズビアンでなくFtMを選択する背景には、日本社会における女性の根本的な生きにくさが存在する。性的マイノリティだけの問題では済まないことを、性的マジョリティの人たちにも知って欲しいと思う。
文献
赤枝香奈子2011『近代日本における女同士の親密な関係』(角川学芸出版)
飯野由里子2008『レズビアンである〈わたしたち〉のストーリー』(生活書院)
池田久美子1999『先生のレズビアン宣言―つながるためのカムアウト』(かもがわ出版)
尾辻かな子2005『カミングアウト〜自分らしさを見つける旅』(講談社)
掛札悠子1992『「レズビアン」である、ということ』(河出書房新社)
風間孝・河口和也2010『同性愛と異性愛』(岩波新書)
桑谷定逸1911「戦慄す可き女性間の顚倒性慾」(『新公論』明治44年9月号)
小峰茂之・南孝夫1985『同性愛と同性心中の研究』(小峰研究所)
笹野みちる1995『Coming OUT!』(幻冬舎)
白倉敬彦2002『江戸の春画―それはポルノだったのか―』(洋泉社新書)
菅 聡子2006「女性同士の絆―近代日本の女性同性愛―」(『国文』106号)
杉浦郁子2006「1970、80年代の一般雑誌における『レズビアン』表象――レズビアンフェミニスト言説の登場まで」(矢島正見編著『戦後日本女装・同性愛研究』(中央大学出版部)
杉浦郁子2008「日本におけるレズビアン・フェミニズムの活動 -1970年代後半の黎明期における」 (『ジェンダー研究』11号)
杉浦郁子2010a「『レズビアン』の概念史――戦後、大衆娯楽雑誌における」(中村桃子編『ジェンダーで学ぶ言語学』世界思想社)
杉浦郁子2010b「レズビアンの欲望/主体/排除を不可視化する社会について―現代日本におけるレズビアン差別の特徴と現状―」(シリーズ「現代の差別と排除」第6巻『セクシュアリティ』明石書店)
性意識調査グループ編1998『310人の性意識―異性愛者ではない女たちのアンケート調査』(七つ森書館)
田中優子2004『張形と江戸をんな』(洋泉社新書)
東 小雪+増原裕子2014『レズビアン的結婚生活』(イースト・プレス)
肥留間由紀子2003「近代日本における女性同性愛の『発見』」(『解放社会学研究』17号)
古川 誠1994「セクシュアリティの変容:近代日本の同性愛をめぐる3つのコード」(『日米女性ジャーナル』17号)
堀江有里2006『「レズビアン」という生き方―キリスト教の異性愛主義を問う』(新教出版社)
堀江有里2015『レズビアン・アイデンティティーズ』(洛北出版)
牧村朝子2013『百合のリアル』(星海社新書)
三橋順子2008『女装と日本人』(講談社現代新書)
三橋順子2013「性と愛のはざま-近代的ジェンダー・セクシュアリティ観を疑う-」(『講座 日本の思想 第5巻 身と心』岩波書店)
三橋順子2015a「『台記』に見る藤原頼長のセクシュアリティの再検討」(倉本一宏編『日記・古記録の世界』思文閣出版)
三橋順子2015b「歴史の中の多様な『性』」(『アステイオン』83号 CCCメディアハウス)
矢島正見編著1999『女性同性愛者のライフヒストリー』(学文社)
Yuki Keiser2008「『ラスト・フレンズ』の脚本家・浅野妙子さんのインタビュー」
http://www.tokyowrestling.com/articles/2008/06/last_friends_3.html
【付記1】入稿後、杉浦郁子「『女性同性愛』言説をめぐる歴史的研究の展開と課題 」(『和光大学現代人間学部紀要』8号 2015年)に接した。本稿と関わるところ大であるが、内容に反映することができなかった。
【付記2】最終的な入稿(2015年2月)の直後、東京都渋谷区の「同性パートナー証明書」発行の条例化(2015年3月31日可決、11月5日実施)問題が浮上し、それをきっかけに「LGBTブーム」が一気に盛り上がり、マス・メディアにおけるレズビアンを含む同性愛関係報道が激増した。その結果、レズビアンのvisibilityは向上したように思われる。しかし、「LGBTブーム」の中で注目されているのは、裕福で、容姿に優れ、社会的地位のある「シャイニー(shiny)」な特定のレズビアンであり、一般のレズビアンが抱えるさまざまな生活の困難を改善していく視点は、まったく不十分である。これはブームの発端が政治的思惑(統一地方選挙)や経済的期待(LGBT消費需要)であり、必ずしも人権的観点でなかったためと思われる。今後、LGBTの人権擁護の論議が深まる中で、本当の意味でのレズビアンの社会的顕在化と生活改善がなされることを期待したい。
小林 富久子・村田 晶子・弓削 尚子編
『ジェンダー研究/教育の深化のために― 早稲田からの発信』

彩流社、2016年3月、474頁、定価4300円+税
ISBN-13: 978-4779121968
これからの「ジェンダー研究/教育」に向けて、文学、表象・メディア、歴史、法・社会などの専門領域の「ジェンダー研究の展開」と、教育実践をもとにした「ジェンダー教育のあり方」の二本立てで、計24編の論考を収録している。
私は、論文「日本におけるレズビアンの隠蔽とその影響」を執筆。
日本における女性同士の性愛の歴史をトピック的にたどり、その隠蔽の在り様を明らかにした上で、その現代における影響、具体的には「なぜ日本では女性から男性への性別移行者(Female to Male=FtM)が(国際比較で)突出的に多いのか?」を考えてみた。
論集では割愛した、図版を加えた。
-------------------------------------------------------------------------
日本におけるレズビアンの隠蔽とその影響
三橋順子(性社会・文化史研究者)
はじめに
「日本にもレズビアンがいると知って驚きました。テレビなどに出てこないのでいないものだと思っていました」
「今までレズビアンは性同一性障害の一種だと思っていましたが、今日の講義でレズビアンと性同一性障害は違うものだとわかりました」
いずれも、私の「ジェンダー論」の受講生のコメント票の記述である。読んで私は愕然とした。レズビアンへの認識不足は実感していたが、まさかこれほどとは……。しかし、学生の無知と笑って済ますことはできない。前者は教員養成で長い実績がある公立大学、後者は日本有数の私立大学の学生だ。つまり、レズビアンへの同様の認識不足は若者たち、いや世間に広く存在することを示しているからだ。
現代日本におけるレズビアン(Lesbian 女性同性愛)への認識と理解は、トランスジェンダー(Transgender性別越境者)の病理化概念である性同一性障害(Gender Identity Disorder=GID)や、同じ同性愛であるゲイ(Gay 男性同性愛)と比べて格段に低い。
その原因としては、学生が「テレビなどに出てこないので」と言っているように、一般の人が目にするところにレズビアンが存在しない(ように見える)ことが大きい。もちろん、現実には日本社会にはたくさんのレズビアンが生活している。その数は男性同性愛者とそれほど大きくは変わらないだろうし、性同一性障害の人よりずっと(おそらく2桁)多いはずだ。概数的に言えば、100人に2~3人いてもおかしくない。なのに、なぜ、目に見えないのか? それは隠されているからにほかならない。
日本におけるレズビアン差別については、杉浦郁子「レズビアンの欲望/主体/排除を不可視にする社会について―現代日本におけるレズビアン差別の特徴と現状―」(杉浦2010b)という優れた研究がある。男性ホモソーシャル体制を堅持するために、ホモフォビアを伴う異性愛主義を浸透させた、「女同士の絆」が未分化で曖昧なものとして構築されている現代日本社会の中で「男を望まない欲望」「男に望まれたくない欲望」を表出することは困難であり、それがレズビアンの不可視化、差別を招いているという杉浦の社会構造的な分析にほとんど異論はない。
しかし、杉浦はレズビアンが隠蔽されてきた個々の事例についてはあまり触れていない。そこで本稿では、不十分ながらレズビアンが隠蔽されてきた歴史をトピック的にたどり、それが現代日本社会にどんな影響を与えているかを考えてみたい。
1 レズビアンの前史 ―先行概念がない―
実態として、平安時代の後宮、江戸時代の将軍家大奥や大名家の奥向き、遊廓の妓楼など、女性が多く集まり暮らす場で、女性同士の性愛はあったと思われる。しかし、文献的に明確な例としては、『我身にたどる姫君』(鎌倉時代中期、1259~1278年頃)第6巻の主人公「前斎宮」(嵯峨院上皇の娘)が周囲の女性たちと次々に関係をもつ話があるくらいで数少ない。あるいは、江戸時代の性具の中に「互形(たがいがた)」と呼ばれた双頭の張形が残っていること(田中2004)や、同時期の春画の中に僅かながら女性同士の性愛を描いたものがあることなどからうかがえるに過ぎない。
このように女性同士の性愛を示す資料は、男と女の関係はもちろん、男と男(正確には男と若衆)の関係に比べても圧倒的に少ない。そもそも、女性同士の性愛を示す概念、言葉がなかった。「互形」を用いた女性同士の擬似性交を「互先(たがいせん)」と言い(田中2004)、女性同士の性愛を示す「貝合せ」とか「合淫(ともぐい)」という言葉があった(白倉2002)。あるいは、「といちはいち(ト一ハ一?)」という語源不詳(「上」「下」の意か?)の言い方もあった。これらは、いずれも卑語、隠語の類であり、世間に広く通用した言葉ではなかった。
これは江戸時代の「色」の概念が、男性から遊女に向かうものを「女色」、男性から若衆に向かうものを「男色」と言い、「色」の発信は常に男性が主体であるとされていたことによる(三橋2013)。つまり、女性が発信主体となることは想定されていないので、女と女の関係は概念として存在しないのだ。さらに、当時の著述・出版事業が圧倒的に男性支配下にあり、女性が自らの性愛を記録し刊行することが困難な事情もあった。
ところで、同性の間の性愛、あるいは性的指向(sexual orientation)が同性に向いていることを意味するhomosexualityという概念は、明治時代の末、1910年頃にドイツの精神医学者リヒャルト・フォン・クラフト=エビングの学説が日本に輸入され、「同性的情慾」「顚倒的同性間性慾」などの訳語で、精神疾患である「変態性慾」のひとつとして概念化された(古川1994)。日本において最初に「女性間の顚倒性慾」が「発見」されたのもこの時期だった(肥留間2003)。その後、訳語は「同性愛」に定着するが、同性愛という言葉が新聞・雑誌などで使用され、倒錯的な性愛として一般に広く知られるようになるのは、1920年代、大正末期から昭和初期のことである。
同性愛概念が導入される以前(明治時代以前)の日本では、同性愛という概念は存在しない。男性同士の性愛は「男色」として概念化されていたが、それは成人した男性と元服前の少年、あるいは年長の少年と年少の少年との関係に限定されていて、成人男性同士の性愛を含む「男性同性愛」とはかなり異なる(三橋2015a、2015b)。とはいえ、それでも類似の先行概念があるだけ男性同性愛という概念を受容しやすかっただろう。
これに対して、女性同士の性愛は、同性愛概念が導入される以前には概念化されていなかった。つまり、女性同性愛は類似の先行概念がなく、(前近代)「男色」→(近代)「男性同性愛」のような概念の継承、読み替えが成り立たず、大正~昭和初期にいきなり世の中に出てくることになる。
このことが、日本近代における女性同性愛の受容に大きく影響しているように思う。大衆は、よくわからないものには警戒的になる。女性同性愛が男性同性愛よりもさらに社会的に警戒されたのは、基本的には男尊女卑の社会構造が大きいが、先行概念の欠落にも理由があったのではないだろうか。
2 「富美子・エリ子事件」―「同性心中」と女性同性愛の危険視―
日本で女性同性愛が注目されたきっかけは、1911年(明治44)7月に新潟で起こった「令嬢風の二美人」の入水心中事件だった。東京の第二高等女学校(都立竹早高校の前身)の同級生だった二人は在学中から「非常の仲よし」だったが、卒業後は交際を控えるよう父親から注意されたのを悲観しての自殺だった。この事件に注目して日本最初の女性同性愛に関する論文、桑谷定逸「戦慄す可き女性間の顚倒性慾」が書かれる(桑谷1911)。日本における女性同性愛は最初から「戦慄すべき」ものだったのだ。
これ以降、昭和戦前期の新聞で、女性同士の「同性心中」がしばしば新聞報道されるようになり、女性同性愛のイメージを「危険」なものにしていった。「同性心中」なのだから男性同士の心中(自殺)もあるはずだが、実際に報道されたもののほとんどは女性同士の心中だった。また、女性同士の自殺だからといって、その二人が同性愛関係だったとは限らないのだが、イメージとして同性心中と女性同性愛が結び付けられ、ことさらに危険視されたことは間違いない。「同性心中」への注目と問題視は戦後期まで継続し、「危険な女性同性愛」のイメージを再生産していくことになる(小峰・南1985)。
ところで、日本で女学校が開設され、女学生が増えるとともに、女学生同士の親密な関係が社会的に浮上してくる。こうした一種の疑似恋愛関係は「エス」(Sisterの頭文字)と呼ばれ、1920年代には女学校文化として定着するようになった(赤枝2011)。それを危険視する見解がある一方で、親にしてみれば女学生の娘が男性と恋愛関係におちいるより、女学生同士の疑似恋愛に没頭している方が安全であり、「エス」の関係は卒業とともに終え、男性と結婚し良妻賢母になってくれればそれでいいという容認的な考えもあったようだ。
もちろん、親の思惑通りに行かない場合もあり、先の新潟の入水心中事件はその典型である。「エス」と女性同性愛の間に明確な線引きができるわけではないにもかかわらず、女学生同士の親密な関係である「エス」は許容され、女性同性愛は危険視されるというダブルスタンダードが生じていく。
一方、1933年(昭和8)に清朝皇室の粛親王善耆の第十四王女である川島芳子(愛新覺羅顯玗)をモデルにした小説、村松梢風『男装の麗人』が出版されたことをきっかけに「男装の麗人」ブームが起こる。その中心は、川島芳子と松竹歌劇団の男役スター「ターキー」こと水の江瀧子だった。当時の新聞は、川島とターキーの動静をしばしば伝えている。


(左)水の江瀧子(右)川島芳子
そんな時代を背景に、1935年(昭和10)1月末、「富美子・エリ子事件」が起こる。増田富美子は大阪の銀行頭取の令嬢ながら増田夷希(やすまれ)と名乗る「男装の麗人」で当時28歳、その恋人西條エリ子は「松竹少女歌劇」の女役トップスターだった人気映画女優で当時23歳。その二人の「女性同士の愛の逃避行」が新聞で大きく報道された。二人は「愛の逃避行」の末に1月28日夜、東京麹町区平河町の「万平ホテル」に同宿する。その夜、富美子はエリ子への遺書を残して睡眠薬自殺をはかり昏睡状態になってしまう。
.jpg)
↑ 増田夷希(やすまれ)と名乗った増田登美子(『読売新聞』1935年1月30日)
まるで犯罪者のように富美子たちの動向を追跡していた『読売新聞』は「『男装の麗人』富美子さん 萬平ホテルで服毒す 西條エリ子と共に投宿 遂に『死』への逃避行」という大見出しのもとに、男姿の富美子の写真と「本当いへば一緒に死んでほしかった」と記された遺書を掲載するなど、連日のようにセンセーショナルに伝えた。

↑ 『読売新聞』1935年1月29日
結局、富美子は一命をとりとめ、エリ子との関係を解消して大阪に帰り一件落着となった。この事件は「同性心中」としては不完全なものだったが、登場人物が著名人だっただけに大きな評判になり、「危険な女性同性愛」を世間にいっそう印象づける「事件」になってしまった。
「富美子・エリ子事件」が印象付けた女性同性愛の危険性とはなんだろう。それは第一に、本来、男性の性愛の対象になるべき女性が(富美子のように)「男を望まない欲望」「男に望まれたくない欲望」を抱くことで、男性の性愛対象から離脱してしまうことである。第二に「男を望まない欲望」が「女を望む欲望」に転化することで、男性の性愛の対象になるべき女性が(エリ子のように)女性同性愛者に奪われてしまうことである。そして、第三はそれらによって男性を主体として築かれた異性愛秩序が崩されかねない危険性を男性たちが感じるからである。
男性たちの女性同性愛への危険視には、本来自分たちのものであるべき女性が奪われることへの怒りが裏打ちされていると思う。
3 「佐良直美事件」―芸能界におけるレズビアン追放―
敗戦(1945年8月)直後の日本は、旧来の社会体制と倫理観の崩壊で、百花繚乱的に多様なセクシュアリティが展開していく。中でも男性同性愛(ゲイ)の顕在化は目覚しく、1950年代後半にはシスターボーイやゲイバーが話題になり、「第1次ゲイブーム」というべき現象が起こる。しかし、そうした社会状況の中でも、レズビアンの顕在化は進まなかった。
この時期の性風俗雑誌には、レズビアンについての記事が散見されるが、男性の興味本位の視点からのものがほとんどで、当事者性のある「語り」はきわめて少ない。そして、「男を望まない」「男に望まれたくない」はずのレズビアンに対して、男性の性的欲望の視線が向けられるようになる。こうして1950年代から60年代にかけて「危険な女性同性愛」は「ポルノグラフィーとしてのレズビアン」へと変化していく。
なぜ、男性の性的欲望を拒絶しているレズビアンに男性の性的視線が向けられるのだろうか。それはレズビアンが「性的快楽を貪欲に追求する」「性的に奔放な」女性としてイメージされたからである(杉浦2010b)。先に述べたように江戸時代において性的欲望の発信は男性に限定されてきた。近代以降の性慾学でも、性的欲望を抱き、性的快楽を追求する女性は「色情狂」であり、変態性慾のカテゴリーだった。同性愛の女性は、単に性愛対象が同性に向いているだけでなく、性的欲望を発信することにおいても変態とされたのだった。
こうした誤った認識がベースになり、性的に奔放な女性なら、男性の性的欲望にも応じるだろう、「レズビアンなんて俺(のペニス)が直してやる」というようなまったくお門違いの妄想がはびこることになる。そこまで愚かでなくても「レズビアン・ポルノビデオは、女性が2人出てくるので2倍おいしい」と言う男性は数多く実在した。
そうした性的奔放というイメージを付与されたレズビアンをめぐって、芸能界の大スキャンダルが勃発する。1980年(昭和55)5月19日、テレビ朝日のワイドショー番組『アフタヌーンショー』が「キャッシー涙の告白!! 佐良直美との愛の破局」と題して、女性歌手佐良直美と女性タレント、キャッシーのレズビアン関係を暴露した「佐良直美事件」である。
佐良直美は、1967年、デビュー曲「世界は二人のために」が120万枚の大ヒットとなり第9回日本レコード大賞の新人賞を受賞し、NHK紅白歌合戦に初出場を果たし、1969年には「いいじゃないの幸せならば」で第11回日本レコード大賞を受賞した。ショートヘアでスカートよりもパンタロンなどのスラックス姿を好み、若い女性にしては低音のハスキーボイスというマニッシュなイメージで、テレビのホームドラマ「ありがとう」(TBS、1970~74年)に出演するなど、歌手だけでなく女優や司会者など多方面で活躍する、押しも押されもせぬ一流歌手で、事件当時35歳だった。
それに対して、キャッシーは大阪弁でまくしたてるハーフのタレントとして注目され、テレビドラマにチョイ役で出演していた。佐良より6歳年下で事件当時は29歳だった。
佐良は、1972年、1974年~1977年と紅白歌合戦の紅組司会を5回も担当しているように、NHK好みの「お茶の間」好感度が高い、スキャンダルとは縁遠い人物と思われていた。それだけにキャッシーの告発は衝撃的だった。
キャッシーの告白は、2人の馴れ初めから佐良家の「嫁」としての同居生活、「姑」(佐良の母)との関係の拗れが原因となった破局まで、3年間の愛情生活を詳細に語った上に、10数通の佐良からの手紙を証拠として添えたものだった(『週刊現代』1980年6月5日号)。
これに対して佐良は同性愛関係を全面否定し、手紙も偽造と決めつけた。両者それぞれ弁護士を立てての泥沼的な訴訟合戦になるかと思われたが、一転して5月末に和解となった。佐良本人は現在に至るまでレズビアン関係を完全に否定しているが、真相は「藪の中」である。
性的スキャンダル、しかもレズビアン・スキャンダルの影響は、両者の芸能界のポジションに格段の差があった分、佐良の方がずっと大きかった。それまでの優等生的なタレントイメージは大きく損なわれてしまった。その年の暮、佐良はデビュー以来13回連続出場を続けていたNHK紅白歌合戦に落選してしまう。確かにヒット曲には恵まれていなかったが、それまでの功績を考えれば唐突な感は否めず、やはりスキャンダルが理由と受け取る人が多かった。それ以降、佐良は徐々に芸能活動から遠ざかりテレビから消えて行った。
後年になって、佐良は芸能界から引退した理由を(レズビアン・スキャンダルではなく)恩師水島早苗の死(1978年)や声帯ポリープの手術(1987年)であると語っている(『東京スポーツ』2010年11月7日号「佐良直美が30年前のレズ騒動を語る」http://www.tokyo-sports.co.jp/entame/2238/)。おそらく事実はそうなのだろう。
しかし、同時代の多くの人は、私も含めそうは受け取らなかった。佐良直美ほどの一流歌手であってもレズビアンであることが世間に知られたら、芸能界から追放されてしまうのだ、と思った。
レズビアンの社会的隠蔽という現象を考える時、事実関係よりも、そうしたイメージが視聴者やテレビ業界に広まってしまったことの方が重要である。「佐良直美事件」によって、日本の芸能界においてレズビアンは絶対的なタブー(禁忌)と認識され、その後のテレビ業界のレズビアン忌避・隠蔽姿勢が決定づけられてしまった。
なお、1970~80年代は、日本でレズビアン・コミュニティが形成されていく時代である。その主体的な歴史については、杉浦郁子の一連の研究を参照されたい(杉浦2006、2008、2010a)。
4 『ラスト・フレンズ』問題 ―なぜレズビアンではいけないのか―
『ラスト・フレンズ』は、2008年(平成20)4月10日から6月19日まで全11回、毎週木曜22時台にフジテレビ系列で放送されたテレビドラマである。
あらすじは、児童虐待(ネグレクト、性的虐待)のトラウマに由来する自我の未確立が影響して家や職場でも居場所が得られず、区役所の児童福祉課で働く恋人宗佑(錦戸亮)からドメスティック・ヴァイオレンス(DV)を受けている藍田美知留(長澤まさみ)、モトクロス選手として全日本選手権優勝を目指す一方、自分の性別に悩みを抱える岸本瑠可(上野樹里)、女性たちの良き相談相手でありながら、過去のトラウマからセックス恐怖症に悩む水島タケル(瑛太)、恋多き女性である滝川えり(水川あさみ)の4人が、シェアハウスで共同生活を始めることで人と人との関わりの大切さを知り、前向きに生きようとする、というものだった。
DV、性同一性障害、セックス恐怖症など当時の社会の若者たちの間で社会問題化しつつあったテーマを取り入れ、主要キャストに旬な若手俳優を起用したこともあって若者たちの間で話題を呼び、高視聴率を記録した(最終回22.8%)。私が大学の講義で当時15~19歳だった受講生を対象に調査したところでは、その世代に限定すれば、視聴率は50%に迫っていたと思われる。また「第57回(2008年春クール)ドラマアカデミー賞」(テレビ雑誌『ザテレビジョン』主催)において、作品賞・助演男優賞(錦戸亮)・助演女優賞(上野樹里)など6冠を達成し、テレビ業界では高く評価された。その一方で、DV男性の美化、レズビアン(女性同性愛)とGIDの混乱などをめぐって、放送時から批判も多かった。
世間的にはハードなDVシーンが注目を集めたが、ここで問題にしたいのは、岸本瑠可の描かれ方である。瑠可は中学校時代の同級生であった美知留にずっと思いを寄せている。第1回のラスト、美知留が初めてシェアハウスに泊まった翌朝、ソファーで眠っている美知留の唇に瑠可がそっと唇を寄せるシーンは、瑠可がレズビアンである可能性を想起させるものだった。しかし、ドラマの中では、「レズビアン」という言葉は一度も使われない。さらに瑠可の性的指向は「男性を好きになれない」という形で表現され、より積極的な「女性が好き」という表現は意識して避けられている。このドラマでは女性が好きな女性を描きながら、レズビアン的なものが隠蔽されているのは明らかだろう。なぜ瑠可はレズビアンではいけないのだろうか。そこに「佐良直美事件」以来のテレビ業界のレズビアン忌避が影を落としているように思われる。
レズビアンが隠蔽される一方で、瑠可がインターネットで病院のサイトを密かに見ているシーンが伏線として描かれ、少し時を置いて瑠可が性同一性障害の診断を求めてメンタルクリニックを受診するシーンが出てくる。その場面にかぶせられた瑠可のモノローグは典型的な性同一性障害の語りであり、ここに至って、瑠可がFtM(Female to Male)の性同一性障害である可能性が視聴者に強く示唆される。
しかし、瑠可の場合、ジェンダー・アイデンティティ(性自認・性同一性)と深く結びついている自称(第一人称)は、ほぼ一貫して「私(わたし)」であり、時に「あたし」と聞こえる箇所もある。FtMは、女性性と関連づけられる「私」を自称として使うことを避ける傾向があり、まして女性性が明確な「あたし」と称することはまずない。FtMの自称としては「自分」「僕」「俺」が用いられることが多いが、瑠可はそうではない。
また、映像表現では、瑠可が女性的なジェンダー表現を好まないこと、男性を愛せないことは強調されているが、FtMに特徴的な女性としての身体に対する違和感は、メンタルクリニックのシーンで語りとして表現されるだけで、映像ではあまり表現されていない。
『ラスト・フレンズ』の脚本家、浅野妙子は、脚本をFtMの当事者にみせたところ、「これってレズビアンじゃん(笑)。レズビアンだと何でいけないの?」と即答されたことを語っている(Yuki Keiser2008)。まさにその通りで、FtMの性同一性障害者をよく知る者からしたら、瑠可がFtMであることはかなり疑問で、ボーイッシュなレズビアンにしか見えない。
ボーイッシュなレズビアンを思わせる瑠可に対して、性同一性障害のレッテルを無理やり貼り付けているのではないか、という疑問に答える場面がやってくる。それは瑠可の父親に対するカミングアウト・シーンだ。瑠可は「私は男の人を好きにならない。なれないんだ」と父親に告白する。ここで問題にされているのは性的指向であり、これは典型的なレズビアンのカミングアウトである。FtMのカミングアウトなら「自分(の心)は男なんだ。女じゃないんだ」というように性自認が問題にされるはずだからだ。
ところが、瑠可のレズビアン的なカミングアウトに対する父親の述懐シーンでは、男の子に混じって活発に遊んでいた瑠可の子供時代が語られる。これは、FtMの子供時代の典型的な語りである。
ここに至って、重大なことに気づく。脚本家が性的指向の問題であるレズビアンと性自認の問題である性同一性障害(FtM)とを混同している、あるいは意図的に混乱させていることに。
実際、脚本家の浅野妙子は、「性同一性障害という設定が最初に決まっていた」こと、その上で「FtMとレズビアンの間」の「グレーゾーン」として瑠可を設定したこと、「どっちともはっきりは言えないけれど」「性同一性障害のほうがレズビアンよりそういった面(「悩み」を連想するという点)で共感を得やすい」と思い、「まずは性同一性障害にしておこう」と考えたことを語っている(Yuki Keiser2008)。レズビアンが悩まないとでも思っているのだろうか。性的マイノリティに対する歪んだ思い込みに基づく安易なドラマ設定があったことがわかる。
「FtMとレズビアンの間」の「グレーゾーン」を描こうとした脚本家の意図が視聴者に伝わったとは思えない。むしろ、瑠可のような、女の子が好きな男っぽい女性は、性同一性障害(FtM)という病気で、メンタルクリニックに通院する必要がある、という誤った情報が視聴者に与えられた可能性が高いと思う。
そうであるならば、このドラマはレズビアンを隠蔽しただけでなく、FtMの性同一性障害のイメージをも歪めて流布し、現実世界に誤った印象・知識を与えたミスリードの事例ということになる。
実際、『ラスト・フレンズ』の放送があった2008年以降、全国のジェンダー・クリニックで10代~20代の若い女性の受診者が急増したことが報告されている。それについては第7節で詳しく述べるが、そこに「ラスフレを見て、自分もそうだと確信しました」というようなミスリードが作用している可能性は十分に考えられる。
5 1990年代以降のレズビアンをめぐる動向
1990年代になると欧米のゲイ・レボリューションの波がようやく日本にも到達する。そうした中で1992年に出版された掛札悠子『「レズビアン」である、ということ』(掛札1992)は、長らく沈黙を強いられてきたレズビアンが初めて堂々と自らの生き方を語ったものとして画期的なものだった。
しかし、それによってレズビアンを取り巻く状況が大きく改善されたかといえば、必ずしもそうとは言えない。掛札に続いてカミングアウトした人は少なく(笹野1995、池田1999)、掛札自身が筆を折ってしまったこともあり、レズビアン・ムーブメントは90年代末に始まる「性同一性障害」の大流行の波に埋もれてしまう(杉浦2010b)。
1990年代末から2000年代前半にマス・メディアによって流布された「性同一性障害」についての情報量は、同性愛のそれと比較できないほど多かった。同性愛の中でも、ゲイはすでに独自のコミュニティを確立し、専門の商業雑誌をもっていたが、コミュニティの規模が小さく商業雑誌がなかなか続かないレズビアンの情報量はさらに少なかった。インターネット時代になって若干改善されたものの、まだ十分と言うには程遠い。
一方、レズビアンの学術的研究としては、性意識調査グループ編の『310人の性意識―異性愛者ではない女たちのアンケート調査』(性意識調査1998)や、中央大学の矢島正見研究室がまとめた『女性同性愛者のライフヒストリー』(矢島1999)がひとつの方向性を示している。それは、ともかくレズビアンの話を聞き記録することで、その存在を顕在化することである。隠蔽されてきた日本のレズビアンを学問的な舞台に載せたという意味で、両書の意味は大きかったと思う。
しかし、同性愛の学術研究全体でみると、杉浦郁子や堀江有里の仕事はあるものの、まだまだ男性主導でアンバランスであることは否めない。たとえば、2010年に岩波書店から出版された風間孝・河口和也『同性愛と異性愛』は、同性愛の当事者が同性愛を書名に掲げて専論した初めての新書として注目されたが、共著者が当事者でないことを理由にレズビアンについてはほとんど触れていない。当事者主義にこだわるのなら、レズビアンの執筆者を招いて章を設けるべきだし、それができないのならば、書名は『男性同性愛と異性愛』にすべきだろう。書名に「同性愛」と銘打ちながらレズビアンについてほとんど記述をしないのは、単にアンバランスなだけでなく、レズビアンの疎外であり、結果的にレズビアンの隠蔽に加担していると言えなくもない。『同性愛と異性愛』という書名にひかれて手に取ったレズビアンが目次を通覧した時の疎外感と落胆を著者や編集者は想像しただろうか。
同性愛者の歴史的な歩みや現在直面している問題が、いつの間にか男性同性愛者(ゲイ)のそれにすり替えられてしまう現象は、この本だけではないように思う。
2005年、大阪府議会議員だった尾辻かな子がレズビアンであることをカミングアウトした(尾辻)。尾辻は2007年の参議院選挙(比例区)に民主党公認として立候補したものの当選ラインに遠く及ばず落選したが、2013年5月、繰り上げ当選によって参議院議員(民主党)となった。任期が僅か一カ月余だったこともあり、残念ながら十分な実績は残せなかったが、尾辻が日本初の性的マイノリティであることを公言した国会議員であることはまぎれもない事実である。
しかし、東京都豊島区議会議員で男性同性愛者(ゲイ)であることを公表している石川大我が2014年の衆議院総選挙で社会民主党の東京比例区名簿1位に登載されると、複数のネット・メディアが「日本初の同性愛者の国会議員を目指す」と報じ、尾辻の存在は「なかったこと」にされた。無知と言えばそれまでだが、石川事務所も「日本初のオープンリーゲイの国会議員」を目指すことをプロフィールに記していて、「日本初のオープンリー同性愛者国会議員」である尾辻への配慮に欠けていたことは否めない。
2000年代後半になると、レズビアン関係の出版も徐々に増えていく(堀江2006、飯野2008、牧村2013)。2013年には世界的な同性婚承認の流れの中で、レズビアン・カップルの東京ディズニーランドでの挙式が話題になった(東小雪+増原裕子2014)。
しかし、レズビアンの存在が日本社会の中で十分に認知され、レズビアンに関する情報が十分に流通し、レズビアンを取り巻く様々な困難な状況について地に足が着いた議論がなされる状況には、残念ながら至っていない。
6 レズビアン・ロールモデルの不在
レズビアンをめぐる現状を考えたとき、情報量の不足もだが、最大の問題はレズビアンのロールモデルの不在だと思う。その原因は、テレビをはじめとするマス・メディアがレズビアンの存在を徹底的に隠蔽してきたことにある。
2010年代になってさえ、日本のマス・メディアは「レズビアン疑惑」という言い方をしてはばからない。「疑惑」という言葉は「覚醒剤使用疑惑」など社会的に問題のある行為を疑う言葉だ。いったいなぜレズビアンであることが問題行為なのだろう。そうした「疑惑」をかけられた女優、女性歌手あるいは女性タレントは、必死に「疑惑」を否定しようとする。本人が沈黙していても事務所が否定に動く。なぜなら、現在の日本のテレビ業界では「レズビアン」であることは仕事を失うことにつながりかねず、デメリットが大きいからだ。その点で、レズビアンをカミングアウトした女優や女性アーティストが活躍する欧米と著しい違いがある。佐良直美事件の呪縛は30年以上たってもまだ解けていないのだ。
なぜ、これほどまでにテレビ・メディアはレズビアンの存在を忌避するのだろうか。その理由を端的に指摘すれば、すべての女性は男性の性的視線を受け止める存在でなければならないという、男性中心のヘテロセクシュアル原理がいまだに貫徹しているのがテレビ業界だということだ。そうした姿勢の背景にはスポンサーとしてテレビ番組を支えている日本の企業社会の男性中心のヘテロセクシャリズムがある。
このように、マス・メディアの隠蔽姿勢がレズビアンのvisibility(目に見えること)を著しく低下させ、魅力的なレズビアン・ロールモデルの出現を阻んでいる。そして、レズビアン・ロールモデルの不在が、レズビアンの自己肯定をいっそう困難にしている。
ところで、レストランでメニューにない料理を注文できる人はごく少ない。ほとんどの人はメニューの中から料理を選ぶ。それと同じで、人は目の前に並んでいる概念にしかアイデンティファイ(カテゴリーへの同一化)できない。私はこれを「メニュー理論」と言っている。
たとえば、20代の私の前に置かれていたメニューには、トランスジェンダーも性同一性障害も無く、ゲイボーイという概念しかなかった。「これは違う」と思ったから、それをつかまなかった。アマチュアの女装者という概念があることを知ったのは30代の初めで、やっとその言葉をつかむことができたが、トランスジェンダーという言葉を知って最終的にアイデンティファイできたのは40歳を過ぎてからだった。
レズビアンを抑圧し、存在を隠蔽してきた結果、レズビアンのロールモデルが提示されず、逆に性同一性障害(FtM)の情報が多く流布されている現状は、メニューに「今月のおすすめ」として「性同一性障害(FtM)」と大書されているのに対し、「レズビアン」は見えるか見えないかの小さい文字でしか書かれていない状態にたとえられる。自分の性的指向(Sexual Orientation)が典型的でないことに気づいた女性がメニューを見たとき、本来ならつかむべきレズビアンではなく、性同一性障害(FtM)をつかんでしまうのも無理からぬ状況がそこにある。
7 なぜ日本はFtM(Female to Male)が多いのか?
性同一性障害の性別比、つまりMtFとFtMの比率は、世界標準的には、2対1くらいでMtFが多いとされている。日本では1990年代末から2000年代中頃までは、MtFがやや多い状態からMtFとFtMの比率が拮抗する状況へと緩やかに推移していた。ところが、2008年以降、全国の複数の病院、クリニックで、若年(10代後半~20代前半)FtMの受診者が急増し、世界標準とは逆に、ほぼ1対2の比率でFtMの受診者が多くなった(2009年2月の第11回GID学会での報告。「関西医大病院ジェンダー・クリニック」MtF134、FtM270=33対67、「札幌医大GIDクリニック」MtF94、FtM220=30対70、「はりまメンタルクリニック」MtF229、FtM409=36対64)。
かつて私は、この現象をテレビドラマ『ラスト・フレンズ』の影響で、本来は、男性っぽいレズビアンの範疇でおさまるはずの(瑠可のような)女性が、性同一性障害(FtM)と自己認識して、ジェンダー・クリニックを受診している結果ではないかと考えていた。しかし、その後もFtMの増加傾向は止まらず、現在では1対3からさらに1対4に近づく状態になっている。
FtMの増加傾向は、受診者レベルではなく、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(GID特例法)」による戸籍の性別変更においても著しい。全国の家庭裁判所に提出される戸籍変更の診断書の約15%を書いている(2012~2014年平均)針間克己医師(はりまメンタルクリニック)によれば、2012年から2015年の戸籍変更診断書の累計はMtF119、FtM464≒1対4だった(「Anno job Log」2015年12月27日 http://d.hatena.ne.jp/annojo/20151227)。日本は世界で最も、そして格段にFtMの比率が高い国になっている。
こうなると、テレビドラマの影響だけとは言えず、それをきっかけとした、もっと大きな構造的な原因があると考えなければならない。生得的な体質、遺伝子的に日本人の女性がFtMになりやすいということはなさそうなので、その原因は社会的なものと考えられる。
そこで考えなければならないのは、世界標準より多い分のFtMがどこから来ているのか?ということだ。その際、ヘテロセクシュアルの女性がFtM化するということは考えにくい。女性に課せられた社会的制約から脱するために男装する女性は過去にはいたが、現代の日本は一般論的に言って女性が男体化しなければ社会活動が難しい状況にはない。また性的指向が男性に向かっているヘテロセクシュアルの女性がFtM化した場合、セクシュアリティ的なメリットはほとんどない。ゲイ男性はヘテロ男性よりずっと少ないからだ。
それに対して、レズビアンがFtM化しているという想定の方がずっと考えやすい。レズビアンがFtM化すれば、性愛対象のヘテロ女性はレズビアン女性よりずっと多いから、ターゲットはぐっと広がる。なにより戸籍の性別を男性に変更すれば、法的に女性と結婚できる。同性婚が法的に許可される見通しが立たない日本では、生得的な女性が女性と法的に婚姻するには、一方の女性がFtMの性同一性障害者として「GID特例法」によって、戸籍の性別を変更するのが唯一の方法だからだ。
このように考えると、日本におけるFtMの増加分はレズビアンからの流入を想定するのが、いちばん蓋然性が高いと思う。その原因として、前節で述べたような、自分の性的指向が典型的でないことに気づいた女性が本来ならアイデンティファイすべきレズビアンではなく、性同一性障害(FtM)として自己認識してしまう状況が存在し、さらに「GID特例法」による一種の「誘導」が作用していると考えられる。
次に考慮すべきは、レズビアンとFtMの比率である。本来、レズビアンは100人に数人いると考えるのが一般的だ。それに対して日本のFtMは10000人に数人と考えられる。つまり両者の人数は本来100倍ほども違う。ということは、レズビアンの1%がFtMに流入すればFtMは本来の数の倍になるし、2%流入すれば3倍に、9%が流入すれば10倍になる。このようにレズビアンからの流入モデルを考えることで、日本で世界標準よりFtMが著しく多い理由を容易に説明することができる。
ところで、レズビアンからFtMへという流入現象がかなりあると想定した場合、ゲイからMtFへの流入はそれに比してなぜ少ないのかという疑問が生じる。この点については次のように説明できると思う。
日本において、ゲイ・コミュニティとMtFのコミュニティは、性同一性障害概念が流布する1990年代後半以前に、すでにかなり明確に分離していた。その分離の時期は1970~1980年代と考えられる(三橋2008)。だから、性同一性障害概念はMtFだけに影響を与え、ゲイにはほとんど影響が及ばなかった(まったく流入がないわけではないが)。それに対して、レズビアン・コミュニティとFtMのコミュニティは分離が進まず混在した状態だったところに、性同一性障害概念が流布した。その結果、本来、性同一性障害概念の影響を受ける必要のないレズビアンにまでその影響が及んでしまい、混乱と流入が起こってしまったと考えられる。そして、レズビアン・コミュニティとFtMのコミュニティの未分離の原因にはレズビアンの隠蔽による情報不足がある。
非典型な性をもつ人たちがどのようにカテゴライズされ、自らをアイデンティファイしていくかは、今まで言われてきたほど固定的ではなく、与えられる情報によってかなり流動的であると私は考える。それゆえに、適切なアイデンティファイをするためには隠蔽や歪曲がない正しい情報提供、つまり、自分にふさわしい料理を選べる「メニュー」が必要なのである。
おわりに
ある年度、「ジェンダー論」の講義の単位レポートに、レズビアンであることの辛い思いを切々と記してきた学生がいた。好きな相手からもレズビアンの存在そのものを否定され、周囲の偏見の中で自己否定感にさいなまれる。なぜ、女性として女性が好きなだけでこんなに苦しまなければならないのか、単位レポートだから冷静に読んで評価しなければいけないのだが、「今まで書いてきたことはすべて事実です。でも、誰にも話したことはありません。やっとレポートという形ですが書くことができて、私は幸せです、ありがとうございました」という結びの文章を読んで、涙が流れるのを抑えることができなかった。
一方では、女性を愛するためには自分が男にならなければならないと思い込み、短命化の可能性が高い男性ホルモンを過剰に摂取し、身体にメスを入れて乳房、子宮・卵巣を摘出し、高額な費用をかけて(トラブルが多く機能的にも不十分な)擬似男性器を形成する人たちがいる。無惨な傷跡が残る症例写真を見るたびに、レズビアンの範疇に収まるのなら、その方がずっと身体リスクは少ないのに、なぜこんなことまでしなければならないのかと考えてしまう。
女性として女性を愛する女性たちが、適切な自己認識を形成するためには、レズビアンが隠蔽されることなく、レズビアンに関する情報が十分に流通し、女性として女性を愛する多様なロールモデルが社会の中で存在することが必要だと思う。さらに言えば、女性を愛する女性がレズビアンでなくFtMを選択する背景には、日本社会における女性の根本的な生きにくさが存在する。性的マイノリティだけの問題では済まないことを、性的マジョリティの人たちにも知って欲しいと思う。
文献
赤枝香奈子2011『近代日本における女同士の親密な関係』(角川学芸出版)
飯野由里子2008『レズビアンである〈わたしたち〉のストーリー』(生活書院)
池田久美子1999『先生のレズビアン宣言―つながるためのカムアウト』(かもがわ出版)
尾辻かな子2005『カミングアウト〜自分らしさを見つける旅』(講談社)
掛札悠子1992『「レズビアン」である、ということ』(河出書房新社)
風間孝・河口和也2010『同性愛と異性愛』(岩波新書)
桑谷定逸1911「戦慄す可き女性間の顚倒性慾」(『新公論』明治44年9月号)
小峰茂之・南孝夫1985『同性愛と同性心中の研究』(小峰研究所)
笹野みちる1995『Coming OUT!』(幻冬舎)
白倉敬彦2002『江戸の春画―それはポルノだったのか―』(洋泉社新書)
菅 聡子2006「女性同士の絆―近代日本の女性同性愛―」(『国文』106号)
杉浦郁子2006「1970、80年代の一般雑誌における『レズビアン』表象――レズビアンフェミニスト言説の登場まで」(矢島正見編著『戦後日本女装・同性愛研究』(中央大学出版部)
杉浦郁子2008「日本におけるレズビアン・フェミニズムの活動 -1970年代後半の黎明期における」 (『ジェンダー研究』11号)
杉浦郁子2010a「『レズビアン』の概念史――戦後、大衆娯楽雑誌における」(中村桃子編『ジェンダーで学ぶ言語学』世界思想社)
杉浦郁子2010b「レズビアンの欲望/主体/排除を不可視化する社会について―現代日本におけるレズビアン差別の特徴と現状―」(シリーズ「現代の差別と排除」第6巻『セクシュアリティ』明石書店)
性意識調査グループ編1998『310人の性意識―異性愛者ではない女たちのアンケート調査』(七つ森書館)
田中優子2004『張形と江戸をんな』(洋泉社新書)
東 小雪+増原裕子2014『レズビアン的結婚生活』(イースト・プレス)
肥留間由紀子2003「近代日本における女性同性愛の『発見』」(『解放社会学研究』17号)
古川 誠1994「セクシュアリティの変容:近代日本の同性愛をめぐる3つのコード」(『日米女性ジャーナル』17号)
堀江有里2006『「レズビアン」という生き方―キリスト教の異性愛主義を問う』(新教出版社)
堀江有里2015『レズビアン・アイデンティティーズ』(洛北出版)
牧村朝子2013『百合のリアル』(星海社新書)
三橋順子2008『女装と日本人』(講談社現代新書)
三橋順子2013「性と愛のはざま-近代的ジェンダー・セクシュアリティ観を疑う-」(『講座 日本の思想 第5巻 身と心』岩波書店)
三橋順子2015a「『台記』に見る藤原頼長のセクシュアリティの再検討」(倉本一宏編『日記・古記録の世界』思文閣出版)
三橋順子2015b「歴史の中の多様な『性』」(『アステイオン』83号 CCCメディアハウス)
矢島正見編著1999『女性同性愛者のライフヒストリー』(学文社)
Yuki Keiser2008「『ラスト・フレンズ』の脚本家・浅野妙子さんのインタビュー」
http://www.tokyowrestling.com/articles/2008/06/last_friends_3.html
【付記1】入稿後、杉浦郁子「『女性同性愛』言説をめぐる歴史的研究の展開と課題 」(『和光大学現代人間学部紀要』8号 2015年)に接した。本稿と関わるところ大であるが、内容に反映することができなかった。
【付記2】最終的な入稿(2015年2月)の直後、東京都渋谷区の「同性パートナー証明書」発行の条例化(2015年3月31日可決、11月5日実施)問題が浮上し、それをきっかけに「LGBTブーム」が一気に盛り上がり、マス・メディアにおけるレズビアンを含む同性愛関係報道が激増した。その結果、レズビアンのvisibilityは向上したように思われる。しかし、「LGBTブーム」の中で注目されているのは、裕福で、容姿に優れ、社会的地位のある「シャイニー(shiny)」な特定のレズビアンであり、一般のレズビアンが抱えるさまざまな生活の困難を改善していく視点は、まったく不十分である。これはブームの発端が政治的思惑(統一地方選挙)や経済的期待(LGBT消費需要)であり、必ずしも人権的観点でなかったためと思われる。今後、LGBTの人権擁護の論議が深まる中で、本当の意味でのレズビアンの社会的顕在化と生活改善がなされることを期待したい。



