【書評③】パトリック・カリフィア『 セックス・チェンジズ -トランスジェンダーの政治学-』 [書評アーカイブ]
パトリック・カリフィア著(石倉 由・吉池 祥子翻訳) 『 セックス・チェンジズ -トランスジェンダーの政治学-』(作品社、2005年7月)の書評。
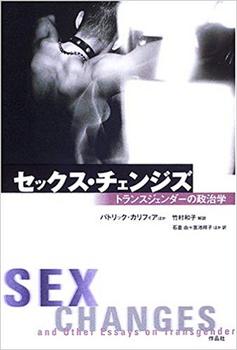
『図書新聞』(図書新聞社)2005年10月8日(2745号)に掲載。
-----------------------------------------------------------------
人が生まれもった性別を人生の途中で「変える」ということは簡単なことではない。本人のとって難事なだけでなく、家族やパートナーなどの親しい人々や取り巻く社会関係(職場・学校・友人など)にも大きな影響を与える。性別移行とはそれだけ壮大な試みなのである。
新しい性別で社会を生きていこうとする時、望みの性別を生きる幸福と同時に、まともな批判力をもった人ならば、今まで気づかなかった性別に伴うさまざまな社会的抑圧や障壁を実感することになる。それは、一つの性別しか生きない人たちには経験できない、性別という視点から人と社会への認識を深める上できわめて有益な体験であると、私は思う。
本書は、アメリカの思想家・アクティビスト、パトリック・カリフィアの論集『Sex changes and Other Essays on Transgender』(1997年初版、2003年第2版)の邦訳である。カリフィアはレズビアンSMフェミニストとして、1980年代から検閲に反対しポルノやセックス・ワークを擁護する立場で論陣を張ってきた人である。本書の初版執筆時にはレズビアンの立場を取っていたが、第2版刊行までの間に男性ホルモンを服用して男性アイデンティティに移行した。
第2版序文に始まる序論と8つの章は、それぞれが十分に読みごたえのある分量と内容になっている。ジェンダー・アイデンティの多様性の承認を求め、社会的性役割の基準概念に異を唱えるカリフィア主張は一見ラディカルである。しかし、アメリカ最初の「性転換者」であるクリスチーナ・ヨルゲンセンとイギリスの著名なジャーナリストで女性に転換したジャン・モリスの自伝などを比較分析した第1章「トランスセクシュアルの自伝」、ハリー・ベンジャミンやジョン・マネーら「性転換」の科学的権威たちの業績を批判的に検証した第2章「父親的存在」などは、きわめて分析で学究的ですらある。
続く、1979年に始まるレズビアン・フェミニストによるトランスセクシュアルへの激しい攻撃と排除運動を振り返った第3章「バックラッシュ」、欧米社会のゲイパラダイムから非欧米社会や前近代社会の第3ジェンダーを見ることの問題点を指摘した第4章「ベルダーシュ戦争と『パッシング・ウーマン』の愚行」、男性から女性に転換して全米女子テニス選手権の予選を勝ち上がったレニー・リチャーズらの語りをヨルゲンセンらの自伝と比較した第5章「現代トランスセクシュアルの自伝」、ほとんど存在を無視されてきたトランスジェンダーのパートナーに照明をあてた第6章「見えないジェンダー・アウトロー」などでも、こうした冷静な筆致に変わりはなく、本書の説得力を高めている。
トランスフォビックな社会に対してトランスジェンダーがどのような実力行使をしたかを紹介する第7章「クリニックを打ち壊し、ビューティ・パーラーを焼き払う」、今なお続く医療者やフェミニストとの軋轢の中でトランスジェンダー行動主義の今後を考える第8章「ジェンダーとトランスジェンダリズムの未来」など、1950年代から現代までの半世紀余の間に、アメリカのトランスジェンダーをめぐって、どのような議論が展開され、何が為されたかを丹念に掘り返し再検討しており、まさに「トランスジェンダーの政治学」という副題にふさわしい内容になっている。それはまた、性別をめぐるアメリカ社会の現代史としても高い資料性をもっている。
こうした豊かな内容をもつ著作を、翻訳者の石倉由と吉池祥子が、複雑な専門用語を丹念に日本語に置き換え、関係部分だけで500頁に近い分量であるにもかかわらず、読みやすいものにしている。特に文中に挿入されている用語解説は的確で、類書の水準を抜いている。
また、本書の特色のひとつは、付載されている論考の充実である。野宮亜紀の「日本における『性同一性障害』をめぐる動きとトランスジェンダーの当事者運動」を収録したことは、この種の翻訳本が日本の状況を無視する傾向が強い中にあって貴重な試みであり、本書を単なる外国思想の紹介に終わらせたくないという訳者たちの意志が伝わってくる。石倉の「訳者あとがき」も短文ながら、男女二元制への「同化主義」と、第三極としての「トランスジェンダー派」との深刻な対立という日本のトランスジェンダーの問題点をしっかり把握し、その相対化をはかることで解決への道筋を示している。
巻末に解説として付されている竹村和子「『セックス・チェンジズ』は、性転換でも、性別適合でもない」は、今までなぜか少なかった日本のフェミニストのトランスセクシュアル(TS)に対する評論として注目される。「TSを性の二分法のなかに閉じこめること、TSの問題をTSだけの問題として扱うことは」、TSを「再差別化し」、TSが「社会に対して投げかけている問題系をふたたび閉じてしまうことになる」という指摘は、常に当事者を中心とした閉じた系で問題処理がはかられてきた日本の現状を考えた時、たいへん示唆的である。
1996年ごろに始まる日本における「性同一性障害」問題の展開の中で、もっとも欠けていたのは、そもそも性別を変えるとはどういうことなのか、社会の中で性別を変えて生きるということはどういうことなのかという議論だったと思う。議論が当事者とそれに直接かかわった専門家(一部の医師や法学者)という狭い範囲で行われ、問題関心が身体(性器の外形)を外科的手術で変える段取りと、戸籍の続柄(性別)を変更する方法に集中してしまった感がある。
つまり、ジェンダー(社会的性別)の視点がほとんど欠落しており、本書でカリフィアが行っているような性別移行と社会についての本質的な論議がほとんど存在しなかったと言ってよい。 結果として、性器や戸籍を変えることなく社会的性別を移行したい人や、性別を変える当事者の家族の問題、さらには性別を変えた人を受け入れる社会の側の問題などが置き去りにされてしまった。
また、医療体制の拡充や法的整備が進んだ反面、当事者の間に医療依存ともいうべき状況が生まれている。性別の移行は本人の自己決定によってなされるべきもので、医療はそれをサポートし技術的サービスを提供するはずなのに、医師の承認がなければ性別移行はできない、だから医師の言うことを聞いて早く許可をもらおう、というような他者決定的な認識が広がってしまった。
政府や行政も、性別を移行して生きようとする人を「性同一性障害」という「障害者」として囲い込み、医療福祉的な見地から特例的に対処すればよいという認識しかなく、そこに性的少数者の人権という観点はきわめて希薄である。
ところで、本書の解説で竹村は「TS」という表記・概念を使っているが、実は現在、日本にはTSを自称する人はほとんどいなくなってしまった。かってTSをアイデンティティにしていた人たちの多くは「性同一性障害者」を称するようになってしまったからだ。
国際学会に出席すると、外国の研究者はトランスジェンダー(TG)/トランスセクシュアル(TS)という言葉を使っている。「性同一性障害」という言葉を聞くことは稀である。ところが、日本では「性同一性障害」という精神疾患カテゴリー名称が、医学の世界だけでなく、マスコミを通じて一般社会でも、TGやTSに比して圧倒的なシェアをもってしまった。こうした「性同一性障害」という医学用語が突出した日本の現状は、欧米だけでなくアジア諸国の状況と比較しても、実はかなり特異なのである。
そうした点で、本書で「セックス・チェンジ」「トランスジェンダー」と言っても、「それは誰のこと? 性同一性障害のことなら知っているけど」と思われてしまう危険性はある。しかし、性別の移行に関する世界の新しい潮流は、性器形成至上主義や、男・女どちらかに組み込めばそれで問題は解決するという従来の考え方を次第に過去のものにしようとしている。性別を移行して生きることは、「病気」ではなく、人権に根差した生き方の選択の問題であるという認識が一般化する時代がやがて来ると信じたい。日本の現状はそうした世界的な動きと未だ遠いところにあるが、状況を改善していくヒントは、本書におけるカリフィアの主張の中に数多く散りばめられている。
本書が性別の移行をめざす当事者と、それにかかわる専門家、そして「性別」という問題に関心をもつ多くの人たちに広く読まれることを、当事者の一人として願ってやまない。
(国際日本文化研究センター共同研究員・お茶の水女子大学非常勤講師)
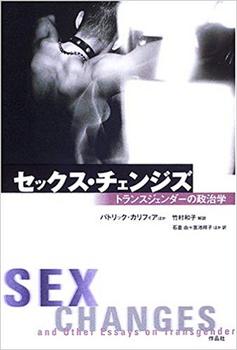
『図書新聞』(図書新聞社)2005年10月8日(2745号)に掲載。
-----------------------------------------------------------------
人が生まれもった性別を人生の途中で「変える」ということは簡単なことではない。本人のとって難事なだけでなく、家族やパートナーなどの親しい人々や取り巻く社会関係(職場・学校・友人など)にも大きな影響を与える。性別移行とはそれだけ壮大な試みなのである。
新しい性別で社会を生きていこうとする時、望みの性別を生きる幸福と同時に、まともな批判力をもった人ならば、今まで気づかなかった性別に伴うさまざまな社会的抑圧や障壁を実感することになる。それは、一つの性別しか生きない人たちには経験できない、性別という視点から人と社会への認識を深める上できわめて有益な体験であると、私は思う。
本書は、アメリカの思想家・アクティビスト、パトリック・カリフィアの論集『Sex changes and Other Essays on Transgender』(1997年初版、2003年第2版)の邦訳である。カリフィアはレズビアンSMフェミニストとして、1980年代から検閲に反対しポルノやセックス・ワークを擁護する立場で論陣を張ってきた人である。本書の初版執筆時にはレズビアンの立場を取っていたが、第2版刊行までの間に男性ホルモンを服用して男性アイデンティティに移行した。
第2版序文に始まる序論と8つの章は、それぞれが十分に読みごたえのある分量と内容になっている。ジェンダー・アイデンティの多様性の承認を求め、社会的性役割の基準概念に異を唱えるカリフィア主張は一見ラディカルである。しかし、アメリカ最初の「性転換者」であるクリスチーナ・ヨルゲンセンとイギリスの著名なジャーナリストで女性に転換したジャン・モリスの自伝などを比較分析した第1章「トランスセクシュアルの自伝」、ハリー・ベンジャミンやジョン・マネーら「性転換」の科学的権威たちの業績を批判的に検証した第2章「父親的存在」などは、きわめて分析で学究的ですらある。
続く、1979年に始まるレズビアン・フェミニストによるトランスセクシュアルへの激しい攻撃と排除運動を振り返った第3章「バックラッシュ」、欧米社会のゲイパラダイムから非欧米社会や前近代社会の第3ジェンダーを見ることの問題点を指摘した第4章「ベルダーシュ戦争と『パッシング・ウーマン』の愚行」、男性から女性に転換して全米女子テニス選手権の予選を勝ち上がったレニー・リチャーズらの語りをヨルゲンセンらの自伝と比較した第5章「現代トランスセクシュアルの自伝」、ほとんど存在を無視されてきたトランスジェンダーのパートナーに照明をあてた第6章「見えないジェンダー・アウトロー」などでも、こうした冷静な筆致に変わりはなく、本書の説得力を高めている。
トランスフォビックな社会に対してトランスジェンダーがどのような実力行使をしたかを紹介する第7章「クリニックを打ち壊し、ビューティ・パーラーを焼き払う」、今なお続く医療者やフェミニストとの軋轢の中でトランスジェンダー行動主義の今後を考える第8章「ジェンダーとトランスジェンダリズムの未来」など、1950年代から現代までの半世紀余の間に、アメリカのトランスジェンダーをめぐって、どのような議論が展開され、何が為されたかを丹念に掘り返し再検討しており、まさに「トランスジェンダーの政治学」という副題にふさわしい内容になっている。それはまた、性別をめぐるアメリカ社会の現代史としても高い資料性をもっている。
こうした豊かな内容をもつ著作を、翻訳者の石倉由と吉池祥子が、複雑な専門用語を丹念に日本語に置き換え、関係部分だけで500頁に近い分量であるにもかかわらず、読みやすいものにしている。特に文中に挿入されている用語解説は的確で、類書の水準を抜いている。
また、本書の特色のひとつは、付載されている論考の充実である。野宮亜紀の「日本における『性同一性障害』をめぐる動きとトランスジェンダーの当事者運動」を収録したことは、この種の翻訳本が日本の状況を無視する傾向が強い中にあって貴重な試みであり、本書を単なる外国思想の紹介に終わらせたくないという訳者たちの意志が伝わってくる。石倉の「訳者あとがき」も短文ながら、男女二元制への「同化主義」と、第三極としての「トランスジェンダー派」との深刻な対立という日本のトランスジェンダーの問題点をしっかり把握し、その相対化をはかることで解決への道筋を示している。
巻末に解説として付されている竹村和子「『セックス・チェンジズ』は、性転換でも、性別適合でもない」は、今までなぜか少なかった日本のフェミニストのトランスセクシュアル(TS)に対する評論として注目される。「TSを性の二分法のなかに閉じこめること、TSの問題をTSだけの問題として扱うことは」、TSを「再差別化し」、TSが「社会に対して投げかけている問題系をふたたび閉じてしまうことになる」という指摘は、常に当事者を中心とした閉じた系で問題処理がはかられてきた日本の現状を考えた時、たいへん示唆的である。
1996年ごろに始まる日本における「性同一性障害」問題の展開の中で、もっとも欠けていたのは、そもそも性別を変えるとはどういうことなのか、社会の中で性別を変えて生きるということはどういうことなのかという議論だったと思う。議論が当事者とそれに直接かかわった専門家(一部の医師や法学者)という狭い範囲で行われ、問題関心が身体(性器の外形)を外科的手術で変える段取りと、戸籍の続柄(性別)を変更する方法に集中してしまった感がある。
つまり、ジェンダー(社会的性別)の視点がほとんど欠落しており、本書でカリフィアが行っているような性別移行と社会についての本質的な論議がほとんど存在しなかったと言ってよい。 結果として、性器や戸籍を変えることなく社会的性別を移行したい人や、性別を変える当事者の家族の問題、さらには性別を変えた人を受け入れる社会の側の問題などが置き去りにされてしまった。
また、医療体制の拡充や法的整備が進んだ反面、当事者の間に医療依存ともいうべき状況が生まれている。性別の移行は本人の自己決定によってなされるべきもので、医療はそれをサポートし技術的サービスを提供するはずなのに、医師の承認がなければ性別移行はできない、だから医師の言うことを聞いて早く許可をもらおう、というような他者決定的な認識が広がってしまった。
政府や行政も、性別を移行して生きようとする人を「性同一性障害」という「障害者」として囲い込み、医療福祉的な見地から特例的に対処すればよいという認識しかなく、そこに性的少数者の人権という観点はきわめて希薄である。
ところで、本書の解説で竹村は「TS」という表記・概念を使っているが、実は現在、日本にはTSを自称する人はほとんどいなくなってしまった。かってTSをアイデンティティにしていた人たちの多くは「性同一性障害者」を称するようになってしまったからだ。
国際学会に出席すると、外国の研究者はトランスジェンダー(TG)/トランスセクシュアル(TS)という言葉を使っている。「性同一性障害」という言葉を聞くことは稀である。ところが、日本では「性同一性障害」という精神疾患カテゴリー名称が、医学の世界だけでなく、マスコミを通じて一般社会でも、TGやTSに比して圧倒的なシェアをもってしまった。こうした「性同一性障害」という医学用語が突出した日本の現状は、欧米だけでなくアジア諸国の状況と比較しても、実はかなり特異なのである。
そうした点で、本書で「セックス・チェンジ」「トランスジェンダー」と言っても、「それは誰のこと? 性同一性障害のことなら知っているけど」と思われてしまう危険性はある。しかし、性別の移行に関する世界の新しい潮流は、性器形成至上主義や、男・女どちらかに組み込めばそれで問題は解決するという従来の考え方を次第に過去のものにしようとしている。性別を移行して生きることは、「病気」ではなく、人権に根差した生き方の選択の問題であるという認識が一般化する時代がやがて来ると信じたい。日本の現状はそうした世界的な動きと未だ遠いところにあるが、状況を改善していくヒントは、本書におけるカリフィアの主張の中に数多く散りばめられている。
本書が性別の移行をめざす当事者と、それにかかわる専門家、そして「性別」という問題に関心をもつ多くの人たちに広く読まれることを、当事者の一人として願ってやまない。
(国際日本文化研究センター共同研究員・お茶の水女子大学非常勤講師)
2018-10-05 02:22
nice!(0)
コメント(0)




コメント 0