【インタビュー】「わたしの光になった表現」(聞き手:外山雄太) [論文・講演アーカイブ]
集英社の文芸誌『すばる』2016年8月号は「特集・LGBT-海の向こうから-」。

虹色の表紙が目印。
インタビュー記事「わたしの光になった表現」(聞き手:外山雄太)は、牧村朝子・杉山文野・中村キヨ・マーガレット・田亀源五郎・橋口亮輔という豪華なメンバーが「人生の大切な局面をともにした三つの作品」を語る。
その他、海外のLGBT関係の評論・エッセイ8本を掲載。
東京の主要書店では、7月6日発売(税込950円)。
インタビューは、5月31日(火)。
明治大学(駿河台)での講義の後、17時少し前、神田神保町三丁目の「集英社」へ。
インタビュアーは外山雄太さん。
昨年3月、『朝日新聞』の原田朱美記者の紹介で知り合った方。
ご縁が形になってうれしい。
最初に撮影。
簡単な撮影かと思ったら、ちゃんとプロのカメラマンが待機していて、まず室内で、さらに、屋外に出て撮影。
着物、着てきてよかった。

↑ 撮影:隼田大輔氏
その後、2時間半ほど、「わたしの光となった表現」というテーマであれこれしゃべる。
まず、1980年代までに青年期を過ごした私の世代は、そもそも世の中に性別越境についての情報が乏しく、それを見つける(実際には、偶然、出会う)ことがたいへんだったことを話す。
「性別違和」という自分の状況を説明する言葉も、「性同一性障害」という概念も日本には入っていなかった。
そんな状況の中で「自分を見つける」導きになった書籍として、
(1)存在への気づき、(2)「成りたい」自己イメージの形成、(3)自己肯定化の理論、という観点で3冊を挙げた。
----------------------------
今回、豪華なメンバーの驥尾に付して出していただいたが、いろいろな意味で、トランスジェンダーとしての私の社会的な役割は終わったのかなと思う、今日この頃。
たくさんの方に「まだまだ」と言っていただけるのは励みにはなるけど、もう表舞台に出るのは心身ともに辛くなってきた。
あと何年生きられるかわからないが、残りの人生は研究生活、とりわけ、自分の著述のまとめに専念しようと思う。
『すばる』は創刊(1970年)から数年間、高校生の頃に購読していた思い出のある雑誌で、そこに出られたのは、そういう意味で良い記念になった。
-----------------------------------------------------
わたしの光となった表現
「あなたはどのような表現に影響を受け、また、支えられてきましたか?」
セクシュアリティー/世代/職業の異なる七名に、
人生の大切な局面をともにした三つの作品との出会いと、
その魅力についてうかがった。
探すものではなく、出会うもの
三橋順子
「二〇〇〇年、初めて大学の教壇に立った最初の講義の日、忘れもしません。週刊誌が三誌も取材に来たんです。日本で最初の、トランスジェンダーの大学教員。いったいそれ何? というまったく興味本位な反応でした」
三橋順子さんは、日本における性別越境、トランスジェンダーの社会・文化史研究家だ。歴史学的な手法で調査対象に取り組み、トランスジェンダーおよびセクシャルマイノリティーの歴史を探求してきた。
「自分が〝ふつう〟の男子と違うかも? と気づいたのは遅かったです。高校生のころ、おぼろげにそうかもしれない……と思ったくらいで、それ以前はとくになにも感じていませんでした。少なくとも、自分としては気づていないことになってました。のちのち専門の精神科医の先生にカウンセリングしてもらうと、どうも〝ふつう〟でない、記憶に蓋をしていたエピソードがたくさん出てきましたが。
自分のなかに別の人格がいて、それが女性だったと気づいたのは二十一歳のころ。性同一性障害とか、性別違和とか、そういう概念がない時代です。すてきな女性に対して、『付き合いたい』よりも、『ああいうふうになりたい』という気持ちを抱きました。
そんな自分が不可解で、図書館で精神分析学の本を読んだけど、答えは見つかりません。二十代後半が、自分がなぜこうなのか、よく分からず、つらかった時期でした。
そんな田舎から東京に出てきた青年が、いちばん最初に共鳴したのが『別冊SMスナイパー』一九八〇年十一月号に掲載されていた館淳一さんの「ナイロンの罠」という小説。一九八三年に単行本が刊行されますが、雑誌掲載時に読んで、これだ……! と思いました。自分の姉と義兄の手によって女性化されていく男子予備校生のお話。 女装の道に引き摺りこまれる美少年に自分を重ねたんですね。この作品は、二十五歳だったわたしのセクシュアル・ファンタジーの形成に多大な影響を与えました。三十数年後、著者の館淳一さんにお会いしたときは、大感激でした。

↑ 館 淳一『ナイロンの罠』(ミリオン出版 1983年)

↑ 初出の『別冊SMスナイパー』1980年11月号。
ほぼ時期を同じくして存在を知ったのが、土田ヒロミ撮影『青い花――東京ドール――』(世文社、一九八一年)でした。これは、一九七〇年代の東京のゲイボーイを主題にした写真集です。ゲイボーイというのは、当時は女装した男性のことを指しました。いまのゲイということばと、、八〇年代までのゲイとでは意味のズレがあるんです。
トランスジェンダー的な人物をテーマに撮影した日本初の写真集の存在は、スポーツ新聞で見て知っていましたが、当時二八〇〇円もする本なんて手が出ませんでした。あるとき、たまたま立ち寄った神保町の古本屋さんでめぐり会ったんです。店の前側には真面目な古本が、奥にSMやポルノ雑誌が置かれているような、お堅い本でエロをカムフラージュした本屋さんでした。そこで、『青い花』をやっと手に入れました。当時は、今のように情報が流通していませんから、こういった本は、探してもなかなか見つかるものではありません。存在が隠されているから探しようがなく、偶然出会うものだったんです。
写真集を見て、それまでぼんやりとしたイメージでしかなかった〝女装〟というものが、明確に可視化されました。「東京のどこかに、こうやって美しく着飾ったゲイボーイがいるんだ!」という強い実感。見えること、視覚的にイメージ化できることはそれだけ重要なんです。被写体になっていた〝お姉さん〟たちは、たぶん、赤坂、六本木あたりでお勤めの方々だったと思います。記載がないから、確かではないけれど。でも、自分と似たような感じの人がこれだけいるということを知って、なりたいわたしのイメージはより強固なものになっていきました」
.jpg)
-a7dc7.jpg)
↑ 土田ヒロミ撮影『青い花ー東京ドールー』(世文社 1981年)
しかし、そんなイメージを頼りに女装をし始めた八〇年代の終わりごろ、また別の問題が浮上したのだという。
「自己イメージは定まってきたけれど、それを言語化することがなかなかできませんでした。そんなときに出会ったのが、渡辺恒夫先生の『脱男性の時代――アンドロジナスを目指す文明学――』(勁草書房、一九八六年)でした。女装、性転換、アンドロジナス(両性具有)の世界を探求した評論集で、 女装者としての私の形成に際して、理論的な面で大きな影響を受けました。
評論として高く評価された『脱男性の時代』以外にも、二冊ほど同じような内容の本を書かれていて、『精神科治療か服装革命か』なんて、いまにも通じる問いを投じられました。〝トランスジェンダー〟というワードを書名にした日本最初の本の著者は、渡辺先生なんです(『トランス・ジェンダーの文化―異世界へ越境する知―』勁草書房、一九八九年)。
でも、その後はトランスジェンダーについては事実上、筆を折っちゃったんです。詳しい事情はよくわかりませんが、「おかしな研究をしている」というような社会的な圧力があったのではないでしょうか。いずれにせよ、日本にトランスジェンダリズムの原点をつくった重要な研究者であることは間違いありません」
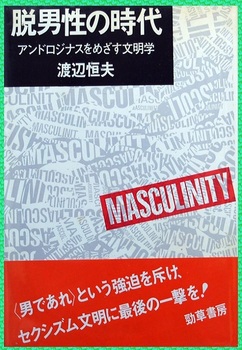
↑ 渡辺恒夫『脱男性の時代ーアンドロジナスを目指す文明学ー』(勁草書房 1986年)
九〇年代に入り、一九七九年創業の女装メイクルーム&サロン「エリザベス会館」に所属、自己流の女装から、本格的な技術を学んで女装をするようになった。のちに新宿歌舞伎町の女装スナック「ジュネ」でホステスとして働きはじめる。現在につながる〝研究〟を本格的に始められたきっかけは、何だったんだろう。
「九六、七年くらいに、〝性同一性障害〟ということばが一気に広まりました。「性同一性障害のあとに、トランスジェンダーということばが入ってきた」と言う人もいるけど、それは事実誤認です。トランスジェンダーが先にあって、その概念こそが性別を越えて生きようというわたしたちの自己肯定の出発点になっていたんです。
〝性同一性障害〟という概念の登場によって、新宿の女装世界はものすごく影響を受けました。分かりやすく言うと、いままでお店のドアを叩いていた女の子になりたい願望を持つ子たちが、みんな病院に行くようになってしまったんです。性別を越えて生きたいと思うのは障害であり、治療すべき病気だという考えが広まるにつれて、ずいぶんお客さんが減りました。
ある常連さんからは、「おまえたちが病気ってことは、俺は病気の人間と、病気をネタに酒を飲んでいるのか? そんなことする俺って人でなしじゃないか」と言われて。「そうじゃないのよ。楽しく飲めばいいじゃない」となだめても、一度落ちた気分は直りません。
そんななか、ママや古いお客さんからお店の昔話を聞くのが好きだったわたしに、先輩ホステスがこんなふうに言いました。
「わたしたちが作ってきた女装世界は、近い将来になくなっちゃうかもしれない。こんな世界があったことを、記録して残すことが、歴史学を勉強した順ちゃんの役目よ」
それ以来、研究者というよりは当事者として、調べて記録しなくてはならないという強い意識を持つようになりました。「ジュネ」という店の歴史、それを中核とした新宿の女装世界の成り立ちを遡って調べていきました。そんな調査をより社会史的な研究にしていこうと思い始めた時期に、中央大学の矢島正見先生(社会学)から声をかけられて、一九九九年に「戦後日本〈トランスジェンダー〉社会史研究会」を立ち上げ、歴史学と社会学の二つの手法で研究をしていくことになりました」
二〇〇〇年代初頭から、「性別を越えて生きることは病ではない」と一貫して性別越境の病理化を批判しつづけ、性同一性障害という病理概念に絡めとられることを拒否してきた三橋さん。ようやく時代の流れが変わりつつあるようだ。
「来年か、再来年かに実施されるWHOの国際疾病分類(ICD)の改訂にともなって、性別越境が精神疾患でなくなる見通しなんです。性同一性障害という病名も国際的には消えることになります。同性愛の脱病理化に遅れること二十七、八年、自分が唱えてきたことが実現することへ期待と喜びはもちろんあります。
「研究ができる女装者がいたんだ!」と驚かれたり、「病気と認められて良かったですね」と善意の人に言われた時代もありました。当時とくらべれば、ずいぶんトランスジェンダーが生きやすい世の中になったと思います。でも、まだまだ調べて記録しなければならないことはたくさんあります」
着物の襟を正しながら、まっすぐ前を見据える三橋さん。
「トランスジェンダー研究をきちんと引き継いでくれるひとが現われるまで、わたしもがんばりますよ」
虹色の表紙が目印。
インタビュー記事「わたしの光になった表現」(聞き手:外山雄太)は、牧村朝子・杉山文野・中村キヨ・マーガレット・田亀源五郎・橋口亮輔という豪華なメンバーが「人生の大切な局面をともにした三つの作品」を語る。
その他、海外のLGBT関係の評論・エッセイ8本を掲載。
東京の主要書店では、7月6日発売(税込950円)。
インタビューは、5月31日(火)。
明治大学(駿河台)での講義の後、17時少し前、神田神保町三丁目の「集英社」へ。
インタビュアーは外山雄太さん。
昨年3月、『朝日新聞』の原田朱美記者の紹介で知り合った方。
ご縁が形になってうれしい。
最初に撮影。
簡単な撮影かと思ったら、ちゃんとプロのカメラマンが待機していて、まず室内で、さらに、屋外に出て撮影。
着物、着てきてよかった。
↑ 撮影:隼田大輔氏
その後、2時間半ほど、「わたしの光となった表現」というテーマであれこれしゃべる。
まず、1980年代までに青年期を過ごした私の世代は、そもそも世の中に性別越境についての情報が乏しく、それを見つける(実際には、偶然、出会う)ことがたいへんだったことを話す。
「性別違和」という自分の状況を説明する言葉も、「性同一性障害」という概念も日本には入っていなかった。
そんな状況の中で「自分を見つける」導きになった書籍として、
(1)存在への気づき、(2)「成りたい」自己イメージの形成、(3)自己肯定化の理論、という観点で3冊を挙げた。
----------------------------
今回、豪華なメンバーの驥尾に付して出していただいたが、いろいろな意味で、トランスジェンダーとしての私の社会的な役割は終わったのかなと思う、今日この頃。
たくさんの方に「まだまだ」と言っていただけるのは励みにはなるけど、もう表舞台に出るのは心身ともに辛くなってきた。
あと何年生きられるかわからないが、残りの人生は研究生活、とりわけ、自分の著述のまとめに専念しようと思う。
『すばる』は創刊(1970年)から数年間、高校生の頃に購読していた思い出のある雑誌で、そこに出られたのは、そういう意味で良い記念になった。
-----------------------------------------------------
わたしの光となった表現
「あなたはどのような表現に影響を受け、また、支えられてきましたか?」
セクシュアリティー/世代/職業の異なる七名に、
人生の大切な局面をともにした三つの作品との出会いと、
その魅力についてうかがった。
探すものではなく、出会うもの
三橋順子
「二〇〇〇年、初めて大学の教壇に立った最初の講義の日、忘れもしません。週刊誌が三誌も取材に来たんです。日本で最初の、トランスジェンダーの大学教員。いったいそれ何? というまったく興味本位な反応でした」
三橋順子さんは、日本における性別越境、トランスジェンダーの社会・文化史研究家だ。歴史学的な手法で調査対象に取り組み、トランスジェンダーおよびセクシャルマイノリティーの歴史を探求してきた。
「自分が〝ふつう〟の男子と違うかも? と気づいたのは遅かったです。高校生のころ、おぼろげにそうかもしれない……と思ったくらいで、それ以前はとくになにも感じていませんでした。少なくとも、自分としては気づていないことになってました。のちのち専門の精神科医の先生にカウンセリングしてもらうと、どうも〝ふつう〟でない、記憶に蓋をしていたエピソードがたくさん出てきましたが。
自分のなかに別の人格がいて、それが女性だったと気づいたのは二十一歳のころ。性同一性障害とか、性別違和とか、そういう概念がない時代です。すてきな女性に対して、『付き合いたい』よりも、『ああいうふうになりたい』という気持ちを抱きました。
そんな自分が不可解で、図書館で精神分析学の本を読んだけど、答えは見つかりません。二十代後半が、自分がなぜこうなのか、よく分からず、つらかった時期でした。
そんな田舎から東京に出てきた青年が、いちばん最初に共鳴したのが『別冊SMスナイパー』一九八〇年十一月号に掲載されていた館淳一さんの「ナイロンの罠」という小説。一九八三年に単行本が刊行されますが、雑誌掲載時に読んで、これだ……! と思いました。自分の姉と義兄の手によって女性化されていく男子予備校生のお話。 女装の道に引き摺りこまれる美少年に自分を重ねたんですね。この作品は、二十五歳だったわたしのセクシュアル・ファンタジーの形成に多大な影響を与えました。三十数年後、著者の館淳一さんにお会いしたときは、大感激でした。

↑ 館 淳一『ナイロンの罠』(ミリオン出版 1983年)

↑ 初出の『別冊SMスナイパー』1980年11月号。
ほぼ時期を同じくして存在を知ったのが、土田ヒロミ撮影『青い花――東京ドール――』(世文社、一九八一年)でした。これは、一九七〇年代の東京のゲイボーイを主題にした写真集です。ゲイボーイというのは、当時は女装した男性のことを指しました。いまのゲイということばと、、八〇年代までのゲイとでは意味のズレがあるんです。
トランスジェンダー的な人物をテーマに撮影した日本初の写真集の存在は、スポーツ新聞で見て知っていましたが、当時二八〇〇円もする本なんて手が出ませんでした。あるとき、たまたま立ち寄った神保町の古本屋さんでめぐり会ったんです。店の前側には真面目な古本が、奥にSMやポルノ雑誌が置かれているような、お堅い本でエロをカムフラージュした本屋さんでした。そこで、『青い花』をやっと手に入れました。当時は、今のように情報が流通していませんから、こういった本は、探してもなかなか見つかるものではありません。存在が隠されているから探しようがなく、偶然出会うものだったんです。
写真集を見て、それまでぼんやりとしたイメージでしかなかった〝女装〟というものが、明確に可視化されました。「東京のどこかに、こうやって美しく着飾ったゲイボーイがいるんだ!」という強い実感。見えること、視覚的にイメージ化できることはそれだけ重要なんです。被写体になっていた〝お姉さん〟たちは、たぶん、赤坂、六本木あたりでお勤めの方々だったと思います。記載がないから、確かではないけれど。でも、自分と似たような感じの人がこれだけいるということを知って、なりたいわたしのイメージはより強固なものになっていきました」
.jpg)
-a7dc7.jpg)
↑ 土田ヒロミ撮影『青い花ー東京ドールー』(世文社 1981年)
しかし、そんなイメージを頼りに女装をし始めた八〇年代の終わりごろ、また別の問題が浮上したのだという。
「自己イメージは定まってきたけれど、それを言語化することがなかなかできませんでした。そんなときに出会ったのが、渡辺恒夫先生の『脱男性の時代――アンドロジナスを目指す文明学――』(勁草書房、一九八六年)でした。女装、性転換、アンドロジナス(両性具有)の世界を探求した評論集で、 女装者としての私の形成に際して、理論的な面で大きな影響を受けました。
評論として高く評価された『脱男性の時代』以外にも、二冊ほど同じような内容の本を書かれていて、『精神科治療か服装革命か』なんて、いまにも通じる問いを投じられました。〝トランスジェンダー〟というワードを書名にした日本最初の本の著者は、渡辺先生なんです(『トランス・ジェンダーの文化―異世界へ越境する知―』勁草書房、一九八九年)。
でも、その後はトランスジェンダーについては事実上、筆を折っちゃったんです。詳しい事情はよくわかりませんが、「おかしな研究をしている」というような社会的な圧力があったのではないでしょうか。いずれにせよ、日本にトランスジェンダリズムの原点をつくった重要な研究者であることは間違いありません」
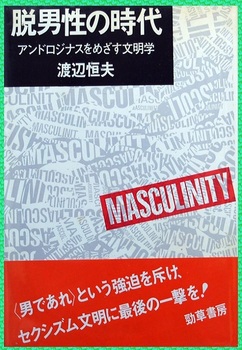
↑ 渡辺恒夫『脱男性の時代ーアンドロジナスを目指す文明学ー』(勁草書房 1986年)
九〇年代に入り、一九七九年創業の女装メイクルーム&サロン「エリザベス会館」に所属、自己流の女装から、本格的な技術を学んで女装をするようになった。のちに新宿歌舞伎町の女装スナック「ジュネ」でホステスとして働きはじめる。現在につながる〝研究〟を本格的に始められたきっかけは、何だったんだろう。
「九六、七年くらいに、〝性同一性障害〟ということばが一気に広まりました。「性同一性障害のあとに、トランスジェンダーということばが入ってきた」と言う人もいるけど、それは事実誤認です。トランスジェンダーが先にあって、その概念こそが性別を越えて生きようというわたしたちの自己肯定の出発点になっていたんです。
〝性同一性障害〟という概念の登場によって、新宿の女装世界はものすごく影響を受けました。分かりやすく言うと、いままでお店のドアを叩いていた女の子になりたい願望を持つ子たちが、みんな病院に行くようになってしまったんです。性別を越えて生きたいと思うのは障害であり、治療すべき病気だという考えが広まるにつれて、ずいぶんお客さんが減りました。
ある常連さんからは、「おまえたちが病気ってことは、俺は病気の人間と、病気をネタに酒を飲んでいるのか? そんなことする俺って人でなしじゃないか」と言われて。「そうじゃないのよ。楽しく飲めばいいじゃない」となだめても、一度落ちた気分は直りません。
そんななか、ママや古いお客さんからお店の昔話を聞くのが好きだったわたしに、先輩ホステスがこんなふうに言いました。
「わたしたちが作ってきた女装世界は、近い将来になくなっちゃうかもしれない。こんな世界があったことを、記録して残すことが、歴史学を勉強した順ちゃんの役目よ」
それ以来、研究者というよりは当事者として、調べて記録しなくてはならないという強い意識を持つようになりました。「ジュネ」という店の歴史、それを中核とした新宿の女装世界の成り立ちを遡って調べていきました。そんな調査をより社会史的な研究にしていこうと思い始めた時期に、中央大学の矢島正見先生(社会学)から声をかけられて、一九九九年に「戦後日本〈トランスジェンダー〉社会史研究会」を立ち上げ、歴史学と社会学の二つの手法で研究をしていくことになりました」
二〇〇〇年代初頭から、「性別を越えて生きることは病ではない」と一貫して性別越境の病理化を批判しつづけ、性同一性障害という病理概念に絡めとられることを拒否してきた三橋さん。ようやく時代の流れが変わりつつあるようだ。
「来年か、再来年かに実施されるWHOの国際疾病分類(ICD)の改訂にともなって、性別越境が精神疾患でなくなる見通しなんです。性同一性障害という病名も国際的には消えることになります。同性愛の脱病理化に遅れること二十七、八年、自分が唱えてきたことが実現することへ期待と喜びはもちろんあります。
「研究ができる女装者がいたんだ!」と驚かれたり、「病気と認められて良かったですね」と善意の人に言われた時代もありました。当時とくらべれば、ずいぶんトランスジェンダーが生きやすい世の中になったと思います。でも、まだまだ調べて記録しなければならないことはたくさんあります」
着物の襟を正しながら、まっすぐ前を見据える三橋さん。
「トランスジェンダー研究をきちんと引き継いでくれるひとが現われるまで、わたしもがんばりますよ」
2016-08-16 21:59
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)




コメント 0